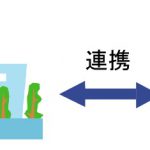「毎日のように反抗や無視をされて疲れてしまう…」「思春期の反抗が激しくてどう接していいかわからない」このような悩みを抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。
反抗期は、子どもが心の成長を遂げる大切なステップですが、実際に向き合うとなると戸惑いや不安がつきものです。
そこで本記事では、反抗期がいつまで続くのか、時期の目安や終わりのサイン、そしてご家庭でできる関わり方まで解説していきます。
反抗期とは

反抗期(はんこうき)とは、子どもが自我を持ち始める時期であり、その際に親や周囲の人との間に価値観のずれがあると強く反発しやすくなります。また、成長の段階で自制心のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなるなど、周囲の大人に対して反抗的な態度を見せやすくなるのが特徴です。
反抗期にみられる行動・言動
反抗期の子どもには以下の行動や言動がみられるケースが多いです。
- イライラする
- 感情的になりやすくなる
- 一度感情的になると気持ちを切り替えるまでに時間がかかる
- 物に当たる
- 暴言を吐く
反抗期は、自分自身でもイライラの原因を理解できず、感情を制御できなくなっている子どもが少なくありません。物に当たってはいけない、他人が傷付く言葉を言ってはいけないと頭で理解しているものの、自制心が働きにくく行動を起こしてしまうケースが多いです。
反抗期の役割
反抗期は、子どもが自立するために必要な時期だと考えられています。
反抗期を通して、子どもは以下のことを学びます。
- 他人との価値観の擦り合わせ
- 自己主張
- 感情のコントロール
- 自分で決断すること
反抗期を通して、主に親とぶつかってしまうことが多いです。しかし、この経験は社会に出て他人と過ごすなかでも必要な事であり、ぶつかり方や許される程度を練習している時期ともいえるでしょう。
親にとっては大変な時期ですが、子どもの自立にとって必要な時期だと割り切って考えることが重要です。
反抗期はいつ始まっていつまで続く?

「反抗期って一体いつ始まって、いつ終わるの?」「うちの子どもは反抗期がこないのかな?」など、疑問に感じている保護者の方は多いかもしれません。
実は反抗期には大きく分けて2つの時期があり、それぞれに違った特徴があります。
ここでは、「第一次反抗期(イヤイヤ期)」「中間反抗期」第二次反抗期(思春期)」の、現れやすい年齢の目安や行動の特徴を説明します。
第一次反抗期(イヤイヤ期)
第一次反抗期は、一般的に1歳半から3歳頃にかけて現れます。この時期の子どもは、自我が芽生え始め、自分の意思を主張するようになります。
たとえば、「イヤ!」と何にでも反発したり、「自分でやる!」と主張したりする行動が見られます。これは、子どもが自分の存在を認識し、自立しようとする自然な過程です。保護者は、子どもの自己主張を尊重しつつ、安全を確保することが大切でしょう。
中間反抗期
中間反抗期は、隠れた反抗期とも呼ばれます。5歳から10歳にかけてみられることが多く、本格的に社会生活をはじめ子どもだけの集団で過ごす時間が長くなる時期です。
親よりも友達を優先したり、友達に影響されて反発したりする様子がみられます。
これも、自分自身の価値観を形成している最中であり、同年代の友達を通してさまざまな価値観を学んでいます。
ある程度見守ることは大切ですが、倫理観は未熟なため保護者や周囲の大人が適切に指導をする必要があるでしょう。
第二次反抗期(思春期)
第二次反抗期は、思春期にあたる11歳から17歳頃にかけて現れます。この時期の子どもは、身体的・精神的な成長に伴い、親や大人の価値観に対して反発するようになります。
たとえば、親の指示に従わなかったり、無視したり、言葉遣いが乱暴になったりすることがあります。これは、子どもが自立し、自分の価値観を確立しようとする過程であり、親子の関係性を再構築する重要な時期です。
反抗期がない、反抗期が長引くのは問題?
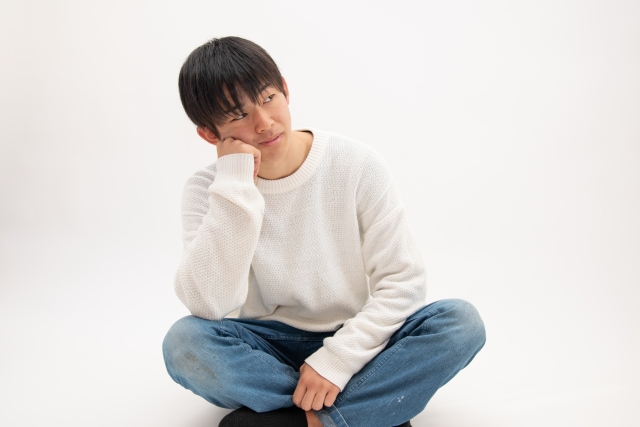
反抗期がない、または長引くことについては、個人差が大きく、どちらも一概に問題があるとは言えません。
反抗期がない場合、一般的に親子のコミュニケーションが良好で、子どもが安心して自己主張できている場合が多いですが、学校など外では違う一面を持っている可能性もあります。一方で、反抗期が長引く場合、子どもが自立に向けてまだ葛藤している可能性があり、親の対応が重要になります。いずれの場合も、子どもの気持ちに寄り添い、適切なサポートを行うことが大切です。
男女の反抗期の違い

反抗期は男女によっても表れ方に違う傾向が見られます。
もちろん、個人差は大きいですが参考にしてみてはいかがでしょうか。
男の子の反抗期の特徴
男の子の二次反抗期は中学生の頃から始まり、高校生まで続くケースが多くみられます。成長期であるため、体もどんどん大きくなり暴力的な態度が見られる際には注意が必要です。
急激に体力がつくことで、有り余る力や体力を発散させられずにイライラしている事もあるため、体力のある子どもはスポーツでストレス発散を促すのもよいでしょう。
女の子の反抗期の特徴
女の子の反抗期は比較的早く始める傾向にあり、小学校高学年から始まり中学を卒業する頃には落ち着いているケースが多くみられます。言動がきつくなったり、ひとりになりたがったりすることも多いため、安全を確保しながら見守ってあげるとよいでしょう。
反抗期の間に初潮を迎える女の子も多く、ホルモンバランスが大きく乱れることで意味もなくイライラしてしまうこともあります。サポートを望む時には十分にケアしてあげることが大切です。
反抗期との向き合い方とご家庭での対応

反抗期の子どもとのやりとりが続くと、つい感情的になってしまったり、「どう接したらいいのかわからない」と悩んでしまったりすることもあるかもしれません。
大変ではありますが、反抗期は子どもが自立へ向かう大切な過程です。だからこそ、親としての接し方がとても重要になります。
ここでは、子どもと感情的にぶつからない工夫や、気持ちを受け止める関わり方、そして保護者自身のストレスをためない方法について解説します。
感情でぶつからないための工夫
反抗期の子どもは、自立心が芽生え、親に対して反発的な態度をとることがあります。この時期、親が感情的に対応すると、子どもとの関係が悪化する可能性があります。
対応のポイント
- 冷静な対応を心がける
子どもの言動に対して感情的にならず、落ち着いて対応しましょう。 - 一呼吸置く
感情が高ぶったときは、その場を離れるなどして冷静さを取り戻す時間を持ちましょう。 - 子どもの気持ちを尊重する
子どもの意見や感情を否定せず、理解しようとする姿勢を示しましょう。
親が冷静に対応することで、子ども自身も安心感を持ち、信頼関係が築かれます。
子どもの気持ちを受け止める関わり方
反抗期の子どもは、自分の気持ちをうまく表現できず、反発的な態度をとることがあります。このような時期には、子どもの気持ちを受け止める関わり方が大切です。
対応のポイント
- 傾聴する
子どもの話を最後までしっかりと聞き、共感を示しましょう。 - 肯定的な言葉をかける
子どもの努力や良い点を見つけて、積極的に褒めてあげましょう。 - 選択肢を与える
子どもに自分で選ばせることで、自立心と責任感を育てましょう。
子どもの気持ちを受け止め、尊重する姿勢を見せることで、親子の信頼関係が深まります。
親側のストレスをためない方法
反抗期の子どもとの関わりは、親自身にとってもストレスがたまるものです。そこで親が心身ともに健康でいることが、子どもとの良好な関係を築くために重要でしょう。
対応のポイント
- 自分の時間を持つ
趣味やリラックスできる時間を確保しましょう。 - 周囲や専門機関に相談する
信頼できる人や専門家に相談することで、気持ちを共有でき、情報も得られます。 - 完璧を求めない
子育てに完璧を求めず、自分を責めないようにしましょう。
親自身がリフレッシュすることで、子どもとの関係も良好に保つことができるはずです。
反抗期は、子どもが自立へと向かう大切な成長の過程です。親が冷静に対応し、子どもの気持ちを受け止めることで、親子の信頼関係が深まり、反抗期を乗り越えることができます。また、親自身のストレスをためない工夫も大切です。ひとりで抱え込まず、必要に応じて周囲のサポートを活用しながら、子どもの成長を見守っていきましょう。
反抗期が終わるサインとは?

「反抗期って、いつまで続くんだろう…」と感じたことはありませんか?日々の小さな衝突が重なる中で、子どもの成長を信じたい気持ちと、疲れた気持ちの両方を抱えている方も多いはずです。
ですが、反抗期にも必ず「終わり」はあります。そして、終わりが近づくと見えてくるサインがいくつかあります。
そこで本項では、子どもの言動や関わり方の中から見えてくる「反抗期の終わり」の兆しについて、具体的にご紹介していきます。
言動が落ち着いてくる
反抗期の子どもは、感情の起伏が激しく、親に対して強い言葉や態度を示すことがあります。しかし、反抗期の終わりが近づくと、次第に言動が穏やかになり、親に対する反発も減少していきます。
たとえば、以前は無視や反抗的な態度が多かった子どもが、挨拶を返すようになったり、親の言葉に耳を傾けるようになるなど、態度の変化が見られます。このような変化は、子どもが自我を確立し、親との関係を再構築しようとしているサインと捉えることができます。
自分の気持ちを言葉で伝えてくる
反抗期の子どもは、自分の感情をうまく表現できず、イライラや不満を態度で示すことが多くなります。しかし、反抗期の終わりが近づくと、子どもは自分の気持ちを言葉で伝えるようになります。
たとえば、「今日は学校でこんなことがあって嫌だった」といった具体的な話をするようになったり、自分の意見や考えを親に伝えるようになるなど、コミュニケーションの質が変化していきます。このような変化は、子どもが自分の感情を整理し、親との信頼関係を築こうとしているサインと考えられるでしょう。
親子の会話が増えてくる
反抗期には、親子の会話が減少し、コミュニケーションが難しくなることがあります。しかし、反抗期の終わりが近づくと、子どもから話しかけてくることが増え、親子の会話が自然と増えていきます。
たとえば、日常の出来事や学校の話、将来の夢など、さまざまな話題について子どもが話すようになると、親子の関係が改善されてきている証拠です。このような変化は、子どもが親との関係を大切にし、信頼を寄せているサインと捉えることができます。
反抗期は、子どもが自立し、自己を確立するための大切な時期です。保護者の方々は、子どもの変化に敏感になり、温かく見守る姿勢を持つことが重要です。
子どもの反抗期についてのまとめ
反抗期は、子どもが心の成長を遂げ、自立へと向かう大切な過程です。
一般的に「第一次反抗期(1歳半〜3歳頃)」「中間反抗期(5歳~10歳)」「第二次反抗期(11歳〜17歳頃)」の3段階があり、それぞれに異なる特徴と対応が求められます。反抗期がない、または長引く場合でも必ずしも問題があるわけではなく、子どもの個性や環境による違いとして見守ることが大切です。
反抗期の終わりには、「言動が落ち着く」「自分の気持ちを言葉で伝える」「親子の会話が増える」といったサインが見られるようになります。感情的にぶつからない工夫や、子どもの気持ちを受け止める姿勢、そして保護者自身のストレスをためない配慮が、親子関係の安定に大きくつながります。
子どもの変化に優しく寄り添いながら、ご家庭の中でできるサポートを重ねていくことが、反抗期を乗り越えるための第一歩です。