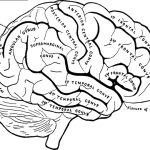爪を噛む行動に隠された心理と親ができること

ふと気づくと、子どもが爪を噛んでいる…。そんな姿を見て、「やめさせたいのにやめてくれない」「もしかして、私の育て方に問題があるの?」と悩んでいませんか。
子どもの爪噛みは珍しいことではありませんが、長く続くと衛生面や健康面も心配になります。大切なのは、その行動の裏に隠された子どもの心理を理解することです。爪を噛むという行動は、子ども自身もうまく言葉にできない不安やストレスのサインかもしれないからです。
この記事では、爪を噛む行動の背景にある心理を年齢別に詳しく解説し、保護者として何ができるのか、叱らずに子どもの心に寄り添う具体的な対処法についても解説します。
子どもが爪を噛む心理的な原因とは?

子どもが爪を噛む行動は、その年齢や発達段階によって、背景にある心理が異なります。
幼児の爪を噛む心理
3歳~6歳頃の幼児期に見られる爪噛みは、多くの場合、言葉でうまく表現できない感情の表れです。
ひとつは、安心感を求める心理です。この時期の爪噛みは指しゃぶりの延長線上にあり、不安や寂しさを感じたときに自分自身を落ち着かせるための行動と考えられています。
次に、欲求や葛藤も関係します。例えば、弟や妹が生まれて親の関心が分散したとき、「もっと私(僕)を見てほしい」という満たされない気持ちが爪噛みとして現れることがあります。また、やりたいことがうまくできないときなど、もどかしい気持ちを爪を噛むことで解消しようとすることもあります。
さらに、退屈している可能性もあります。テレビを見ている時や車での移動中など、手持ち無沙汰になるときに無意識に爪を噛んでしまうケースです。
子どもの爪を噛む心理
子どもが小学生に上がると、生活環境は大きく変わり、幼児期とは異なる種類のストレスや心理的なプレッシャーに直面します。
最も大きな要因は、緊張やプレッシャーです。新しいクラス、友人関係、本格的に始まる勉強など、「ちゃんとしなきゃ」「間違えたらどうしよう」といったプレッシャーや不安が、爪を噛むという形で現れます。特に、真面目で繊細な傾向がある子は、この傾向が強まることがあります。
また、不満や不安も複雑化します。友人関係の悩みや、勉強についていけない焦り、習い事のプレッシャーなど、心に抱えるモヤモヤも多様化します。これらを言葉でうまく親に相談できず、ひとりで抱え込んだ結果、緊張を緩和するために爪を噛む行動が癖になってしまうのです。
爪を噛むのは愛情不足?
子どもの爪噛みを見て、多くの保護者が、愛情不足が原因とご自身を責めてしまうかもしれません。
しかし、「爪を噛む=愛情不足」と短絡的に結論づけるのは間違いです。
もちろん、親とのコミュニケーション不足が引き金になるケースはあります。しかし、それだけが原因のすべてではありません。子どもの生まれ持った気質(繊細、緊張しやすいなど)や、集団生活でのプレッシャーなど、原因は非常に多岐にわたります。保護者がどれだけ深く愛情を注いでいても、子どもが外の世界で感じるストレスが大きければ、爪噛みという行動に出ることは十分にあり得ます。
大切なのは、ご自身を責めることではなく、「この子は今、何か不安を感じているのかもしれない」と、行動の裏にあるものをしっかりと受け止めてあげることです。
爪を噛み続けることで起こりうる3つのリスク

子どもの癖だから、そのうち治るだろうと軽く考えていると、思わぬ問題につながる可能性もあります。爪を噛むという行動を長期間続けることで起こりうる、3つのリスクについて解説します。
衛生面の問題
私たちの手や指先、特に爪の間には多くの雑菌が付着しています。爪を噛むことで、これらの細菌が口から体内に入り込み、風邪や感染性胃腸炎などのリスクを高めます。
また、爪を噛むことでできた指先のささくれや傷口から細菌が入り込み、「ひょうそ(爪周囲炎)」という炎症を起こすこともあります。指先が赤く腫れ上がり、痛みを伴うため注意が必要です。
身体的な問題
爪を噛み続けると、爪自体にもダメージを与えます。「深爪」の状態が続くと指先で物をつかむ力が弱くなったり、爪が皮膚に食い込んで痛みが出る「陥入爪(かんにゅうそう)」や、爪が変形したりすることもあります。
さらに、見落とされがちなのが「歯並びへの影響」です。一定の場所に継続的に圧力をかけ続けることになるため、前歯が欠けたり、歯並びが悪くなる(不正咬合)原因のひとつにもなり得ると指摘されています。
精神的な問題
幼児期は気にしなくても、小学生くらいになると、友達から「まだ爪噛んでるの?」とからかわれたり、指摘されたりすることがあります。それにより、子ども自身が自分の癖を「恥ずかしいことだ」と強く意識するようになります。
人前で手を隠すようになったり、「やめたいのにやめられない」という葛藤が新たなストレスになったりすることで、自己肯定感が低下してしまう恐れがあります。
子どもの爪噛みをやめさせるための対処法5選

爪噛みをやめさせたいと思ってもどうしたら良いかと悩まれる方も多いと思います。やめなさい、と頭ごなしに叱る方法は逆効果になることがほとんどです。ここでは、子どもの心に寄り添いながら、行動を変えていくための5つのステップを紹介します。
ストレスの原因を探り、ストレスを和らげる
まずは、爪噛みの根本原因となっている心理的な負担を軽減することから始めましょう。
最近、子どもの様子で変わったことはないか、生活を振り返ってみてください。「学校で嫌なことはない?」と優しく声をかけ、子どもが話し始めたら「うん、うん」と最後までじっくりと耳を傾けてあげてください。
もし、うまく言葉にできないようなら、無理に聞き出す必要はありません。その代わり、1日5分でも良いので、その子だけと向き合う「特別な時間」を作りましょう。一緒に絵本を読んだり、抱きしめて「大好きだよ」と伝えたりするだけでも、子どもの心は満たされます。スキンシップを増やし、自分は愛されているという安心感を育てることが、ストレスを和らげる一番の特効薬です。
爪噛みに代わる安心方法を見つける
爪噛みは、不安や緊張を紛らわすための癖になっていることが多いです。そこで、爪を噛むこと以外の方法で心を落ち着けられるよう、代わりの行動(代替行動)を一緒に見つけてあげましょう。
例えば、手が口に行きそうになったら、代わりに粘土やスクイーズ(柔らかいおもちゃ)を握る、ハンドタオルを握りしめる、といった方法があります。
また、親子でできるハンドマッサージもおすすめです。「手が寂しいのかな?マッサージしようか」と声をかけ、指先を優しく揉んであげることで、安心感を与えると同時に、指先への意識を噛むことから心地よい刺激へとそらすことができます。
叱る以外の声掛けと関わり方
爪を噛んでいる現場を見ると、つい「また噛んでる!」「何度言ったらわかるの!」と強い言葉で注意してしまいがちです。しかし、これは子どもを緊張させ、さらに爪噛みを悪化させる原因になります。
大切なのは、「叱る」のではなく「気づかせる」声かけです。 例えば、以下のような言い換えを試してみてください。
・NG
「やめなさい!」「汚い!」
・OK
「あ、指さん、お口に入ってるよ」「手が寂しいのかな?」「ぎゅってしようか?」
行動そのものを否定するのではなく、その裏にある心理に寄り添うような言葉や、別のことに意識をそらすような声かけを心がけましょう。爪を噛んでいないときに「あれ、今お指さんお口に行ってないね。すごいね!」と、できていないときではなく、できているときに注目して褒めることも非常に効果的です。
物理的なアプローチと注意点
子どもの心理面に配慮しつつ、物理的に爪を噛みにくくする工夫も併用すると効果的な場合があります。
最も基本的で重要なのは、爪をこまめに短く切ってあげることです。爪が短ければ、噛む部分がなくなり、噛んだときの「達成感」も得られにくくなります。また、爪の間に雑菌が溜まるのを防ぐ意味でも、常に清潔に保つことは大切です。
市販されている「苦い味のマニキュア(ビターネイル)」も選択肢のひとつです。口に入れたときに強い苦味を感じさせ、無意識の爪噛みを防ぐ効果が期待できます。 ただし、子どもによっては、その苦味が強いストレスになったり、「罰を与えられた」と心理的に追い詰められたりすることがあります。もし使用する場合は、子どもに目的をしっかり説明し、同意を得てから使うようにしましょう。
自己肯定感を育む関わり
爪噛みをやめさせる上で、最終的に最も大切なのは、子どもの自己肯定感を育むことです。爪噛みというひとつの行動にばかり注目しすぎると、保護者も子どもも「爪を噛む=悪いこと」という認識に縛られてしまいます。
爪を噛んでしまっても、「あ、またやっちゃったね。でも、大丈夫だよ」と、失敗を責めずに受け止めてあげましょう。
そして、爪噛み以外のことに目を向け、子どもの良いところをたくさん見つけて褒めてあげてください。「ご飯を全部食べたね」「元気にご挨拶できたね」。どんな些細なことでも構いません。自分は爪を噛んでしまうけれど、お母さん(お父さん)は自分を丸ごと認めてくれている、という安心感が心の土台を強くし、結果として不安や緊張からくる爪噛みを減らしていく力になります。
子どもの気になる行動にどのように対応すればよいかわからないときは、専門機関に相談することもひとつの方法です。
ステラ幼児教室にお気軽にご相談ください。
大人の男性や女性が爪を噛む心理

子どもの頃の爪噛みが、適切な対処がされないまま癖として定着してしまうと、大人になっても続いてしまうケースは少なくありません。大人の爪噛みも、根本にある心理は子どもの頃と同じ「ストレスや不安の緩和」ですが、直面するストレスがより複雑になります。
男性の場合、仕事のプレッシャーや大きな責任、締め切りへの焦り、イライラなど、強い緊張状態にさらされたときに、それを紛らわすために無意識に爪を噛んでしまう傾向が見られます。男性は集中して考え事をしているときに、無意識の癖として出やすいのも特徴です。
女性の場合も仕事のストレスはありますが、それに加えて人間関係の悩みや将来への漠然とした不安があるときに見られることがあります。女性も考え事をし、手持ち無沙汰なときなどに、癖として出てしまうことがあります。
大人の場合、男性も女性も、子どもの頃とは違い「みっともない」「やめたい」と強く自覚していることが多いのが特徴です。それなのにやめられない自分に対して自己嫌悪に陥り、その葛藤自体が新たなストレスとなって、さらに爪噛みを引き起こすという悪循環に陥りがちです。
このように、一度定着した癖を大人になってから治すのは簡単ではありません。だからこそ、子どものうちに、爪噛み以外の適切なストレス対処法(リラックス方法)を身につけておくことが大切なのです。
改善しないときはひとりで悩まず相談を

紹介した対処法を家庭で試してみても、「爪噛みが一向に良くならない」「爪噛み以外にも、癇しゃくがひどいなど、気になる行動がある」…。そんなときは、決してひとりで抱え込まないでください。専門的なサポートが必要な場合や、発達の特性が隠れている可能性もあります。
どんな専門機関に相談すれば良いか
まずは、かかりつけの小児科や小児歯科で身体的な問題を相談できます。心理面や発達面のサポートは、地域の保健センターや学校のスクールカウンセラーも身近な相談相手です。さらに専門的なアプローチが必要な場合は、児童精神科や、ステラ幼児教室のような発達支援・療育機関が選択肢となります。
専門機関で受けられるサポートとは
専門機関では、まずカウンセリングやアセスメントを通して、子どもが爪を噛んでしまう根本的な原因(心理的な要因や発達特性)を探ります。
その上で、「プレイセラピー(遊びを通した心理療法)」や療育支援などを通して、不安やストレスを爪噛み以外の方法(言葉で表現する、リラックスするなど)で発散するスキルを学んでいきます。
また、保護者自身が、子どもへの最適な関わり方を学ぶためのサポートを受けられることも、専門機関を利用する大きなメリットです。
爪を噛む心理についてのまとめ
この記事では、子どもが爪を噛む行動の裏にある心理と、家庭でできる具体的な対処法について解説しました。
・爪を噛む行動は、幼児も子どもも、言葉にできない不安や緊張を抱えた心理的なSOSサインであることが多いです。
・原因は愛情不足だけでなく、子どもの気質や環境などさまざまです。
・対処法として最も大切なのは、叱るのではなく、まずは安心感を与え、ストレスの原因を探ることです。
・安心感と自己肯定感を育む関わりが根本的な解決につながります。
・家庭で試しても改善しない場合は、ひとりで悩まず専門機関に相談することが大切です。
子どもの爪噛みが治らないからといって、ご自身を責める必要は全くありません。その行動の裏にある心理に気づいてあげられたこと、それが何よりの第一歩です。
もし、子どもの行動面での不安や発達に関して、専門的なサポートが必要だと感じたときは、その子の特性を理解し、個性に合わせたサポートを提供してくれる場所を頼ることも考えてみてください。
ステラ幼児教室では随時見学受付中
名古屋市、大阪市に展開している児童発達支援事業所、ステラ幼児教室では随時見学を行っています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。