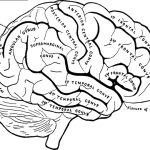「子どもが歩きはじめるのが遅い」「少し体の動きがぎこちない」と感じることはありませんか?
生活するための土台となる動きを粗大運動と呼び、子どもが健やかな成長をするために欠かせません。
このコラムでは、粗大運動のことや発達のステップ、微細運動との違い、家庭でできる粗大運動のサポートなどを解説します。こどもの成長に寄り添うための参考になれば幸いです。
粗大運動とは?
子どもがいる保護者の中には、粗大運動という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、詳しく知っている方はそれほど多くないでしょう。そのため、まず粗大運動という言葉の意味の解説から始めます。
粗大運動は体を使った大きな動き

粗大運動とは、生活するために必要な大きな動きのことを指します。具体的には、「歩く」「立つ」「座る」「姿勢を保つ」「ジャンプする」などの動作のことです。粗大運動には、筋力やバランス感覚などさまざまな身体機能が関係しており、子どもが健やかに成長するためには欠かせません。
粗大運動と微細運動との違い
粗大運動と似たような言葉として微細運動があります。粗大運動は大きな動きを指す言葉ですが、微細運動は細かい動きを指す言葉です。具体的には、「字を書く」「箸を使う」「絵を描く」などの動作について使われます。
どちらの運動も、子どもが健やかに成長するには欠かせません。一般的に、粗大運動が発達し分化して、微細運動が発達するといわれています。 そのため、器用に手先を動かすためには、粗大運動をしっかり行っておくことが大切です。


粗大運動の発達の目安
子どもの発達には個人差がありますが、おおよその目安を知っておくと安心して成長を見守る助けとなります。月齢や年齢に応じた粗大活動の目安を紹介します。
0~3ヶ月
生後3か月頃に首がすわりはじめ、手足を動かしたり顔の向きを変えたりできるようになります。
3~6ヵ月
寝返りや頭を持ち上げるなど自分の意思で徐々に体を動かせるようになります。支えてあげると座れるようになるのもこの時期です。
6~9ヶ月
手足の筋肉がつき、ずりばいやはいはいで移動できるようになります。腹筋や背筋もついてくるため、お座りもできるようになります。
9~12ヶ月
ずりばいやはいはいでの移動速度があがり、つかまり立ちやつたい歩きができるようになります。この頃から立っていられる時間が長くなっていきます。
1歳~1歳半
まだ不安定ですがバランスを取りながら、ひとりで歩けるようになります。足に筋肉がつき立ったりしゃがんだり、ゆっくり階段を上ったりできるようになります。
1歳半~2歳
バランス感覚が発達し、歩行が安定してきます。体力もつき歩ける距離が長くなり、走ることもできるようになります。さらにボールを投げたり蹴ったりもできるようになるため、全身を使った運動を楽しめるようになります。
2歳~2歳半
さらに手足に筋肉がつき、鉄棒にぶら下がったり、ジャンプしたりできるようになります。三輪車に乗れるようになるのもこの時期です。バランス感覚も発達し、短時間なら片足立ちもできるようになります。
2歳半~3歳
自分の思い通りにかなり体を動かせるようになります。スムーズな階段の上り下り、平均台の移動、片足立ちなどができるようになります。
「できない」ときは見守り、必要に応じて相談を
発達には個人差があることを理解していても「他の子どもより少し遅れているかも」と感じたら、どう対応すればよいのかと不安になるかもしれません。
子どもが他の子どもに比べて「よくつまずく」「上手く三輪車に乗れない」といったことに気づいたときは、あまり不安にならず見守りましょう。
気になるときは、必要に応じ、保健センターや医療機関などに相談するのも一つの方法です。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育機関でも、子どもに合わせて粗大運動を取り入れているところもあります。
メモや動画を撮っておくと、専門機関に相談するときに役立つのでおすすめです。
粗大運動が育つメリットとは?
粗大運動は、体を動かすだけではなく、成長の中で体と心にさまざまな影響を及ぼします。
粗大運動を育てると次のようなメリットがあります。
体力と姿勢を支える
粗大運動を通して、子どもは全身の筋肉をつけバランス感覚を発達させていきます。特に、走る・ジャンプする・上るといった動作では、足の筋肉や体幹が鍛えられ、姿勢の安定につながります。
姿勢の安定は、スムーズに動けるようになるだけでなく、転びにくくなりケガの予防にも役立ちます。自分の思い通りに体を動かせるようになると、友達と遊ぶことやスポーツへの意欲向上にもつながります。
社会性の向上
他の子どもと一緒に体を動かして遊ぶことで、社会性の向上も期待できます。例えば、公園で追いかけっこやボール遊びなどで他の子どもと遊ぶと、ルールを守ることや子ども同士でコミュニケーションをとることを学びます。
このような経験から社会性の基本となる「相手の存在を意識する」「自分の意思を言葉で伝える」「他者との関係を築く」といった力が少しずつ身に付いていきます。
自信や意欲が育まれる
粗大運動に取り組む中で、子どもは「できた」という達成感を経験します。最初はできなかったことができるようになると自信につながり、新しいことにも挑戦したいという意欲も芽生えていきます。
また、多くの成功体験により、できないことがあっても、もう一度挑戦してみようと思う諦めない気持ちも育っていきます。
さらに、体を動かすことは、イライラを発散したり、気持ちを切り替えたりする手段としても有効であるため、心の安定にもつながります。
家庭でできる粗大運動のサポート
家庭の中でも、特別な準備をせずに粗大運動を育むことができます。大切なことは、子どもの発達に合った遊びを取り入れることです。発達に合っていない遊びを取り入れると、ケガにつながるリスクが高くなります。
ここでは毎日の生活の中に、無理なく取り入れていける粗大運動のサポート方法を紹介します。
家の中で取り入れやすい粗大運動のサポート
以下のようなシンプルな遊びは、特別な用意をしなくても家の中で楽しく取り組めます。
●ソファのクッションを積んで登る
●床にテープを貼って、テープに沿ってバランスをとりながら歩く
●複数のクッションを適当に床に置き、その上を落ちないように歩く
※家庭で行う際は、子どもの発達に合わせて無理のないものを取り入れ、けがのないように注意してください。
屋外で楽しめる粗大運動のサポート
屋外では家の中よりもさらにさまざまなサポートが可能です。滑り台やジャングルジム、ボールを使った遊び、子ども同士の追いかけっこなどは、遊びながら自然と身体を動かすことができる機会となります。保護者も一緒に遊ぶと、親子のコミュニケーションも深まるでしょう。
まとめ~粗大運動は子どもの健やかな成長に不可欠な体の動き
粗大運動のことや発達のステップ、微細運動との違い、家庭でできる粗大運動のサポートなどを解説しました。
粗大運動は、子どもがいきいきと生活するための土台となる大切な力です。できることを少しずつ積み重ねていくことで、自信につながり、活動の幅が広がっていくでしょう。
子どもの発達が気になる場合は、ひとりで悩まず、かかりつけの小児科や保健センターなどの専門機関や、児童発達支援などの療育機関に相談するとよいでしょう。