運動療育で苦手改善をめざす

「ほかの子と比べて運動が苦手かもしれない」「手先が不器用で生活に支障がある」 子育ての中で、こうした運動面の悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
近年、このような悩みに対して運動療育という専門的なサポートが注目されています。 運動療育は、単なるスポーツ技術の習得を目指す体操教室とは異なります。その最大の目的は、運動を通して心と身体の発達の土台を築くことです。
苦手意識を持たせず、その子の発達段階に合わせた遊びを通して「できた!」という経験を積み重ねていく。それが運動療育の基本的な考え方です。 この記事では、療育における運動のねらいや、具体的なプログラム内容、家庭でできる遊びについて解説します。
運動療育のねらいは心と身体の発達

運動療育には、身体的な機能の向上だけでなく、心の成長を促すという重要なねらいがあります。
運動が苦手になる背景や不器用さの理由
子どもが運動を苦手と感じたり、極端に不器用だったりする背景には、いくつかの理由が考えられます。本人のやる気や努力が足りないわけではありません。
理由のひとつとして、感覚統合がうまくいっていない可能性があります。感覚統合とは、目や耳から入る情報だけでなく、筋肉の動きを感じる固有受容覚や、身体の傾きやスピードを感じる前庭覚といったさまざまな感覚を、脳内で整理してまとめる働きのことです。 ここがうまくいかないと、自分の身体の幅が感覚的にわからずにドアや机によくぶつかったり、力の入れ具合が調整できずに友達を強く押しすぎてしまったりすることがあります。
また、生まれつき筋肉の張りが弱い(低緊張)ために、姿勢を保つだけで疲れやすく、すぐにぐにゃっとしてしまう子もいます。 さらに、赤ちゃん時代の反射(原始反射)が強く残っている影響で、特定の姿勢をとることが無意識のうちに辛くなってしまうケースもあります。どのような順序で身体を動かせば良いかを脳内で計画する運動企画の弱さも、ぎこちない動きの原因となります。
ねらいは身体機能と自己肯定感の向上
運動療育には、大きく分けて身体面と精神面の2つのねらいがあります。
身体面のねらい
日常生活に必要な身体機能の土台を作ります。
・体幹の安定
良い姿勢を保ち、手足をスムーズに動かす土台となります。
・バランス感覚
転びそうになっても姿勢を立て直す力や、不安定な場所で身体を支える力を養います。
・協調運動
「目で見た情報に合わせて手を動かす(ボールキャッチなど)」「右手と左手で違う動きをする(紙を押さえてはさみで切るなど)」といった、複数の動作をまとまりのある動きにする力を育てます。
精神面のねらい
やればできるという心の土台を育てます。
・自己肯定感の向上
苦手なことに挑戦し、小さな成功体験を積むことは、子どもにとって大きな自信となります。
・意欲の向上
「どうせできない」という諦めの気持ち(学習性無力感)を防ぎ、新しいことにも「やってみよう」と思える意欲を育てます。
・社会性やルールの理解
順番を守る、合図に合わせて動くといった経験を通して、社会性やコミュニケーション能力を自然に育みます。
運動療育は遊びを通して行うのが基本
運動療育で最も大切なのは、子ども自身が「楽しい」「もっとやりたい」と感じることです。そのため、プログラムは訓練ではなく遊びの形で行われます。
子どもは楽しい遊びに夢中になっているとき、主体的に身体を動かします。指導員は、その遊びの中に、その子に必要な動きの要素(バランスを取る、しっかり握る、タイミングを合わせるなど)を巧みに組み込んでいます。
遊びを通して自然に身体を動かすことで、結果として必要な機能が発達していくのです。
運動プログラムの粗大運動と微細運動
運動療育のプログラムは、粗大運動と微細運動の2つに大きく分けられます。これらは互いに深く関係し合っており、どちらもバランスよく発達することが大切です。
全身を使う粗大運動とは
粗大運動とは、姿勢を保ったり、歩いたり走ったりするような、身体全体を使った大きな動きのことです。
すべての活動の土台となるのがこの粗大運動です。たとえば、学校の授業中に座って落ち着いて先生の話を聞くためには、背中や腹筋で上半身を支え続ける体幹の力が必要です。粗大運動の発達が不十分だと、すぐに姿勢が崩れて頬杖をついたり、椅子の上でもじもじしたりしてしまい、集中力が続かない原因になることもあります。
粗大運動の具体的なプログラム例
療育施設では、さまざまな器具や遊びを使って粗大運動を促します。

・トランポリン・バランスボール
揺れる不安定な場所で姿勢を保とうとすることで、無意識のうちに体幹やバランス感覚(前庭覚)が養われます。
・サーキット遊び
「トンネルをくぐる(空間認知)」「ケンケンパで進む(バランスとリズム)」「マットで転がる(前庭覚)」といった異なる動きを連続して行います。「赤いフープをくぐってから青いマットへ」といったルールを加えることで、聞き取る力や記憶力のトレーニングにもなります。
・模倣遊び(リトミック)
動物の動きをまねたり、音楽に合わせて動いたりすることで、自分の身体をイメージ通りに動かす練習をします。
手先や指先を使う微細運動とは
微細運動とは、つまむ、握る、書く、はさみを使うといった、手や指先を使った細かく精密な動きのことです。
食事(箸やスプーン)、着替え(ボタンやファスナー)、学習(鉛筆で書く)など、日常生活の多くの動作に直結します。 小学校に入ると、算数セットの小さなおはじきを扱う、コンパスで円を描く、給食当番でエプロンのひもを結ぶなど、高度な微細運動が求められる場面が増えます。そのため、就学前に遊びを通して手先の経験を積んでおくことは非常に重要です。
微細運動をスムーズに行うためには、粗大運動による姿勢の安定が欠かせません。身体の中心が安定して初めて、腕や手先を自由に、そして細かくコントロールすることができるのです。
微細運動の具体的なプログラム例
微細運動は、机に向かって行う遊びの中で楽しく練習します。

・粘土やお絵描き
手でこねる、ちぎる、クレヨンをしっかり握って描くといった活動は、指先の力加減を学びます。
・ひも通し・ビーズ遊び
小さな穴にひもを通す活動は、目で見た位置に正確に手を動かす「目と手の協応」の良い練習になります。
パズル・ブロック・ペグさし
形や向きを認識する力や、小さなペグ(杭)を狙った穴にはめ込む動作を通して、鉛筆を持つために必要な指先の機能(親指、人差し指、中指の3点持ち)を育てます。
家庭でできる簡単な運動遊び

特別な道具がなくても、ご家庭にあるものを使って、発達を促す運動遊びはできます。親子で触れ合いながら楽しむことが一番のポイントです。
粗大運動を促すおすすめの室内遊び
・タオル綱引き
フェイスタオルなどを親子で引っ張り合います。しっかりと握る力や、踏ん張ることで体幹や足腰が鍛えられます。
・クッション飛び石
床にクッションや座布団を並べて、落ちないように渡り歩きます。バランス感覚を養う楽しい遊びです。
・鏡あそび(まねっこゲーム)
鏡のように向かい合い、保護者の動きを子どもがまねします。手を上げる、片足立ちするなど、自分の身体をイメージ通りに動かす練習になります。
・だるまさんがころんだ
「動く」と「止まる」を自分でコントロールする力(身体の抑制機能)が育ちます。慣れてきたら「だるまさんが寝転んだ」「片足立ちした」などポーズを指定するのも楽しいでしょう。
微細運動を促すおすすめの遊びやお手伝い
・洗濯バサミ遊び
厚紙などに洗濯バサミを挟んでいきます。つまむ動作は、鉛筆やお箸を持つための基礎になります。
・新聞紙ビリビリ
新聞紙をできるだけ長く破いたり、細かくちぎったりします。指先の分化した動き(親指と人差し指を使うなど)を促します。
・タオル絞り(雑巾絞り)
お風呂遊びの中で、小さなタオルを両手で絞る、慣れたら片手で握って絞る練習をします。手のひらの筋肉を鍛えるのに効果的です。
・料理や洗濯のお手伝い
ラップでおにぎりを握る、しめじをほぐす、乾いた靴下をペアにしてたたむといったお手伝いは、立派な微細運動です。「ありがとう」と感謝されることで自己肯定感も高まります。
家庭で運動遊びをするときの3つの注意点
1.安全第一で
転んでも危なくないよう周囲を片付け、滑りやすい靴下は脱ぐなど、環境を整えてから行いましょう。ジョイントマットなどを敷くのもおすすめです。
2.無理強いは禁物
子どもが乗り気でないときに無理やりやらせようとすると、運動そのものが嫌いになってしまうかもしれません。楽しいと思えるタイミングで行いましょう。
3.「できた」を具体的に褒める
結果だけでなく過程も具体的に褒めることが大切です。難しいときは、平均台の上を歩くではなくまたぐだけ、ボールを投げるではなく転がすだけのように、絶対に成功できるレベルまでスモールステップ化して、自信をつけさせてあげましょう。
運動療育は施設利用と家庭どちらが良いか
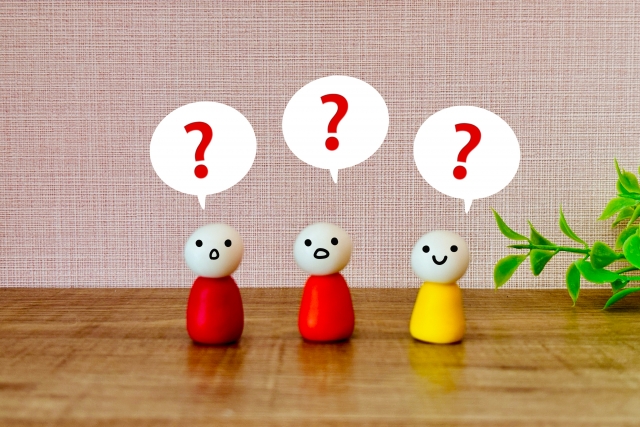
家庭でできる遊びを取り入れつつも、「うちの子には専門的な療育が必要なのだろうか」と迷うこともあるかもしれません。
家庭での取り組みと専門的な療育の違い
家庭は、子どもが最もリラックスできる場所であり、日常生活の中で自然に反復練習ができる良さがあります。 一方、専門的な療育施設では、専門知識を持ったスタッフが子どもの特性を客観的に評価し、その子に合ったプログラムを提供してくれます。
単に「できる・できない」を見るのではなく、身体の使い方のクセや姿勢、視線の動きなどを細かく分析し、苦手さの根本的な原因を探り当てることができるのが専門家の強みです。また、家庭にはない大型の器具を使ったダイナミックな活動ができるのも大きなメリットです。
専門施設の利用をおすすめするケース
・家庭での関わり方に限界を感じている
・運動の苦手さが原因で、園での集団活動に参加しづらくなっている
・「なぜできないのか」の原因がわからず、どうサポートして良いか悩んでいる
・専門家から療育を勧められた
・小学校入学を見据えて、着替えや給食などの身辺自立に向けた具体的な動作の練習をしておきたい
子どもの発達で心配なことはまず専門家へ相談
子どもの発達について少しでも不安がある場合は、一人で抱え込まず、専門家に相談してみることをおすすめします。自治体の子育て支援センターや保健センター、または近くの児童発達支援事業所などに相談するとよいでしょう。
専門家の視点が入ることで、子どものできない理由が明確になり、具体的な関わり方が見えてくるはずです。
個別療育はステラ幼児教室
療育施設には、集団で行うところと、マンツーマンの個別療育を行うところがあります。 運動が苦手な子どもは、集団の中では萎縮してしまい、十分に身体を動かせないこともあります。また、感覚過敏がある子にとっては、集団の音や動きが気になって集中できないことも少なくありません。
ステラ幼児教室のような個別療育では、その子のペースに合わせてじっくりと課題に取り組むことができます。
ステラ幼児教室では一人ひとりの特性に合わせてきめ細かくプログラムを作成し、「できた!」という成功体験を積み重ねていきます。
また、目と身体の協応動作が苦手な子どもに対して特化した「ビジョンクラス」があることもステラ幼児教室の特長のひとつです。
ビジョンクラスは少人数のクラスで、より目と身体を使ったプログラムを行います。
★ビジョンクラスについては詳しくはこちら。
運動療育についてのまとめ
療育における運動は、単なるスポーツの練習ではなく、遊びを通して心と身体の発達の土台を作るための大切なアプローチです。
全身を使う「粗大運動」と手先を使う「微細運動」は、相互に関連し合いながら子どもの成長を支えています。
ご家庭で楽しく身体を動かす遊びを取り入れることも大変効果的ですが、もし子どもの発達に不安を感じたら、専門機関に相談してみてください。
その子に合った適切なサポートを受けることで、子どもの可能性は大きく広がっていきます。
ステラ幼児教室では随時見学受付中
名古屋市、大阪市に展開している児童発達支援事業所、ステラ幼児教室では随時見学を行っています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。
お気軽にご相談ください。














