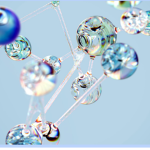保護者の方の中には、発達が気になるお子さんが幼稚園や保育園などを卒園後、
「小学校に行って、お友達との関わりは大丈夫だろうか?」「勉強についていけるだろうか?」
など不安や心配を抱えている声がよく聞かれます。
しかし、不安や心配を抱えるものの、どのようにしたらよいのかわからない保護者の方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、発達が気になる子どもの就学先にどのようなものがあるのか、また、就学相談とは何か、その目的などについて、お伝えします。
就学相談とは何か?目的・流れ・内容を解説
就学相談とは何?
就学相談とは、発達が気になる年長のお子さんの小学校入学前に、お子さんに合う学びの場(支援学級、通級、支援学校など)を決めるために行われる話し合いや相談のことを言います。
お子さんが年長になった4月頃から相談の受付が始まり、受付窓口は通学校区の小学校や教育委員会の場合や、園を通じて申し込む場合など市町村により様々です。
通っている園の先生に尋ねたり、お住まいの市町村の教育委員会などに問い合わせたりするとよいでしょう。

※参考 大阪市では通学校区の小学校が窓口になっています。
就学相談の目的は何?
就学先については、お子さんの障がいの状態のみで判断するのではなく、一人一人の教育的なニーズや学校や地域の状況、保護者や専門家の意見等も含め総合的に検討し、決定されることになっています。
つまり、お子さんがよりよい環境で教育を受けられるようにすることが、就学相談の大きな目的となります。
また、就学先について具体的な情報を得ることができるのはもちろんですが、就学先にお子さんのことを知ってもらう良い機会でもあると思います。
就学相談の流れと内容~申し込みから就学先の決定まで
就学相談についての通知はありませんので、就学についての相談を希望する場合は、保護者の方からの申し込みが必要です。
お子さんが年長になったらできれば早めに(夏休みごろまでに)申し込む方がよいでしょう。

面談では、お子さんの発達や障がいの状況、成育歴や家庭環境、教育や就学先に対する保護者の希望などが訊かれます。面談は複数回実施されることが多いです。

※参考 大阪市では就学支援シートに記入して提出できるようになっています。
学校見学を行っているところでは、実際に校区の学校の支援級や支援学校を見学したり、先生から話を訊いたりし、具体的にどのような支援が行われているのか、情報を得る機会になります。
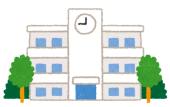
就学相談の担当者がお子さんの園に訪問し、お子さんの様子を観察し、担任の先生よりお子さんについての話を伺うことがあります。
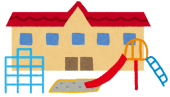
※②、③、④は順不同です。
教育委員会や専門家での話し合いによる方針と、保護者の方の意向をまとめ、最終的には11月~12月頃に決定します。

発達に課題がある子どもの就学先の選択肢は
先ほどは就学の流れについて見ていきました。
次に、発達に課題があるお子さんの就学先の選択肢としてあげられる、「通常学級」「支援級」「通級」「支援学級」。
その中で「支援級」「通級」「支援学級」について、その違いを詳しく見ていきます。
支援級とは
支援級(特別支援学級)とは、様々な障がいを持つお子さんや、学習上や生活上で困難な面を持つお子さんのために、小学校や中学校が設置している少人数の学級のことを言います。
支援級の1クラスの上限定員は8人であり、お子さんの課題やニーズに合わせた学習内容や支援を受けることができます。
基本的な教科学習を支援級で受け、給食や一部の学習を通常学級で受ける場合や、通常学級で授業を受け、必要な教科のみ支援級の先生が入って援助する場合など、お子さんのニーズや学校の体制、住んでいる地域によって取られる支援方法は異なります。
就学相談で、具体的に話を聞いたり、学校見学に行ったりし、お子さんの学校の支援級について情報を得るとよいでしょう。

通級とは
通級(通級指導教室)とは、通常学級に在籍し、基本的な教科学習や給食などは通常学級で受け通級指導の時間のみ、そのお子さんに合わせた指導を受ける学級のことを言い、小学校や中学校等に設置されています。
すべての学校で通級が設置されているわけではなく、お子さんの通う学校に通級がない場合は、通級の時間のみ他の学校に通うことになり、その時は保護者の送迎が必要となります。
通級指導の時間は週1~2時間などと限られているので、基本的に通常学級で授業を受け、学校生活を通常学級で過ごすことができ、学習障がいや言語障がいなどにより一部の特別な支援が必要なお子さんが通級に向いているかと思います。
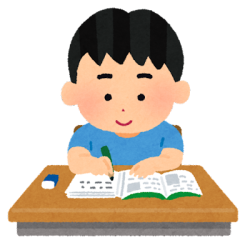
支援学校とは
支援学校(特別支援学校)とは、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がいなど様々な障がいを持つお子さんを対象とした学校です。
個々に合わせて学習内容が決められ、身辺自立や学習上や生活上の困難に対する支援が行われています。
地域の学校とは違うカリキュラムで授業が行われています。
幼稚部から高等部まであり、幼稚部は支援学校に行き、小学校は地域の小学校に行くお子さんもいれば、高等部から支援学校に通うお子さんなど様々です。
1クラスの人数は少なく、小学部と中学部は6人、高等部は8人、障がいを2つ以上併せ持つお子さんのみの学級は3人が基準です。
住む地域により通学できる学校が決まっており、校区が広いため、通学バスが出ている学校も多いです。
就学に向けて、学校見学や学校体験などを実施することが多いため、その時に実際に学校の様子を見学し、情報を得るとよいでしょう。

就学相談についてよくある質問
Q.1就学相談を受けた後、どのように就学先は決定するのですか?
就学相談の流れでお伝えしたように、面談や園への訪問や、就学時健診などを経て、お子さんのニーズや必要な支援内容を踏まえて検討されます。
具体的には、専門家などを含めた教育支援委員会で審議され、お子さんや保護者の方の意向を含め、最終的には市町村の教育委員会で決定されます。
保護者の方の意向も重要視されるため、学校見学や、就学先についての情報を集め、お子さんやご家族で話し合い、就学先を検討されることをお勧めします
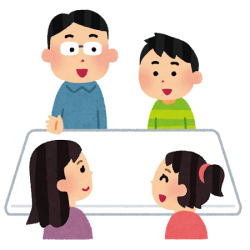
Q.2就学した後、転学はできるのですか?
就学後もお子さんの育ちに合わせて柔軟に学びの場を見直すことができると定められているため、転学は可能です。
例えば、小学校の支援級に在籍していたお子さんが、小学校の中学年頃に支援学校に転学したケースなどがあります。
しかし、地域によって転学の手続きが難しい場合や、時間を要する場合がありますので、できるだけ、就学相談でお子さんに合う環境をじっくり検討し、決めることが重要だと思われます。
転学を考えられる時には、年度途中で転学は難しいため、余裕をもって学校に相談することが望ましいです。
Q.3就学相談を受けると特別な目で見られないか心配です
就学相談を受けたことを周りの人に公表されることはありません。就学相談を受けても通常学級のお子さんもいますし、入学前にお子さんの気になるところを学校に知ってもらう機会にもなります。
近年はこどもの数は減っていますが、通常学級で支援が必要なお子さんや、支援級に在籍するお子さんの数は増えてきています。
通常学級でも視覚支援などわかりやすい授業の工夫がされ、担任の先生の配慮はあります。
しかし、担任の先生は一人で何十人ものお子さんを見ているので、なかなか支援級のように手厚い支援を受けることは難しいと思われます。
支援級の先生のサポートは、支援級に所属していないと受けることができません。
特に小学校は6年間という長い期間であり、お子さんが大きく成長する大切な時期でもあります。
集団の一斉指示についていけるのか、通常学級での流れや授業についていけるのかなど、お子さんに支援が必要かどうか、また、お子さんにとってどの環境が合うのかを軸に考えてみられてはいかがでしょうか。

Q.4支援級を選ぶメリット、デメリットはありますか?
Q.3でお話ししたように、お子さんに合わせた支援が受けやすいということ、支援級は少人数なので細やかなサポートを受けやすい点が支援級に入るメリットです。
逆にデメリットは、支援級は通常学級と評価の仕方が異なるため、内申点が大きく関わる公立高校の受験が難しくなることがあることで、その点を憂慮され、中学校は普通学級を選ぶ方もおられます。
しかし、近年は公立高校や私立高校以外にも、専修学校や、サポート校と連携した通信制高校など、様々な進路先が増えているので、お子さんやご家族で話し合い、お子さんに合った納得できる就学先を選ばれるとよいでしょう。
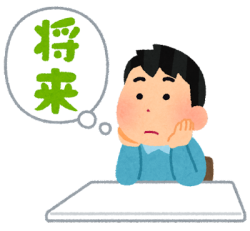
★ステラ幼児教室のある名古屋市の就学相談についての詳細ページ
★ステラ幼児教室のある大阪市の就学相談についての詳細ページ