はじめに
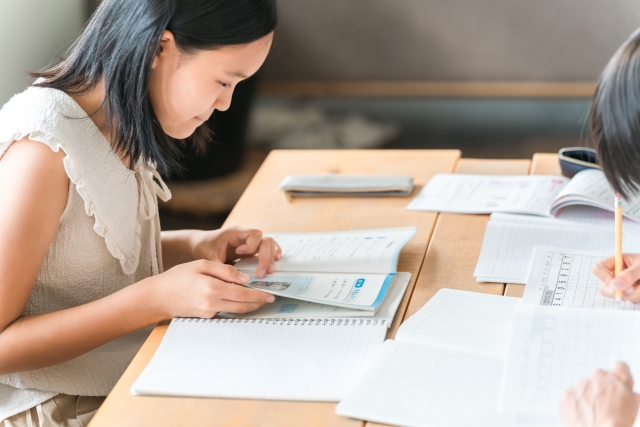
「またお友達とケンカして帰ってきた…」 「どうして、うちの子だけうまく輪に入れないんだろう…」 「仲良くしなさいって、毎日言っているのに…」
小学生の息子さんの友達関係を見て、このように心を痛めていませんか?特に男の子は、自分の気持ちを言葉にするのが苦手だったり、つい手が出てしまったりして、トラブルに発展しやすいものです。
頭ごなしに叱ったり、ただ「仲良くしなさい」と繰り返したりしても、状況はなかなか改善しません。なぜなら、お子さん自身も「どうすればよかったのか分からない」と困っていることが多いからです。
そんな悩みの解決の糸口となるのが、SST(ソーシャルスキルトレーニング)という考え方です。
この記事を読めば、SSTの基本から、ご家庭で今日から始められる具体的な実践方法までが分かります。お子さんが友達と円滑な関係を築き、学校生活を笑顔で過ごすためのヒントがきっと見つかるはずです。
SSTトレーニングとは?社会生活で必須の対人関係スキルを育む
SSTは社会でうまくやっていくための練習

SSTとは、Social Skills Training(ソーシャルスキルトレーニング)の略です。日本語に直訳すると「社会技能訓練」となりますが、決して難しいものではありません。
簡単に言えば、気持ちの上手な伝え方、友達との関わり方、トラブルの避け方といった、社会生活を送る上で欠かせない対人関係のスキルを、具体的な練習を通して身につけていくことを指します。
自転車の乗り方を何度も練習するように、人との関わり方も、練習することで少しずつ上手になっていくのです。
一方的に叱るしつけ」とSSTの決定的な違い
多くのお母さんが、「うちの子の友達トラブルは、私のしつけが悪いせいかもしれない」とご自身を責めてしまいます。しかし、SSTは従来のしつけとは少し考え方が異なります。
従来のしつけ
「ダメ!」「やめなさい!」と、望ましくない行動を制止することが中心。
SST
「じゃあ、どうすれば良かったんだろう?」と、望ましい行動を一緒に考えて練習することが中心。
例えば、お子さんが友達のおもちゃをいきなり取ってしまった場合、「取り上げたらダメでしょ!」と叱るのがしつけです。 一方SSTでは、「おもちゃが使いたかったんだね。そんな時は『かして』って言ってみようか」と、具体的な代替案を教え、練習するところまで行います。
SSTは、お子さんのできなかったことを責めるのではなく、「こうすればできる」という自信と具体的なスキルを育む、ポジティブなアプローチなのです。
なぜ今、小学生にSSTが必要?友人関係が複雑になる時期
幼児期と比べ、小学生の人間関係はぐっと複雑になります。1対1だけでなくグループでの関わりが増え、言葉の裏を読んだり、相手の気持ちを推し量ったりする場面も多くなります。
この大切な時期に、対人関係でつまずいた経験が続くと、「どうせ僕なんて…」と自己肯定感が下がってしまうことにも繋がりかねません。
小学生のうちにSSTを通して成功体験を積み重ね、対人関係の基礎的なスキルを身につけておくことは、中学校以降のより複雑な人間関係や、将来の社会生活の大きな土台となるのです。
なぜ?小学生が友達とトラブルを起こしてしまう3つの理由

お子さんが友達とトラブルを起こしてしまうのは、決して性格が悪いからでも、親の育て方のせいでもありません。多くの場合、子どもが元々持っている発達の特性が関係しています。ここでは、小学生によく見られる3つの理由をご紹介します。
理由1 自分の気持ちを言葉で表現するのが苦手
嬉しい、楽しいといったポジティブな感情は表現できても、嫌だ、やめてほしい、悲しいといったネガティブな気持ちを適切な言葉にするのが苦手な子がいます。言葉にできないモヤモヤした気持ちが、相手を押したり、物を投げたりといった、衝動的な行動として現れてしまうのです。
理由2 相手の気持ちや場の空気を想像するのが苦手
自分の視点から物事を見る力が強く、相手の立場に立って「これを言ったらどう思うかな?」「今これをしたら迷惑かな?」と想像するのが難しいケースです。悪気は全くないのに、相手が嫌がっていることに気づかずしつこくしてしまったり、冗談のつもりが相手をひどく傷つけてしまったりします。
理由3 気持ちのコントロールが苦手
ゲームで負けた時の「悔しい!」という気持ちや、自分の思い通りにならない時の「腹が立つ!」という感情の波をうまくコントロールできず、大声を出したり、癇癪(かんしゃく)を起こしたりしてしまいます。気持ちの切り替えが苦手で、一度パニックになると、周りの声が耳に入らなくなってしまうこともあります。
これらの特性は、発達障害やその傾向(グレーゾーン)があるお子さんによく見られますが、多くの子どもたちが持っている発達途中の姿でもあります。大切なのは、その特性を理解し、言葉や行動で具体的に教えてあげることです。
家庭でできる!SSTトレーニングの具体的な4ステップと場面別の実践例

SSTは専門機関だけでなく、ご家庭でも実践できます。ここでは、基本的な進め方と、小学生男子によくある場面別の実践例をご紹介します。
まずは基本の4ステップを覚えよう
SSTを家庭で進める際は、以下の4ステップを意識するとスムーズです。
教示(お手本を見せる)
まず、親が「こんな時、こう言ってみるといいよ」と具体的なセリフや行動のお手本(モデリング)を見せます。
教習(ロールプレイング)
次に、お子さんが実際にやってみます。親が友達役になるなど、役割を交代しながら、寸劇のように練習(ロールプレイング)します。
称賛(フィードバック)
上手にできたら、「今の言い方、すごく良かったよ!」「声の大きさがちょうどいいね!」など、具体的に褒めてあげます。うまくいかなくても決して責めず、「もう一回やってみようか」と励まします。
課題(実際の場面で試す)
「今度、公園で同じような場面があったら、今日練習したみたいに言ってみようか」と、実際の生活で試してみる約束をします。
【場面別】小学生男子のよくあるトラブル実践例
ケース1 遊びの輪にいれて、が言えない
友達が楽しそうに遊んでいる輪に、どう声をかけていいか分からず、黙って周りをウロウロしたり、いきなり輪に入って邪魔をしてしまったりするケースです。
お母さん
「みんなと遊びたかったんだね。でも、黙って入るとみんなビックリしちゃうかも。一緒に『いれて』の練習をしてみようか。お母さんが〇〇(息子の名前)役をやるから、見ててね」
お手本(母)
(友達役の息子に近づき)「ねえ、何してるの?面白そうだね!僕も混ぜて!」
ロールプレイング
次はお子さんの番です。「今のママみたいに言えるかな?」と促し、練習させます。上手に言えたら「すごくいい感じ!それならみんな、いいよって言ってくれるよ!」と思いっきり褒めてあげましょう。
ケース2 おもちゃをかして、が言えずに取ってしまう
友達が使っているおもちゃが欲しくなり、言葉で伝えられずにいきなり奪い取ってしまうケースです。
お母さん
「あのおもちゃで遊びたかったんだね。でも、いきなり取られたら悲しい気持ちになるよね。『かして』って言う練習をしてみない?」
お手本(母)
「そのおもちゃ、かっこいいね。今使ってる?もし終わったら、次にかしてほしいな」
ロールプレイング
ポイントは「今使ってる?」と相手の状況を確認するワンクッションを入れることです。「順番を待つ」という練習にもなります。お子さんが練習できたら、「相手のことも考えられて偉いね!」と褒めてあげましょう。
ケース3 ゲームで負けると癇癪を起こす
対戦ゲームなどで負けると、悔しさのあまり泣きわめいたり、コントローラーを投げたりしてしまうケースです。
お母さん
「負けたらすっごく悔しいよね。その気持ちは分かるよ。でも、物に当たるともっと嫌な気持ちになっちゃう。悔しい気持ちが出てきたら、一回コントローラーを置いて、深呼吸を3回してみようか」
クールダウンの練習
これはロールプレイングというより、気持ちのコントロール方法を具体的に教えるSSTです。「悔しい!」→「深呼吸」という行動のパターンを一緒に練習します。
終わりの言葉の練習
「悔しかったけど、楽しかったね!」「また対戦しようね!」など、気持ちを切り替えるポジティブな言葉を教えてあげるのも効果的です。
SSTトレーニングの効果を高める3つのコツと市販教材

家庭でのSSTをより効果的にするために、以下の3つのコツを意識してみてください。
コツ1 スモールステップでできた!を増やす
最初から完璧を目指す必要はありません。「友達に挨拶ができた」「順番を一つだけ待てた」など、ほんの小さな「できた!」を見つけて、大げさなくらい褒めてあげましょう。小さな成功体験の積み重ねが、お子さんの自信と次への意欲に繋がります。
コツ2 親子で楽しみながらゲーム感覚で取り組む
「練習」「勉強」という雰囲気になると、お子さんは構えてしまいます。「ヒーローごっこ」「お店やさんごっこ」のように、SSTを遊びの延長線上で楽しむ工夫をしてみましょう。親子で笑いながら取り組むことが、継続の秘訣です。
コツ3 市販のSSTカードや教材も上手に活用する
家庭でのSSTをサポートしてくれる便利なツールもたくさんあります。「こんな時どうする?」というお題が書かれた場面カードや、様々な気持ちが描かれた表情カード、ソーシャルスキルを学べるかるたやボードゲームなどです。こういった教材を使うと、テーマが明確になり、親子でより楽しく取り組むことができます。書店やインターネットで探してみてください。
家庭だけでは難しい…そんな時は専門家を頼る選択肢も

ご家庭でのSSTは非常に有効ですが、続けていくうちに難しさを感じることもあります。
●お手本を見せようにも、どうすればいいか分からない場面がある
●親子だけだと、客観的な練習がしにくい
そんな時は、決して一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを検討してみてください。
放課後等デイサービスや療育機関、個別指導塾などでは、ソーシャルスキルトレーニングの専門家がお子さんの特性を客観的に分析し、その子に合ったプログラムを組んでくれます。
また、同じような悩みを持つ同年代の子どもたちとのグループワークを通して、家庭だけではできない、より実践的なコミュニケーションスキルを安全な環境で学ぶことができます。
お子さん一人ひとりの特性やペースに合わせた専門的なソーシャルスキルトレーニングに関心のある方は、ぜひ一度、ステラ個別指導塾のサイトをご覧ください。学校生活での困りごとを抱えるお子さんが、安心して学び、自信を育むための環境が整っています。
SSTトレーニングについてのまとめ

今回は、小学生の友達トラブルを解決するSST(ソーシャルスキルトレーニング)について解説しました。
●「叱る」のではなく、「どうすれば良いか」を一緒に考えるアプローチ
●トラブルの背景には、子どもの発達の特性がある
●SSTは、お手本、ロールプレイング、称賛のステップで家庭でも実践できる
●家庭での実践が難しい場合は、専門家を頼ることも大切
SSTは、一度やればすぐに効果が出る魔法ではありません。自転車の練習と同じで、何度も転びながら、少しずつ上達していくものです。
結果を焦らず、お子さんの小さな「できた!」をたくさん見つけて褒めてあげてください。そして何より、お母さん一人で悩みを抱え込まないでくださいね。
お子さんが社会生活を送る上で大丈夫か不安に感じたら、ぜひSSTの活用を検討してみてください。
また、一人では難しいと感じたら、遠慮なく専門家の力を借りてくださいね。













