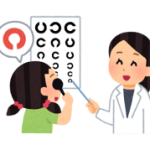小学校入学を前に実施される「就学時健診」は、子どもの健康や発達の様子を確認し、安心して学校生活を始められるようにするための大切な機会です。しかし、初めての場に戸惑ったり、どのように準備すればよいのか不安に感じたりする保護者の方も少なくありません。
この記事では、健診当日の流れや持ち物、子どもへの声かけや事前にできる工夫などを整理しました。ポイントを押さえて落ち着いて健診に臨み、入学への一歩を前向きに迎えられるようにしていきましょう。
就学時健診とは?

就学時健診(就学時健康診断)とは、学校安全保健法に基づき実施されるもので、翌年に小学校へ入学予定の子どもを対象に、市区町村の教育委員会が実施する健康診断です。子どもにとっては、来年度から同じ教室で学ぶ仲間と出会う最初の機会にもなります。
就学時健診の主な目的は次の通りです。
・子どもと保護者が健康状態を把握し、関心を持つきっかけとする
・疾病や異常を早期に発見し、入学までに治療や支援を受けられるようにする
・学校生活に必要な発達や適応の状況を確認し、必要な支援につなげる
・健診結果を家庭や学校で共有し、学級編成や支援体制に役立てる
単に健康面の診断をすることが目的ではなく、子どもが安心して新しい環境で学校生活を始められるようにすることが、就学時健診の大きな役割です。
いつ・どこで就学時健診は行われる?
就学時健診は、市区町村の教育委員会が主体となり、入学の数か月前に行われます。
就学時の健康診断マニュアル(平成29年度改定)によると、一般的には10月から11月頃に実施されることが多く、保護者のもとには9〜10月ごろに案内通知が届きます。健診の結果については、11月から1月ごろに事後通知されることになっています。
会場は、基本的に お住まいの学区の小学校 です。ただし、自治体によっては、体調不良や予定が合わない場合に別日程や別会場を案内することもあります。詳細は通知に記載されるので、必ず確認しましょう。
就学時健診ではどんなことをするの?

就学時健診では、体の健康状態以外にも、学校生活に向けた準備のためにさまざまな確認が行われます。ここでは当日の流れや検査の内容、保護者や子どもへどんな質問をされるか解説します。
就学時健診の流れ
就学時健診の流れは自治体や学校によって少しずつ異なりますが、一般的には次のような形です。
1.受付
通知に記載された時刻に会場へ行き、受付を済ませます。
2.健診
身体測定や視力・聴力などの基本的な健診が行われます。親子で一緒に健診を回るケースと、教員や高学年の児童に付き添われて子どもだけで回るケースがあります。
3.保護者向け説明
親子で分かれる場合、保護者は別室で、入学説明会や学童保育の案内、PTA活動の概要などの説明を受けるのが一般的です。この場で提出を求められる書類が配布されることもあります。
4.面接
教員が子どもと簡単にやり取りをし、言葉や理解の様子を確認する「面接」が行われる場合があります。
主な検査内容例
就学時健診では、子どもの身体や発達の状態を幅広く確認します。内容は自治体によって多少異なりますが、一般的には次のような検査が行われます。
<健康に関する検査>
内科健診:全身の健康状態を確認し、栄養状態や発育の様子、内科的な疾患の有無などを見ます。
耳鼻咽喉科健診:耳・鼻・のどに病気がないかを調べます。器具を使うため、苦手なお子さんには事前に伝えておくと安心です。
眼科健診・視力検査:眼科医が目の病気の有無を確認し、ランドルト環を使って視力を測ります。口頭で答えにくい場合は、指差しでも対応できます。
聴力検査:流れる音が聞こえたらボタンを押して答える方式です。ヘッドホンを装着して検査する場合が多いです。
歯科健診:虫歯や歯ぐきの状態、歯並びなどを確認します。
その他:皮膚の病気や、必要に応じて発達の状態を確認することもあります。
<面接や相談に関するもの>
子どもと先生のやり取り:自己紹介や簡単な会話を通して言葉や理解の様子を確認します。
保護者同席の面談:子どもの家庭での様子を伝える機会となる場合があります。
アレルギー面談:食物アレルギーなどがある場合、健診時や後日改めて面談を行い、入学後の対応を相談するケースもあります。
保護者や子どもに聞かれること
就学時健診で子どもや保護者にやり取りがあるかどうかは、自治体や学校によって異なります。面談が設けられている場合には質問されることがありますが、面談がなく、検査中心に短時間で進むケースもあります。ここでは、面談がある場合に想定される質問や、面談以外でやり取りがある場面について解説します。
子どもとのやり取り
面談がある場合は、次のような簡単な質問を通して受け答えや言葉や理解の様子を確認することがあります。
「お名前を教えてください」
「どこの幼稚園(保育園)に通っていますか?」
「園ではどんな遊びが好きですか?」
面談がない場合でも、検査の場で「右手を出してね」「ここに座ってね」といった声かけがあるため、会話の延長のようにやり取りが行われます。
保護者への確認
保護者に対しては、医師や学校側から以下のような点について確認されることがあります。
子どもの健康状態や既往歴
例:持病・通院歴・アレルギーなど
生活面で気になること
例:友達との関わり、生活習慣など
就学に向けての相談(必要に応じて)
就学に関して不安がある場合は、当日に軽く声をかけて相談できることもありますが、より詳しい話をしたいときは前もって教育委員会や学校に連絡しておくと、個別に対応してもらえることが多いです。
学校側が見ているポイント
就学時健診では、検査そのものだけでなく、子どもが安心して学校生活を始められそうかどうかという視点でも様子を見守っています。例えば、次のような点が参考にされます。
・子どもの態度や様子
・先生の声かけや指示にどの程度反応できるか
・集団の中での振る舞いや、保護者との関わり方
検査が不安で泣いてしまったり、部屋に入れなかったり困ったときにはサポートできるよう職員が体制を整えていることが多いです。こうした観察は、入学後にどのようなサポートがあれば安心して過ごせるかを考える手がかりにもなります。
「引っかかるケース」や対応は?就学時健診で確認されること

就学時健診では、病気や異常の有無を確認するためにさまざまな検査が行われます。状態によっては指摘されることもありますが、多くは虫歯や視力・聴力の低下など、比較的身近なものです。早めに受診や支援につなげることで、入学前に改善や準備ができるケースも多いので、必要以上に心配しなくても大丈夫です。
引っかかる可能性があるケース
就学時健診で「指摘あり」とされるのは、必ずしも「問題がある」という意味ではなく、「今後注意深く見守りましょう」という意味合いで伝えられると考えておくとよいでしょう。通知の仕方は自治体によって異なり、当日に伝えられることもあれば、後日通知書で案内されることもあります。
主に確認されるポイントは次のようなものです。
健康面
・身体的な健康状態
・視力や聴力の低下(遠視・乱視・難聴など)
・虫歯やかみ合わせの不良
・肥満ややせ、内科的な疾患の疑い
これらの状態で指摘された場合、専門医での再検査や治療につなげるよう案内されることがあります。ただし、視力検査で要領を得られずうまく答えられない、歯科健診で怖くて口を大きく開けられない、乳歯だから経過を見ればよいとされるという、発達段階上仕方のないケースもよく見られます。
発達や行動の面
・言葉の発音が不明瞭、語彙が少ない
・落ち着きがなく検査に集中できない
・集団での行動や指示理解に難しさが見られる
その他の確認点
皮膚疾患や慢性的な持病(喘息・食物アレルギーなど)
こうした指摘は「入学できない」ことを意味するのではなく、むしろ入学前に気づいておくことで、学校生活を安心して始められるようにするためのサポートの一環です。
引っかかった場合の対応
就学時健診で何らかの指摘を受けると、多くの保護者は驚きや不安を感じるかもしれません。しかし、就学時健診は子どもや家庭を否定するものではなく、入学後に安心して学校生活を送るための準備のひとつです。必要な支援につなげる大切なきっかけと捉えるとよいでしょう。
基本的な捉え方
✓指摘があっても「問題」と捉えすぎない
就学時健診は「子どもの状態を確認して、必要があれば整えていく」ための場です。虫歯や視力などは治療で改善できることが多く、発達や行動に関する指摘も「入学後の配慮を考えておきましょう」という意味合いがあります。
健診をきっかけに「子どもの成長を支える準備ができる」と考えると安心です。
✓早めの受診・相談と連携が安心につながる
健診で指摘を受けたら、そのままにせず対応しておくことが大切です。健康状態に関することであれば、小児科や眼科・耳鼻科・歯科などの医療機関を早めに受診して確認しましょう。
発達や行動面で気になることがある場合は、教育委員会の就学相談窓口や発達支援センターなどに事前に相談しておくと、入学に向けた準備や支援につながります。
また、入学予定の学校とも情報を共有しておくと、入学後に必要な配慮を受けやすくなり、子どもが安心して学校生活をスタートしやすくなります。
主な相談先や支援機関
就学時健診で指摘を受けた場合、どこに相談したらよいのか迷う方も多いでしょう。内容によって相談先は異なりますが、以下のような窓口や機関が利用できます。ひとりで抱え込まず、必要に応じて専門家や支援機関につながることで、入学準備を一緒に整えていくことができます。
✓小児科・眼科・耳鼻科・歯科などの医療機関
虫歯や視力・聴力の低下、内科的な健康課題など、治療や検査が必要なときの基本の相談先です。健康状態によっては入学後の学校生活に影響することもあるため、早めに受診して整えておくと安心です。
✓市区町村の教育委員会(就学相談窓口)
「どのような学び方が子どもに合うか」を一緒に考えてくれる窓口です。特別支援学級や通級指導教室などの利用を検討したいときに役立ちます。健診を通して就学後の生活に不安が出てきた場合や、支援の必要性を感じるときは、できるだけ早めに教育委員会の就学相談窓口に連絡しておくと安心です。時期によっては相談が集中することもあるため、余裕をもって動くとスムーズです。
✓通学予定の小学校(養護教諭・特別支援コーディネーターなど)
入学前から学校に伝えておきたい配慮がある場合の相談先です。アレルギー対応や座席の位置など、具体的に学校生活で必要な支援を事前に話し合うことができます。
✓発達障害支援センターや児童相談所
発達や行動面で気になることがあるときに頼れる機関です。医療や教育の両面から支援を検討してもらえるため、困りごとが複合的な場合でも相談しやすいのが特徴です。
自治体によって設置状況や窓口の名称が異なるため、お住まいの地域の公式サイトで確認しておくと安心です。
✓児童発達支援事業所
就学前の子どもを対象に、発達を促すプログラムを受けられる施設です。保護者が直接相談・申し込みできるので、言葉や行動、対人関係など幅広い面でサポートを受けられます。
入学前から少しずつ準備を整えたいときに活用できる身近な相談先のひとつです。
<h2 id=”11″安心して就学時健診を迎えるための事前準備

初めて迎える就学時健診は、子どもにとっても保護者にとっても大きな行事です。当日の流れや内容が分かっていても「しっかり検査を受けられるかな」と心配になることもあるでしょう。当日を落ち着いて迎えるために、事前に準備しておくとよいポイントを紹介します。
持ち物や服装
就学時健診の持ち物は、自治体から届くお知らせに記載されています。まずは通知書をよく確認して準備しましょう。一般的には次のようなものが必要になります。
・就学時健診の通知書や受診票
・母子健康手帳(予防接種や既往歴の確認に使われる場合があります)
・筆記用具
・室内履き(保護者用と子ども用)と靴を入れる袋
・水筒(必要に応じて)
内科健診で上着を脱ぐこともあるので、子どもの服は着脱しやすいものがおすすめです。寒さが気になる時期なので、体温調節できる羽織りものを持参するとよいでしょう。
髪が長い子は、身長測定に支障が出ないよう、頭の上ではなく下の方で結んでおくとスムーズです。
保護者は特別な服装は必要なく、普段着で問題ありません。動きやすさを意識しつつ、学校内が冷える場合もあるので、上着や防寒対策をしておくと安心です。
子どもへの前向きな声かけ
初めての場所や人に会う就学時健診は、楽しみにしている子どもでも緊張したり不安になったりすることがあります。保護者があらかじめ内容を伝えておくことで、安心して臨めることが多いです。
たとえば以下のような声をかけてあげましょう。
「小学校に元気に通えるように、目や耳を調べるよ。痛くないから大丈夫だよ」
「一緒に行くから心配しなくていいよ」
「今日は初めて小学校に行けるね。どんな教室かな、楽しみだね」
前向きな声かけで気持ちを和らげることで、子どもにとっても健診が「ちょっと楽しみな体験」になります。
家でできる練習
就学時健診では、普段の生活ではあまり経験しない検査ややり取りがあります。突然の体験に戸惑う子も多いため、事前に検査の内容や目的を簡単に伝え、家でちょっとした練習をしておくことが安心につながります。
検査の疑似体験
次のような方法で疑似体験をしておくと、各検査に向けた心の準備ができます。
視力検査
「Cの形」を描いて「切れ目はどっちかな?」と指さしで答える。
片目ずつ隠す練習をする。
聴力検査
音が聞こえたら手をあげるルールで遊ぶ。
ヘッドホンをつける練習をする。
内科健診
聴診器のおもちゃを使って慣れておく。
耳鼻科
「耳や鼻の中をちょっと見るよ」と事前に体験しておく。
「やったことある!」という感覚があると、当日もリラックスしやすくなります。
事前に確認しておきたいこと
学校によっては先生との面談やクイズ形式の発達検査が行われることもあります。そのため、日常の中で次のようなことも意識しておくと安心です。
・一人で教室に入れるか
・集団の中に入れるか
・音に敏感さがないか(大きな音が苦手など)
・トイレのこだわり(学校のトイレを使えるか)
・短時間でも座って先生の話を聞けるか
不安が強いお子さんには、検査の流れを事前に説明して見通しを持たせることも有効です。「聴診器でおなかの音を聴くよ」「お名前を言うだけだよ」と伝えておくと、安心感につながります。
就学時健診に関するよくある質問
就学時健診は子どもにとっても保護者にとっても初めての体験です。そのため「欠席したらどうなる?」など、さまざまな疑問や不安を持つ方も少なくありません。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。事前に知っておくことで、当日を落ち着いて迎えやすくなります。
当日行けなかったらどうなるの?
体調不良や家庭の都合で指定日に健診を受けられない場合は、まずは案内に記載されている入学予定の小学校へ連絡しましょう。その後の対応は自治体によって異なります。
一般的なケースとしては、次のような対応がとられることがあります。
・別の日程に振り替えて受けられる
・他の学校で実施される健診に参加する
・個別に病院を受診して診断書を提出するよう案内される
中には「就学時健診は義務ではないため、未実施のままでも入学に支障はない」としている自治体もあります。病院受診の場合は歯科・内科・眼科・耳鼻科などを個別にまわる必要があり、自費診療となる場合があるため注意が必要です。
子どもがうまく検査を受けられるか心配
発達の特性や体質などによって、「検査を最後まで受けられるかな」「嫌がって受けられないのでは」と心配になることもあるでしょう。事前にできる工夫としては、家庭での体験が有効です。例えば、視力検査ごっこや聴力検査ごっこをしておくと、当日の不安が軽くなります。
それでも不安がある場合は、あらかじめ健診予定の小学校に相談しておくと安心です。必要に応じて、配慮の仕方や当日のサポート体制を検討してもらえます。
また、就学時健診に関わる医師や教職員は、多様な子どもを見てきているため、当日も子どもの様子に合わせて対応してくれることも多いです。保護者だけで抱え込まず、事前の準備と相談を組み合わせて臨むとよいでしょう。
付き添いは親以外でもいい?
就学時健診は、原則として子どもの保護者が付き添います。ここでいう保護者は親に限らず、祖父母など日常的に子どもの養育に関わっている方も含まれます。子どもの健康や生活について必要事項を答えられるのであれば、親以外の保護者が同行しても問題ありません。
当日子どもの支援が必要な場合には、支援員や相談員などが保護者と一緒に付き添うケースもあります。
対応の可否や条件は自治体や学校によって異なるため、迷ったときは案内に記載されている学校へ確認してください。
就学時健診を安心して迎えるために

この記事では、就学時健診の流れや準備、当日によくある不安とその対応についてお伝えしました。持ち物の工夫や家庭での声かけ次第で、子どもも保護者も落ち着いて当日を迎えられます。
健診は子どもを評価する場ではなく、入学後に安心して学校生活を送れるようにするための大切なステップです。気になることがあっても一人で抱え込まず、学校や教育委員会、地域の支援機関に相談してみましょう。
もし現時点で不安を感じたら、児童発達支援事業所などのサポートを早めに活用してみてください。ステラ幼児教室では、遊び・ことば・体の動きなど幅広い面から、発達段階に合わせたマンツーマンの支援を行っています。ともに子どもの成長を支え、安心して入学の日を迎えましょう。