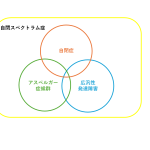高校卒業後にどこへ進むか、あるいは中学校卒業後に選択できる学校はどこか。中学や高校卒業後の子どもの進路に悩むことはありませんか?
進路先には、高校や大学の他に、専門学校や専修学校、高等専門学校もあり、名前は聞いたことがあるけれど、どんな学校か知らない保護者の方も多いでしょう。
そうした選択肢を理解しておくことは非常に重要です。特に「専門学校」「専修学校」「高等専門学校(高専)」といった学校は、似ている意味合いを感じさせるものの、その学習対象・入学資格・教育内容・認可制度・最終学歴などに違いがあります。
この記事では、まず「専修学校」と「専門学校」の関係と違いを整理し、次に「高等専修学校の仕組みについて触れ、「高等専門学校(高専)」も採りあげます。さらに、それぞれの進学制度・種類・学歴の取り扱いなどを含め、比較しながら解説していきます。
専修学校と専門学校の違いとは?

まず、「専修学校」と「専門学校」の違いや関係から確認しておきましょう。進路を考えるときに、それらの違いや関係を確認していることが重要です。
専修学校とは?
「専修学校」は、日本の学校教育法における学校種のひとつで、以下のように定義が定められています。
- 専修学校は、修業年限1年以上、年間授業数800時間以上、常時40名以上の学生が在籍している教育施設であることなど、一定の基準を満たす教育機関である必要があります。
- 専修学校は、その教育内容や対象者によって、3つの課程(「高等課程」「専門課程」「一般課程」)を設けうるとされています。
- 高等課程(高等専修学校):中学校卒業を入学要件とし、後期中等教育レベルの教育を行う課程。
- 専門課程(専門学校):高校卒業程度を入学要件とし、専門技術・技能教育を行う課程。
- 一般課程:入学資格を特に定めず、教養・教職課程・市民講座的な分野などを扱う課程。
このように、専修学校は、いわば「上記3つの課程を含めうる“枠”」を持つ学校だと考えられます。
専門学校とは?
では、専門学校はどういったもので、どのように専修学校と異なるのでしょうか。
- 専修学校の中でも、専門課程を設置している学校が「専門学校」と称することができます。つまり、すべての専門学校は専修学校ですが、すべての専修学校が専門学校というわけではありません。
- 専門学校に入学できるのは、基本的には「高等学校卒業またはこれと同等以上の学力がある者」などです。
- また、呼称上の注意点として、専修学校のうち専門課程を持つものは「専門学校」という名称を用いることが許されます。逆に、専門課程を持たない専修学校(たとえば高等課程のみ、あるいは一般課程のみ)には「専門学校」という名称を使ってはいけません。
- なお、専門学校には「認可校」と「無認可校」があります。認可校であれば公的な支援・奨学金制度の対象になることがありますが、無認可校や企業立校ではその扱いが異なることがあります。
このように、専修学校 と 専門学校の違いは、制度上・名称上の束ね方・条件との関係の違いととらえることができます。
両課程併設型の特例
実際には、多くの学校では高等課程と専門課程が併設されており、その場合、学校名は「○○専門学校」とすることが一般的です。こうした併設型の学校では、中学卒業者も高校卒業者も在籍しているケースがあります。
この点から、学校名だけを見て「専門学校だから高校卒しか入れない」と判断するのは誤りの場合があります。
高等専修学校とは?
先ほど触れた「高等課程(高等専修学校)」について、もう少し詳しく整理しておきます。
定義と役割
- 高等専修学校(専修学校高等課程)は、専修学校のうち、中学校卒業者を対象として設置される課程です。
- 高等専修学校では、職業教育・実践的技能教育を中核に据えながら、基礎的な普通教科も含む教育を行います。
- 高等専修学校の修業年限は通常3年が基本で、3年制のものが多いですが、科目や目的によってはそれ以上になることもあります。
- ある高等専修学校が「大学入学資格付与指定校」であれば、その卒業者は、高等学校の卒業者と同等の大学入学資格を持つと認定されます。そのため、大学受験を希望する場合、すべての高等専修学校卒業者が大学受験できるわけではなく、上記指定を受けている学校・学科であることが条件になります。
- 高等専修学校の卒業者は、制度上は高等学校卒業と同等扱いされることがあります。たとえば国家公務員試験などでの受験資格・初任給基準で「高校卒」として見なされることもあります。
高等専修学校卒業後の進路や処遇
- 高等専修学校の卒業者は、まず就職先を選ぶこともありますが、多くは専門学校(専修学校専門課程)や大学・短期大学などへの進学を選択します。
- また、高等専修学校で一定要件を満たす卒業者には、専門課程への進学だけでなく、大学入学資格相当扱いを受けられるものもあります(前述の大学入学資格付与制度)。
- 高等専修学校は、通常の高等学校とは異なる特色を持つ進路も提供できるため、より専門性志向・職業系教育志向のある生徒にとって選択肢となります。
このように、高等専修学校は、中学卒業後の進路として「職業教育・実践教育を重視しつつ、大学進学の道も残す」役割を担っています。
ステラ個別支援塾は、発達障害を持つ子どもの個別指導塾です。専門学校や専修学校への進学相談にも対応し、一人ひとりに合わせた学習の支援をしています。お気軽にご相談ください。
高等専門学校とは?

次に、記事タイトルに入っている「高等専門学校(高専)」について詳しく解説します。
定義と目的
- 高等専門学校(通称「高専」)は、実践的・創造的技術者を育成することを目的とした、5年一貫の高等教育機関です。
- 入学対象は中学校卒業者で、高校とは異なるルートで専門教育を受けることができます。
- 高専は全国に設置されており、国公立・公立・私立を含めて58校(令和6年度時点)存在します。
- 在学生数規模では、全体で約5万人以上が学んでいるというデータがあります。
高等専門学校の教育課程と特色
高等専門学校には、いくつかの特徴的な点があります。
5年一貫教育
-
- 入学から卒業まで5年かけて一般教科と専門教科を組み合わせたカリキュラムで学ぶ形式です。
- 商船学科などでは5年6か月の課程を置くところもあります。
- 初年度から工学・技術・理科系を主体とした科目が導入され、徐々に専門性を高めていく形です。
実験や実習重視
-
- 理論だけでなく実習・実験・現場実習を重視した教育が行われます。
- 実践的な技能を通じて技術者としての素養を身につけることを重視しています。
段階的進度や専門性深化
-
- 初期段階では一般教科(数学・理科・英語など)をバランスよく学びながら、後期ほど専門科目に比重を置く設計となっています。
- 最終学年にかけて、高度な専門科目・卒業研究などを行うことが一般的です。
進学の観点から見た各学校の長所と短所

次に、進学という観点から、専門学校・専修学校・高等専門学校を選ぶ際の長所と短所を考えてみましょう。
専門学校を選ぶ長所と短所
長所
- 学びたい専門分野を絞って、実践的・即戦力型の教育を早くから受けることができる
- 資格取得・就職支援に強い学校が多く、業界との連携が進んでいるケースもある
- 在学期間が比較的短いため、経済的負担を抑える可能性がある
- 編入制度を使えば、大学進学の道も確保できる
短所
- 大学卒と比べて最初から学術・理論教育や研究の幅が制限される可能性
- 編入・転学には大学側の受け入れ条件・単位認定条件の制約がある
- 一部の大学・職種では、大学卒を前提とした採用条件がある場合がある
専門学校を選ぶなら、「将来就きたい職業に直結する分野があり、その分野で実践力を早く身につけたい」という志向が強い人に向いています。
専修学校を選ぶ長所と短所
長所
- 中学校卒業後すぐに専門性を学べるため、早い段階でキャリアに向けた学びを始められる
- 高校とは異なる特色ある教育・技能教育が受けられる
- 大学入学資格付与指定校であれば、大学進学の選択肢もある
短所
- 指定校・課程でないと大学入学資格が付与されないことがある
- 専攻分野が限定されるため、途中で進路を変えたい場合、選択肢が狭まる可能性
- 一部の学校では設備・講師体制に差があるため、学校選びが重要
高等専修学校を選ぶ場合は、その学校が大学入学資格付与指定校かどうかを確認しておくことが重要です。
高等専門学校を選ぶ長所と短所
長所
- 5年間という時間をかけて、理論+技能をバランスよく学べる
- 実験・実習・卒業研究などを通じて専門性と技術力を高められる
- 就職率が高く、企業側からも技術者としての評価が得やすい
- 大学編入制度も利用でき、大学進学の道も開かれている
短所
- 高校進学ルートを諦める形となるため、文系・一般教養を深く学びたい人には選択肢が狭くなる可能性
- 大学卒業と比べると、学問研究の深さ・範囲で制約を感じることがある
- 編入・進学の枠や合格率には限界があり、希望大学への編入を保証するものではない
- 学び直し・進路変更には制約がある場合もある
高等専門学校を選ぶなら、「理系・技術系分野に進みたい」「早く専門性を身につけたい」「将来的に大学編入も視野に入れたい」という人に適した選択肢と言えます。
学歴としての扱いや評価の実際

制度上の「学歴扱い」と、実際の社会・就職・大学入試における扱い・評価は、必ずしも一致するわけではありません。ここでは、そのギャップや注意点についていくつか視点を示します。
制度上の扱いと称号
- 専門学校修了者(2年制以上)は「専門士」の称号、4年制以上のものは「高度専門士」の称号を得ます。これらは、いわば「専門教育を修めた証」としての公的称号です。
- 高等専修学校卒業者のうち、所定の要件(修業年限・授業時間・教科履修など)を満たした場合は、高校卒業と同等扱いとされ、大学入学資格付与指定校であれば大学入学資格を得ることができます。
- 高専卒業・専攻科修了に関しては、制度上「準学士」「学士相当」などと扱われることがありますが、大学の正式な「学士号」と同等とはされません。
制度上はこれらの扱いが定められていますが、実際の大学入試・企業採用などにおいては、別の基準・慣例が影響することが多いです。
大学入試での扱いと選抜制度
- 大学・短大の入学試験は、多くの学部・学科で「高校卒業(またはそれに準ずる資格)」を入学要件としています。高等専修学校卒業者で大学入学資格付与指定校卒業者であれば、通常の高校卒業者と同じく受験可能となるケースがあります。
- しかし、大学・学部・入試方式によっては、専門学校卒業者・高専卒業者を対象とした特別選抜を設けているところもある一方で、一般入試枠に制限がある大学もあります。
- また、大学入試における学力試験・科目選択などにおいて、高専・専門学校で履修していない科目が出題されるケースもあり、受験準備の負担になることがあります。
企業採用における評価や学歴観
- 多くの企業では、新卒採用時に学歴(大学卒・学部・偏差値など)を一つの選考要素とすることがあります。こうした“学歴フィルター”の存在は、専門学校卒・高専卒・高等専修卒といった出身者にとって壁となる場合があります。
- 一方で、技術職・専門職・技能職など実務能力を重視する職種では、専門知識・技能・実習経験といった「即戦力性」が評価され、必ずしも学歴だけで判断されないこともあります。
- 特に高専卒業者は、実践的な技術力を備えているというブランド性・信頼性を認められ、大学卒と同等またはそれ以上に評価されるケースもあります。高専卒業者の就職率の高さも、それを一定裏付けるものといえるでしょう。
- ただし、管理職・研究職・企画職などを志向する場合、大学卒以上を前提とする求人もあり、出身校や学歴が足枷になることもあります。
このように、制度上の学歴扱いや称号だけでなく、「実際の就職市場・大学選抜制度」がどのように評価をしているかをチェックしておくことが、進路選びでは重要です。
専修学校と専門学校の違いや特徴のまとめ
最後に、専修学校と専門学校の違いや特徴の要点をまとめておきましょう。
専修学校とは、修業年限1年以上、年間授業数800時間以上、常時40名以上の学生が在籍している教育施設です。専修学校は、3つの課程(「高等課程」「専門課程」「一般課程」)を設けることができます。
専修学校のうち、専門課程を持つものは「専門学校」という名称を用いることもできます。専修学校は、大学入学資格付与指定校であれば、大学進学の選択肢もあります。
専門学校とは、専修学校の中でも、専門課程を設置している学校を指します。専門学校に入学できるのは、基本的には「高等学校卒業またはこれと同等以上の学力がある者」とされています。
専門学校には、「認可校」と「無認可校」があります。認可校であれば公的な支援・奨学金制度の対象になることがありますが、無認可校や企業立校ではその扱いが異なることがあります。
専門学校と専修学校、それぞれの特徴を知り、子どもに合う進路を見つけていきましょう。
ステラ個別支援塾は、発達障害を持つ子どもの個別指導塾です。専門学校や専修学校への進学相談にも対応し、一人ひとりに合わせた学習の支援をしています。お気軽にご相談ください。
ステラ個別支援塾では無料体験実施中
ステラ個別支援塾では、随時無料体験を実施しています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業で、学習をサポートします。
お気軽にご相談ください。