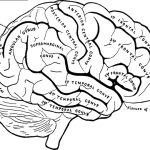子どもの発達について「少し気になることがあるけれど、どこに相談したらよいのかわからない」と感じていませんか?
特に、健診や保育園・幼稚園などで「療育」や「発達支援」という言葉を聞くと、不安になる保護者の方も少なくありません。
そこで本記事では療育(発達支援)」の意味、内容、対象となる子どもや受けられる施設などわかりやすく解説していきます。
療育(発達支援)とは?

「療育」や「発達支援」という言葉を聞いたことがあっても、その意味や定義についてしっかり理解できているという方は少ないかもしれません。
「療育って特別な支援?」「発達支援とはどう違うの?」などと戸惑うこともあるでしょう。
そこで本項では、療育と発達支援の基本的な考え方や、どんな支援を指すのかについてご紹介します。
療育の意味や定義
療育とは、障害を持つ子どもが社会的に自立できるよう、医療と教育の両面から支援することを指します。
もともとは医療機関で行うものでしたが、今は障害を持った人をサポートする取り組みとして、「発達支援」とほとんど同じ意味で使われています。さまざまな障害を持つ子どもたちの発達を促すための総合的な支援を意味するのが一般的です。具体的には、日常生活のスキル習得や社会性の向上を目指し、個々の特性に合わせたプログラムが提供されます。
発達支援の意味や定義
発達支援とは、障害の有無にかかわらず、発達に課題を抱える子どもたちが健やかに成長し、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう支援することを指します。
具体的には、福祉的、心理的、教育的、医療的な援助を通じて、身体的・精神的な機能の発達を促進します。この支援は、子どもの特性やニーズに応じて提供され、家庭や学校、地域社会との連携が重視されます。
療育と発達支援の違い
療育と発達支援は「どちらも子どもの成長をサポートする取り組み」です。もともとは、療育が治療と教育の意味合いを持った支援として始まったのに対して、発達支援は福祉や心理的な援助も含めた広範な支援を指していました。
現在では、両者の違いは曖昧になり、ほとんど同じ意味で使われることが多くなっています。両者とも、子どもの個々のニーズに合わせた適切な支援を提供することを重視しています。そのため、「発達支援」を行っている児童発達支援センターの中には「療育センター」と呼ばれているところもあります。
療育(発達支援)の内容

療育(発達支援)の内容として、子ども家庭庁のガイドラインに書かれている「児童発達支援」の内容を取り上げます。
児童発達支援とは、障害のある子どもの心や体の発達を促し、ご家庭や社会の中で安心して生活できるように支援する取り組みです。
支援は「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援」の4つに分かれ、特に本人支援では「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」など5つの視点から子どもの状態を見て、個別に合った支援が行われます。
ご家庭や地域と連携しながら、こどもが充実した毎日を過ごし、望ましい未来を作り出し、生涯にわたるウェルビーイングを実現していく力の基礎を培うことが重要としており、児童発達支援センターはその中心的な役割を担っています。
参考元 子ども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/93d83e4a-f48a-4922-befd-517fe9d7c6d4/aa2da96d/20250307-councils-support-personnel-93d83e4a-10.pdf
療育(発達支援)の対象者や目的は?
療育は、障害や発達に遅れを持つ子どもたちが、自分らしく生活できるように支えるための支援です。
ただし「うちの子どもは療育が必要なの?」「療育って具体的に何をするの?」「どんな効果があるの?」といった疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、療育の対象者やその目的、重要性や効果、また療育を行っている場所などについて説明していきます。
療育の対象者
療育は、主に「障害や発達の遅れをもつ子どもたち」を対象に、将来的には自立し、社会に参加できるように支援することです。対象となるのは、以下のような子どもたちです。
身体障害のある子ども
手足の動きや視覚・聴覚などに障害がある場合、日常動作や周囲とのやりとりに困りごとが生じやすいため、作業療法や理学療法を通じて発達を支援します。
知的障害のある子ども
言葉の理解や判断、記憶の面で困難さを抱える子どもには、日常生活に必要なスキルを身につける支援や、社会性を育むサポートが行われます。
精神障害・発達障害のある子ども
自閉症スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害の子どもには、特性や発達に合わせた支援が、感情のコントロールや対人関係に課題がある子どもには、安心できる関係性の中で行動や気持ちを育てる支援が行われます。
療育は診断がなくても、「発達のことで気になることがある」という時点で相談できます。小さな不安でも、早めに支援につなげることで子どもとご家族の安心につながります。困っているのは「子ども自身だけでなく、関わる大人も」という視点が療育の出発点です。
療育(発達支援)の目的
療育の主な目的は、障害や発達の遅れを持つ子どもたちが「将来的に自立し、社会に参加できるよう支援すること」です。具体的には、日常生活のスキルやコミュニケーション能力、社会性の向上をサポートします。
たとえば、
●日常生活に必要な動作の習得
●学習
●運動
●コミュニケーションの始動
●集団生活への適応
●遊びや学びの場所の提供
●機能訓練 など
これらの支援を通じて、子どもたちが自分らしく生活し、社会での役割を果たせるようになることを目指します。
療育(発達支援)の重要性
療育は「子どもたちの発達を促進し、生活の質を良くするために非常に重要なこと」です。特に早期の療育は、社会性やコミュニケーション能力の向上に効果的であるとされています。
また、療育を通じて、子どもたちが日常生活や社会生活を円滑に営むためのスキルを身につけることができます。療育は、家族や支援者との連携も深め、子どもたちを取り巻く環境全体のサポート体制を強化する役割も果たします。
療育(発達支援)の効果やメリット
療育は、子どもの発達を促し、生活の質を高めるためのさまざまな支援を提供します。療育は以下のような効果やメリットをもたらします。
子どもにとってのメリット
●発達の促進(運動能力、言語能力、認知能力、社会性など)
●スキルの向上(日常生活、学習、社会性を身につける)
●問題行動の軽減(問題行動の原因を探り、適切に指導)
●自己肯定感の向上(良いところや得意なところを認め伸ばす)
保護者にとってのメリット
●子育ての不安軽減(子どもの発達に関する専門的な知識を提供)
●子どもの理解(子どもの特性や発達段階についての詳細を共有)
●家族関係の改善(家族全体のコミュニケーションや関わり方を支援)
療育は、子どもだけでなく、保護者の方にとっても多くのメリットをもたらします。子どもの成長をサポートするために、ぜひ療育についてもご相談してみてください。
療育(発達支援)を行っている場所
療育は、子どもの発達を支援するさまざまな場所で行われています。それぞれの特性に合わせて、以下のような機関があります。

病院・医療機関
発達外来などで診断や専門的な評価、医師の指導のもと療育を受けることができます。
療育センター
治療・相談・検査・支援が一体となった地域の中核的な機関です。治療が行われない児童発達支援センターを療育センターと呼んでいるところもあります。
児童発達支援事業所
主に未就学の子どもを対象に、日常生活動作やコミュニケーション、社会性を育てるなど、子どもの発達に合わせた支援を行っています。
放課後等デイサービス事業所
就学後の子どもたちが放課後に通う支援の場で、学習や生活面、コミュニケーション面など、個々の子どもに必要な支援が行われています。
それぞれの施設には特徴があり、子どもに合った環境を選ぶことが大切です。
療育(発達支援)に関するまとめ
療育とは、障害や発達に遅れのある子どもが、将来的に自立し社会で生活できるように支援する取り組みで、医療・教育・福祉が連携して行われます。
発達支援は、障害の有無にかかわらず発達に課題のある子どもに対して、日常生活や社会性を育む支援を行うもので、ご家庭や地域と連携して進められます。
両者は近年ではほぼ同じ意味で使われることが多くなっており、子ども一人ひとりの特性に応じた支援が重視されています。療育や発達支援には、運動・言語・学習・社会性などを伸ばすプログラムがあり、自己肯定感の向上や問題行動の軽減にもつながります。
対象となるのは、身体障害・知的障害・発達障害などの子どもたちで、支援は病院や療育センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービスなどで受けられます。早期の支援が成長に大きく影響するため、気になることがあれば早めの相談が大切です。
参考元
各 支援機関 等
子ども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/93d83e4a-f48a-4922-befd-517fe9d7c6d4/aa2da96d/20250307-councils-support-personnel-93d83e4a-10.pdf