就学を前に新版K式発達検査を受けたとき、「ボーダーライン」という結果に戸惑う保護者は少なくありません。
通常級に進むべきか、それとも支援級を検討したほうが良いのか。
子どもの将来を思えばこそ、不安や迷いが大きくなるものです。
本記事では、新版K式発達検査の基本的な内容から結果の見方や、ボーダーラインとされる数値の意味、さらに他の発達検査との違いや実際の体験談まで解説します。
検査結果をどう受け止め、これからの支援や学習環境をどう整えていけばよいか、一緒に整理していきましょう。
新版K式発達検査の概要

新版K式発達検査は、子どもの発達の様子を確認するために広く使われている検査です。
対象は乳幼児から成人までと幅広く、特に5歳前後の就学を控えた時期に受ける方が増えています。
検査では「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会」という三つの領域を中心に、子どもがどのくらいできているかを丁寧に見ていくのがポイント。
その結果として「発達年齢(DA)」や「発達指数(DQ)」といった数値が示され、成長のバランスや得意・不得意が分かります。
あくまで発達の状態を知るための目安であり、診断名をつけるためのものではありません。
検査を通して得られた情報は、今後の関わり方や支援の方向性を考えるうえで大切な参考になります。
新版K式発達検査の歴史
K式発達検査は、日本で生まれた独自の発達検査として長く活用されてきました。
初版は1950年代に作られ、その後の研究や社会の変化に合わせて改訂が重ねられています。
最新版である「新版K式発達検査」は、従来の検査内容を見直し、より幅広い年齢層と発達の特徴に対応できるよう工夫されました。
日本の子どもたちの実態に即した評価基準を持つ点が特徴であり、医療機関や教育現場でも安心して利用されています。
半世紀以上の歴史を経て蓄積された知見が反映されているため、結果を支援や教育に役立てやすい検査として信頼されているのです。
新版K式発達検査の目的
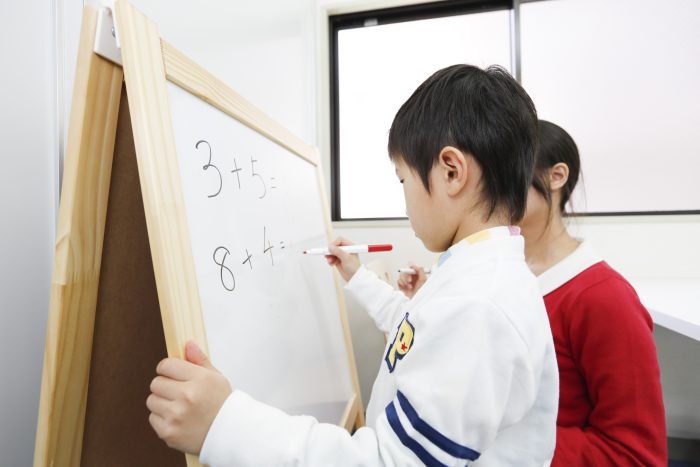
子どもが安心して成長できる環境を整えること、それが新版K式発達検査の目的です。
そのために、発達の状態を数値として示し、成長のバランスや特徴を客観的に把握します。
どの領域が得意で、どこに支援が必要かを見極めることで、早い段階から適切なサポートにつなげられるのです。
また、診断を下すためではなく、あくまで今後の育ちを支える参考資料として新版K式発達検査が活用されます。
結果をもとに家庭や保育園、幼稚園、学校などが協力し合い、子どもがのびのびと成長できる環境を整えることが重視されています。
したがって、検査結果は「できる」「できない」を決めつけるものではなく、子どもを理解し支えていくための出発点となるのです。
新版K式発達検査の方法

新版K式発達検査では、子どもの発達を三つの領域から総合的に見ていきます。
「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会」を通して、体の動きや考える力、人との関わり方を確認し、それぞれの得意と課題を明らかにします。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
姿勢・運動領域
姿勢・運動領域では、子どもの体の動きやバランスを中心に確認します。
日常生活に直結する力が多く含まれており、成長の基盤を知るために欠かせない項目です。
検査では以下のような動きを見ていきます。
- 自分の体をしっかり支える力
- 寝返りをして姿勢を変える動き
- 両脚を使ったジャンプや弾む動作
- 体の向きを変える動き(方向転換)
- 足を手や口へ持っていく柔軟な動き
- 高い場所や段差をよじ登る動作
- 台や階段から飛び降りる動き
- 左右交互に足を出して歩く・昇る動作
- 片足で跳ぶ「ケンケン」のような動作
これらは単に運動能力を測るだけではなく、学習や社会生活の土台にもつながります。
例えば、姿勢が安定していなければ机に向かうことが難しくなり、集中力に影響が出ることもあるでしょう。
そのため、この領域の結果は就学に向けた支援を考えるうえで大切な手がかりとなります。
認知・適応領域
認知・適応領域では、子どもが物を見て、手を使いながら理解し、工夫していく力を確かめます。
物との関わり方や周囲の状況への適応力が中心であり、学習や社会生活の基盤となる重要な領域です。
検査では次のような動作が確認されます。
- 両手を近づけて協調させる動き
- 顔を相手や物に向ける反応
- おもちゃを目で追いかける視線の動き
- 両手で物を10秒間持ち続ける
- 瓶などの容器に手を伸ばす動作
- 物を持ち上げる力
- コップに触れて反応する動き
- 物をコップの中に入れる操作
- 積み木を積んで置く動作
- 物の重さを比べる判断
これらを通して「見て理解し、考えて動かす力」の発達が見えてきます。
数値だけでなく、動作の様子や工夫の仕方も観察のポイントです。
言語・社会領域
言語・社会領域では、子どもが人や物にどのように関わり、言葉を使ってやりとりできるかを確認します。
対人関係やコミュニケーションの力は、就学後の生活や学びに大きく関わるため、検査の中でも重要な位置を占めています。
具体的には次のような反応や行動を見ていきます。
- 名前を呼ばれて反応する
- 人の指さしを見て対象を理解する
- 相手とボールをやり取りして遊ぶ
- 短い文章をそのまま言い返す
- 数字を順番どおりに繰り返す
- 聞いた文章の内容を整理して理解する
- 今日の日付や時間を答える
- 言葉の逆の意味を答える
- 物の大きさを比べて答える
- 物の長さを比べて答える
これらの様子を通して、子どもが言葉で考え、人とのつながりを築いていく力が分かります。
単に語彙の数を見るのではなく、状況に応じてどのようにやりとりしているかが大切な観点です。
新版K式発達検査の診断結果

新版K式発達検査を受けると、結果は数値やグラフとして示されます。
しかし、初めて目にする保護者にとっては分かりにくい部分も多いでしょう。
ここでは、発達年齢や発達指数といった指標の意味、グラフから読み取れるポイント、さらに専門家に解説を受ける重要性について順に説明していきます。
発達指数と発達年齢の指標で表される
結果が「発達年齢(DA)」と「発達指数(DQ)」で示されるのが新版K式発達検査です。
発達年齢とは、子どもの実年齢と比べてどのくらいの発達段階にあるかを数値化したもの。
たとえば5歳児であっても、結果が4歳半相当であれば、その領域に少し遅れがあると分かります。
発達指数は100を基準に、平均より上か下かを判断する指標で、85〜115程度が「おおむね年齢相応」とされます。
それより低い場合には、支援を検討するきっかけになるでしょう。
ただし新版K式発達検査の数値は診断名を決めるものではなく、あくまで成長の目安です。
子どもの得意な分野や課題を把握し、今後の支援や学習環境を考えるための材料となります。
グラフで見ることができる
結果は数値だけでなくグラフでも示されるのが新版K式発達検査の特徴です。
姿勢・運動、認知・適応、言語・社会の三領域が並び、それぞれの発達指数(DQ)が折れ線や棒グラフで表されます。
数値だけでは見落としがちな偏りや凸凹が、視覚的に確認できる点は大きな利点といえるでしょう。
たとえば運動は年齢相応でも、言語で遅れが見られる場合は、その差が一目で理解できます。
家庭や学校、専門機関と情報を共有するときにもグラフは役立ち、支援が必要な部分を明確に示しやすくなります。
子どもの得意と苦手を整理する指標として活用できるのが新版K式発達検査なのです。
専門家に解説を受ける
結果は数値やグラフだけでは理解しにくい部分があるのが新版K式発達検査です。
そのため、心理士や医師など専門家から説明を受けることが重要となります。
たとえば数値が平均より低くても「一時的な体調や気分の影響かもしれない」「特定の領域を支援すれば伸びやすい」といった見方が加わるでしょう。
専門的な解釈を聞くことで、結果を正しく受け止められるようになります。
また、家庭や学校での支援方法や就学先を検討する際の具体的なアドバイスも得られるのです。
親が一人で判断するのではなく、専門家と一緒に子どもの成長を考えることで、不安が和らぎ前向きな支援へとつなげやすくなるのが新版K式発達検査の活かし方といえます。
他の発達検査と新版K式発達検査の比較
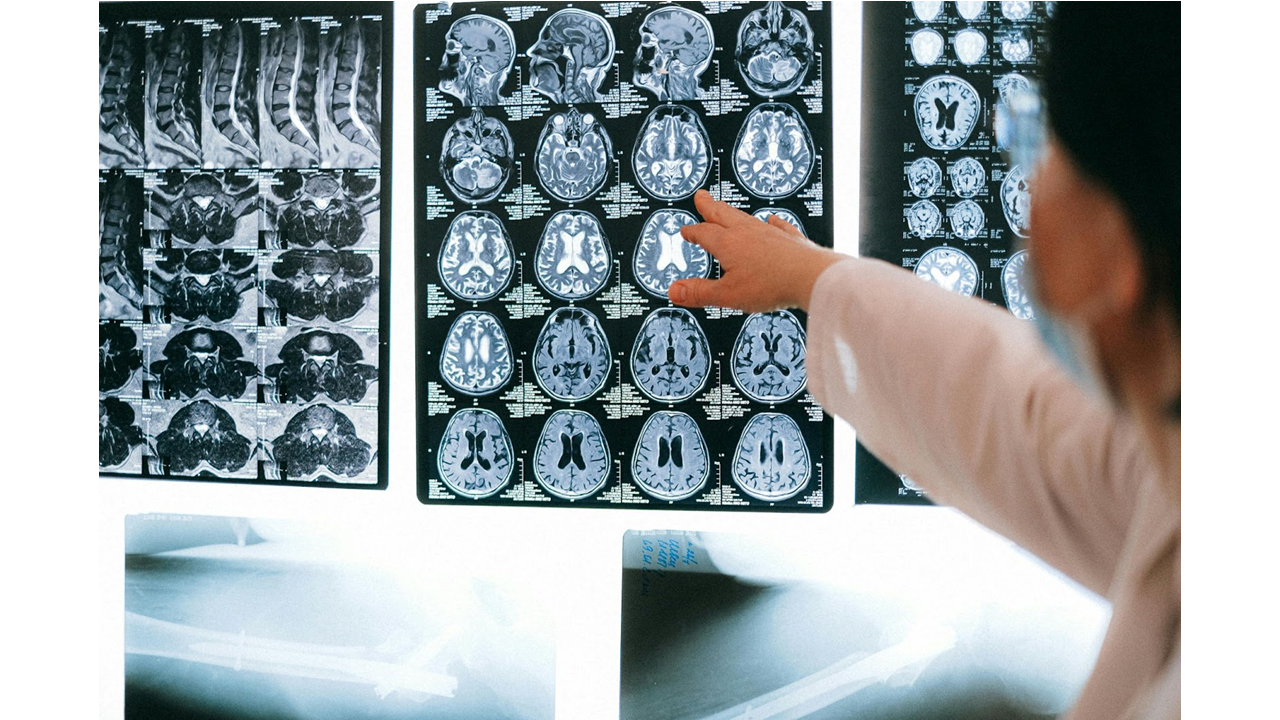
発達検査は新版K式発達検査以外にも複数あります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
田中ビネー知能検査
田中ビネー知能検査は、知能の発達を年齢に応じて測定する代表的な知能検査です。
フランスの心理学者ビネーの理論をもとに、日本で改訂が重ねられ、現在は「第五版」が広く使われています。
検査では記憶力や言語理解、推理力、判断力など多面的な能力を確認し、知能指数(IQ)として数値化します。
対象年齢は2歳から成人までと幅広く、発達の程度を総合的に把握できる点が特徴です。
新版K式発達検査が「発達のバランス」を見るのに対し、田中ビネーは「知能の水準」を測る検査といえます。
就学判定や特別支援教育の判断材料としても用いられ、教育現場や医療機関で長く信頼されてきた検査です。
ウェクスラー式知能検査
ウェクスラー式知能検査は、世界的に最も広く使われている知能検査のひとつです。
幼児には「WPPSI」、学童期には「WISC」、成人では「WAIS」が用いられ、対象年齢ごとに内容が調整されています。
検査は「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」といった複数の下位尺度で構成され、それぞれの得点と全体の知能指数(IQ)を算出します。
単なる数値だけでなく、得意分野と苦手分野の差を把握できるため、学習上の困難や特別支援の必要性を判断する材料になります。
発達の流れやバランスを確認できる新版K式発達検査と組み合わせることで、子どもの理解がさらに深まるのです。
Vineland-II
知能検査が「できる力」を数値化するのに対し、Vineland-II(ヴィナランドⅡ)は「実際の生活の中でどのように力を発揮しているか」を測定するのが特徴です。
評価領域は「コミュニケーション」「日常生活スキル」「社会性」「運動」「不適応行動」の5つで、保護者や指導者への聞き取りを通じて行われます。
対象年齢は乳幼児から92歳までと幅広く、発達障害や知的障害の診断補助、支援計画を立てる際に活用されます。
発達段階の目安を示す新版K式発達検査とあわせて活用することで、子どもの姿をより多面的に理解できるのです。
両者を組み合わせることで、子どもの姿をより多面的に理解できるようになります。
軽度知的障害のボーダーラインは?
知的障害の程度は、一般的に知能指数(IQ)を基準に区分されるのが一般的です。
軽度知的障害はIQ50〜70前後が目安とされ、この範囲にあたる場合には「ボーダーライン」と呼ばれることもあります。
ただし、数値だけで判断するのは適切ではありません。
同じ数値でも生活に支障が少ない子どももいれば、日常で困りごとが大きい子どももいます。
新版K式発達検査で発達指数がやや低めに出た場合でも、体調や環境によって変動することがあるため、繰り返しの検査や家庭・園での様子を総合的に見ていくことが大切です。
数値はあくまで一つの目安であり、支援や就学の判断は専門家と相談しながら慎重に進める必要があります。
新版K式発達検査において知っておきたいこと
子どもの発達を理解するための大切な手がかりとなるのが新版K式発達検査の結果です。
しかし、それだけで将来や進路を決めるものではありません。
数値やグラフは一時点での姿を切り取ったにすぎず、体調や気分によって変動することもあります。
大切なのは、結果を診断と直接結びつけるのではなく、日常の様子や成長の変化とあわせて見ていくことです。
専門家からの解説を受け、家庭や学校と連携しながら支援方法を考えることで、子どもに合った学びや生活の環境が整っていきます。
新版K式発達検査はゴールではなく、これからの成長を支えるスタート地点と捉えることが大切なのです。
新版K式発達検査の体験談
最後に、新版K式発達検査を実際に受けた方の体験談を紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
5歳で軽度知的障害と診断された子ども
就学を控えた5歳の子どもが発達検査を受けたところ、以前よりも数値が高く出て驚いたという体験談があります。
特に処理速度の得点が高く、全体の知能指数も平均以上となりました。
ただ一方で、言語理解は他の領域に比べて低めで、コミュニケーション面の課題は残っていると感じたそうです。
保護者は結果に安心しつつも「数値だけで判断してよいのか」と迷いも抱いています。
今後は学校や専門家と相談しながら、子どもに合った支援のあり方を考えていく予定だと綴られていました。
5歳の子どもが新版K式発達検査を受けた所感
5歳半の子どもが新版K式発達検査を受けた体験があります。
認知や言語の発達指数は80台半ばで、平均よりやや低い結果となりました。
運動面の評価は就学相談の関係で一部省かれ、実際より高めに見える数値に保護者は複雑な思いを抱いたそうです。
また、言葉での指示が通りにくい、課題の切り替えが苦手、新しいことに慎重すぎるといった課題も見えてきました。
一方で視覚的な記憶は良好で、できるようになったことも増えていると感じています。検査を単なる数値ではなく「成長の記録」として受けとめ、次回の検査での変化を確かめたいという前向きな気持ちも綴られていました。
子どもの発達障害・発達の遅れに不安がある方へ
発達の遅れや発達障害について「気になるけれど、どうしたらよいか分からない」と感じる方も少なくありません。
ステラ幼児教室では、0歳から就学前までの子どもを対象に、言葉・社会性・運動・学習など多面的に支援を行っています。
専門スタッフが一人ひとりに合わせたプログラムを用意し、安心して成長をサポートできる環境です。
年少から年長までは無償化制度の対象となるため、費用面でも利用しやすいのが特徴。
家庭だけで抱え込まず、専門的なサポートを取り入れることで子どもの力を引き出すきっかけにつながります。
新版K式発達検査についてのまとめ
新版K式発達検査は、子どもの発達の状態を知るための大切な手がかりになります。
しかし、数値やグラフだけですべてを判断するのではなく、日常生活の様子や専門家の意見と合わせて理解することが大切です。
発達指数がボーダーラインに出たとしても、それは「これからどう支えていくか」を考えるきっかけに過ぎません。
就学に向けて不安があるときは、学校や地域の支援制度を活用し、必要に応じて幼児教室や療育機関と連携することで安心につながります。
子どもの成長は一人ひとり違うもの。焦らずに、その子に合った環境を整えていくことが、未来への力強い一歩になります。














