周囲の出来事や人の感情に敏感に反応し、ちょっとした変化にも心を動かされるお子さんがいます。そんな姿を見て、「どう接すればいいのだろう」と悩まれる保護者の方も少なくありません。けれども、その繊細さは決してマイナスではなく、お子さんの中にある豊かな感性の表れです。
この記事では、感受性が強いお子さんの特徴やその背景となる原因、そして日々の関わり方のヒントをお伝えします。少しでもお子さんの理解を深めるきっかけになれば幸いです。
感受性が強いとは
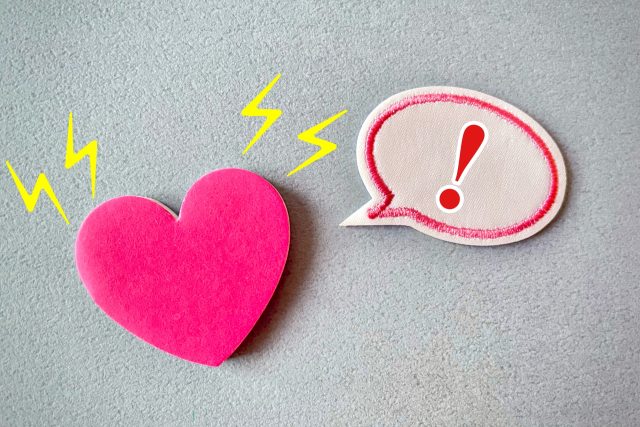
感受性が強いとは、外からの刺激や人の気持ちを敏感に感じ取り、深く受け止める傾向を指します。音や光、においなどの感覚刺激だけでなく、人の表情の変化や声の調子、場の雰囲気にも敏感に反応します。
感受性が強い人の特徴
感受性の高い方は、物事を細やかに感じ取り、深く考える傾向があります。美しい風景を見て感動したり、物語の登場人物に強く共感したりすることも多いです。また、他の人の気持ちを察して思いやりある行動ができるという素敵な面もあります。
一方で、注意された言葉や人混みなどの刺激を強く受け取りやすく、疲れやすさを感じることもあります。その繊細さが、時にはストレスの原因になることもあるでしょう。
悪いことではない理由
保護者の方の中には、「このままで大丈夫なのだろうか」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、感受性の高さは“気質”のひとつであり、決して悪いものではありません。むしろ、人の気持ちを深く理解できる力や、芸術的な感性、創造的な発想につながる大切な特性です。
周りと違うことで戸惑うこともあるかもしれませんが、理解あるサポートがあれば、お子さんは自分らしい強みを発揮していけます。大切なのは、この特性を否定せず、「そういう感性を持っているんだね」と受け止めることです。
HSCという気質について
HSC(Highly Sensitive Child)とは、「ひといちばい敏感な子ども」という意味で、心理学者エレイン・アーロン博士によって提唱された概念です。人口のおよそ15〜20%がこの気質を持つといわれています。
HSCのはっきりとした原因はわかっていませんが、病気や障がいではなく、生まれつきの気質として捉えられています。
主な特徴として、
●情報を深く処理する
●強い刺激を受けやすい
●感情の反応が豊かで強い
●小さな変化に気づく
といった点が挙げられます。
お子さんがこのような傾向を持っている場合は、「どうしてそう感じるのか」を理解しようとする姿勢が、安心感と成長につながります。
感受性の強い子どもに見られる特徴

感受性の強いお子さんは、日常の中で他の子どもたちとは少し違った反応を見せることがあります。 ちょっとした出来事にも深く心を動かされることがあり、その繊細さが行動や感情に表れます。
ここでは、感情面・感覚面・行動面・対人関係という4つの側面から、具体的な特徴を見ていきましょう。
感情面での特徴
感情表現がとても豊かで、嬉しいときは全身で喜びを表し、悲しいときは深く心を痛めるといったように、気持ちの動きがはっきりしています。
例えば、友だちが悲しんでいると自分のことのように感じて涙を流したり、誰かが叱られている場面を見ると胸が締めつけられるような不安を覚えたりすることもあります。
映画や絵本を読むと、登場人物の気持ちに強く共感し、まるでその世界の中に入り込んでいるように感じることも多いです。
このような感情の豊かさは、人の気持ちを理解しようとする力や、思いやりのある行動、芸術的な感性を育てる上で大きな強みになります。
周りの大人からは、周りを見て動ける「頭がいい」子と見られるかもしれませんが、お子さん本人は実はしんどい思いをしていることもあります。
感覚面での特徴
音や光、においなどの感覚に対してとても敏感で、他の人が気にならないような刺激にも強く反応することがあります。 例えば、洋服のタグが肌に当たるのを嫌がったり、食べ物の食感やにおいに敏感に反応したりすることがあります。
また、賑やかな場所や人混みの中では疲れやすく、静かな環境を好む傾向も見られます。 さらに、気温の変化にも敏感で、暑さや寒さを感じやすい子も少なくありません。
こうした感覚の鋭さは、細やかな観察力や美しいものを見つける力、美的センスの高さにもつながります。 日常の中でお子さんが心地よく過ごせる環境を整えることが大切です。
行動面での特徴
感受性の強いお子さんは、新しい環境や初めての体験に対して慎重な姿勢を見せることが多いです。 まずはまわりの様子をじっくり観察し、安心できると感じてから行動を起こします。 急な予定の変更や思いがけない出来事に戸惑いやすいため、事前に予定や流れを伝えておくと安心して過ごせます。
また、完璧を求める気持ちが強く、自分に厳しくなりすぎることもあります。
うまくいかないと強く落ち込んでしまうこともあるため、「失敗しても大丈夫」「挑戦できたことが素晴らしい」と伝えてあげることが、次への自信につながります。
対人関係での特徴
人の表情や声のトーンから気持ちを読み取る力に優れており、周囲の感情に敏感に反応します。 そのため、友だちの何気ない言葉に傷ついたり、相手の機嫌を気にして気をつかいすぎたりすることもあります。
大人数の集まりよりも、少人数や一対一の関係を好む傾向があり、信頼できる人との深いつながりを大切にします。 ときにはひとりで静かに過ごす時間が必要になることもあり、その時間が気持ちの整理やリフレッシュにつながります。
感受性が強くなる原因
感受性が強いお子さんには、いくつかの理由が重なっていることが多いようです。 もともと持って生まれた性質にくわえ、育ってきた環境や、物事の感じ取り方・考え方なども影響していると考えられます。 ここでは、「生まれつきの気質」「環境的な影響」「知性との関わり」という3つの面から、その背景を少し丁寧に見ていきましょう。
生まれつきの気質
まず挙げられるのが、生まれ持った気質です。 神経系が刺激を受け取りやすく、脳の中でその情報を深く処理する傾向があるとされていますが、はっきりとした原因はわかっていません。
HSC(ひといちばい敏感な子ども)の研究では、こうした特性に遺伝的な影響が大きいことが示されています。 この傾向は、赤ちゃんのころから見られることもあります。 音や光に敏感だったり、環境の変化に泣いてしまったりといった反応が早い段階で現れることがあります。
こうした特徴は「その子が生まれながらに持っている個性」として受け止めることが大切です。
環境的な要因
生まれ持った気質に加え、育つ環境も感受性の強さに影響を与える原因のひとつです。 温かく、受け入れられていると感じられる環境の中では、お子さんの感受性がプラスの方向に働きやすくなります。 一方で、否定的な言葉が多い環境や過度に厳しい対応が続くと、必要以上に敏感になったり、自己肯定感が下がったりすることもあります。
また、家庭や学校などでストレスの多い状態が続くと、繊細さがさらに強まることがあります。 お子さんが安心できる時間や空間を持てるよう、日常の中で穏やかな環境づくりを意識することが大切です。
頭がいいことと知性の関係
感受性の強いお子さんは、観察力や思考力に優れていることも多く、周囲の情報を深く理解しようとします。 ひとつの物事を多面的に捉えることができ、細かな違いに気づく力があります。 そのため、「頭がいい」「理解が早い」と感じられる場面も少なくありません。 ただし、感受性の高さと知的能力は必ずしも同じものではありません。 お子さんそれぞれが持つ個性や得意分野を理解し、その子に合った学び方やサポートを見つけていくことが、伸び伸びとした成長につながります。
セルフ診断チェックリスト

現在は、HSCは気質であり、はっきり医師から診断名がつけられるわけではありません。
そこで、お子さんについて理解を深めるために、簡単なセルフ診断チェックリストをご紹介します。
子ども向けチェック項目
HSCの概念を提唱したアメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士は、お子さんがHSCかどうかを知るための質問表を作成しています。お子さんの特性を理解する参考として、ご紹介します。
以下の質問について、お子さんに当てはまる、どちらかというと当てはまる場合はチェックをし、あまり当てはまらない、あるいはまったく当てはまらない場合はチェックをしないでください。
●すぐびっくりする
●チクチクするような服、靴下の縫い目、肌に触れる襟元のタグなどを嫌がる
●サプライズしてあげてもほとんど喜ばない
●厳しい罰を与えるよりも、優しく間違いを正す方が言うことをわかってくれる
●私の気持ちをよく察するように感じる
●年齢の割には難しい言葉を使う
●ほんのかすかなにおいにも気づく
●優れたユーモアのセンスを持っている
●直感力が優れているように思える
●興奮したことがあった日はなかなか眠れない
●大きな変化にはうまく対応できない
●服が濡れたり砂で汚れたときは着替えたがる
●質問を山のようにぶつけてくる
●完璧主義なところがある
●他人の苦しみによく気づく
●静かな遊びが好き
●深い示唆に富む質問をしてくる
●痛みにとても敏感
●うるさい場所を苦にする
●微妙なことによく気づく
●高い場所に上る前に、安全かどうかじっくり考える
●知らない人がいると、一番良いときの実力を発揮できない
●ものごとを深く感じ取る
13もしくはそれ以上の質問に当てはまった場合、お子さんはHSCの可能性があります。ただし、完璧に診断できる心理テストというものはありません。ですから、保護者の方がお子さんをどのように受け止めているかを基に判断したほうがよいでしょう。
もし当てはまった項目が1つか2つであっても、ものすごく当てはまると感じるようであれば、お子さんをHSCと呼んでいいかもしれません。
HSCとわかったら、まず最初に、この特性が素晴らしいものだということを正しく理解してください。病気として診断名がつくわけでもありません。お子さんの個性を理解し、受け入れることが大切です。
参考:エレイン・N・アーロン博士 公式サイト日本語版 http://hspjk.life.coocan.jp/
女性と男性の違い

性別による大きな違いはありませんが、表れ方に傾向の差が見られることがあります。
女性に見られる傾向
女性は、感情表現が豊かで、共感力の高さが表に出やすい傾向があります。友だち関係を大切にし、他者の気持ちに寄り添う姿勢が強く見られます。また、繊細な感性を持つことが周囲に受け入れられやすく、芸術的な活動や表現に興味を持つことも多いです。
一方で、友だち関係での些細なトラブルに悩みやすく、他者の評価を気にしすぎることもあります。
男性に見られる傾向
男性も同じ特性を持っていますが、社会的な期待から感情を表に出しにくいことがあります。周囲から強くあることを求められる中で、自分の繊細さを隠そうとすることもあります。
しかし、内面では深く物事を感じており、静かに思いを巡らせていることが多いです。ひとりで集中できる活動や、創造的な分野で才能を発揮することがあります。保護者の方が、お子さんの特性を理解し、ありのままを受け入れることが大切です。
効果的な接し方のポイント
感受性の強いお子さんには、その特性を理解した関わり方がとても大切です。 ほんの少しの配慮で、お子さんの安心感や自己肯定感が大きく変わります。
基本的な心構えと声かけ方法
まず意識したいのは、「お子さんの感じ方を否定しない」という姿勢です。 大人から見ると「そんなことで?」と思えるような出来事でも、お子さんにとっては本当に心が動く出来事であることがあります。 「そう感じたんだね」「つらかったね」と、共感の言葉を返してあげるだけでも、お子さんは安心できます。
声をかけるときは、穏やかなトーンで、できるだけ具体的に伝えましょう。「ちゃんとしてね」よりも「これをこうしようね」と示す方がわかりやすく、気持ちが落ち着きます。また、予定や変更があるときには、前もって伝えておくことで心の準備ができます。
注意や叱り方にもポイントがあります。感情的に強い言葉を使うより、落ち着いた声で「どうすればよかったか」を一緒に考えるように伝えると効果的です。叱った後には「あなたのことが嫌いなんじゃないよ」とフォローすることも忘れずに。この安心感が、次への前向きな行動につながります。
強みを伸ばす育て方
感受性の高さは、適切に育てていくことで大きな才能へとつながります。 お子さんの興味をよく観察し、得意なことや夢中になれることを見つけてあげましょう。 絵を描く、音楽を楽しむ、読書に没頭するなど、表現を通して感性を活かせる活動はおすすめです。創作をする中で、思考の深さや想像力が自然に育まれます。
また、自然の中で過ごす時間も大切です。季節の変化や音・香りを感じ取ることは、お子さんの心を整え、情緒を豊かにします。
学習の場面では、急かさず、お子さんのペースを尊重することがポイントです。考える時間をじっくりと与えることで、より深い理解につながります。細部に気づく力や多角的に物事を見る視点は、将来の学びや探究の強みとなります。
発達障害との違い
感受性の高さは発達障害とは別のものですが、特性の一部が重なるため、見分けが難しいことがあります。
感受性が強いだけの場合、周囲の理解や環境の工夫によって日常生活はおおむね問題なく過ごせます。一方で、発達障害では複数の場面で継続的な困難が見られるのが特徴です。たとえば、ASD(自閉スペクトラム症)では社会的なコミュニケーションの難しさ、ADHD(注意欠如多動症)では注意の集中や衝動のコントロールに課題が見られることがあります。
なお、感受性の高さと発達障害の特性を両方持っているお子さんもいます。もし、日常生活の中で強いストレスや困りごとが続く場合は、早めに専門家へ相談してみましょう。医療機関、児童相談所、発達支援センターなどで、適切な評価や支援の方法を一緒に考えてもらうことができます。
感受性が強いお子さんとの関わりで大切なこと
感受性の強いお子さんを育てる中で、保護者の方自身が疲れてしまうこともあるかもしれません。お子さんの繊細な気持ちに寄り添い続けることは、時に大きなエネルギーを必要とします。
感受性の豊かさは、長い目で見ればお子さんの大きな強みになります。幼い頃は手がかかるように見えても、成長とともにその特性を自分の力として活かせるようになります。人を思いやる気持ちや創造性、深く考える力は、これからの社会で確実に価値のある力です。
お子さんを信じ、焦らず、ゆっくりと見守る姿勢が何よりのサポートになります。保護者の方が困ったときはひとりで抱え込まず、周囲や専門家の力を頼ってください。
ステラ個別支援塾では、お子さん一人ひとりの特性に合わせたオーダーメイドの学習支援を行っています。
お子さんの特性に不安を感じたときは、お気軽にご相談ください。
個性を才能に変える子育てを

繊細で感受性の豊かなお子さんは、周囲の刺激に敏感で、人の気持ちを深く感じ取る力を持っています。その力は決して弱さではなく、むしろ大切に育てたい“伸びしろ”です。
お子さんの感じ方を尊重し、安心できる環境を整えることで、その繊細さは思いやりや創造力、洞察力といった力へと変わるでしょう。保護者の方が「ありのままのあなたでいい」と伝えることが、最大の励ましになります。
感受性の高さは、お子さんにとっての“宝物”であり、未来を支える大切な個性です。もし不安を感じたときは、専門家や支援機関にご相談ください。
ステラ個別支援塾では無料体験実施中
ステラ個別支援塾では、随時無料体験を実施しています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業で、学習をサポートします。
お気軽にご相談ください。














