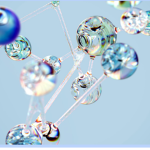子育てをしていると、ついつい子どもに過干渉になっていませんか?
子どもを大切に育てようとする気持ちは大切ですが、過度な干渉は悪影響を及ぼすことがあります。
しかし、親にとっては「どの程度が過干渉と言うのかわからない」という悩みもあるでしょう。
当記事では、過干渉の親の特徴、子どもへの影響、対処方法まで詳しく解説します。
ぜひ参考にご覧ください。
過干渉とは
過干渉とは、 親や周囲の大人が子どもの行動に過度に口出しし、本人の意思や判断を尊重せずに管理・指示することを指します。
例えば子どもが自分で決める前に親が全て決めたり、失敗を防ぐために先回りして指示を出したりすることが挙げられます。
親自身が過干渉に育てられていると、同じように過干渉になる可能性が高いとも言われています。
過干渉と過保護の違い
過干渉と類似する行為として、過保護があります。
過保護は、子どもの行為を甘やかしてしまう状態のことです。
過干渉は親の意向を子どもに押し付けるのに対して、過保護は全ての行為を許します。
どちらも過度な状態を指すため、よいとは言えません。
しかし、いつまでたっても親にとって「子は子」なので、口出しすぎたり、世話を焼きすぎたりし、子どもの成長や状況に合わせて適度に変えていくことが難しいという方も多いかもしれません。
では次に、親の「過干渉」な状態を具体的に見ていきます。
過干渉の親の特徴
過干渉の親には、以下のような特徴があります。
●子どもの話を遮る
●子どもの意見を尊重していない
●子どもの友人関係に口を出す
●問題点・課題ばかりを指摘する
●完璧を求めやすい
それでは詳しく説明します。
子どもの話を遮る
子どもが返答する前に話し始める親は、過干渉になる可能性が高いです。
例えば先生との面談時に子どもへ向けられた質問に対して、親が先に答えるケースがあります。
子どもが口下手な場合は親が口出しをしてしまいがちですが、あまりに続くと過干渉になってしまうので注意が必要です。
子どもの意見を尊重していない
過干渉の親は、子どもが考える意見を尊重していない傾向にあります。
例えば、子どもの進学や進路など親が心配になり、よかれと思い口出しをしてしまうケースがあります。
「学校はここを受験しなさい」、「将来はこうなりなさい」など、子どもが納得していない意見を押しつけることは過干渉の特徴の一つです。
子どもの友人関係に口を出す
子どもの友人関係に口を出すことも、過干渉の親にありがちな行為です。
親の個人的な観点で遊ぶ子どもを制限するなど、口を出すケースがあります。
親と子どもの見方は違うということをお互いに認識していないと、子どもは自分の世界を広げることができなくなってしまいます。
問題点・課題ばかりを指摘する
問題点や課題ばかりを指摘する行動も過干渉の親に当てはまりがちな特徴です。
子どもの長所より短所の方が目につきやすいため、褒めることよりも悪い点ばかりを指摘してしまいがちです。
親はよかれと思ってアドバイスをしているつもりでも、悪い点ばかりを言われ続けると、子どもの自信を奪ってしまいます。
完璧を求めやすい
子どもに対して完璧を求めやすい点も過干渉の親に見られる特徴です。
親が完璧主義である場合、子育てに熱心になり、子どもにも完璧を求めやすくなります。
しかし、子どものことを考えていても、子どもの能力以上に完璧を求めすぎてしまうと、親は子ども思い通りにならないときにストレスを感じ、子どもは親の期待に応えられない自分に落ち込むなどの負のスパイラルに陥ってしまいます。
過干渉の親がもたらす子どもへの影響
では、親の過干渉は子どもにどのような影響をもたらすのでしょうか。
過干渉の親がもたらす子どもへの影響として、以下のような点が考えられます。
●自分に自信が持てなくなる
●罪悪感を覚えやすくなる
●自分の意思で行動できなくなる
それでは詳しく解説します。
自分に自信が持てなくなる
代表的な悪影響として、過干渉によって子どもが自分に自信を持てなくなります。
過干渉の親が子どもの価値観や好きなことを否定すると、子ども自身が自分の選択に自信が持てません。
いつも自分が間違っているのではないかという気持ちになってしまい、子どもが自分から行動する意欲がなくなってしまうことがあります。
罪悪感を覚えやすくなる
過干渉の親に頻繁に口出しされ、感情的に怒られると、子どもは自分が悪いのではないかと罪悪感を覚えやすくなります。
親の言うことをしっかり聞ける子どもほど、心の中で罪悪感を持っていることもあります。
罪悪感を覚えやすい子どもは、人から注意を受けた時に、自分を責めてしまう傾向が強くなり、生きづらさを感じてしまうことがあります。
自分の意思で行動できなくなる
親の過干渉が強すぎる場合、自分の意思で行動できなくなる場合があります。
親の多くは子どものことを第一に考えていますが、親の思いが強いと子どもの自由な意思を奪ってしまう可能性があります。
子どもが自分に自信を持てなくなり、親に決定権を委ねるようになると、自分で決断することが難しくなってしまいます。
では、親自身、自分が過干渉ではないかと感じた時、どのようにすればよいでしょうか。 ●子どもの意思を尊重する 子どもとの正しい関係を維持するためにも、ぜひチェックしてください。 親は子どもと自分が同じように考えてしまいがちですが、親と子どもは違う人間で違う意思を持っているので、まず、子どもの自主的な主張を尊重しましょう。 親は子どもが失敗しないように先回りしてしまいがちですが、子どもの頃の小さな失敗はおおらかに受けとめ、失敗は子どもの経験と捉えてみましょう。 親はよかれと思い、先回りして子どもにすぐに指示をしてしまいがちです。 親が自分だけでは対処できないときは、専門的な支援機関に相談することも一つの方法です。 今回は、過干渉の詳細から過干渉の親の特徴、子どもへの影響、対処方法まで詳しく解説しました。
過干渉の親の対処方法として、以下のようなポイントがあります。
●子どもの失敗も経験と捉える
●子ども自身に考えさせる
●専門的な支援機関に相談する子どもの意思を尊重する
子どもの主張を受けとめ、親が子どもの意思を尊重していると、子どもは自分が認められたと感じ、自分に自信が持てるようになります。子どもの失敗も経験と捉える
失敗したときも感情的に怒らず、「どうしたらよかったか」「次はどうするか」などを一緒に考えてみましょう。子ども自身に考えさせる
自分である程度考える力がついた子どもには、子ども自身に「どうしたいか」「どうするとよいか」など考えさせてみるのもよいでしょう。
子どもの主体性や自立心を育み、自分で考えて行動できる大人に成長できるようにしていきましょう。専門的な支援機関に相談する
専門的な知識のある専門家や支援機関に相談することで、自分の子育てを客観的に把握できるようになります。
子育て支援関係の施設や、園や学校の先生やスクールカウンセラーなど相談先は豊富にあるため、利用しやすい支援機関に相談してみるとよいでしょう。まとめ
子どもによかれと思う気持ちから、親が過干渉になってしまうケースは少なくありません。
親の過干渉が、子どもの自信の喪失や自己決定が出来なくなるなど、影響を及ぼすことがあります。
ぜひ当記事で紹介した対処方法を参考にしながら、子どもと適切な関係を築き、子どもの主体性や自立心を育んでいきましょう。