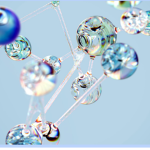「どうして発達障害は起こるの?」「自分の育て方が悪かったのでは…?」そんな不安や疑問を抱えている方がおられるかもしれません。目には見えにくい発達障害の特性は、周囲と比べることで心配が大きくなりがちです。
しかし、発達障害は決して誰かのせいで起きるものではなく、脳の特性や様々な要因が総合的に関係していることがわかってきています。また、誤ったイメージや古い考え方が、保護者の気持ちを追い詰めてしまっている場合もあるかもしれません。
そこで本記事では「発達障害」はなぜ生まれるのかという基本的な理解から、よくある誤解と正しい知識、そして子どもにとって大切なサポートの考え方まで解説していきます。
発達障害はどうして起こるのか?
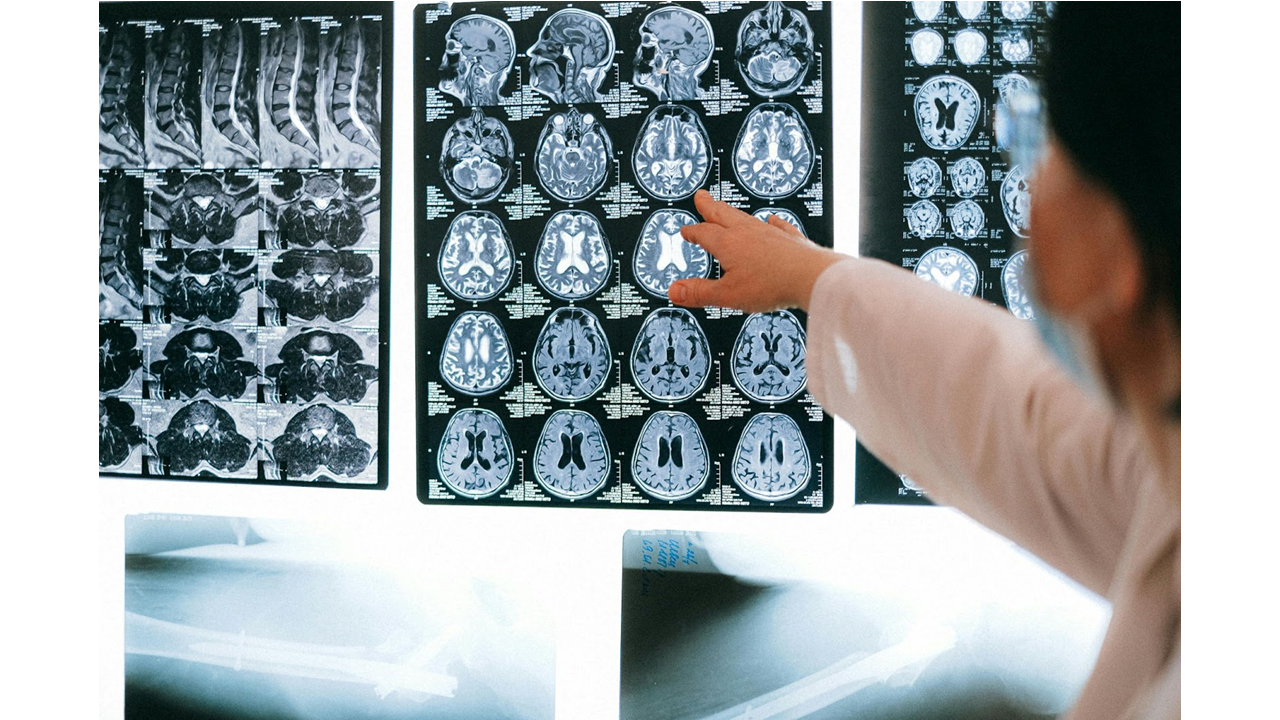
「発達障害は何が原因なの?」「遺伝や妊娠中のことと関係あるの?」など、発達障害の理由について知りたいと感じている方もおられることと思います。
特に診断を受けたばかりの頃には、どうしてそうなったのか、どう関わっていけばいいのかと、戸惑いや不安でいっぱいになることでしょう。
ここでは、発達障害の主な要因とされている様々な内容をわかりやすく整理し、保護者の方が安心して理解を深められるように解説していきます。
発達障害の定義と主な種類
発達障害とは、脳の機能に関する障害で、通常、幼少期にその症状が現れます。主な種類として以下が挙げられます。
自閉スペクトラム症(ASD)
他者とのコミュニケーションや社会的関係の形成が難しく、特定の興味や行動のパターンが見られます。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
注意力の持続が難しい、多動性や衝動的な行動が特徴です。
学習障害(LD)
全体的な知的発達には遅れがないものの、読む、書く、計算するといった特定の能力の習得や使用に困難を伴います。
これらの障害は、それぞれ異なる特性を持ち、子どもによって現れ方も様々です。
発達障害が起こる原因とは
発達障害の原因に関する研究は今もなお進められており、原因は一つではなく、さまざまな要因が関与していると考えられています。主な要因として以下が挙げられます。
| 遺伝的要因 | 家族内で同様の特性が見られることから、遺伝が関与している可能性があります。 |
|---|---|
| 脳の機能や構造の違い | 脳の特定部位の活動や情報伝達に違いがあることが指摘されています。 |
| 環境的要因 | 妊娠中の母体の健康状態や出生時の状況など、環境的な影響も考えられています。 |
しかし、これらの要因がどのように組み合わさって発達障害を引き起こすのか、現時点では完全には解明されていません。
遺伝的な要因とされるもの
発達障害は家族内での発生率が高いことから、遺伝的な要因が関与していると考えられています。
具体的には、特定の遺伝子の変異や組み合わせが、脳の発達や機能に影響を及ぼす可能性が指摘されています。しかし、環境要因などと複合的に絡み合って発症すると考えられているのが現状です。特定の遺伝子の変異が関連しているケースも報告されていますが、これらの遺伝子がどのように発達障害の症状を引き起こすのか、詳細はまだ研究段階にあります。
妊娠中・出生前後の環境要因
発達障害はさまざまな要因が関係するとされており、その中には妊娠中や出生前後の環境要因も含まれます。
たとえば、妊娠中の母体の健康状態や生活習慣(栄養状態、喫煙、アルコール摂取)、感染症などは、胎児の脳の発達に影響を与える可能性があるとされています。ただし、これらはあくまで「リスク要因」であり、すべてのケースで発達障害が起きるわけではありません。大切なのは、妊娠期から安心できる環境を整え、気になることがあれば専門機関に相談することです。
明確な原因は不透明な現状
発達障害の原因については、多くの研究が進められていますが、未だ明確には解明されていません。
遺伝的要因、脳の機能的・構造的な違い、環境要因など、複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。そのため、発達障害のある子ども一人ひとりの特性やニーズを理解して、個々に合わせた支援が重要なのです。
発達障害に関する誤解と正しい理解

発達障害について、今でも「自分の育て方のせいでは?」「しつけが足りないのでは?」といった誤解が根強く残っています。こうした誤解は、保護者自身を苦しめるだけでなく、子どもがありのままの自分で過ごすことを難しくしてしまうこともあります。
発達障害は、生まれ持った脳の特性に関係しています。そして「できないこと」がある一方で、「得意なこと」や「強み」もたくさん持っています。
本項では、発達障害に関する誤解を一つずつ解きながら、子どもを理解し、サポートするために大切な視点や関わり方についてお伝えしていきます。
育て方が原因ではない
発達障害は、親の育て方や愛情のかけ方が原因で起こるものではありません。先述しているように、発達障害は主に脳の機能や神経伝達の仕組みや、遺伝的要因や環境的要因が複雑に関係しているとされています。
そのため、保護者の努力やしつけ方の問題ではないことを、まず理解することが大切です。過去には「親のせい」とされてきた時代もありましたが、現在は科学的に否定されています。大切なのは「どう育てるか」ではなく「どう支えるか」です。自責の念を抱くのではなく、子どもの特性を受け入れたうえで前向きに関わる姿勢が、子どもの安心や成長につながるでしょう。
発達障害=できないではない
発達障害があるからといって「何もできない」というわけではありません。むしろ、特定の分野で優れた集中力や独創性を持っている子どもも多くいます。
たとえば、記憶力が非常に良かったり、興味のある分野では大人顔負けの知識を持っていることもあります。周囲がその子の「できないこと」ばかりに目を向けてしまうと、子どもは自信を失いがちです。逆に「できること」や「得意なこと」に注目して関わることで、自己肯定感が育ちやすくなります。子どもが自分らしく力を発揮できる環境を整えることが、支援の第一歩です。
子ども本人のせいではない
発達障害は、子ども本人の努力不足や性格のせいではありません。集中できない・順番を守れない・言葉の使い方が独特などの行動も、脳の特性や感覚の違いによって起こるものです。
周囲の理解がないことで「わがまま」「しつけができていない」など誤解されがちですが、本人は決して怠けているわけではなく、「うまくできない」だけなのです。こうした誤解を解くには、まず大人が発達障害への正しい知識を持つことが大切でしょう。「どうしたらできるようになるか」を一緒に考える姿勢が、子どもにとって大きな安心となります。
早期的な理解と支援が重要
発達障害の特性は、早い段階で気づき、周囲が理解して関わることで、子どもの成長や社会適応に大きなプラスになります。特性に合った支援をすることで、苦手なことをサポートしながら得意な力を伸ばすことができるからです。
「少し気になるかも」と感じた段階で、保健師や小児科医などに相談することは決して早すぎることではありません。早期に支援につながることで、子ども自身も「わかってもらえる」という経験ができ、自信を持って過ごせるようになります。大切なのは、子どもに合った関わり方を見つけていくことです。
周囲の理解と協力が大切
発達障害を持つ子どもが安心して過ごすには、家庭だけではなく、保育園・学校・地域社会など、周囲の理解との協力も欠かせません。
特性を理解したうえでの声かけや環境調整は、子どもにとって「過ごしやすさ」や「安心感」につながります。また、家庭で一人で抱え込まずに、必要に応じて専門機関に相談することも大切です。
主な相談・支援先
●地域の保健センター(乳幼児健診や育児相談などを実施)
●児童発達支援センター(就学前の子どもへの発達支援)
●子ども家庭支援センター(子育てに関する広い相談に対応)
●医療機関/小児科・児童精神科等(専門的評価や診断が可能)
早めに頼れる場所を知っておくことで、心にゆとりが生まれ、前向きに子どもと向き合えるようになります。
発達障害の原因と正しい理解のまとめ
発達障害は、育て方や本人の努力によるものではなく、脳の特性や遺伝的要因、妊娠中・出生時の環境要因など、複数の要素が重なって起こると考えられています。
ただし、明確な原因はまだ完全には解明されていません。「発達障害=できない」ではなく、特性を理解し、得意を伸ばすことで大きな可能性を発揮する子どもも多くいます。早い段階で気づき、周囲が理解し支援することで、子どもは安心して成長できるでしょう。
保護者の方だけで抱え込まず、保健センターや医療機関など専門機関の力を借りることも大切で、正しい理解と温かいサポートが、子どもの未来を広げる大きな力になります。
参考元
文部科学省「発達障害について」
https://www.chamomile.jp/blog/is-developmental-disorder-congenital
厚生労働省「発達障害の理解のために」
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/17.html
国立成育医療研究センター研究所
https://www.niph.go.jp/journal/data/59-4/201059040004.pdf