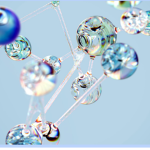「10ヶ月になってもハイハイをしないけれど、大丈夫なのかな…?」そう感じている保護者の方は少なくありません。周りの子どもが元気に動き回っていると「うちの子どもは遅れているのかも…」と心配になるのは自然なことです。
ハイハイは発達過程の一つで、時期や進み方には個人差があるため、焦らず見守ることが大切です。それと同時に、早めに気づいてできるサポートもあります。
そこで本記事では、10ヶ月でハイハイをしないことは問題なのかどうか、考えられる原因やご家庭でできるサポートについて解説していきます。
10ヶ月でハイハイしないのはおかしい?

「他の赤ちゃんはもうハイハイしているのに…」そんな不安を感じている方もいるでしょう。一般的にハイハイは生後6〜10ヶ月頃に始まるといわれていますが、これはあくまで目安であり、全ての赤ちゃんに当てはまるわけではありません。
中には、ずりばいやおすわりのまま移動する場合もあれば、ハイハイをほとんどせずにつかまり立ちに移行する場合もあります。
ここでは、10ヶ月頃の赤ちゃんの発達の目安や見守り方のポイントについて解説します。
10ヶ月の発達段階の目安
一般的に、赤ちゃんは生後6〜10ヶ月頃にハイハイを始めることが多く、厚生労働省の調査結果によると、生後8ヶ月が最も多い傾向にあるとのことです。 しかし、これはあくまで目安や傾向であり、発達のスピードや順序には個人差があります。10ヶ月頃の赤ちゃんには、以下のような発達が見られることが多いです。
●おすわりが安定する
●ずりばいで移動する
●つかまり立ちを始める
ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、すべての赤ちゃんが同じ時期に同じ行動を示すわけではありません。
ハイハイしない場合もある?
ハイハイは多くの赤ちゃんが経験する発達段階ですが、全ての赤ちゃんがハイハイをするわけではありません。中には、ハイハイをせずにおすわりの姿勢から直接つかまり立ちや歩行に移行する場合もあります。 このような場合でも、他の発達が順調であれば過度に心配する必要はありません。
発達には個人差がある理由
赤ちゃんの発達には、以下のような要因が影響し、個人差が生じます。
●遺伝的要因:親や兄弟の発達傾向
●環境的要因:家庭内の刺激や育児環境
●性格や気質:興味や好奇心の度合い
これらの要因が組み合わさり、赤ちゃん一人ひとりの発達パターンが形成されます。そのため、周りと比較して焦るのではなく、それぞれのペースを尊重し、温かく見守ることが大切です。
こんな場合には注意が必要
以下のような場合には、一度専門家に相談することをおすすめします。
●全身の筋肉の緊張が極端に低い、または高いと感じる場合
●10ヶ月を過ぎてもおすわりや寝返りが見られない場合
●左右どちらかの手足のみを頻繁に使うなど、偏りがある場合
これらの兆候が見られる場合、発達に関する専門的な評価が必要な場合があります。地域の保健センターや小児科医に相談し、適切なアドバイスを受けることも重要です。
赤ちゃんの成長は一人ひとり異なります。焦らず、それぞれのペースを大切にしながら、必要に応じて専門家の意見を取り入れていきましょう。
ハイハイをしない原因
「どうしてハイハイをしないんだろう?」と原因を知りたい方に向けて、ここでは考えられる理由を解説します。
体の筋力バランスや感覚の特性、育つ環境や関わり方など、ハイハイをしない背景にはさまざまな要因が考えられます。また、性格や好みによっても動き方に違いが出ることもあるでしょう。
本項では、主な原因として「体の使い方」「感覚面の影響」「モチベーションや環境」などに分けて解説していきます。
体の使い方のクセや筋力の発達
赤ちゃんがハイハイをしない理由の一つに、体の使い方のクセや筋力の発達状況が関係している場合があります。
ハイハイをするためには、首や肩、背中、腹部、手足などの筋肉の発達が必要です。しかし、これらの筋力が十分でない場合、四つん這いの姿勢を維持するのが難しく、結果としてハイハイを避けることがあります。たとえば、座ったままでの移動を好む赤ちゃんは、ハイハイをせずにおすわりから直接立ち上がることもあります。このような場合でも、他の運動発達が順調であれば、過度に心配する必要はありません。
感覚過敏や感覚鈍麻からの影響
感覚過敏や感覚鈍麻(感覚の鈍さ)といった感覚の特性も、赤ちゃんがハイハイをしない要因となることがあります。
感覚過敏の赤ちゃんは、床に手や膝が触れる際の感触を不快に感じ、ハイハイを避けることがあります。一方で、感覚鈍麻の場合、床からの刺激を十分に感じ取れず、ハイハイへの興味や必要性を感じにくいことがあります。これらの感覚の特性は、赤ちゃん一人ひとり異なり、日常生活の中での行動や反応にも影響を与えることがあるでしょう。感覚過敏や感覚鈍麻が疑われる場合、専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
モチベーションや環境的な影響
赤ちゃんがハイハイをしない背景には、モチベーションや周囲の環境も関係している場合もあります。
たとえば、赤ちゃんが興味を持つおもちゃや人が手の届く範囲に常にある場合、自ら移動する必要性を感じず、ハイハイをしないことがあります。また、床が滑りやすい、硬い、冷たいなど、赤ちゃんにとって不快な環境である場合も、ハイハイを避ける原因となるでしょう。さらに、赤ちゃんが過度に抱っこされている、歩行器などの使用が多いなど、自分で移動する機会が減ると、ハイハイをする動機が低下することも考えられます。
赤ちゃんの発達は個人差が大きく、ハイハイをしないことが早急な問題を示すわけではありません。しかし、他の発達面でも気になる点がある場合は専門家に相談することもおすすめします。
ハイハイをしない場合のサポート

「このまま見守っていていいのかな?」「何か家庭でできることはある?」と悩んでいる方に向けて、この章ではハイハイを促すためのサポート方法をご紹介します。
たとえば、赤ちゃんが安心して動けるスペースを整えたり、うつぶせ遊びを取り入れたりすることで、自然な形でハイハイを引き出すきっかけになります。また、不安な場合は早めに相談できる専門機関を知っておくことも大切でしょう。
本項では、今日からでも取り入れやすい関わり方や、相談すべきサインと窓口について、やさしくご案内します。
安心できるスペースづくり
赤ちゃんが自由に動き回れる安全な環境を整えてあげることが大切です。
床にマットを敷いたり、家具の角にコーナーガードを取り付けるなどして、怪我のリスクを減らしましょう。また、部屋の中を整理し、赤ちゃんが興味を持って移動したくなるようなおもちゃを少し離れた場所に配置することで、自然とハイハイを促すことにつながります。
うつぶせ遊びを取り入れる
うつぶせの姿勢は、赤ちゃんの首や背中、腕の筋肉を鍛えるのに効果的です。
赤ちゃんが機嫌の良い時に、少しずつ試してみましょう。たとえば、うつぶせの状態でお気に入りのおもちゃを目の前に置き、手を伸ばして取るよう促すと、自然に筋力を鍛えることができます。ただし、赤ちゃんが嫌がる場合は無理をせず、少しずつ慣れさせることが必要です。
不安な場合の相談先とタイミング
赤ちゃんの発達には個人差がありますが、以下のような場合には専門家への相談を検討すると良いでしょう。
●10ヶ月を過ぎても寝返りやおすわりができない
●筋肉の緊張が極端に強い、または弱いと感じる
●視線が合わない、反応が乏しいなどの様子が見られる
相談先としては、地域の保健センターや小児科医、子育て支援センターなどがあります。早めに専門家に相談することで、必要なサポートやアドバイスを受けることができ、保護者の不安も軽減されるでしょう。
赤ちゃんの成長は一人ひとり異なります。焦らず、温かく見守りながら、必要に応じて適切なサポートを行っていきましょう。
まとめ
10ヶ月の段階でハイハイをしない子どもに対して不安を感じてしまう保護者は多くいますが、ハイハイの時期や有無には個人差があるため、必ずしも検査が必要とは限りません。
中にはずりばいで移動したり、ハイハイをせずに立ち上がる赤ちゃんもいます。発達には筋力や体の使い方、感覚の特性、環境や性格などさまざまな要因が影響しています。もし他の発達段階にも遅れや気になる点があるのであれば、早めに専門家に相談することも重要でしょう。
また、家庭では安心して動ける環境を整えたり、うつぶせ遊びを取り入れたりすることで、自然にハイハイを引き出すサポートが可能です。焦らず、それぞれのペースを尊重しながら、必要なサポートを行っていきましょう。
参考元
各 支援機関 等
厚生労働省