「そんな言い方しないで」と言いたくなるような、子どもの口から出たひどい言葉にドキッとした経験はありませんか。
そのような友達や家族に向けられる“ちくちく言葉”は、相手の心を傷つけるだけでなく、人間関係にも影響します。反対に、思いやりのある“ふわふわ言葉”は、お互いの関係を温かくし、安心できる場をつくります。
そこで本記事では、ちくちく言葉の意味や背景、ご家庭や学校でできる対応、そして自然と優しい言葉が増える環境づくりの工夫についてわかりやすく解説していきます。
ちくちく言葉とは?子どもが使う言葉の大切さ

「そんな言い方しなくてもいいのに…」と、子どもの口から出た一言に驚いた経験はありませんか?何気なく発した言葉でも、相手の心に傷を残すことがあります。これが、いわゆる「ちくちく言葉」です。
子どもは日々のやり取りを通じて、言葉の選び方や伝え方を学んでいきます。そのため、使う言葉は、相手との関係性や自己肯定感に大きな影響を与えるのです。
そこで本記事では「ちくちく言葉」の意味や背景を整理し、言葉の大切さについて解説していきます。
ちくちく言葉の意味と由来
「ちくちく言葉」とは、相手の気持ちを傷つけてしまうような言葉を指し、教育現場では「心にトゲを刺す言葉」として扱われます。
子どもが無意識に、「バカ」「キモい」「あっちへ行け」などの言葉を使ってしまう背景には、発達段階での言葉選びの未熟さや環境の影響があります。こうした言葉が、子ども同士の関係性に思わぬ摩擦を生むこともあるため注意が必要です。
なぜちくちく言葉が問題なのか
ちくちく言葉は単なる悪口ではなく、言われた側の心に深く刺さり、孤立感や人間関係のトラブルにもつながるため注意が必要です。
また、言う本人も無意識にストレス発散をしてしまい、感情の暴走につながる恐れがあります。「ちくちく言葉」の多い環境にいると、心が緊張し、心身ともに不健全な状態に陥りやすくなるため問題なのです。
子どもがちくちく言葉を使う背景
言葉選びが未発達な時期である子どもは、感情や不安を表現する方法がまだ未熟なため、相手を思いやらずに「ちくちく言葉」を使ってしまうことがあります。
言葉の使い方を学ぶ機会が少なかったり、周囲が見本を示していないと、無意識に模倣してしまうこともあるかもしれません。また、友達との関係で自分を守ろうとする気持ちから、否定的な表現を使ってしまうこともあります。
ふわふわ言葉とは

ちくちく言葉とは反対に、相手の心を優しく包むような言葉で、「ありがとう」「すごいね」「がんばったね」など、言われた人が嬉しい気持ちになれる表現を「ふわふわ言葉」と言います。
ちくちく言葉は、本人が無意識に使ってしまっても相手にダメージを与えるため、教育現場ではふわふわ言葉への言い換えが重視されています。これにより言葉の受け手だけではなく、発信者自身の自己肯定感も育まれます。
ちくちく言葉・ふわふわ言葉の一覧

ちくちく言葉やふわふわ言葉にはさまざまな種類があります。
続いては、それぞれの言葉のなかでも子ども達の間で使われることが多い、ちくちく言葉・ふわふわ言葉を一覧で紹介します。
よく使われるちくちく言葉の一覧
子どもたちがよく使ってしまうちくちく言葉には次のようなものがあります。
- 「バカ」
- 「アホ」
- 「ウザい」
- 「キモい」
- 「あっちへ行け」
- 「関係ない」 など
こうした言葉は本人に悪意がなくても、相手を深く悲しませてしまうことがあります。言葉を紡ぐ前に「相手はどう感じるか?」と一呼吸置く習慣が大切です。
よく使われるふわふわ言葉の一覧
子どもたちがよく使うふわふわ言葉には次のようなものがあります。
- 「ありがとう」
- 「一緒にやろう」
- 「すごい」
- 「楽しいね」
- 「えらいね」
- 「嬉しいよ」 など
ふわふわ言葉は大人であっても言われると心が穏やかになり嬉しい気持ちになるものばかりです。ポジティブで優しいふわふわ言葉を自然に使えることは、子ども達がこれから社会で生きていくうえで重要なスキルになるとも考えられるのではないでしょうか。
ちくちく言葉をふわふわ言葉に言い換えることで期待できる効果
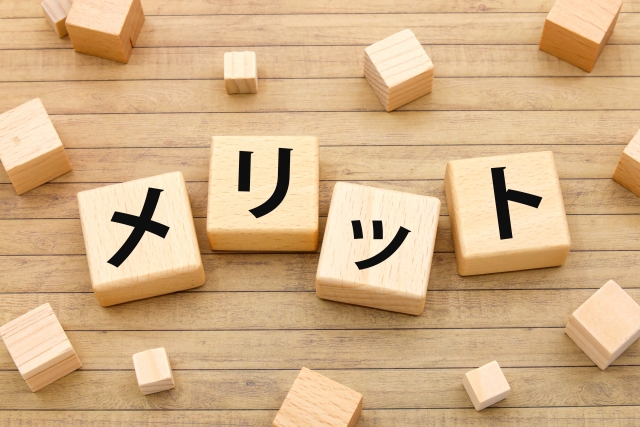
ちくちく言葉をふわふわ言葉に言い換えることで、子ども達にどのような効果が期待できるのでしょうか。
言葉使いを換えることで期待できる効果には以下のものが挙げられます。
人間関係が円滑になる
ちくちく言葉をふわふわ言葉に言い換えることで、人間関係を円滑にしてトラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。
特に、思った事を考え無しに発してしまいやすい子ども達の間では、ちくちく言葉が原因で対人関係のトラブルが起きてしまうことも珍しくありません。意識的にふわふわ言葉を使うことでトラブルを避け、円満に他人と関わるスキルが向上する効果も期待できます。
自己肯定感が上がる
ふわふわ言葉のなかには、感謝の気持ちを伝える言葉や相手を褒める言葉が多く使われています。そのため、ふわふわ言葉を受け取った相手は自己肯定感が高まりポジティブな気持ちになりやすいでしょう。
相手にふわふわ言葉を伝えることで、自分にもふわふわ言葉が返ってきやすくなります。そうすることで、自分自身も自己肯定感が高まり、子どもに自信を持たせる効果も期待できるでしょう。
ふわふわ言葉による自尊感情を育む研究結果

上越教育大学の教育実践研究として小学2年生を対象に行われた研究では、ふわふわ言葉による子どもの自尊感情向上の結果が報告されています。
この研究では、ふわふわ言葉の授業を行った後、自己評価アンケートを作成して子ども達に回答してもらいました。アンケートには「自分のことが好きですか?」や「自分の好きなところはどこですか?」など、自尊感情に関する項目が多く設定されています。
その後、毎日終わりの会で「ふわふわタイム」という時間をとり、自己評価や他者評価をふわふわ言葉で行う機会を設けました。
ふわふわタイムを始めて約1か月後、改めて子ども達に自己評価アンケートを行ったところ、以前のアンケート結果と比べてポジティブな回答数が増えていたと報告されています。
ふわふわタイムによって自尊感情が育まれた結果、「自分のことが好きですか?」という質問に「あてはまる」と回答した子どもの割合は、活動実施前に比べて16%増加していました。
参考:自尊感情を育む学級活動の工夫
ちくちく言葉への対応とご家庭や学校でできること

「そんなつもりじゃなかった…」という子どもの言葉も、受け取る側には大きなダメージになることがあります。そこで重要なのが、ご家庭や学校での適切な対応です。
頭ごなしに叱るだけではなく、「どう言い換えれば良かったか」を一緒に考えることで、子どもは自分の言葉に責任を持つ力を育てられます。また、日常の中でポジティブな言葉を意識的に増やす工夫も効果的です。
そこで本項では、日々のやり取りを改善し、優しい言葉を選べるようになるための具体的な方法を紹介します。
大人が率先してふわふわ言葉を使う
子どもは身近な大人の言動をよく聞いています。そのため、まずは大人が率先してふわふわ言葉を使うことを意識してみてください。
子どもに教える前に、自分自身がちくちく言葉を使っていないか顧みてみましょう。まずは大人が子どもにふわふわ言葉を使う姿を見せることで、子どもも自然とふわふわ言葉を受け入れられるようになります。
また、子どもが優しい言葉を自然に使えるようになるには、大人がお手本を示すことが大切です。ポイントは以下の通りです。
- 大人自身が「ふわふわ言葉(あたたかな言葉)」※を日常的に使う
- 子どもは大人の言葉遣いを模倣しやすい
- 安心できる言葉のやり取りが、コミュニケーション力の基盤になる
- 子どものプラスの言葉や行動を褒め、強化する
※例「ありがとう」「すごいね」「よくがんばったね」など、相手を肯定する言葉を意識
このような習慣が、ご家庭や学校での言葉の雰囲気をやわらげ、子どもの心の安定にもつながります。
ちくちく言葉に対して過度な指導をしない
ちくちく言葉を辞めさせようとすると、些細な言動にも過度に注意してしまうことがあります。しかし、この方法は逆効果です。
なるべく、ちくちく言葉に関しては反応せずスルーするようにしましょう。
過度に指導をすると、そのストレスで余計に感情が高ぶりちくちく言葉が出やすくなってしまうこともあります。万が一子どもがちくちく言葉を使ってきても「へー、そうなの」位の反応で、過度に叱らず流す方法がおすすめです。
ふわふわ言葉を使ったときにたくさん褒める
子どもがふわふわ言葉を率先して使ったときには、大げさな位褒めましょう。たくさん褒められることで子どもも気分がよくなり、ふわふわ言葉とポジティブな感情が紐づけされます。
また褒められたい、ポジティブな気持ちになりたいという欲求からふわふわ言葉を率先して使うようになり、自然と身に付きやすくなるでしょう。
ちくちく言葉をふわふわ言葉に言い換える練習をしてみよう

なかには、ちくちく言葉をどのようなふわふわ言葉に言い換えればいいのか分からないという子どももいます。学校や家庭などで、ちくちく言葉をふわふわ言葉に言い換える練習をして、地道に言葉のバリエーションを増やしていくことも大切です。
- 「バカ」と友達に言ったとき→「何が嫌だったのかな?」「どうしてほしかったのかな?」などと聞き、感情を受け止め、別の言葉に置き換える
- ご家庭や学校で「言い換えゲーム」や「言い換えカード」を活用する
- 「今のちくちく言葉だったね。ふわふわ言葉にすると?」と具体的に問いかける
- 続けることで、子どもが自分で訂正・言い換えできるようになる
- 場面ごとに「この言葉はどんな気持ちになる?」などと話し合う
- 学級やご家庭で「嬉しい言葉/つらい言葉」を一緒に整理する
- 「楽しかったこと」「うれしかったこと」など、日常でポジティブな感情を共有する時間をつくる
- トラブルがあったときは「嫌だった」「びっくりした」など、感情を安全に言葉にする練習をする
- 司会役や聞き役を交代しながら、お互いの話を最後まで聞く習慣を身につける
- 「今の言葉、相手はどんな気持ちになるかな?」と問いかける
- 「もし言い直すなら、どんなふうに言う?」と代替案を本人に考えさせる
- 選択肢を示して「AとBならどちらの言葉を使う?」と促す
- 正しい言葉を使えたときは、必ず肯定的にフィードバックする
- 読み聞かせや物語の感想共有で「登場人物の気持ち」を考える
- ロールプレイ(役割交代)で、相手役を体験する
- クラスやご家庭で「ありがとう」「助かったよ」など感謝の言葉を意識的に使う
- 行事やグループ活動で、助け合う場面を意図的に作る
こうした日頃の習慣と積み重ねが、子どもの言葉選びの力を高めていきます。
ちくちく言葉やふわふわ言葉の学習におすすめの絵本

学校の授業でも習うちくちく言葉・ふわふわ言葉ですが、すぐに子どもに身に付けて欲しいと思うのであれば絵本を使った家庭学習に取り組むのもおすすめです。
視覚的な教材やストーリーは、言葉の影響を理解する助けになります。おすすめの活用方法は以下のとおりです。
このような活動は、楽しく学びながら優しい言葉の定着を促すことができます。
続いては、ちくちく言葉やふわふわ言葉の学習にぴったりなおすすめの絵本を紹介します。
ちくちくとふわふわ
CHICORA BOOKSから出版されている絵本で、著者は「なないろ」さんです。3~5歳を対象とした幼児向けの絵本ですが、直観的にちくちく言葉やふわふわ言葉を学べるため、小学校低学年にもおすすめです。
ちくちくのキャラクター・スパイキーとふわふわのキャラクター・フラッフィーを通して、楽しくちくちく言葉やふわふわ言葉について学べます。
ふわふわとちくちく: ことばえらびえほん
教育学者・齋藤孝氏が監修して制作された「ふわふわとちくちく:ことばえらびえほん」は、ポップでかわいいイラストから分かりやすくちくちく言葉とふわふわ言葉を学ぶことができます。
絵本として読み進めるだけでなく、ワークブックのように自分で考える教材としても使えるため、親子でちくちく言葉やふわふわ言葉について考える機会を与えてくれるでしょう。
ちくちく言葉を減らすための環境づくり

「何度注意しても、またきつい言葉を使ってしまう…」そんなときは、子どもを取り巻く環境そのものを見直す必要があります。
安心して気持ちを伝えられる空気や、選びたい言葉を考える余裕があれば、ちくちく言葉は自然と減っていきます。さらに、学校やご家庭での人間関係づくりや、思いやりを育てる活動が大切です。
ここでは、子どもが優しい言葉を選びやすくなる環境づくりのポイントを、具体例とともに解説します。
子ども同士が気持ちを伝えやすい場面をつくる
ちくちく言葉を減らすには、安心して気持ちを話せる環境が必要です。ポイントは以下の通りです。
感情を受け止めてもらえる経験が増えるほど、攻撃的な言葉は減っていきます。
叱るより選ばせる声かけの工夫をする
ちくちく言葉を使ったとき、頭ごなしに叱るよりも「どの言葉を選ぶか」を考えさせる方が効果的です。
こうしたやり取りは、自分で言葉を選ぶ意識を育て、思慮深いコミュニケーションにつながります。
思いやりやことばの力を育てる取り組みをする
日常生活や学びの中で「相手の立場になる」経験を増やすことが大切です。
こうした経験は、言葉の選び方だけでなく、相手を思いやる気持ちそのものを育てます。
ちくちく言葉を大人が言い換えるなど手本を見せて、思いやりのある言葉選びを
ちくちく言葉は「バカ」「キモい」など相手の心にトゲを刺すような表現で、悪意がなくても相手を傷つけ、人間関係や自己肯定感に影響してしまいます。
背景には、言葉選びの未熟さ、周囲の言葉環境、自己防衛としての否定的表現などがあります。一方、「ありがとう」「すごいね」などの“ふわふわ言葉”は関係を温め、安心感を与えます。
減らすためには、大人がふわふわ言葉を使って手本を示し、子どもに言い換えの練習をさせることが大切です。叱るだけでなく、どう言い換えるかを一緒に考え、日常でポジティブな言葉を意識的に増やします。絵本やワークシートの活用も効果的でしょう。
また、安心して気持ちを伝えられる場や、言葉を選ぶ機会を増やす工夫、相手の立場を考える経験を積むことで、思いやりと適切な言葉選びの力が育ち、自然と優しい言葉が増えていきます。















