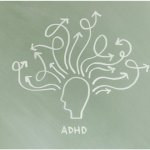ADHDの中学生を持つ親御さんの中には、「子どもが勉強できないと悩んでいるが、どうしたらいいか分からない」「ADHDの子どもにどのように向き合えばいいか悩んでいる」など、不安な気持ちを持つ方がいるでしょう。また、「もしかしたら子どもがADHDかもしれない」という悩みを持つ親御さんも少なくありません。
そこで本記事では、ADHDの中学生が勉強を進めるポイントや、親が気をつけるべきことを紹介します。また、ADHDの特徴やよくみられる行動、診断チェックリストなども解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ADHDとは?

ADHD(注意欠如多動性障害)は、不注意・多動性・衝動性の3つの症状を特徴としている生まれつきの精神疾患です。3つの症状がすべて同時に現れるわけではなく、「不注意」が目立つ人もいれば、「多動性」と「衝動性」を併せ持つ人もいるなど、人によって症状はさまざまです。
「不注意」の症状が強い場合は、宿題や課題などの提出物を頻繁に忘れたり、時間を守れずに遅刻が多かったりするなどの特徴が見られます。一方、「多動性」や「衝動性」が強い場合は、計画を立てて行動することが苦手であったり、授業中に落ち着きがなかったりするなどの特徴が見られます。
ADHD診断チェックリスト
「子どもがADHDか分からない」という場合は、以下のチェックリストを参考にしてください。
・忘れ物やなくし物が多い
・話しかけても聞いていない
・約束を忘れてしまう
・宿題や遊びなどを途中でやめてしまう
・整理整頓ができない
・じっとしていられず、手足をそわそわ動かす
・授業中に席を離れてしまう
・静かにすることができず、おしゃべりが多い
・順番を抜かしてしまう
・友人や家族がしていることをさえぎる
上記に多く当てはまっていると、ADHDである可能性は高いと言えます。しかし、ADHDの症状は人によって異なります。当てはまる数が少なくてもADHDの場合があるため、心配であれば医師に相談しましょう。
ADHDの長所と短所
ADHDの特性や特徴は、長所にも短所にもなりえます。長所として挙げられる点は、以下の通りです。
・興味がある物事に対して、強い集中力を発揮する
・好奇心旺盛
・決断から行動に移すまでのスピードが速い
一方、短所といわれる点は、以下の通りです。
・ケアレスミスしやすい
・整理整頓が苦手で、物をなくしやすい
・苦手なことを先延ばしにしがち
ADHDの子どもを持つ親は、長所を伸ばしながら短所をサポートすることが大切です。
女子特有の症状
ADHDは男子に多いと言われていますが、女子にも見られ、特有の症状があります。女子特有の症状は、「不注意と過度の空想」です。3歳〜5歳ごろにあらわれる症状は、「成長の一環」と判断され、見過ごされ、8歳を過ぎた頃に「ADHD」と診断されることが多い傾向にあります。
また、女子は注意欠陥や多動性が目立ちにくいため、親や先生が気づかずに診断が遅れるケースもあります。「ADHDかもしれない」と思ったら、チェックリストを活用して確認し、早めに医師に相談することが大切です。
ADHDの中学生によくみられる特徴や行動

続いて、ADHDの中学生によくみられる特徴や行動について紹介します。ADHDの場合、学校生活で支障を感じるときは不注意の特性によるものが多い傾向です。
・勉強や授業に集中できない
・整理整頓や持ち物の管理が苦手
・宿題や課題など計画的に勉強できない
・複数のことを同時進行できない
・頼まれたことを断れない
・集団行動や学校行事への参加が苦手
・頻繁に体調不良を起こす
それぞれ、詳しく解説します。
勉強や授業に集中できない
ADHDの中学生は、勉強や授業に集中できない場合があります。興味がある事柄には集中力を発揮する一方、興味がない事柄には注意散漫となり、集中力が持続しにくいためです。
また、授業中に聞こえた話し声に注意が向いてしまい、先生の話が頭に入らないケースもあります。
整理整頓や持ち物の管理が苦手
ADHDの中学生は、整理整頓や持ち物の管理が苦手であることが多いです。中学校では、個人ロッカーで持ち物を管理する場合がほとんどですが、ADHDの中学生は教科書やノートでいっぱいになっていたり、散らかっていたりするケースが見られます。
また、家庭では脱いだ服をそのままにしていたり、親に見せなければいけない書類を渡し忘れたりなど、親が困ってしまう場面もあります。
宿題や課題など計画的に勉強できない
ADHDの中学生は、宿題や課題などを計画的に勉強できない場合があります。スケジュール管理が苦手な特性を持っている子どもは、宿題や課題を先延ばしにする傾向があるためです。子どもによっては、「締め切りを気にしていない」「そもそも宿題や課題があることを忘れていた」というケースもあります。
その結果、宿題や課題を提出できず、学校の先生から怒られたり、成績に影響したりすることも、少なくはありません。
複数のことを同時進行できない
複数のことを同時進行できないADHDの中学生は、多く見られます。脳の情報処理能力の特性から、一度に2つ以上の情報を処理することが困難なためです。具体的には、先生の話を聞きながらノートをとったり、たくさんの指示を出されたときに優先順位をつけられなかったりします。
頼まれたことを断れない
ADHDの中学生は、先生や友人などから頼まれたことを断れない場合があります。ADHDは人柄が良く、正義感が強い一面があるためです。そのため、周りから頼みごとをされる機会が多く、衝動的に引き受けてしまいます。
また、「断って嫌われたくない」という思いから、複数の頼まれごとを同時に引き受けてしまうケースもあります。その結果、遂行できない頼まれごとがでてきたり、心身の体調を崩したりすることも少なくありません。
集団行動や学校行事への参加が苦手
ADHDは、集団行動や学校行事への参加が苦手な場合があります。いつもと異なる環境に身を置いたり、臨機応変な対応をしたりすることが困難であるためです。
頻繁に体調不良を起こす
ADHDは、体調不良を起こす頻度が高い傾向です。頭痛や胃痛、めまい、気分の浮き沈みが激しいなど、人によって症状は異なります。子どもが体調不良を訴えているときは、素直に休ませましょう。
学校生活でADHDの中学生はどんなことに注意すべき?

続いて、学校生活でADHDの中学生が注意するべき点を紹介します。
・学校の先生やカウンセラー、医師と話し合う
・無理や我慢をさせない
・忘れ物しにくい環境をつくる
それぞれ、詳しく解説します。
学校の先生やカウンセラー、医師と話し合う
ADHDの中学生は、学校生活で困りごとや問題に直面するケースが多く見られます。そのため、子どもと保護者のみで抱えるのではなく、学校の先生や医師と話し合うことが重要です。学校にスクールカウンセラーが配置されている場合は、相談すると良いでしょう。スクールカウンセラーは外部から派遣された、心理の専門家です。学校側に気を遣わずに相談できるため、保護者にとって安心できます。
子どもの様子がおかしいときだけではなく、普段から情報共有しておきましょう。家庭ではいつもと変わらないように見えても、学校生活で問題が発生している可能性もあります。周りがサポートすることで、子どもはのびのびと学校生活を過ごせます。
無理や我慢をさせない
ADHDの原因は、生まれつき脳の機能に偏りがあるためだと言われています。そのため、本人の努力のみで特性をカバーすることは、極めて難しいと言えます。決して無理をさせず、本人が「今日は学校を休みたい」「勉強中だけど、少し休憩したい」などと申し出た場合は、できるだけ受け入れましょう。
また、はじめは特別支援学級や個別支援学級に在籍させてサポートを受け、本人の状態をみて普通学級に転籍させることも、ひとつの選択肢として考えておくと良いでしょう。
忘れ物しにくい環境をつくる
ADHDの中学生は、忘れ物しやすい傾向にあります。耳で聞いた情報を正しく記憶することが難しく、注意を持続させることが困難であるためです。忘れ物しにくい環境をつくるために、以下のような取り組みを実施することがおすすめです。
・前日に持ち物を用意しておく
・カバンを複数に分けるのではなく、大きいカバン1つにまとめる
・紙に持ち物リストをまとめ、目につくところに貼っておく
忘れ物しないように、保護者が声をかけてあげることも重要なポイントです。
勉強できないと感じるADHDの中学生が勉強を進めるポイント4選

「勉強できない」と感じるADHDの中学生が勉強を進めるポイントは、以下の4つです。
・勉強を小分けにしてその日にやることを決める
・ご褒美リストを作成する
・保護者が勉強に付き合う
・ADHDの子どもの教育実績がある塾に通う
それぞれ、詳しく紹介します。
宿題を小分けにしてその日にやることを決める
学校から宿題や課題を出されたら、小分けにしてその日にやることを決めましょう。ADHDの子どもは、宿題や課題を漠然と捉えている場合が多く、やるべきことを細かく分けたり、パーツに分けて考えたりすることが困難です。
そのため、親が「宿題や課題を切り分ける」手伝いをしましょう。たとえば、「夏休み中に問題集1冊」という宿題が出た場合は、1日に取り組むページ数を決めてあげると、取り組みやすくなります。
ご褒美リストを作成する
積極的に勉強してもらうためには、子どものやる気を引き出すことが重要です。ADHDの中学生に限らず、親が「宿題しなさい」「遊んでばかりいないで勉強しなさい」などと言うと、かえってやる気をなくしたり、反発したりしてしまいます。
そのため、ご褒美リストを作成しましょう。ご褒美リストは、「問題集を1ページ進めると1ポイント」などとルールを設けて、一定のポイントが溜まったらご褒美と交換できるというリストです。リストを目につくところに貼っておくと目標をイメージでき、勉強に集中しやすくなります。
保護者が勉強に付き合う
保護者が勉強に付き合うことも、子どもが勉強しやすくなるポイントの1つです。ADHDの中学生は、近くで一緒に考えてくれる人がいると、勉強に取り組みやすくなる場合があります。また、保護者も「どこでつまずいてしまうのか」「具体的に何が苦手なのか」など、子どもの特性を深く知れます。
ADHDの子どもの教育実績がある塾に通う
ADHDの子どもの教育実績がある塾に通うことも、ADHDの中学生が勉強を進める上で効果的です。塾や家庭教師によっては、ADHDやASDなど、発達障害のある子どもの指導やサポートを行っています。発達障害の教育実績がある塾では、勉強以外にも、以下のようなサポートを受けられる場合があります。
・日常生活を送る上でのアドバイス
・学校生活でのケアに関するサポート
・進路先についての相談(高校や大学、専門学校など)
まずは、近くにある発達障害の子どもの教育実績がある塾に問い合わせてみると良いでしょう。
ADHDの中学生を持つ親が気を付けること

ADHDの中学生を持つ親が気をつけることは、以下の3点です。
・子供を褒める
・話を聞く姿勢を大切にする
・ペアレントトレーニングを受ける
それぞれ、詳しく解説します。
子どもを褒める
ADHDの中学生は、周りの子どもたちと比べると授業についていけなかったり、勉強が遅れたりする場合があります。そのため、保護者はつい「どうしてできないの」と、きつく当たってしまいがちです。その結果、子どもは自信をなくしてしまい、さらに勉強ができなくなる可能性があります。
子どもに自信をつけてもらうためには、子どもの長所や良い部分に目を向けて、褒めることが大切です。できるだけ機会を見つけて、子どもを褒める時間をつくりましょう。
話を聞く姿勢を大切にする
ADHDの中学生を持つ親は、子どもが安心して話せる環境を作ることが重要です。そのため、「どんなときでもあなたの味方でいるよ」と、子どもの話を聞く姿勢を大切にしましょう。親が心がけるべき点は、以下の通りです。
・できるだけ1対1で話を聞く
・「悪いのはあなた」などの決めつけはしない
・必要以上に干渉せず、見守ってあげる
・子どもの悩みと解決方法を紙に書いて説明する
ペアレントトレーニングを受ける
ADHDの子どもを持つ親は、ペアレントトレーニングを受けることも有効です。ペアレントトレーニングとは、ADHDを含めた発達障害の子どもを持つ親に、親としての効果的なスキルを教えるもので、ADHDの治療のひとつとして知られています。
ADHDの特性や関わり方などについて理解を深められるだけではなく、同じ悩みを抱えた保護者と交流し、情報共有することも可能です。
塾を活用してADHDの中学生の勉強を進めよう!
ADHDの中学生は、勉強や授業に集中できなかったり、宿題や課題など計画的に勉強できなかったりなど、学校生活でさまざまな問題に直面することがあります。子どもに無理や我慢をさせず、保護者や学校の先生、カウンセラー、医師などがサポートすることが重要です。
「勉強できない」と感じるADHDの中学生に対しては、勉強を小分けにしてその日にやることを決めたり、ご褒美リストを作成したりすることが大切です。また、ひとりで勉強させるのではなく、保護者が勉強に付き合いましょう。保護者だけで勉強に付き合うことが難しい場合は、ADHDの子どもの教育実績がある塾に通わせることもおすすめです。勉強だけではなく、普段の生活や学校生活においてのサポートをしている場合もあります。