日々、学校からの連絡帳に「忘れ物がありました」と記されるたび、心を痛めておられる保護者の方も多いのではないでしょうか。何度注意しても忘れ物が減らず、どう向き合えばよいのか分からない。そのような悩みは、ご家庭に少なからず重くのしかかります。
忘れ物が多い子どもに対して、「しっかりしなさい」と叱るだけでは根本的な解決にはつながりません。その背景には、発達の段階に応じた特性や認知の偏り、生活習慣の積み重ね、さらには家庭や学校の環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合っている可能性があります。
本記事では、そうした忘れ物の原因を明らかにしつつ、保護者の方が日常生活の中で実践できる、具体的かつ現実的な対応策をご紹介します。
子どもの忘れ物が多いときの主な原因

子どもが繰り返し忘れ物をしてしまう背景には、さまざまな原因が考えられます。注意不足や習慣の問題と捉えられがちですが、実際にはその子の発達段階や特性または病気、置かれている環境などが複雑に関係していることも少なくありません。まずは原因を理解することで、子どもに合った適切な対応の糸口が見えてきます。
成長や発達の段階で忘れ物が増える理由
子どもは日々の暮らしの中で、少しずつ「覚える」「考える」「段取りを立てる」といった力を育てていきます。けれども、その発達の途中にある段階では、こうした力がまだ未成熟なため、忘れ物が起きやすいのはごく自然なことです。
特に小学校低学年では、「順番に行動する」「いくつかのことを同時に頭に入れておく」といった働きが難しく、注意がそれやすい傾向があります。
入学直後や、新しい学年になって時間割や教材が変わった時期などは、環境の変化に心と体が追いつかず、忘れ物が一時的に増えることも珍しくありません。これは一過性のものであり、多くの場合、成長とともに少しずつ落ち着いていくものです。
注意力や記憶力の発達が忘れ物に影響する
子どもの忘れ物が多い原因として、注意力や記憶力の発達の個人差があります。特にワーキングメモリと呼ばれる、情報を一時的に保持しながら作業する能力の発達には個人差が大きく、この能力が育ちにくい子どもは忘れ物をしやすい傾向があります。
ワーキングメモリが十分に働かないと、先生の指示を聞きながらメモを取る、連絡帳を見ながら明日の準備をするといった複数の作業を同時に行うことが困難になります。これは努力や性格の問題ではなく、脳の発達の特性によるものです。
環境の変化が子どもの忘れ物を引き起こすことも
引っ越しや転校、家族構成の変化、学校でのトラブルなど、環境の変化も忘れ物を増やす原因になります。心に不安やストレスを抱えていると、注意が散漫になり、持ち物の管理にまで気が回らなくなることがあります。
また、家庭内が慌ただしく朝の準備時間が十分に取れない、持ち物を置く場所が定まっていないなど、物理的な環境も忘れ物に大きく影響します。
忘れ物が多い子どもに見られる行動の特徴

忘れ物が多い子どもには、いくつかの共通した行動パターンが見られます。お子さんに当てはまるものがあるか確認してみましょう。
整理整頓が苦手
忘れ物が多い子どもは、机の中やランドセル、部屋が散らかっていることが多いです。これは単に片付けが嫌いというわけではなく、どこに何を置けばよいのか、どういう順番で片付ければよいのかという整理の仕方がわからないことが原因となります。
プリントがぐちゃぐちゃになっている、教科書とノートが混ざっている、前の日の持ち物がランドセルに入ったままといった状態は、必要なものを見つけられず忘れ物につながります。
支度が遅れやすく時間の感覚がつかみにくい
時間の感覚がつかみにくい子どもは、準備にどのくらい時間がかかるのか見通しが立てられず、ギリギリになって慌てて支度をすることになります。その結果、確認が不十分になり忘れ物をするのです。
あと5分で出かけなければいけないのに遊んでいる、準備が終わったと思っていたら重要なものを忘れているなど、時間管理の苦手さが忘れ物につながります。
興味が次々移ってうっかりする
好奇心旺盛で興味の対象が次々と変わる子どもは、準備の途中で他のことに気を取られてしまい、結果的に忘れ物をすることがあります。連絡帳を見て体操着を出したものの、途中で面白い本を見つけて読み始めてしまうといったケースです。
これは集中力がないわけではなく、むしろ興味のあることには深く集中できる子どもに多く見られる特徴です。
頭が良いのに忘れ物が多い子どもがいる理由
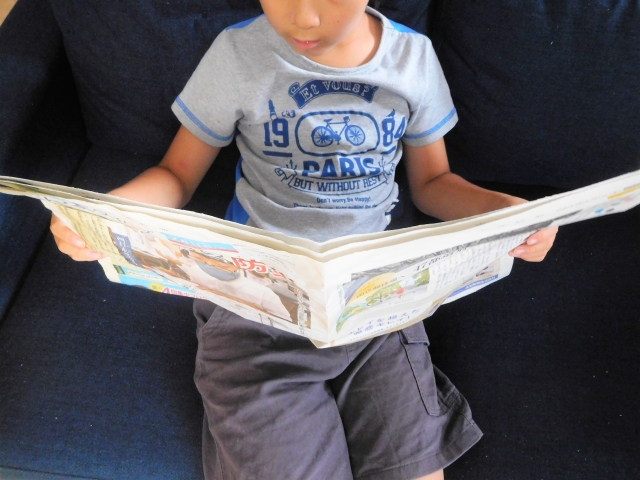
勉強ができるのに忘れ物が多い、テストの点数は良いのに持ち物管理ができないという子どもは少なくありません。頭が良いことと忘れ物の多さは一見矛盾しているように見えますが、実は関連する場合があるのです
得意分野に集中しすぎて他を忘れてしまう
頭が良い子どもは、自分が興味を持った分野に深く没頭する傾向があります。本を読むことや計算、工作など好きなことに集中しているときは、周囲のことが目に入りません。
その結果、明日の準備をしなければいけない時間なのに本を読み続けてしまう、算数の問題を解くことに夢中で連絡帳を確認し忘れるといったことが起こりがちです。これは集中力があるからこその忘れ物ともいうこともできます。
情報処理が速い子ほど確認を省いてしまいがち
頭が良い子どもは、理解力が高く情報処理の速いので、準備も素早くできると思い込んで確認作業を省いてしまうことがあります。自分では完璧に準備したつもりでも、実際には重要なものを見落としていることが少なくありません。
また、頭の中でシミュレーションして準備が終わったような気持ちになり、実際の行動が伴っていないということもしばしばあります。思考と行動のギャップが忘れ物を生んでいるのです。
病気や発達特性が関係する忘れ物の原因
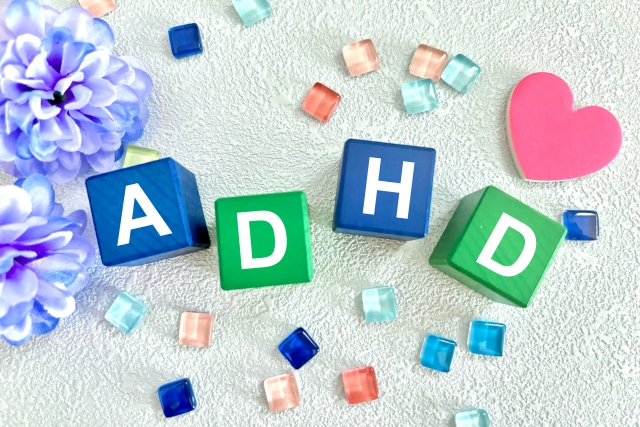
忘れ物が極端に多い場合や、日常生活に支障が出ている場合は、発達特性や病気が関係していることがあります。
ADHDなど発達特性と忘れ物の関係
ADHD(注意欠如多動症)は、不注意、多動性、衝動性を特徴とする発達特性です。特に不注意の特性が強い子どもは、忘れ物が非常に多くなります。
ADHDの子どもは注意が散りやすく、目の前のことに集中できないため、準備の途中で他のことに気を取られてしまいます。また、計画を立てて物事を進めることや、優先順位をつけることが苦手なため、何から準備すればよいのかわからなくなることもあります。
実行機能の発達がゆっくりな子どもは忘れ物が多い傾向
実行機能とは、目標を設定し計画を立て、それを実行し、結果を評価するという一連のプロセスを管理する脳の働きです。この実行機能の発達がゆっくりな子どもは、準備という作業を計画的に進めることが難しく、忘れ物が多くなります。
実行機能の課題は、ADHDだけでなく、ASD(自閉スペクトラム症)やLD(学習障害)など、様々な発達特性に共通して見られることがあります。
病気が心配なときに確認しておきたいポイント
忘れ物の多さだけで病気や発達特性があるとは言えませんが、以下のような様子が見られる場合は、専門機関への相談を検討してもよいでしょう。
- ●忘れ物が極端に多く、学校生活に大きな支障が出ている
- ●何度対策をしても全く改善が見られない
- ●忘れ物以外にも、整理整頓、時間管理、指示の理解などに困難がある
- ●本人が非常に困っている、または自信を失っている
これらに当てはまる場合は、学校のスクールカウンセラーや教育相談、小児科、児童精神科などに相談してみることをおすすめします。
ADHDの子どもの忘れ物や学習面でお悩みの場合、ステラ個別支援塾にご相談ください。
一人ひとりの特性に合わせたオーダーメイドの授業で、子どもの学習をサポートしています。
家庭でできる忘れ物対策

忘れ物を減らすために、家庭ですぐに実践できる具体的な対策をご紹介します。お子さんに合わせて、できそうなものから試してみてください。
視覚的サポートで支度をスムーズに
言葉で「準備しなさい」と伝えるだけでなく、目で見てわかる工夫が効果的です。持ち物リストをイラスト付きで作成したり、明日の時間割を大きく書いて貼り出したりすることで、子どもは何を準備すればよいのかが一目でわかります。
曜日ごとに色分けしたカードを用意する、準備が終わったものにシールを貼るなど、視覚的に達成感を得られる方法も良いでしょう。特に低学年の子どもには、文字だけでなく絵や写真を使うとより効果的です。
チェックリストで親子一緒に忘れ物を防ぐ
毎日使う持ち物や曜日ごとに必要なものをチェックリストにまとめ、子どもが自分でチェックできるようにします。最初は親が一緒に確認しながら、徐々に子ども一人でできるように見守りましょう。
チェックリストは、玄関やランドセルを置く場所など、子どもが必ず目にする場所に貼っておくことがポイントです。また、チェックが終わったら親に報告するという習慣をつけると、確認漏れを防げます。
持ち物の定位置を決めて整理しやすくする
学校で使うものは決まった場所に置くというルールを作ることで、探す時間が減り、忘れ物も減らせます。ランドセルはここ、体操着はここ、連絡帳はここというように、すべての持ち物に定位置を決めましょう。
透明な箱やかごを使って中身が見えるようにする、ラベルを貼って何を入れる場所か明示するなど、子どもが自分で片付けやすい工夫も大切です。戻す場所が決まっていれば、準備のときにも迷いません。
前日準備を習慣にして忘れ物を減らす
朝は時間に余裕がなく慌ただしいため、前日の夜に準備を済ませる習慣をつけることが忘れ物対策の基本です。夕食後や寝る前など、毎日同じ時間に準備タイムを設けると習慣化しやすくなります。
最初は親が一緒に付き添い、連絡帳を確認しながら一つずつ準備していきます。慣れてきたら、子どもが準備したものを親が最終確認するという形に移行していくとよいでしょう。
年齢に合わせた忘れ物対策の工夫

子どもの年齢や発達段階に応じて、サポートの仕方を変えていくことが大切です。
低学年の子どもには親が寄り添って支える
小学校低学年のうちは、まだ自分一人で準備を完結させることは難しいです。親が一緒に連絡帳を確認し、持ち物を一つずつ声に出して確認しながら準備を進めましょう。
「明日は水曜日だから、体操着が必要だね」「算数のノートは入ったかな」と、具体的に声をかけながら一緒に準備することで、子どもは準備の手順を少しずつ覚えていきます。できたことを「ちゃんと確認できたね」と褒めるのも、ポイントの一つです。
中学年以上の子どもには自立を促す声かけを
小学校中学年以上になったら、少しずつ自分で準備できるように見守る姿勢に切り替えていきます。「準備は終わった?」と確認する程度にとどめ、子ども自身に考えさせる機会を増やしましょう。
ただし、完全に任せきりにするのではなく、困っているときには手を差し伸べる、週に一度は一緒に持ち物の整理をするなど、適度なサポートは続けることが大切です。自立を促しながらも、子どもが安心できる距離感を保ちましょう。
【まとめ】忘れ物の原因を知り子どもに合った対策を一緒に考えよう
子どもの忘れ物が多いことには、発達段階、注意力や記憶力の特性、環境など様々な原因があります。頭が良い子でも忘れ物が多いことはあり、また発達特性が関係していることもあります。
大切なのは、叱るのではなく原因を理解し、子どもに合った対策を一緒に考えていくことです。視覚的サポート、チェックリスト、定位置管理、前日準備の習慣化など、今日からできる対策を試してみてください。
忘れ物が多い子どもも、適切なサポートがあれば必ず改善していきます。すぐに結果が出なくても焦らず、子どものペースを尊重しながら見守りましょう。もし、忘れ物以外にも困りごとが多く心配な場合は、専門機関に相談することも検討してください。
ADHDの子どもの忘れ物や学習面でお悩みの場合、ステラ個別支援塾にご相談ください。
一人ひとりの特性に合わせたオーダーメイドの授業で、子どもの学習をサポートしています。
ステラ個別支援塾では無料体験実施中
発達障害専門のステラ個別支援塾では、随時無料体験を実施しています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業で、学習をサポートします。
お気軽にご相談ください。














