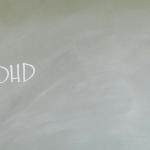「子どもに療育を始めさせるかと悩んでいるけど、いつから始めたらいいの?」「まだ早すぎるのでは…?」などと悩んでいませんか?
初めて「療育」という言葉に触れたとき、多くの保護者が戸惑いや不安を感じるものです。
ですが、療育は特別なものではなく、子どもの成長を支えるためのやさしいサポートの一つです。
この記事では、療育を始める適切な時期や早期に支援を受けることの大切さ、そして実際に始めるタイミングの目安などについて解説していきます。
療育はいつから始めるべき?

子どもの療育を検討しているとき、すぐに療育を始めたほうがいいのか、それとももう少し様子を見るべきなのか迷うことがありますよね。
療育は、子どもが困っているサインに気づいたときが、はじめどきとされており、「早期療育」が重要という考え方もあります。
ここでは、療育の基本や早期療育について、早期療育の重要性などについて解説していきます。
そもそも療育とは?
療育とは、障害を持つ子どもが社会的に自立できるよう、医療と教育の両面から支援することを指します。
もともとは医療機関で行うものでしたが、今は障害を持った人をサポートする取り組みとして、「発達支援」とほとんど同じ意味で使われています。
たとえば、言葉が出にくい、集団生活が苦手、感情のコントロールが難しい…など、子どもによって困りごとはさまざまです。
療育は、そのような子どもたちの「できる力」を育て、ご家庭や社会で安心して過ごせるよう支援していくものです。
診断の有無に関係なく、発達に不安があるときは気軽に相談してみましょう。
早期療育について
「早期療育」とは、子どもの発達に気づいた段階で、できるだけ早く適切な支援を始めることです。
たとえば、2歳ごろの言葉の遅れや、集団にうまくなじめないといったサインがあれば、療育の専門機関に相談することがすすめられています。
早期に支援を始めることで、子どもの「困りごと」が大きな壁になる前に対応でき、成長の可能性を引き出しやすくなります。
必ず「早く始めないとダメ」ということではなく、「気づいたときがスタート」と考えるとよいでしょう。
早期療育の重要性
早期療育には、子どもの将来にわたる成長や生活の質を高める効果がある※と言われています。
年齢を重ねるごとに社会性・言語・学習などすべての面で高度な内容を求められるようになりますが、幼児期に学ぶべきことをその時に学んでおけば、その後の成長もスムーズになります。
たとえば、早い段階で言葉や人との関わり方を練習することで、自己表現や社会性が育ちやすくなります。
また、子どもが安心して過ごせる環境を整えることで、問題行動の軽減や自己肯定感の向上にもつながります。
早期療育は、子どもとご家族の未来を守るための大切な一歩なのです。
※アメリカのロヴァース博士の自閉症児(ASD児)に対するABA(応用行動分析)療育の集中介入によって、ABAを活用した早期集中行動介入(EIBI)は、療育効果が高いことが証明されています。
また、ノーベル経済学賞を受賞したジェームス・J・ヘックマン博士は、幼児教育が経済的にも効果が高いことを実証し、幼少期の子どもに療育をすることの大切さを説いています。
療育を始めるタイミングについて
子どもの発達に関して「気になること」があるとき、療育を始めるタイミングは非常に重要です。
とはいえ、「0歳から受けられるの?」「言葉が遅いだけでも相談していいの?」など、判断に迷う保護者も多いのではないでしょうか。
ここでは、年齢ごとの発達段階に合わせた療育の開始時期の目安の例についてそれぞれ解説していきます。
0〜1歳
0〜1歳はまだ発達の個人差が大きいため、「発達が遅れているのでは?」と不安に思っても、様子を見るよう言われることもあります。
ただし、視線が合わない、泣き声に反応しない、身体の動きが極端に乏しいなどの特徴が強い場合は、専門機関に相談することもすすめられます。
療育そのものをすぐに開始するかどうかは状態によりますが、相談しておくことで「見守る目」が増え、安心して子育てを続けることができるため、早すぎるということはありません。
1〜2歳
1〜2歳になると、「言葉が出ない」「人とのやりとりが苦手」「癇癪が激しい」などの特徴が気になりはじめることがあります。
この時期は発達のスピードに個人差があるため、単に「ゆっくりなだけ」と言われることもありますが、不安がある場合は一人で抱え込まず相談してみましょう。
療育を始めることで、子どもの「困りごと」に早く気づき、ご家庭での関わり方も見直すことができます。
大切なのは「早く始める」というよりも「気づいたときに動くこと」です。
2〜3歳
2〜3歳になると、言葉・運動・社会性の発達が本格的になり、周囲の子どもとの違いがより目立ってくる時期です。
「言葉がなかなか出ない」「友達と関わらない」「こだわりが極端に強い」などが見られたときは、療育を始めるよいタイミングかもしれません。
早期に支援を受けることで、子どもが安心して社会とのつながりを築く土台づくりができます。
この時期は、保育園・幼稚園との連携も視野に入れて、生活全体のサポート体制を整えていくことが大切です。
3〜5歳
3〜5歳は集団生活が本格化する時期で、療育の効果が見えやすくなる年齢でもあります。
言葉の遅れや多動傾向、こだわり行動などがあると、園生活での困りごととして現れやすくなります。
この時期に療育を始めることで、社会性やコミュニケーション能力を伸ばし、就学に向けた準備にもつながります。
また、保護者自身も子どもの特性や関わり方を理解しやすくなり、ご家庭での子育てがより前向きになります。
就学前の今こそ、支援を考える大切なタイミングです。
療育に関するよくある疑問について
療育を検討していると、タイミングやその効果など、さまざまな疑問が出てきます。
こうした不安をひとつずつ解消していくことが、安心して一歩踏み出すためには大切です。
ここでは、療育に関してよく寄せられる質問とその答えをまとめました。
悩みを整理しながら、支援につながるヒントを見つけていきましょう。
療育を受けるのが早すぎないか?
幼児期の成長は速く、非常に多くのことを吸収する時期のため、できるだけ早く受ける方が望ましいです。
ステラ幼児教室の個別療育では、子どもの成長や発達に合わせたオーダーメイドの授業を行っており、子どものペースに合わせた取り組みを進められています。
母子分離が難しい子どもでも徐々に一人で授業を受けられるようになっています。
療育に効果はあるのか?
療育内容をすべて同じものにすると、子どもによって合う内容、合わない内容があるかもしれません。
ステラ幼児教室の個別授業は、一人ひとりの子どもに合わせて必要な内容を子どものペースで行うため、子どもの成長や効果を実感していただけています。
療育を勧められたが本当に必要か?
就学に向けて利用を決める方もいれば、成長して療育の必要性がなくなれば、辞める方もいらっしゃいます。
子どもの成長や発達で心配な面がありましたら、まずはお問い合わせにてご相談ください。
受給者証の取得や療育に抵抗がある
受給者証は障害者手帳とは異なり、障害者手帳を取らないと受給者証が取れないということはありません。
また、療育内容は事業所によっても様々ですので、事業所の見学や相談を行ってみて、それから療育を受けるか検討してみてもよいでしょう。
まとめ
療育とは、障害を持つ子どもが社会的に自立できるよう、医療と教育の両面から支援することを指します。
医療や教育、福祉の視点から個別にサポートを行い、近年では「発達支援」ともほとんど同じ意味で使われています。
なかでも重要とされているのが「早期療育」で、気になるサインが見られたら、できるだけ早い段階で支援につなげることが推奨されています。
例としては、0〜1歳でも視線が合わない、感情表現が乏しいなどの様子があれば相談のタイミング。
1〜2歳以降は、言葉の遅れや人との関わりが苦手など、行動の特徴がよりはっきりしてきます。
2〜3歳では発達の差が目立ちやすくなり、3〜5歳になると集団生活や就学準備との関係から療育の効果も見えやすくなります。
療育に関する不安として「早すぎないか」「効果があるのか」などの不安の声もありますが、支援は子ども一人ひとりに合わせて進めることが大切ですが、幼児期の成長は速く、非常に多くのことを吸収する時期でもあるため、できるだけ早く受ける方が望ましいです。
まずは気軽に相談から始めてみましょう。
参考元
各 支援機関 等