「療育手帳」という言葉を初めて聞いたとき、「うちの子どもにも必要なの?」「どんな手帳なの?」と戸惑う保護者の方も多いかと思います。
特に、発達障害の診断を受けた子どもについて「療育手帳がとれるのかどうか」悩む場面は少なくありません。
そこで本記事では、療育手帳の基本的な仕組みや対象となるケース、発達障害との関係、取得までの手続きや支援内容について解説していきます。
療育手帳とは?

「療育手帳ってどんな手帳?」「障害者手帳とどう違うの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
療育手帳は、知的障害があることを証明するための公的な手帳であり、福祉サービスや経済的支援を受ける際に役立つものです。
ここでは、療育手帳の基本的な概要や等級区分、取得によってどのような支援が受けられるのかなど、まず押さえておきたいポイントをご紹介していきます。
療育手帳の概要
療育手帳とは、知的障害(知的発達症)のある方へ交付される障害者手帳のことで、発達障害のうち、知的障害をともなう方が対象となります。
この手帳があることで、福祉サービスや各種支援制度を利用しやすくなります。(内容は後述)
自治体によって名称が異なり、たとえば、名古屋市では「愛護手帳」、東京都では「愛の手帳」とも呼ばれています。
いずれも内容は同じで、知的障害の程度に応じて等級が判定され、本人の支援に活かされます。
等級と判定基準
療育手帳には、知的障害の程度に応じた等級が設定されており、判定は専門の機関による面接や発達検査などを通じて行われます。
たとえば、名古屋市では、A判定(1度・最重度/2度・重度)、B判定(3度・中度/4度・軽度)の4段階で評価されます。
一方、大阪市ではA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の3区分となっており、自治体によって基準の分け方に違いがあります。
こうした等級によって、受けられる福祉サービスの内容や支援の程度が異なるため、子どもに合った支援を受けるための大切な診断になります。
現在、療育手帳は自治体によって名称や判定の基準が異なっていますが、いずれ全国的に統一される動きがあります。
療育手帳で受けられる支援やメリット
療育手帳を持っていると、さまざまな支援やサービスを受けられるというメリットがあります。
たとえば以下のような内容です。
●福祉サービス(通所施設や相談支援の利用)
●医療費や交通運賃の助成
●公共施設の入場料や公共駐車場の割引
●所得税・住民税の控除などの税制優遇
子どもの特性やご家庭の状況に合わせて必要な支援が受けやすくなります。
申請や利用にあたっては、市区町村の障害福祉窓口での相談が第一歩になります。
これらの支援は等級によって内容が異なる場合がありますが、子どもにとって暮らしやすい環境を整えるための強い味方になるはずです。
発達障害でも療育手帳を取得できるの?
発達障害と診断された場合、「療育手帳の対象になるのかどうか」は非常に気になるポイントだと思います。
「知的障害がないと申請できない?」「うちの子どもはグレーゾーンだけど大丈夫?」と迷われる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
そこで本項では、知的障害を伴う発達障害との関係や、療育手帳の対象となるかどうかの目安、場合によっては別の手帳が取得できる可能性についてもご紹介します。
知的障害を伴う発達障害の方は対象の場合も
療育手帳は「知的障害があること」を公的に証明するための手帳であり、発達障害の方でも、知的障害を併せ持つ場合は対象になることがあります。
たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)と診断されていても、知能検査の結果などから知的な遅れが見られ、自治体の判定基準に当てはまれば療育手帳が交付されます。
判定は医師の診断や発達検査、行動観察などを通じて行われるため、まずはお住まいの市区町村に相談してみるとよいでしょう。
知的な遅れがない場合は対象外になることが多い
発達障害があっても、知的障害がない(知的な遅れが見られない)場合は、療育手帳の対象にはならないことが一般的です。
療育手帳は、次の全ての条件を満たす場合に対象となります。
①18歳未満の発症
②おおむねIQ70ないし75以下
③適応行動の障害を伴うもの
療育手帳はあくまで知的障害の有無をもとに交付される制度のため、ASDやADHDなどの特性があっても、知能検査で基準を満たさなければ交付されない場合があります。
「困りごとはあるのに、手帳が取れない…」と感じたときは、他の支援制度や相談窓口の活用も検討するとよいでしょう。
参考元 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000088917.pdf
精神障害者手帳の取得が可能な場合も
知的障害がない発達障害の方には、「精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)」の取得が可能な場合があります。
この手帳は、発達障害(ASD・ADHDなど)やうつ病、統合失調症など、長期的に生活に支障をきたす精神障害がある方が対象※です。
精神障害者保健福祉手帳の交付基準(自治体によって異なる)
●1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
●2級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
●3級
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
診断を受けた医療機関で診断書を発行してもらい、自治体に申請することで、精神障害者手帳の対象となる場合に交付されます。
精神障害者手帳にも、税の控除や交通機関の割引、就労支援などのメリットがあります。
療育手帳の対象外であっても、別の形で支援を受けられる制度があることを知っておくと安心です。
療育手帳を取得するための手続き方法
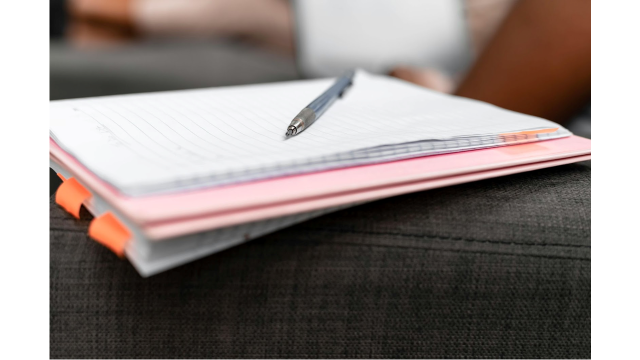
「療育手帳の申請にはどこへ行けばいいの?」「なにが必要?」といった手続きに関する疑問がでてくるでしょう。
初めてのことで不安に感じる方もいるかもしれませんが、流れを知っておけば安心して準備を進めることができます。
ここでは、市区町村での申請から検査、交付までの具体的なステップや、必要書類について分かりやすく解説していきます。
①市町村の障害福祉窓口で申請
療育手帳を取得するには、まずお住まいの市区町村の障害福祉課や子ども家庭支援課などの窓口で申請手続きを行います。
申請は保護者が行い、基本的には予約制となっている自治体が多いため、事前に電話などで相談するとスムーズでしょう。
窓口では、子どもの発達の様子や、療育手帳を希望する理由などを簡単に確認されることもあります。「手帳の対象になるか不安…」という方でも、まずは気軽に相談してみることが大切です。
②発達検査や面談、ヒアリング
申請後は、知的障害の程度を確認するための発達検査(知能検査)が行われます。
たとえば、「WISC(ウィスク)」や「田中ビネー」などの検査が使われることが多く、子どもの発達の特性を専門的に評価するプロセスです。
検査に加え、面談やヒアリングで保護者からの聞き取りも実施され、ご家庭や園・学校での様子などが詳しく確認されます。
この評価をもとに、障害の程度や等級(区分)を決める材料となります。緊張せず、普段の様子をありのままに伝えることが大切です。
③判定結果がでて、区分が決定し交付
発達検査や面談の結果をもとに、専門機関での判定会議が行われます。
その後、障害の程度に応じた等級(たとえば、名古屋市ではA1〜B4、大阪市ではA・B1・B2など)が決定され、結果が通知されます。
等級が確定すると、療育手帳が交付されます。
交付までの期間は自治体によって異なりますが、概ね1〜2か月以上かかることが多いです。
手帳は後日、窓口での受け取りまたは郵送される場合もあります。
先述しているように、発行後は福祉サービスや各種支援が受けやすくなります。
必要書類:申請書、診断書、写真など
療育手帳の申請時には、いくつかの必要書類を用意する必要があります。主な書類例は以下の通りです。
●療育手帳交付申請書
●診断書(必要な場合)
●顔写真(縦4cm×横3cm程度)
●本人確認書類(保険証、マイナンバーなど)
自治体によって少し違いがあるため、申請前にホームページを確認するか、窓口に直接問い合わせると安心です。
写真については、要件を満たしていればスナップ写真でも可能な場合があるため、うまく撮れないときは窓口に相談するとよいでしょう。
まとめ:療育手帳とは、主に知的障害のある方に交付される障害者手帳 障害の程度によって支援の内容が変わる
療育手帳とは、主に知的障害のある方に交付される障害者手帳で、福祉サービスや割引や税控除など経済的支援を受けるために必要となる公的な証明書です。
名古屋市では「愛護手帳」、東京都では「愛の手帳」と呼ばれるなど、名称は自治体によって異なりますが、基本的な制度内容は同じです。
今は自治体によって異なりますが、いずれ統一される動きがあります。
手帳は知的障害の程度によって等級が分かれ、支援の内容もそれに応じて変わります。
発達障害がある場合でも、知的障害を併せ持っていれば療育手帳を取得できるケースがあります。
一方で、知的な遅れがない場合は対象外となることが多く、その場合は「精神障害者保健福祉手帳」の対象となる可能性もあります。
取得までの手続きは、市区町村の障害福祉窓口で申請し、発達検査やヒアリングを経て等級が判定されます。
必要書類としては申請書、写真、本人確認書類などが求められます。
療育手帳の交付により、交通費の割引や税控除、福祉サービス利用など、子どもの成長と生活を支えるさまざまなメリットを受けることができます。
悩んだときは、まず自治体窓口に相談してみることが第一歩です。
参考元
各支援機関 等
総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000088917.pdf















