「子どもに療育が必要かもしれません」と言われたとき、多くの保護者の方が初めて耳にするのが「受給者証」という言葉です。
「受給者証って何?」「どうやって取るの?」「どこに相談すればいいの?」など、分からないことが多く、不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、療育を受ける際に必要となる「受給者証」について、その基本的な仕組みや申請の流れを解説していきます。
そもそも「受給者証」とは?
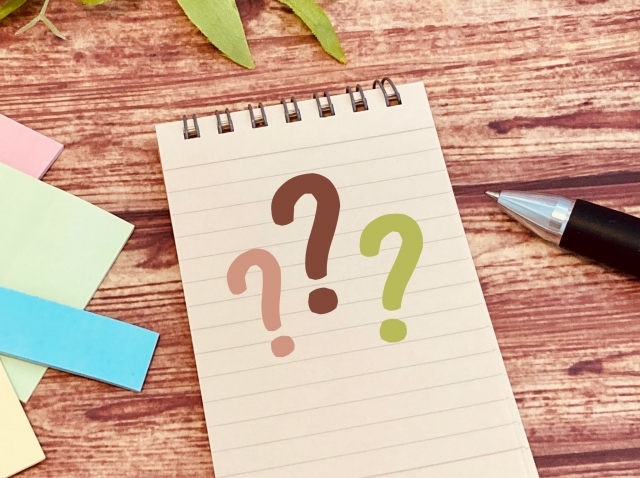
療育を検討していると、「受給者証が必要です」と説明されることがありますが、そもそも「受給者証」とはどのようなものなのでしょうか?
「障害者手帳とは違うの?」「受給者証がないと療育は受けられないの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
ここでは、受給者証の基本的な概要や種類、対象、受給者証で受けられる支援についてわかりやすくご紹介していきます。
受給者証の概要
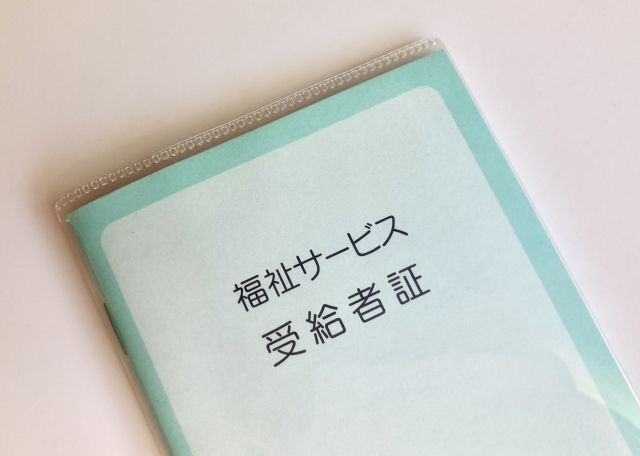
「受給者証」とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用する際に必要な証明書です。
正式には「障害児通所支援受給者証」や「通所受給者証」と呼ばれ、市区町村から交付されます。
対象となる子どもがサービスを受ける際に、支給量(週何回利用できるか)や自己負担の上限額がこの証で決まります。
療育の利用には必須となることが多いため、「まずは受給者証の申請から」と案内されることもあります。
受給者証の種類
受給者証には大きく分けて、「福祉サービスに関するもの」と「医療に関するもの」の2種類があります。
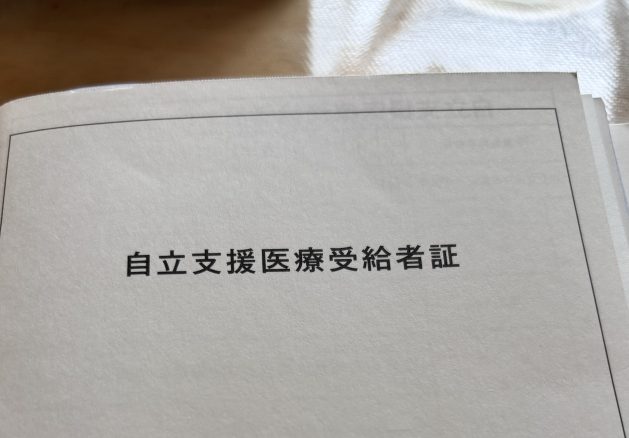
福祉サービスの受給者証
児童発達支援など療育機関への通所や相談支援、短期入所の利用など、福祉サービスを使うために必要です。
市区町村が発行し、支給量(週何回通えるかなど)が決められます。
この受給者証があることで、自己負担を抑えてサービスを受けることができます。
⇨「障害児通所受給者証」「障害児入所受給者証」など
医療型受給者証(自立支援医療)
発達障害や精神的な課題に対する通院治療に使われる受給者証です。
たとえば、児童精神科や心療内科での診察・治療に対し、医療費の一部助成が受けられます。
こちらも市町村に申請して取得します。
⇨「障害者医療費受給者証」「自立支援医療受給者証」など
両者は目的が異なり、福祉は施設通所などのサービス利用のため、医療は通院支援のために用いられる点が特徴です。
関連記事
受給者証と障害者手帳の違い
療育を受ける際、「受給者証」と「障害者手帳」は混同されやすいですが、目的や役割が異なります。
受給者証
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスや医療を受けるために必要な証明書です。
障害者手帳がなくても、診断名がある場合や発達の遅れなどで療育が必要である場合に申請※することができます。
市区町村の判断により支給され、支援の回数や内容が決まります。
※市区町村により申請の条件が異なる場合があるため、事前に問い合わせてみるとよいでしょう
障害者手帳
一方で、障害者手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳)は、障害があることを公的に証明するもので、税の控除や交通機関の割引などが受けられます。

どちらも支援のための大切な制度ですが、受給者証だけでも療育を受けることは可能ですので、まずは気軽に自治体へ相談してみましょう。
関連記事
受給者証(障害児通所受給者証)の対象
受給者証(障害児通所受給者証)は、発達障害や知的障害、身体障害などがあり、日常生活に何らかの支援が必要な子どもが対象です。
ただし、診断がなくても「発達に不安がある」「園生活に困りごとがある」などの理由で、支援が必要と判断されるケースでも交付されることがあります。
対象年齢は原則として18歳未満で、主に未就学児や小学生が多く申請しています。
申請については後述しますが、市区町村の相談窓口で子どもの状況を伝えることが第一歩です。
受給者証(障害児通所受給者証)で受けられる支援
受給者証を取得すると、以下のような福祉サービスを利用することができます。
●児童発達支援(未就学児対象):コミュニケーションや運動、生活面などの支援
●放課後等デイサービス(就学児対象):学習・生活面のフォローや居場所支援
●保育所等訪問支援:保育所などに訪問し、集団生活に適応するための支援
●障害児相談支援:困りごとの相談やサービスを利用するための計画の作成
●医療型児童発達支援(肢体不自由児対象):リハビリ等の機能訓練や医療的ケア下での支援(必要に応じて)
これらのサービスは原則1割の自己負担で利用できますが(障害児相談支援は自己負担なし)、所得に応じて月額の上限が設けられています。
たとえば、児童発達支援を利用の場合、年少児~年長児は受給者証を使うと自己負担はありませんが、2歳までは市区町村によって異なります。(名古屋市は2歳までも負担なしですが、大阪市は負担があります。)
また、子どもの特性やご家庭の状況に応じて、柔軟に組み合わせて利用することができます。
たとえば、児童発達支援と保育所等訪問支援の組み合わせや、障害児相談支援と児童発達支援の組み合わせ、医療型児童発達支援と(福祉型)児童発達支援の組み合わせなどが申請可能です。
他にも、受給者証の提示で、割引サービスが受けられる施設もあります。
(キッザニアやディズニーリゾートなどで割引サービスが受けられるようですが、確認を取ってから利用しましょう。)
参考サイト
https://www.kidzania.jp/about/security
https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/bfree/bfree_ticket.html
受給者証(障害児通所受給者証)をとるための流れや手続き方法

「受給者証を取ってください」と言われても、何から始めればよいのか迷ってしまうかもしれません。
各自治体によって手続きに少し違いはありますが、基本的な流れを知っておくことでスムーズに進めることができます。
ここでは、市区町村への相談から申請、受給者証の発行、そして実際に療育サービスを利用するまでの一連の流れを、5つのステップに分けて解説していきます。
①市区町村の窓口を調べる
受給者証は、国ではなくお住まいの市区町村が発行する制度です。
療育サービスを受けるには、お住まいの自治体の担当窓口に申請を行う必要があります。
市役所・区役所・町村役場の「障害福祉課」や「子ども家庭支援課」などが窓口となっていることが多いです。
手続きの内容や必要書類は自治体によって少しずつ異なるため、まずは電話などで問い合わせてみるのが安心でしょう。
②必要な書類があれば揃える
受給者証の申請時には、子どもの発達状況を詳しく確認するために、小児科や発達外来などで医師の診断書や意見書を求められる場合があります。
すべてのケースで必要とは限りませんが、診断書があると支援の必要性を客観的に説明でき、手続きがスムーズになることがあります。
自治体によっては、独自のフォーマットを指定していることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
③市区町村の窓口で申請
窓口では、子どもの発達状況や生活で困っていることなどについて相談・聞き取りが行われます。
そのうえで「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」など、どのサービスを使うかを検討しながら申請書を記入します。
わからないことは心配せずに相談してみましょう。
自治体によっては、子どもの様子を記録したメモや、園からの報告書などがあるとスムーズです。
④支給決定・支給量の通知
申請内容と必要書類がそろうと、自治体による審査が行われ、利用の可否と「支給量(週に何回サービスを受けられるか)」が決まります。
審査には1〜数週間ほどかかることが一般的です。
決定通知は郵送で届き、利用できるサービスの種類や回数、利用者負担の上限額などが書かれています。
希望通りの支給量が出ない場合もあるため、不明点があれば再度窓口に相談してみましょう。
⑤受給者証の発行と利用開始
支給決定がされると、いよいよ受給者証が交付されます。
多くの自治体では、受給者証は郵送で届き、支給開始日から指定の療育サービスを利用できるようになります。
利用する事業所(児童発達支援や放課後等デイなど)と契約を交わし、支援がスタートします。
初めての療育は不安もあるかもしれませんが、支援者やスタッフと連携しながら、それぞれの子どもに合ったペースで進めていけるようになります。
関連記事
まとめ
療育を受ける際に必要となる「受給者証(障害児通所受給者証)」は、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスや医療支援を利用するための大切な証明書です。
受給者証には福祉サービス用(通所受給者証など)と医療費助成用(自立支援医療受給者証など)の2種類があり、目的に応じて使い分けられています。
対象となるのは原則18歳未満の子どもで、障害の診断がある場合はもちろん、園やご家庭での困りごとが見られる場合にも支給される場合があります。
申請はお住まいの市区町村で行い、窓口での聞き取り、必要に応じて医師の意見書の提出などを経て、支給決定と支給量の通知が届きます。
受給者証の交付日より、療育サービスの利用をスタートできます。
子どもの状態に応じた支援を受けることで、ご家庭での子育ても前向きに進められるようになります。
迷ったときは、まず自治体や療育機関に相談してみましょう。
ステラ幼児教室は随時見学を行っています
ステラ幼児教室は通所受給者証を使い、通っていただく児童発達支援の事業所です。
お子さまの発達や成長に合わせて、マンツーマンの個別指導を行っています。
受給者証をまだお持ちでない方も、気軽にご相談ください。












