周りのお子さんがトイレトレーニングを終えているのに、わが子はまだおむつを使っている。そんな状況に焦りや不安を感じていませんか。お友達が次々とパンツに移行していく様子を見て、「うちの子は大丈夫だろうか」と心配になるのは、とても自然なことです。
おむつをいつまで使うかは、お子さんの心と身体の発達に深く関わっています。平均的な時期はあるものの、実際にはそれぞれのお子さんでペースが大きく異なります。それは決して発達の遅れではなく、お子さんなりの成長のリズムなのです。
この記事では、おむつをいつまで使うのが一般的なのか、平均的な卒業時期や夜だけ使う場合の対応、さらには発達に特性があるお子さんへの配慮など、多くのお母さんが抱える疑問や不安に寄り添いながらお伝えしていきます。
おむつはいつまで使う?気になる平均年齢の目安

おむつをいつまで使うか、まずはおむつが外れる平均的な時期を知っておくことで、お子さんの状況を客観的に見つめることができます。ただし、平均はあくまでも目安であり、お子さんの発達には個人差があることを前提にお読みください。
昼のおむつをいつまで使うかの平均は?
昼間のおむつを外す時期の平均は、だいたい2歳から3歳頃です。この時期になると、膀胱におしっこを一定時間ためておく力が育ち、「トイレに行きたい」という感覚を自分で認識できるようになってきます。
保育園や幼稚園に通い始めるタイミングで、トイレトレーニングを開始するご家庭も多いです。集団生活の中で、お友達がトイレを使う様子を見ることで、自然と興味を持つお子さんもいます。ただし、2歳になったからといって必ずしもすぐに外れるわけではありません。2歳半や3歳過ぎに外れるお子さんも多く、幅があることは理解しておきましょう。
夜だけおむつはいつまで使う?平均的な卒業時期
寝る時のおむつが外れる時期の平均は、昼間よりもかなり遅く、4歳から5歳頃です。寝ている間は尿意を意識的にコントロールすることができないため、昼間のおむつが外れてからも1年以上、夜だけおむつを使い続けるお子さんは珍しくありません。
寝る時だけおむつを使うことに罪悪感を持つお母さんもいますが、これは身体の発達に深く関わっており、意志の力だけではどうにもならない部分です。小学校入学前後まで夜のおむつが必要なお子さんも一定数いて、これも正常な発達の範囲内とされています。
おむつをいつまで使うかに男女差はある?
おむつ卒業の時期には、男女で若干の差があることが知られています。一般的に、女の子のほうが男の子よりも早くおむつが外れる傾向があります。これは、女の子のほうが言語発達が早く、尿意を言葉で伝えやすいことや、身体の構造上トイレでの排泄がしやすいことなどが理由として考えられています。
ただし、これはあくまで統計的な傾向であり、個人差のほうがはるかに大きいものです。男の子でも早くおむつが外れる子もいれば、女の子でも時間がかかる子もいます。性別による差を気にしすぎず、それぞれのお子さんのペースを大事にしましょう。
おむつをいつまで使うか見極める子どものサイン
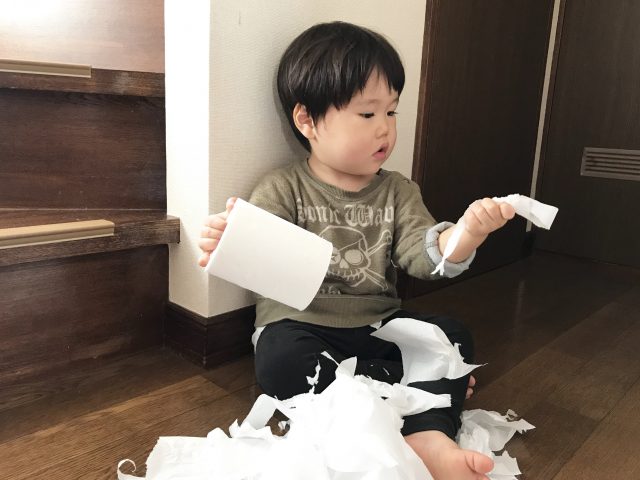
おむつを外すトイレトレーニングを始めるには、お子さんの心と身体が準備できているかを見極めることが大切です。無理にトイレトレーニングを始めると、トイレへの抵抗感を生んでしまうこともあります。お子さんからのサインを見逃さないようにしましょう。
おしっこの平均間隔で見るおむつ卒業のタイミング
おしっこの間隔が2時間程度に開いてきたら、膀胱に一定量をためておける力がついてきたというサインです。2時間よりも頻繁におむつが濡れる状態ではトイレに間に合わないことが多く、トレーニングがスムーズに進みません。
お子さんのおむつを替えるタイミングを数日間記録してみると、間隔の変化が分かりやすくなります。朝起きたときのおむつが濡れていない日が増えてきたら、夜間も膀胱のコントロール機能が育ってきた可能性があります。これらのサインが見られたら、トイレトレーニングを始める良いタイミングです。
言葉や行動で分かるおむつ卒業の合図
お子さんが自分からトイレに興味を持ち始めることも、おむつ卒業への準備が整ってきた証拠です。大人がトイレに行く様子を見て「何してるの」と聞いたり、自分も一緒についてきたりする行動が見られるようになります。
また、おむつが濡れたときに「気持ち悪い」と感じ、それを言葉や仕草で伝えられるようになることも重要なサインです。おむつを替えてほしいと訴えたり、濡れたおむつを自分で脱ごうとしたりする行動は、不快感を認識できている証です。「しーしー出た」「おしっこ」などの言葉が出始めたら、トイレでの排泄を教えていく良いタイミングといえます。
お子さんの言葉や行動面など、発達が気になるときは、ステラ幼児教室にご相談ください。
一人ひとりに合わせた個別療育で、お子さんの成長をサポートします。
なぜ?おむつをいつまでも使う子の気持ちと理由

おむつがなかなか外れないお子さんには、それぞれの理由があります。お子さんの気持ちや身体の状態を理解することで、焦らず向き合うことができるようになります。
おむつをいつまでも使うのは心身の発達段階が理由
おむつが外れるには、心身が十分に発達する必要があります。例えばお子さんの膀胱の成長スピード、神経系の発達、さらには性格や環境など、さまざまな要因が絡み合って、おむつ卒業のタイミングは決まります。膀胱がおしっこを十分にためておける容量まで成長することが不可欠で、この大きさや、尿意を脳に伝える神経系の成熟度には、お子さんによって大きな差があります。
また、寝ている間におしっこの量を減らす「抗利尿ホルモン」も、個人差が大きい要素のひとつです。このホルモンの働きが十分でないと、夜間に多くの尿が作られてしまい、夜のおむつが外れにくくなります。これは意志や努力とは関係のない、身体の成長の問題なのです。
自閉スペクトラム症の子がおむつを使い続ける気持ち
ここで注意が必要なのは、自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんです。自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんは、全般的に変化への適応に時間がかかる傾向にあります。おむつという慣れ親しんだ状態から、トイレという新しい環境に移行することに強い抵抗を感じる場合もあります。トイレの音や匂い、座る感覚などの感覚的な刺激が苦手で、トイレ自体を嫌がることもあります。
また、排泄という身体の変化を言葉で表現することが難しく、尿意を感じてもそれを伝えられないことがあります。焦らず、お子さんのペースを尊重しながら、少しずつ慣れていけるよう支援することが大切です。
ダウン症の子のおむつ卒業がゆっくりな理由
ダウン症のお子さんは、全身の筋肉の発達がゆるやかな傾向があり、膀胱まわりの筋肉のコントロールにも時間を要することがあります。そのため、おむつを使用する期間が平均より長くなるのは自然なことです。
また、認知や言語の発達にも時間をかけて進む傾向があり、「トイレに行きたい」という感覚を自覚し、それを行動に結びつけるまでの流れも、ゆっくり進むことがあります。大切なのは、焦らずお子さんの発達のペースに合わせて少しずつ取り組むことです。
できたことを丁寧に褒め、失敗を責めない環境を整えることで、お子さんは安心してトイレトレーニングに臨むことができるでしょう。安心感の積み重ねが、最終的な成功につながります。
おむつをいつまでと焦らない卒業トレーニングのコツ

トイレトレーニングは、お子さんにとってもお母さんにとっても、大きなチャレンジです。焦らず、寄り添いながら進めることで、お子さんの自信を育てていくことができます。
トイレを好きになる工夫でおむつ卒業へ
おむつ卒業への近道は、トイレを楽しい場所にすることです。お子さんが好きなキャラクターのトイレシートや便座カバーを用意したり、トイレの壁に好きなポスターを貼ったりすることで、トイレに行きたくなる環境を作りましょう。
また、トイレで成功したときに大げさなくらいに褒めることも大切です。「すごいね」「できたね」という言葉とともに、ハイタッチをしたり抱きしめたりすることで、お子さんは「トイレでできると嬉しい」という気持ちを持つようになります。シールを貼ったり、カレンダーに印をつけたりして、成功を目に見える形で記録するのも効果的です。
おむつが外れない時に使いたいポジティブな声かけ
トイレトレーニング中は、失敗がつきものです。お漏らしをしてしまったときに叱ったり、がっかりした表情を見せたりすると、お子さんは「失敗してはいけない」というプレッシャーを感じ、トイレに行くこと自体を怖がるようになることがあります。
「大丈夫だよ」「次は間に合うように教えてね」と、失敗を責めない姿勢を示すことが大切です。うまくいった場合は、「今日はトイレでできたね」と一緒に喜びましょう。その積み重ねが、お子さんの自信を育てます。「もうすぐできるようになるよ」「お母さんも応援してるよ」といった前向きな言葉が、お子さんの意欲を支えます。
便利な絵本やグッズを使うのもおすすめ
トイレトレーニングを題材にした絵本は、お子さんがトイレの流れを理解するのに役立ちます。「ノンタンおしっこしーしー」や「ひとりでうんちできるかな」などの絵本を読み聞かせることで、トイレへの興味を自然に引き出すことができます。
また、トレーニングパンツやおまるなどのグッズを上手に使いましょう。お子さんが自分で選んだパンツは、「これを履きたいからトイレに行く」という動機づけになります。子ども用のおまるは、大人用のトイレが怖いお子さんにとって、安心して使える第一歩になることがあります。
お子さんの言葉や行動面など、発達が気になるときは、ステラ幼児教室にご相談ください。
一人ひとりに合わせた個別療育で、お子さんの成長をサポートします。
夜だけおむつが外れない時のチェックポイント

昼間のおむつは外れたのに、夜だけまだ使っているという状況に悩むお母さんも多いです。夜のおむつが外れにくいのには身体の発達に関わる理由もありますが、生活習慣を見直すことで改善できる場合もあります。
寝る時のおむつ卒業は水分や食事の見直しから
夜のおむつを外すための準備として、まず生活習慣を見直してみましょう。寝る1時間前からは水分を控えめにすることで、夜間の尿量を減らすことができます。特に、利尿作用のある飲み物は避けるようにしましょう。
また、夕食の時間が遅くなったり、塩分の多い食事をとったりすると、夜間にのどが渇きやすくなり、水分を多く摂ってしまうことがあります。その結果、夜のおしっこの回数が増えてしまう場合もあります。
できるだけ、夕食は就寝の2時間前までに済ませ、塩分を控えめにすることを心がけましょう。こうした日々のちょっとした工夫が、夜間の排尿を落ち着かせる助けになります。そして、寝る直前にもう一度トイレに誘い、膀胱を空にしてから就寝する習慣をつけましょう。
生活リズムの乱れが夜だけおむつを使う原因に
寝る時のおむつが外れにくい原因として、生活リズムの乱れが関係していることもあります。就寝時間や起床時間が不規則だと、身体のリズムが整わず、夜間の尿のコントロールにも影響します。
毎日同じ時間に寝起きする習慣をつけることで、身体のリズムが整い、夜間の尿量を減らすホルモンの分泌も安定してきます。また、昼寝の時間が長すぎたり、夜遅くまで起きていたりすると、深い眠りに入りすぎて、膀胱がいっぱいになっても目が覚めにくくなります。規則正しい生活を心がけることが、夜のおむつ卒業への第一歩です。
自閉スペクトラム症やダウン症の特性に合わせたおむつ卒業
発達に特性があるお子さんの場合、その特性に合わせたアプローチが効果的です。専門家のアドバイスを受けながら、お子さんに合った方法を見つけていきましょう。
自閉スペクトラム症の子が見通しを持てるトレーニング
自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんには、視覚的な支援が効果的な場合が多くあります。例えば、トイレの流れを絵カードで示したり、写真付きのスケジュール表を作ったりすると、「次に何をすればいいのか」が一目でわかるようになります。
また、トイレに行く時間をあらかじめ決め、タイマーで知らせる方法も有効です。見通しが立つことで、お子さんが安心してトイレに向かうことができます。
さらに、成功したときにシールを貼るなど、目で確認できる形で達成感を伝えると、やる気を保ちやすくなります。まずは「トイレという場所に慣れること」から始め、最初は座るだけ、次は水の音に慣れる、といったように少しずつ段階を踏むことも大切です。
ダウン症の子の身体発達に合わせた進め方
ダウン症のお子さんは、筋肉の発達がゆっくりなため、膀胱のコントロールや便座に座る姿勢の保持にも時間がかかります。補助便座や足置き台を上手く利用して、安定した姿勢で座れる環境を整えてあげましょう。
また、言葉の理解に時間がかかる場合は、実際にトイレに座る動作を繰り返し見せながら、シンプルな言葉で伝えることが効果的です。「トイレ、座る、しーしー」といった短い言葉で、一つひとつの動作を確認しながら進めましょう。焦らず、お子さんができたことを丁寧に褒め、失敗を責めない環境を作ることで、お子さんは安心してトイレトレーニングに取り組めます。
おむつをいつまでも使う悩みとの向き合い方
お子さんのおむつがなかなか外れず、不安が募っているお母さんに向けて、どのように考え、どこに相談すればよいのかを簡単にお伝えします。
おむつの平均使用期間はあくまでも参考にするだけ
「平均」という言葉は、しばしば「基準」のように受け取られがちです。実際には、平均より早くてもゆっくりでも、いずれも正常な発達の範囲内にあります。おむつを使用する期間が平均より長いからといって、それだけで発達の遅れを示すものではありません。
周囲のお子さんと比較して焦りを感じるのは、お母さんとして自然な感情です。しかし、おむつの使用期間を無理に短くしようとすると、お子さんにもお母さんにも負担がかかり、トイレに対して苦手意識を持つことがあります。
大切なのは、「いつかはきっと外れる」という視点を持ち、焦らずに見守ることです。お子さんのペースを尊重しながら進めることで、結果的により穏やかにトイレトレーニングを進めることができるでしょう。
おむつをいつまで使うか悩んだら専門家へ相談を
次のような場合には、専門機関への相談を検討されることをおすすめします。例えば、5歳を過ぎても昼間のおむつが外れない場合、トイレトレーニングを始めてもまったく進展が見られない場合、あるいはおむつ以外の発達面にも気がかりな点がある場合などです。
発達に関する相談は、まずお住まいの市区町村にある保健センターや子育て支援センターが窓口となります。必要に応じて、児童発達支援センターや小児科の発達外来など、より専門的な機関を紹介してもらうことができます。また、発達に特性のあるお子さんや、発達のペースがゆっくりなお子さんを対象に支援を行っている専門施設もあります。ひとりで抱え込まず、早めに相談してみることで、より適切なサポートや安心につながる場合も多いでしょう。
【まとめ】おむつはいつまでという悩みから卒業しよう
おむつを卒業する時期は、お子さんの心身の発達によって異なります。平均的な目安はありますが、それはあくまで参考に過ぎず、一人ひとりに最適なタイミングがあります。昼のおむつは2〜3歳頃、寝る時のおむつは4〜5歳頃に外れることが多いものの、多少遅くても心配はいりません。特に夜間は身体の成長とともに自然に整っていくため、無理をせず発達の流れを見守ることが大切です。
また、自閉スペクトラム症(ASD)やダウン症など発達に特性のあるお子さんでは、おむつを使う期間が長くなることもありますが、個々のペースに応じた支援で着実に進歩していきます。焦らずお子さんを信じ、必要に応じて専門家へ相談する姿勢が、安心した成長を支える土台となります。
お子さんの言葉や行動面など、発達が気になるときは、ステラ幼児教室にご相談ください。
一人ひとりに合わせた個別療育で、お子さんの成長をサポートします。
ステラ幼児教室では随時見学受付中
名古屋市、大阪市に展開している児童発達支援事業所、ステラ幼児教室では随時見学を行っています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。
お気軽にご相談ください。














