
赤ちゃんがおしゃべりする内容がわかったら良いなと思いませんか。この文章では、赤ちゃんがどのような発達段階を経て言葉を覚えていくのかと、おもな赤ちゃん言葉の一覧をご紹介していきます。
赤ちゃんはどういう発達段階を経て言葉を覚えていく?

赤ちゃんは、大きく分けると5つの段階を経て、大人のように会話できるようになっていきます。
クーイング
早い子では生後1ヶ月ころから、『アー』や『クー』といった声を出すようになります。
これらの発生はクーイングと呼ばれるほか、非叫喚発声とも呼ばれます。
母音が中心のクーイング。食後や目覚めた直後など、落ち着いて機嫌が良いときにリラックスした状態で発せられる言葉です。
呼吸のコントロールが安定してくると、クーイングを話すことができるようになります。
『アー』と言ったとき、お母さんも『アー』と返してあげると、赤ちゃんは『アー、アー』などの返事をしてくれます。
喃語(なんご)
おおよそ4ヶ月~10ヶ月ごろ、くちびるや舌を自由に使えるようになってから発せられる言葉が『喃語』です。
クーイングと同じく、まだ発する言葉に意味はありません。
赤ちゃんは、くちびると舌の動かし方によって違う音が出ることを、だんだん理解していきます。赤ちゃんは、喃語を声に出すことや自分で聞くことが楽しくてしょうがないので、同じ言葉を何度も繰り返ししゃべります。
初語(一語文)
早ければ1歳ごろに話し始める初語(しょご)は、意味や意図を持って発せられる単語です。
例えば、ご飯が食べたいときの『マンマ』、車を指す『ブーブー』などで、ひとつの単語で意味や意図を伝えようとするので、一語文とも呼ばれています。
赤ちゃんにとっては、『まみむめも』や『ぱぴぷぺぽ』が聞きとりやすいうえに、話しやすい音でもあるので、はじめて話す言葉が『マンマ』や『ブーブー』になることも多いです。
この時期に話すのは、幼児期に特有の赤ちゃん言葉(幼児語)です。おもな赤ちゃん言葉は、のちほど一覧でご紹介します。
言葉を発しはじめたばかりの赤ちゃんは、『マンマ』という言葉ひとつで、ご飯、犬、お母さん、猫、ちょうちょなど、いろんなものについて伝えようとしますが、だんだんと『マンマ』がご飯、『ワンワン』が犬、『ニャンニャン』が猫など、ものに名前があることを理解します。
理解した言葉を実際に言えるようになるまでには、約半年かかるそうです。
二語文(電文体発話)
1歳半~2歳ごろになると、文法の構造(主語と述語)を理解し、『マンマ、食べる』などの二語文を発するようになります。
格助詞が省略された二語文は、電報に使われる文体に似ていることから、電文体発話と呼ばれることもあります。
ものに名前があることを理解した赤ちゃんは、ものや人の名前が知りたくなり、質問を頻繁に繰り返します。
1歳半ころは約50語を超えるくらいの語彙力ですが、2歳ころまでに約300語を理解するといわれ、この時期は『語彙爆発』の時期とも呼ばれています。
三語以上(多語文)
3歳ごろには、『赤い、長靴、はきたい』のように3語以上の言葉を使ったり、『ママ、お外で遊びたい』のように、単語をつなげただけでなく、助詞や接続詞も使った文を話したりすることができるようになります。
4歳ころには、ほぼ話し言葉は完成し、大人ともかなりスムーズに会話ができるようになります。
また、ある単語(例えば『りんご』)を音に分けて認識する(例えば『り』・『ん』・『ご』)『音韻分解』も身につくので、『テレビ』を『テビレ』と言い間違えたりするようなことも、このころにはなくなります。
喃語にはどんな種類がある?

先ほど大まかに紹介した喃語ですが、大きく3種類に分けることができます。
未分化喃語(過渡期喃語、過渡的喃語)
生後4~5ヶ月ころになると、『アーアー』など、母音中心の未分化喃語を話し始めます。
話す言葉自体はクーイングに似ていますが、このころには口の中の空間がクーイングを話していたころよりも広がり、舌もさまざまに動かせるようになります。また、声の高さや強さに変化が見られるようになります。
規準喃語(反復喃語)
生後6~9ヶ月ごろには、子音と母音を組み合わせた規準喃語を話せるようになります。
規準喃語は『ダダダダ』、『バババ』のように同じ音を繰り返すことから、反復喃語とも呼ばれます。
このころ、赤ちゃんは大人がしゃべる言葉のリズムやイントネーションをまねをしたり、大人が話している言葉の意味を理解したりします。
非重複喃語(ジャーゴン)
生後11~12ヶ月ころになると、『アバ』、『バブ』のように、反復される音の母音や子音が異なる、規準喃語よりも複雑な非重複喃語を話し始めます。
非重複喃語自体は意味のない音の繰り返しですが、赤ちゃんは誰かに何かを語りかけているような、独り言を言っているような風にも聞こえます。そのため、ジャーゴン(宇宙語)と呼ばれることもあります。
おもな赤ちゃん言葉の一覧表
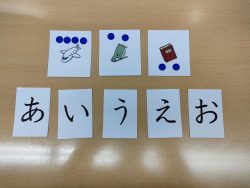
これから、全国共通の赤ちゃん言葉のほか、愛知県・中部地方・大阪府・近畿地方の方言別に赤ちゃん言葉をご紹介していきたいと思います。
赤ちゃんが何をしゃべっているのか理解するための参考にしてみてください。
人やいきものに関する赤ちゃん言葉
| お母さん | ママ、カーチャン、オカーチャン(全国)、チャーチャン、アーチャン(中部地方)、オカーン、マンマ(大阪) |
|---|---|
| お父さん | パパ、トーチャン、オトーチャン、トト(全国)、トー(愛知)、オトン、オトッタン、ト-シャン、チャン(大阪) |
| 犬 | ワンワン(全国)、ワンワ(愛知)、ワンコ、コイコイ(大阪)、コッコ(近畿地方) |
| 猫 | ニャンニャン、ニャーニャー、ニャンコ(全国)、ニャーニャ、ニャー、コマ(愛知)、ニャゴニャゴ、ニャンコチャン、ニャーオ、ニャオ(大阪)、ニャン、ニャーン(近畿地方) |
| 牛 | モーモー、モーモ、モー(全国)、ボーボー、ボー、ウシンボー(愛知)、モーサン、モーチャン、モーコ(大阪) |
| 馬 | ヒンヒン、ヒヒーン、パカパカ、オウマサン(全国)、ドード(中部地方)、ヒーヒーン、パッカパッカ、ポカポカ、ポッカポッカ(大阪)、バーバ(近畿地方) |
| 魚 | トト、トット、トート、オトト(中部地方)、タイタイ(大阪)、トト、トット、オトト(近畿地方) |
食事に関する赤ちゃん言葉
| ご飯 | マンマ、ママ、ウマウマ(全国)、オマンマ、ママチャン(大阪) |
|---|---|
| めん類 | ツルツル、チュルチュル(全国)、ズーズ、ゾーゾ、ゾンゾ(愛知)、オズル、ゾロ(中部地方)、チューチュー(大阪)、ツーツー(近畿地方) |
| 卵 | タマタマ(全国)、オタマチャン、タンタン、コッコー(大阪)、タマ、オタマ(近畿地方) |
| お茶 | チャチャ、ブー、ブーブー、オブー(全国)、チャー、オチャチャ、ブーチャン、ブーチャ(大阪)、ブブ(近畿地方) |
| 水 | オブー、ブー、ブーブー(全国)、ブンブ(中部地方)、オブーチャン、ブーチャン(大阪)、ブブ(近畿地方) |
| 飲む | ゴクゴク、ゴックン、ゴクン(全国)、クック(大阪) |
| なめる | ペロペロ、ナメナメ(全国)、ベロベロ(大阪) |
| 口を開ける | アーン(全国)、アー(近畿地方) |
| おいしい | オイチー(全国)、ウンマ(大阪)、オイチーオイチー、ウマイウマイ(近畿地方) |
体やものに関する赤ちゃん言葉
| 頭 | テンテン、オツム(全国)、ビンタ(愛知)、メメ、オツモ、アンマ(大阪) |
|---|---|
| 髪 | カンカン、カンカ(全国)、ケケ(中部地方) |
| 目 | メメ、オメメ、メンメ(全国)、メーメ(中部地方)、メーメー(大阪) |
| 舌 | ベロベロ(全国) |
| おなか | ポンポン、ポンポ、オナカ(全国) |
| 手 | テテ、オテテ、テッテ(全国) |
| 足 | アンヨ(全国)、アイヨ(中部地方)、アイヨ、アイヤ(近畿地方) |
| 自動車 | ブーブー(全国)、ブーブ、ブッブー(大阪) |
| 飛行機 | ブーン、ブーンブーン、ブンブン(全国)、ブーブ、ブー、バタバタ(大阪) |
動作や状態に関する赤ちゃん言葉
| 寝る・眠る | ネンネ(全国)、ネンネン、ゴロン(大阪) |
|---|---|
| 座る | エッコ、オチャン、チャン(愛知)、エンコ、チャンコ(中部地方)、チャンチャン、オチン、オッチョン(大阪)、オチン、オッチン(近畿地方) |
| 起きる | オッキ、オキオキ(全国)、オーキ(愛知)、オキ(近畿地方) |
| 立つ | タッチ、タッタ(全国)、タチタチ、アンヨ(大阪)、タッタタッタ(近畿地方) |
| 歩く | アンヨ、アンヨアンヨ(全国)、アイヤ、パカパカ(大阪) |
| 捨てる | ポイ、パイ、ポーン(全国)、ポーイ、ポン(大阪)、チャイ(近畿地方) |
| 隠す・しまう | ナイナイ(全国) |
| たたく | トントン(全国)、パン(愛知)、パチパチ、パン、ポンポン、テン、タンタン、チャイ(大阪) |
| きたない | バッチ(全国)、ヤニコイ(愛知)、バーチー、ババッチ、バイ、バイシー、チャナイ、イヤラシー(大阪)、ババチ、ババイ(近畿地方) |
| 美しい・きれい | キレキレ、キレーキレー(全国)、オッコイ、ケッコイ、ケッカイ(愛知)、ウッツイ(中部地方)、キエイキエイ(大阪) |
| 熱い | アッチ(全国)、アチアチ(大阪)、アチチ、アッチッチ、アチュイ、アチュイアチュイ(近畿地方) |
| 寒い | サムサム(全国)、アブイ(中部地方)、チャムイ、コンコン、ブルブル(大阪) |
| ぬれる | ビショビショ、ビチョビチョ、ベチャベチャ(全国)、ビシャビシャ、ビシャーコ、ビチョ、ピチャピチャ、ズクズク、ピチョ(大阪)、ビチャビチャ(近畿地方) |
| 嫌い | イヤイヤ(全国) |
| 好き | スキスキ(全国)、チュキチュキ(近畿地方) |
| 痛い | イタイイタイ、イタイタ(全国)、イタタ(大阪) |
| くすぐったい | コソバイ(愛知)、コソバイ(近畿地方) |
出典:『全国幼児語辞典』
お子さんの成長が心配になったときのおもな相談先

お子さんが話し始める時期には個人差があり、奥手のお子さんは3歳過ぎまで言葉が出にくくても、その後に追いついて問題なくなることがあります。
また、『さしすせそ』がた行になってしまうことはよくあるようで、『さしすせそ』、『ざじずぜぞ』、『らりるれろ』は発音が難しいため、多くの子が正しく発音できるのは5歳半から6歳ごろともいわれています。
2歳を過ぎても、言葉を話さない、言葉の数が増えない、発音がはっきりしない、などの状況が続き、心配になったときには、下記の相談先に相談してみるのも良いでしょう。検査などで、ご自身とは異なるお子さんならではの特性を発見できるかもしれません。
自治体の発達相談窓口
自治体の乳幼児健診(1歳6ヶ月児検診や3歳児検診など)では、『育児相談』の際に保健師・管理栄養士・歯科衛生士などに悩みを相談することができます。乳幼児健診のとき以外でも、自治体の保健センター内の子育て相談窓口などで随時、無料で相談することができます。
発達には個人差があり、実際に遅れているのかどうかの判断は難しいので、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
小児科医
かかりつけの小児科には定期的に通うため、小児科医はお子さんの発達状況を把握しています。そのため、発達の相談をした場合、適切な治療を受けることができたり、専門の治療を行う医療機関に紹介してもらうことができたりする可能性が高いです。
- 発達障害に関しては、小児科の発達外来のほか、小児神経科や児童精神科
- 聴覚障害に関しては、耳鼻咽喉科
- 口腔機能の発達遅れに関しては、歯科
などが治療を行います。
公認心理師・臨床心理士
公認心理師は2017年に制定された国家資格で、臨床心理士は1988年からはじまった民間資格です。
公認心理師や臨床心理士は、自治体の相談支援専門員(療育相談員)として、発達に心配があるお子さんの相談を受け、必要に応じて福祉・医療機関への橋渡しを行うほか、小児神経科や小児心療内科・小児科などで、心理検査や心理相談などを行い、お子さんを心理的な面でサポートします。
言語聴覚士
言語聴覚士は、話す、聞く、食べるに関するスペシャリストです。1997年に国家資格として制定されました。
名古屋市にある、愛知県言語聴覚士会が開く『ことばの教室』では、発達障害や機能性構音障害(医学的原因がなく、発音がうまくできない状態)を持つ小学生以上のお子さんを対象に、言葉や情緒の発達に関する相談や訓練を行っています。民間の施設では、もう少し小さいお子さんが対象の『ことばの教室』が開かれているようです。
大阪市では、民間の施設で、言語聴覚士による『ことばの教室』を受講できます。
お子さまの発達で気になる点がある方はステラ幼児教室に相談してみませんか
名古屋市と大阪市のステラ幼児教室では、お子さまの発達や興味に合わせて個別療育を行い、お子さまの可能性を伸ばします。
マンツーマンなので、恥ずかしがり屋のお子さんでも安心。年長さんまで通えるので、小学校への準備過程としてもご利用できます。
個別の無料見学も行っていますので、気になった方は、ぜひ1度お問い合わせください。














