「些細なことで突然怒り出す」「思い通りにならないと手がつけられなくなる」など、子供の癇癪(かんしゃく)に悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。また、大人でも感情のコントロールが難しく、癇癪を起こす人もいます。
そもそも「癇癪もち」とはどのような状態や人のことを指すのでしょうか?また、その背景にはどのような要因があるのでしょうか?
そこで本記事では、癇癪もちの特徴や子供と大人の違い、癇癪を起こす原因について解説していきます。
癇癪持ちとは?

癇癪(かんしゃく)とは、感情のコントロールが効かずに何かのきかっけで強い興奮状態に陥ることを指します。そんな癇癪を起こしやすい人のことを「癇癪もち」と呼ぶことがあります。
「癇癪もち」の人は、感情のコントロールが難しく、怒りやすいことが多いです。
子供の場合は、成長過程の中で癇癪を起こすことも珍しくありません。しかし、頻度や強度によっては何らかの障害や不調のサインである可能性もあるため注意深く観察する必要があるでしょう。
癇癪もちの特徴
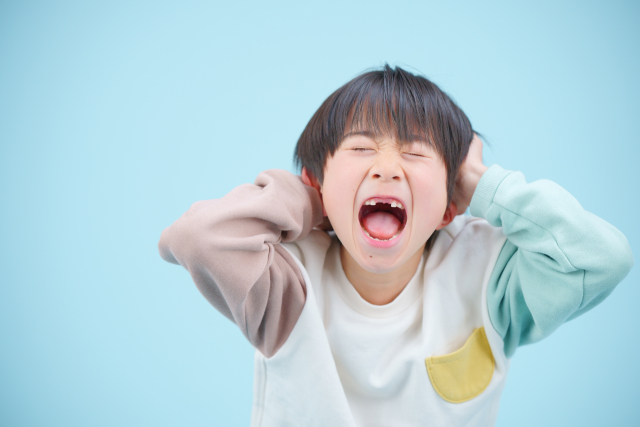
癇癪もちの人には、以下のような特徴が見られることがあります。
- 感情のコントロールが難しい
- 些細なことで強い怒りを感じてしまう
- ストレスへの耐性が低い
- 衝動的な行動をとることが多い
- 他者とのトラブルが頻繁に起こる
- 自己中心的な思考傾向がある
これらの特徴は、子供だけでなく大人にも共通して見られることがあります。適切な対処法を学び、感情のコントロールを身につけることが重要です。
子供と大人の癇癪の違い

子供と大人の癇癪(かんしゃく)には、それぞれ特徴があり、周囲の捉え方も異なります。以下に、その違いをまとめました。
| 子供と大人の癇癪の違い | 子供の癇癪 | 大人の癇癪 |
|---|---|---|
| 特徴 | 感情のコントロールが未熟で、欲求不満や環境の 変化に敏感に反応し、発達障害(ASDやADHD)を持つ子供は、感情の起伏がより激しい場合があります。 |
感情のコントロールが難しく、怒りやすいため、衝動的な行動が見られることがあります。 発達障害が背景にある場合、感情のコントロールが特性上困難なことがあります。 |
| 捉え方 | 成長段階や過程の一部として理解されることが多く、保護者や教育者は忍耐強く対応します。発達障害の可能性がある場合、専門的な支援や適切な対応も必要です。 | 社会的な期待から、自己管理ができていないと見なされ、批判的に受け取られることがあります。発達障害が原因の場合、職場や家庭での理解と適切なサポートが重要です。 |
このように、子どもと大人の癇癪には特徴や周囲の捉え方に違いがあります。それぞれの状況に応じた理解と対応が大切です。
子供が癇癪を起こす原因
癇癪は、単なる「わがまま」や「甘え」ではなく、さまざまな要因や環境が絡み合って起こるものです。たとえば、生活習慣の乱れや欲求不満、ストレスなどが引き金となることがあります。また、環境の変化やコミュニケーションの困難さも、癇癪の要因となることもあるでしょう。
そこで本項では、癇癪を引き起こす主な原因を「生活習慣」「心理的要因」「環境要因」「コミュニケーションの問題」の視点から解説していきます。
【睡眠不足・栄養の偏りなど】生活習慣の問題
子どもの基本的な生活習慣の睡眠や食事のリズムが乱れると、情緒の安定が損なわれ、癇癪を起こしやすくなります。
たとえば、睡眠不足や不規則な食事は、子どもの集中力や気分に影響を与え、イライラしやすい状態を招くことがあります。規則正しい生活リズムは、子どもの心身の健康を支える基盤です。そのため、適切な睡眠時間の確保やバランスの良い食事、そして適度な運動を取り入れることが重要です。これらの生活習慣の改善は、子どもの情緒の安定に繋がり、癇癪の頻度を減少させる効果が期待できます。
【ストレス】欲求不満など心理的な問題
子供は自分の欲求や感情を上手に表現することがまだ難しい場合があり、その結果、欲求不満やストレスが溜まり、癇癪として現れることがあります。
たとえば、自分の思い通りにならない状況や、期待していたことが叶わない場合、子供は強いフラストレーションを感じて、癇癪が起こりやすくなる場合があります。自己肯定感の低さや不安感も、癇癪のひとつの原因です。保護者や周囲の大人は、子供の感情に寄り添い、共感する姿勢を持つことが大切です。子供が自分の気持ちを言葉で表現できるように、日常的にコミュニケーションを図ることも効果的でしょう。
【不安】環境など外的な要因の問題
子供の生活環境や周囲の外的状況の変化も、癇癪の原因となることがあります。
たとえば、家庭内の緊張状態や親子関係の不和、学校でのいじめや友人関係のトラブルなどが挙げられます。また、引越しや転校などの環境の変化も、子供にとって大きなストレスとなっているはずです。保護者は、子供の生活環境に目を向けてあげて、安心して過ごせる環境づくりを心掛けることが重要です。子供の話にもよく耳を傾け、感じているストレスや不安を理解し、適切なサポートをしてあげましょう。
コミュニケーションの問題
子供が自分の気持ちや考えを適切に伝える手段を持たない場合、周囲とのコミュニケーションが円滑に進まず、フラストレーションが溜まることがあります。
特に、言葉の発達が未熟な幼児期や、発達障害を持つ子供は、意思疎通に困難を感じることがより多いです。このような状況では、周囲の大人が子供の非言語的なサインや行動を注意深く観察し、子供の意図や感情を汲み取る努力が必要です。また、絵カードやジェスチャーなど、言葉以外のコミュニケーションをとることで、子供が自分の気持ちを表現しやすくなります。これにより、子供のフラストレーションを軽減し、癇癪の発生を防ぐことが期待できるでしょう。
年齢別の癇癪を起こす意味

癇癪は、子どもが感情を爆発させる行動で、発達段階で見られることがあります。しかし、頻繁で激しい癇癪が続く場合、発達障害との関連が考えられることがあります。
赤ちゃん(0~1歳)が起こす癇癪の意味
赤ちゃんは生理的な不快感を表現するために癇癪を起こします。
空腹、痛み、眠気、痒さ、暑さ、寒さなど、言葉による意思疎通ができないため、癇癪を起こして大人に伝えようとします。
この時期の癇癪は、赤ちゃんにとってもコミュニケーション方法のひとつであり、保護者は原因となっている生理的な欲求に応えてあげる事が大切でしょう。
イヤイヤ期の幼児(2~3歳)の癇癪の意味
イヤイヤ期の幼児の場合、癇癪は不快を表現する行動から目的を達成するための行動へと変化します。自分自身の不都合を取り除き、望む目的を達成するために癇癪を起こすことが多い傾向にあるでしょう。
しかし、感情のコントロールが未熟なため、途中から目的を見失ってしまい自分自身でもどうしてこんなに怒っているのか、泣いているのか分からなくなることが多いです。
小学生以降の癇癪
情緒が育ちつつある小学生以降の癇癪については、言語化できない不快感をコントロールできずに起こっている可能性があります。
癇癪を起こすことが良いことではないと理解し、周囲を困らせることを分かっていても止められないのです。
このようなケースでは、癇癪を起こしている理由を辛抱強く探ることが必要です。日常生活や精神状態、なかには障害の影響を受けて癇癪を起こしている可能性もあるでしょう。
大人の癇癪は発達障害が潜んでいる可能性も
大人になると社会のなかで癇癪を起こす悪影響を十分に理解しています。善悪についての判断もできるため、感情のままに癇癪を起こすことは激減するでしょう。
しかし、後先を考えずに癇癪を起こしてしまう人の場合、その影に発達障害が潜んでいる可能性があります。いわゆる「大人の発達障害」です。
幼少期に見過ごしてしまい、発達障害による生きづらさを抱えたまま大人になった人もいます。あまりに頻繁に癇癪を起こしてしまう人や癇癪によって社会生活に問題が起きている人は、医療機関の受診を検討してみるのがよいでしょう。
癇癪と発達障害の関係性

癇癪は、子どもが感情を爆発させる行動で、発達段階で見られることがあります。しかし、頻繁で激しい癇癪が続く場合、発達障害との関連が考えられることがあります。
自閉スペクトラム症(ASD)と癇癪
自閉スペクトラム症(ASD)の子どもは、感覚過敏や環境の変化に敏感で、ストレスを感じやすいため、癇癪を起こすことがあります。
強いこだわりがあったり、物事の見通しが立ちにくい状況に不安やストレスを感じてしまやすかったりするケースも多く、許容量以上の刺激を受けてしまった際に癇癪が起こるケースが多いです。
注意欠如・多動症(ADHD)と癇癪
注意欠如・多動症(ADHD)の子どもは、衝動的な行動や注意の持続が難しく、フラストレーションを感じやすい傾向があります。
周囲の人に特性を理解されにくく、否定的な言葉を受け続けることで、コミュニケーションの受け取り方に否定的な癖を持つケースも少なくありません。
結果、他人の言葉や態度を必要以上にネガティブに捉えて感情が昂ぶり、癇癪を起こしてしまうことが多い傾向にあります。
発達障害は癇癪もちが多いと言われてしまう理由
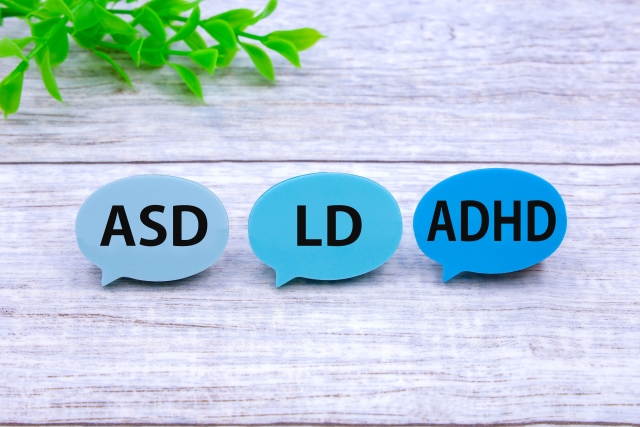
発達障害の人は癇癪もちが多いと言われてしまうことが多いです。しかし、そこには特性ゆえの理由があります。
こだわりが強い特性があるから
発達障害のなかでも自閉スペクトラム症の場合、強いこだわりをもつ人が多いです。ルーティーンを非常に好み、毎日同じように過ごすことを望む人が少なくありません。
そんなこだわりが崩れた時に、強い衝動を受けやすいのも自閉スペクトラム症の特徴です。
こだわっている事を邪魔されてしまった時やルーティーンが崩れてしまった時に、一瞬でパニックに陥って癇癪を起こしてしまうことがあります。
他者との意思疎通が苦手だから
自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症の場合、それぞれに異なるソーシャルスキルの問題を抱えていることが多いです。
自閉スペクトラム症の場合、相手の感情を読み取ったり言葉の裏に隠された意味や気持ちを察したりするのが苦手な傾向にあります。また、注意欠如・多動症の場合、自分が気になったことに注意力が直ぐに移ってしまうため、他人とのコミュニケーションを蔑ろにしてしまうことが少なくありません。
それぞれに持っているソーシャルスキル面での特性によって他人との意思疎通が上手くいかず、ストレスを抱えて癇癪を起こしてしまうこともあるでしょう。
感情のコントロールが苦手だから
発達障害の人のなかには、自分の感情のコントロールが苦手だという人が少なくありません。これは、我慢できない訳ではなく、脳の特性として感情が昂ぶりやすいケースもあります。
必要以上に感情が昂ってしまうことで、癇癪を起こし、自分自身をコントロールできなくなってしまうのです。
癇癪もちの子供への対処法

子供が癇癪を起こしてしまった場合、保護者はどのように対処すればよいのでしょうか。続いては、癇癪もちの子供に対する保護者の対処法を紹介します。
怪我をしないように見守る
子供が癇癪を起こした場合、物を投げたり自傷行為をとったりするケースもあります。周囲に危険を及ぼすものがあるなら、それらを取り除き、怪我をしないよう見守ってあげましょう。
癇癪が治まるのを待つ
癇癪を起こしている子供は、パニックになって思考が停止していることが多いです。この状態で声かけをしても、新たな刺激を受けて癇癪がより激しくなったり長引いたりする可能性が高いでしょう。
外出している先で癇癪を起こしてしまうと、場所を移動するなどの強制的な対処が必要なケースがあるかと思いますが、もしも可能なのであれば癇癪が治まるまで待つのがおすすめです。
光や音などの刺激を減らす
癇癪を起こしている時はさまざまな刺激に過剰に反応してしまうことがあります。光や音など、刺激を減らすことを心がけましょう。
屋外にいるなら、なるべく人が少ない静かな場所に移動してみてください。また、自宅内にいるなら、部屋の照明を少し暗くしてテレビを消し光と音の刺激を遮断するのがおすすめです。
癇癪が治まったことを褒める
癇癪が治まった際にはすぐに、気持ちを落ち着けられたことを褒めましょう。癇癪を起こすと子供はエネルギーを使い疲れてしまいます。回復する頃には、どうして癇癪を起こしたのかも何がきっかけだったのかも忘れてしまうことが多いでしょう。
癇癪が治まったことをポジティブに受け止めることで、「どうして癇癪が起きたのか」「何がきっかけだったのか」「どうすればよかったのか」などの改善策を考える心の余裕が生まれやすくなります。
癇癪もちの子供と関わる保護者の方へのアドバイス

子供の癇癪に悩まれている保護者の方は、以下の点に注意してみてください。
子供の行動を観察する
どのような状況で癇癪が起きてしまうのか、パターンを把握することで、適切な対応をとりやすくなります。
専門、支援機関への相談
発達障害の可能性がある場合、早めに専門機関や医療機関に相談することが重要です。
適切な支援を受ける
発達障害者支援センターなどの専門機関と連携し、子供に合った支援を受けることが大切です。
子供の特性を理解し、適切なサポートを行うことで、癇癪の頻度や強度を軽減することが期待できます。
癇癪もちの特徴と対応についてまとめ
癇癪(かんしゃく)は、感情のコントロールが難しく、怒りを抑えきれないような状態を指します。子供は成長の過程で癇癪を起こすことがありますが、頻度や強度によっては注意が必要です。大人の癇癪も、衝動的な行動や自己制御の難しさが特徴で、社会的によくない影響を及ぼすことがあります。
癇癪を引き起こす原因としては、生活習慣の乱れ、欲求不満、環境の変化、コミュニケーションの困難さなどが挙げられます。子供は自分の気持ちを言葉で表現することが難しく、その結果、フラストレーションが溜まり癇癪として現れることがあります。また、発達障害(ASDやADHD)を持つ子供は、特性として癇癪を起こしやすい傾向があります。
癇癪を減らすためには、子供の生活習慣を整え、感情に寄り添う姿勢を持ち、安心できる環境を提供することが大切です。専門機関への相談や適切な支援を受けることで、子供が落ち着いて過ごせるようになる可能性もあります。癇癪の背景を理解し、適切な対応を取ることで、子供の情緒の安定や成長を支えることにつながります。















