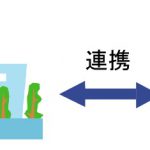小学生の子どもが「漢字をすぐ忘れる」「何度書いても覚えられない」と悩むケースは珍しくありません。しかし、こうした場合、単に努力不足ではなく、発達障害(学習障害やディスレクシアなど)の特性が影響していることもあります。
この記事では、「原因の理解から家庭でできる工夫」や「漢字をすぐに忘れてしまう子への対応策」「代替手段」「専門機関」による支援までを解説し、親子が安心して学習に取り組める道筋をご紹介します。
漢字が覚えられない発達障害とその背景
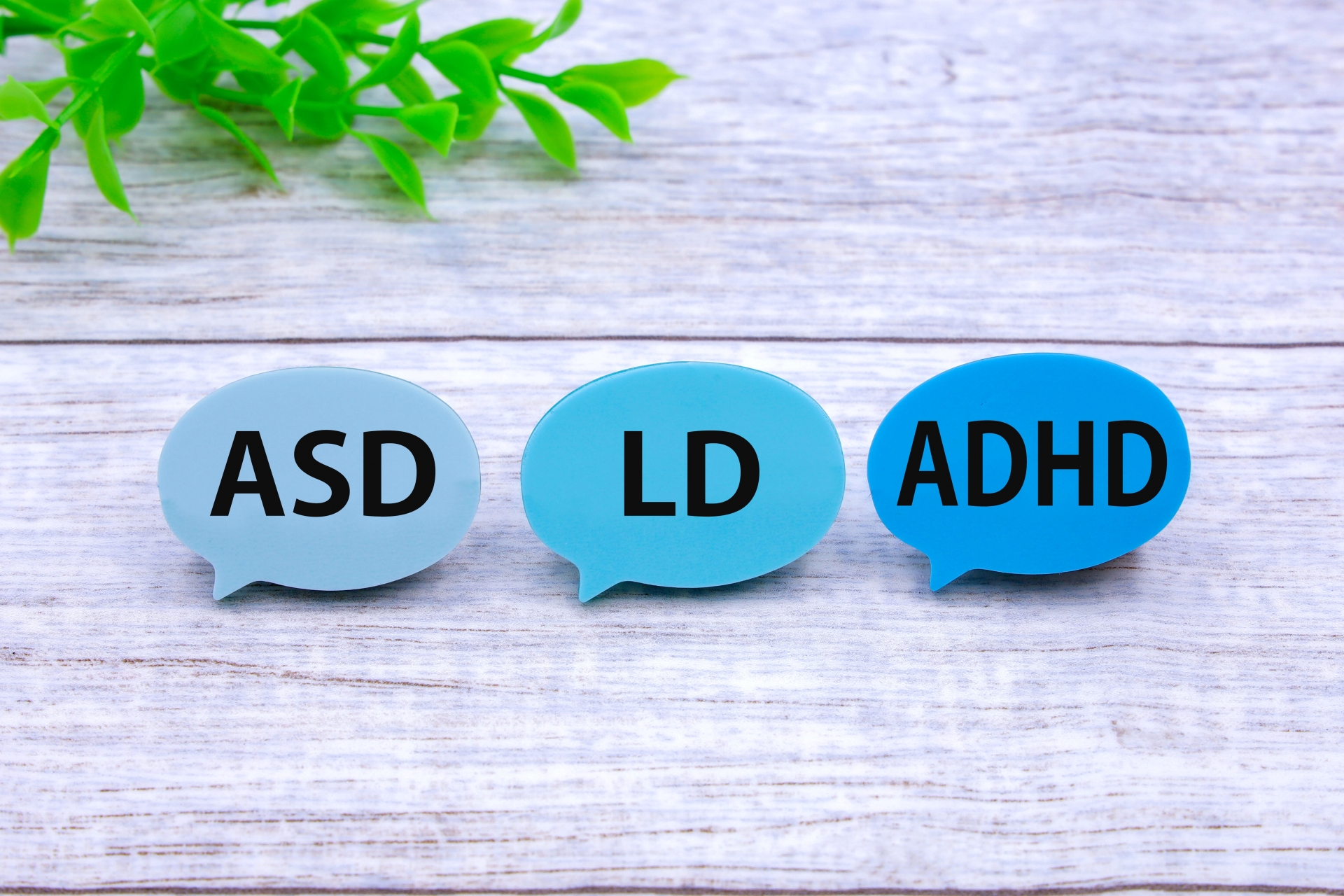
ここでは、発達障害が漢字学習にどのように影響するのか、その基本的な背景を解説します。とくにLDやディスレクシア、ADHDやASDの特性がどのように関連しているのかについて説明します。
学習障害(LD)とディスレクシアの特徴
学習障害(LD)のうち、ディスレクシアはとくに文字の読み書きに困難さがあるという特徴があります。漢字の形を認識しにくい、音と文字の対応づけが難しいといった特性から、何度練習しても覚えられない状況に直結するのです。
とくに小学生のうちは、学年が上がるごとに漢字の画数や意味が複雑になります。そのため、ディスレクシアの子どもにとっては大きな負担になりやすいものです。
さらに、ワーキングメモリが弱いと、書き順や構造を一時的に記憶してもすぐに忘れてしまうことが多く、結果として「努力しても成果が出ない」と感じて、自己肯定感が下がりやすくなります。このような背景を理解することが、適切な支援の第一歩となります。
ADHDやASDとの関連
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、集中力を持続することが難しく、漢字練習に取り組んでも途中で気が散ってしまいがちです。その結果、覚えた内容をすぐに忘れる、練習量が安定しないといった課題につながります。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合、漢字の形や意味を抽象的に理解するのが難しく、パターン化した覚え方が役立つこともあります。
ここでいうパターン化とは、共通する部首や形のグループごとに整理して覚える方法や、書き順や構造を「部品」に分けて繰り返す方法など、規則性を利用して学習を助ける工夫のことです。また、感覚の過敏さやこだわりの強さがあると、学習環境によっては、文字を書くこと自体に抵抗を感じる場合も少なくありません。
ADHDやASDの特性を理解し、それに応じた学習方法を工夫することが、漢字を覚えられない背景にアプローチする重要な視点となります。
発達障害で漢字が覚えられない子どもに見られる具体的な困りごと

ここでは、学校や家庭で実際に子どもたちがどのような困難に直面しているのかを紹介します。日常の学習場面で現れる具体的な課題を把握することが、適切な支援を考える第一歩です。
小学生が直面する学校での困難(テスト・授業)
小学生の子どもにとって、漢字の習得は学習の大きな柱です。しかし、発達障害の特性がある場合、テストや授業の場面で著しい困難が表れます。
たとえば、「何度も練習しているはずなのにテスト本番で思い出せない」「板書のスピードについていけない」「読み書きの遅れから授業全体が苦手に感じられる」といったケースが少なくありません。
教師から「努力不足」と誤解されることもあり、子どもの自信や学習意欲に悪影響を及ぼすこともあります。小学生の段階でこうした困難に直面すると、学年が上がるにつれて差が拡大しやすく、早期の理解と支援が欠かせません。
家庭学習でのつまずき
家庭学習の場面でも、漢字が覚えられない発達障害の子どもは多くのつまずきを経験します。
たとえば、「前日に覚えた漢字を翌日には思い出せない」「同じ字を何度も間違える」といった、「すぐ忘れる」状況が繰り返されます。親が隣で指導しても成果が出にくく、親子ともにストレスがたまりやすいのも特徴です。
また、漢字学習に時間がかかりすぎることで他の教科の学習に影響が出て、繰り返し指導することで親子関係がぎくしゃくするなど、二次的な問題が生じることもあります。こうした家庭での困難を理解し、無理のない工夫や支援方法を取り入れることが大切です。
漢字が覚えられない発達障害の原因を理解する

ここでは、子どもが漢字を覚えにくい背景にどのような認知機能の特性があるのかを説明します。ワーキングメモリや視覚認知、書字動作など、学習に直結する要素を掘り下げていきます。
記憶の仕組みとワーキングメモリ
漢字を覚えるには、まず短期的に情報を保持するワーキングメモリが大きな役割を果たします。黒板や教科書で見た文字を頭の中で一時的に記憶し、それを繰り返し書いて長期記憶に定着させる仕組みです。
しかし、発達障害の子どもは、このワーキングメモリの容量が小さい。または情報維持が難しいケースもあり、学んだ内容を保持する前に忘れてしまうことが多いのです。
さらに、注意が散漫になりやすい特性が加わると、漢字の書き順や細部を正確に覚える前に記憶が途切れてしまいます。そのため、覚えたはずの漢字を翌日には思い出せなかったり、繰り返し練習しても十分な成果が得られなかったりすることがあります。
こうした記憶の仕組みを理解することにより、子どもに合った学習法を見つける手がかりとなるのです。
視覚認知・書字動作の課題
漢字を正しく書き覚えるには、形を正確に認識する視覚認知と、筆順やバランスを保ちながら運筆する書字動作の力が必要です。
発達障害の子どもの中には、この視覚認知の弱さや手指の協調運動が苦手なことから、漢字の構造をとらえにくい場合があります。そのため、似た形の字を混同する、パーツを抜かして書くといった誤りが頻発します。
また、書くこと自体に強い負担を感じるため、学習を避ける傾向につながることも少なくありません。こうした特性を理解したうえで、マス目のあるノートを使う、部首ごとに区切って練習するなど、視覚的にわかりやすい工夫を採り入れることが大切です。
発達障害で漢字が覚えられない子への家庭学習の工夫
ここでは、家庭でできる具体的な学習支援の工夫を紹介します。無理のない範囲で楽しく取り組める方法を知ることで、子どもの負担を減らしながら学習意欲を高めることができます。
覚えやすくするコツ
漢字を覚えやすくするためには、子どもの特性に合った工夫が重要です。たとえば、音読と視覚カードを組み合わせることで、聴覚と視覚の両方から記憶を定着させやすくなります。また、漢字の意味や成り立ちをイメージと結びつけると、単なる暗記ではなく理解を伴った学習につながります。
短時間の学習を1日に複数回行う「分散学習」も効果的です。集中力が続きにくい発達障害の子どもでも、5分や10分程度なら取り組みやすく、繰り返すことで記憶に残りやすくなります。また、成功体験を積ませることが学習意欲の維持や、学習に対する前向きな姿勢の育成につながります。
すぐ忘れる子へのサポート法
漢字を「すぐ忘れる」子どもには、記憶を定着させる工夫が欠かせません。たとえば、翌日や1週間後に復習する「間隔反復法」を採り入れると、長期記憶に結びつきやすくなります。書く練習だけでなく、声に出して読む、カードを使って確認するなど多感覚を使った学習が有効です。
また、完璧を求めず部分的にできたことを認めることも大切です。小さな成功体験を積み重ねることで自信が育ち、学習への意欲が高まります。親や指導者は「忘れるのは特性の一部である」と理解し、叱責ではなく励ましを中心にサポートする姿勢が望まれます。
発達障害で漢字が覚えられない子への学校や周囲のサポート
ここでは、学校や家庭といった周囲の人々がどのように理解し、支援できるのかを考えます。先生や友だち、家族との関わり方が子どもの学習意欲や安心感に直結します。
先生に伝えるべきこと
学校でのサポートを受けるためには、保護者から先生へ子どもの特性を具体的に伝えることが重要です。たとえば「漢字をすぐ忘れてしまう」「板書のスピードについていけない」といった具体的なエピソードを共有することで、先生も状況を理解しやすくなります。
また、漢字テストの評価方法を工夫してもらう、課題の量や形式を調整してもらうなどの配慮をお願いすることも大切です。事前に家庭での様子をまとめて伝えることで、学校と家庭が一体となって子どもを支援しやすくなります。
友だち・家庭での理解づくり
子どもが漢字を覚えられない理由は、友だちや家族には理解されにくいことがあります。そのため、周囲には「努力不足ではなく、発達障害の特性によるもの」であると伝えることが大切です。
友だちに対しては、間違いをからかわない、得意な分野を認め合うといった配慮を促すことが有効です。
家庭では、叱るよりも励ましを中心に声をかけ、子どもが安心して学習に取り組める環境を整えることが大切です。兄弟姉妹にも協力をお願いし、家族全体で支え合う姿勢が、子どもの自尊心を守り、前向きな学習意欲につながります。
漢字が覚えられない発達障害の子への代替手段とICT活用

ここでは、従来の漢字学習にとらわれず、ICTや代替手段を使って学習を支える方法について紹介します。書くことに強い負担を感じる子どもでも取り組みやすい選択肢が広がっています。
ICT教材やアプリ
近年は、発達障害の子どもを支援するためのICT教材やアプリが数多く登場。漢字学習に特化したアプリでは、読み上げ機能やクイズ形式の確認テストを通して、反復練習を継続しやすい工夫がされています。
視覚的に漢字の構造を示すアニメーションや、正しく書けた際にポイントがたまる仕組みなど、取り組みやすくするための工夫も多く採り入れられています。
また、タブレットやパソコンを使うと筆圧や書き順に縛られず、気軽に入力して学べるため、書字に強い抵抗がある子どもにとっても有効です。アプリやICT教材を適切に活用することで、学習への負担を軽減し、継続的な取り組みが可能となります。
代替手段の具体例
漢字の習得が難しい場合でも、学習や生活を支えるための代替手段は増えてきました。たとえば、タブレット端末での文字入力や音声入力を活用すれば、手書きにこだわらずに表現する力を発揮できます。また、漢字変換機能や予測変換を使うことで、覚えていない字でもスムーズに文章が書けるようになります。
学校や家庭で、レポートや課題を提出する際にデジタル機器の使用を認めることで、子どもが学習内容に集中しやすい環境を整えることが可能です。こうした代替手段の活用は「逃げ」ではなく、子どもの特性に合った合理的な支援であり、将来の可能性を広げる大切な方法です。
漢字が覚えられない発達障害の子どもと専門機関・学習塾の活用
ここでは、家庭や学校だけで解決できない場合に利用できる専門機関や支援塾について解説します。相談先や制度の活用に加え、専門的な支援環境のメリットを紹介します。
相談窓口や公的支援制度
発達障害の子どもが漢字を覚えられない場合、家庭や学校だけで抱え込まず、公的な相談窓口を利用することが大切です。
各自治体には発達障害者支援センターや教育相談室があり、学習や生活面の困難について専門家に相談可能です。また、学校と連携して合理的配慮のアドバイスも受けられます。
さらに、放課後等デイサービスや療育機関など、日常生活や学習支援を行う施設もあります。これらの制度を活用することで、子どもが安心して学習できる環境づくりが可能です。
ステラ個別支援塾のご案内
漢字の学習につまずきを感じたとき、専門の支援塾で学ぶことは大きな助けです。
ステラ個別支援塾では、お子さま一人ひとりの特性に合わせた学習支援を行い、安心して取り組める環境を提供しています。漢字が覚えられない、すぐに忘れてしまうといった課題にも、専門的な視点できめ細かく対応しています。
漢字が覚えられない発達障害の子どもへの支援方法まとめ

漢字が覚えられない背景には、ワーキングメモリや視覚認知の弱さ、ADHDやASDなどの発達障害の特性が関係しています。小学生の段階で困難が表れると、学校や家庭で大きな負担となり、自己肯定感の低下にもつながりかねません。
しかし、「家庭でできる工夫やICT教材の活用」「代替手段の導入」「専門機関・支援塾のサポート」によって、子どもの学習環境は大きく改善できます。大切なのは、「努力不足」ではなく、その子どもの特性に応じた支援が求められるということを理解することです。
この記事でご紹介した方法を参考に、子どもたちが自信を持って学習に取り組めるよう、周囲が温かく支援を続けていきましょう。