受給者証とは子どもの療育に必要なもの

子どもの発達について保育園や検診で指摘を受けたり、保護者ご自身が少し育てにくさを感じていたりするとき、専門機関から療育を勧められることがあります。 その際、多くの保護者の方が初めて耳にするのが受給者証という言葉です。
受給者証とはいったい何だろう、療育手帳とは違うものだろうか、どうすればもらえるのか、手続きが難しいのではないか、などど戸惑う方も多いことでしょう。また、受給者証の申請は、子どもの障害を認めるようで抵抗がある、と感じるかもしれません。
しかし、療育の目的は、子どもの苦手さを補い、得意なことを伸ばし、将来の可能性を広げることです。受給者証は、そのための専門的なサポートを受けるための切符のようなものだと捉えることが大切です。
この記事では、子どもの療育に必要となる受給者証とは何か、その役割や種類、よく混同される療育手帳との違い、そして実際に受給者証をもらうまでの申請方法について、詳しく解説します。
受給者証とは
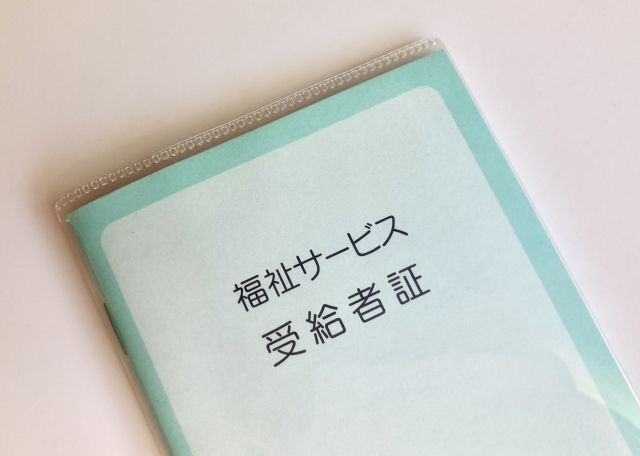
受給者証とは、児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援という福祉サービスを利用するために、お住まいの自治体(市区町村)から交付される利用許可証のようなものです。
この受給者証があることで、利用者は原則1割の自己負担で療育サービスを受けることができます。つまり、療育を受けるためのパスポートであり、同時に利用料の割引券でもある、とイメージすると分かりやすいでしょう。
受給者証の対象となる子ども
受給者証という名前や、利用するサービスが障害児通所支援となっているため、障害の診断がないともらえないと誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。
受給者証の交付対象は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、または難病などがある子どもです。しかし、療育手帳や身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、医師の診断書や、専門家の意見書(例えば、自治体の発達相談センターでの面談結果など)に基づき、自治体が療育の必要性ありと判断すれば、受給者証は交付されます。
子どもの発達は、脳が柔軟な幼児期に適切なサポートを受けることで、大きく伸びる可能性があります。そのため、診断が確定するのを待つよりも、困難さが見られる時点で早期に支援を始めることが重要であるという考え方に基づいています。就学前に適切な支援を受けることで、集団生活でのつまずきを減らし、自己肯定感を高く持って小学校生活をスタートできる可能性が高まります。
受給者証で利用できるサービスの種類
受給者証で利用できる障害児通所支援には、いくつかの種類があります。子どもの年齢やニーズによって、利用するサービスが異なります。
・児童発達支援
主に未就学(0歳から6歳)の子どもが対象です。日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練、運動機能や認知機能の発達を促すプログラムが提供されます。生活スキルの土台や、就学に向けた基盤づくりを行う場です。ステラ幼児教室もこの児童発達支援に該当します。
・放課後等デイサービス
主に就学中(小学1年生から高校3年生)の子どもが対象です。学校の授業終了後や夏休みなどの長期休暇中に通い、生活能力の向上や社会との交流(ソーシャルスキルトレーニングなど)、学習のサポート、居場所の提供など、学齢期に必要な支援を行います。
・保育所等訪問支援
子どもが通っている保育園や幼稚園、学校などに支援員が訪問し、子どもが他の子どもたちとスムーズに集団生活を送れるように、専門的な支援や先生へのアドバイスを行います。
・医療型児童発達支援
肢体不自由がある子どもや、重度の障害がある子どもが対象で、児童発達支援の内容に加えて、治療や看護などの医療的ケアも同時に行われます。
療育手帳との違いは何か?

受給者証と最も混同されやすいのが療育手帳です。この2つは名前が似ていますが、その目的と役割、発行元が全く異なります。
受給者証はサービスの利用券
前述の通り、受給者証(障害児通所受給者証)の目的は療育サービスを利用するためのものです。
・役割: サービスの利用許可証・利用料の割引券
・根拠法: 児童福祉法
・発行元: 市区町村(お住まいの自治体)
これがないと、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用(契約)することができません。
療育手帳は障害の証明書
一方、療育手帳の目的は知的障害(または知的障害を伴う発達障害)があることを証明するためのものです。自治体によっては愛の手帳やみどりの手帳など異なる名称で呼ばれます。
・役割: 障害の程度を証明する身分証
・根拠法: 自治体ごとの判定基準(国のガイドラインに基づく)
・発行元: 都道府県または政令指定都市
療育手帳を持っていると、JRやバスなどの公共交通機関の運賃割引、美術館や動物園などの公共施設の入場料免除、各種税金の控除、高速道路料金や携帯電話料金の割引など、障害の程度に応じたさまざまな経済的支援や割引制度を受けることができます。
療育手帳がなくても療育は受けられる
ここが最も重要なポイントで、療育を受けるために療育手帳は必須ではありません。
療育(障害児通所支援)を利用するために必要なのは、あくまで受給者証です。 療育という言葉が共通しているため、療育手帳がないと療育が受けられないと誤解されがちですが、これらは全く別の制度です。
療育手帳を持っていなくても、医師の意見書などで療育が必要と判断されれば、受給者証の申請は可能です。 実際、療育手帳の取得基準には満たないグレーゾーンの子どもや、診断がつく前の早い段階から療育を始める子どもの多くは、受給者証だけを持っている状態でサービスを利用しています。
両方持つことはできるか
両方持つことは可能です。申請窓口も根拠法も異なります。 療育手帳の交付基準に該当する子どもは、障害の証明と各種割引のために療育手帳を持ち、さらに療育サービスを利用するために受給者証を持つ、という両方を持っているケースが一般的です。
受給者証をもらうには?申請から利用までの流れ

では、実際に受給者証をもらうには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。自治体によって細かなルールは異なりますが、大まかな流れは以下の通りです。
まずは自治体の相談窓口へ
最初に、お住まいの自治体(市区町村)の担当窓口に相談することから始まります。 多くの場合、障害福祉課、こども発達支援課、子育て支援課といった名称の窓口が担当しています。
ここで、子どもの発達が気になり、療育(児童発達支援など)の利用を考えていると伝えます。 相談に行く前に、どんな場面で困るか、いつから気になっているかなど、子どもの具体的な様子をメモにまとめておくと、スムーズに伝わります。もしあれば、医師の診断書や意見書、発達検査の結果などを持参します。 また、先にステラ幼児教室のような療育施設に相談し、見学や体験をした上で、この事業所を利用したいと考えていますと伝えるのも良い方法です。
利用計画案の作成
受給者証の申請には、障害児支援利用計画案(またはサービス等利用計画案)という書類を添付する必要があります。 これは、子どもにどのような課題があり、どのサービスをどのくらいの頻度で利用するのが適切かをまとめた計画書です。
この計画案は、保護者ご自身が作成するセルフプランも可能です。しかし、どのようなサービスが必要か、月に何回程度が適切かを判断が難しい場合は、自治体が指定する相談支援事業所の相談支援専門員に作成を依頼します。 相談支援専門員が子どもや保護者と面談し、ニーズを詳しく聞き取った上で、無料で計画案を作成してくれます。
自治体への申請と必要なもの
利用計画案が完成したら、以下のものなどを揃えて、再度自治体の窓口に申請します。
・申請書(窓口でもらえます)
・障害児支援利用計画案(セルフプランの場合は窓口で記入も可)
・マイナンバーが分かるもの
・医師の診断書や意見書、療育手帳など(自治体から必要と判断された場合)
・世帯の所得がわかる書類(住民税課税証明書など ※自己負担額を算定するために必要です)
※自治体によって必要なものは異なることもあるため、自治体に問い合わせをすると良いです。
受給者証の交付と利用開始
申請書類が受理されると、自治体内で審査が行われます。審査では、サービス利用の必要性や、適切な利用日数(月に○日など)が決定されます。 審査が通ると、約1〜2ヶ月程度で、自宅に受給者証が郵送されてきます。
受給者証が手元に届いたら、それを持って利用したい療育施設(例えばステラ幼児教室)に行き、正式に利用契約を結びます。これで、療育サービスの利用がスタートできます。
受給者証に関するよくある質問

受給者証に関して、保護者の方からよく寄せられる質問をまとめました。
利用料金(利用者負担額)はいくらか
療育サービス(障害児通所支援)の利用料金は、法律で定められています。利用料の9割は自治体などが負担し、利用者は1割を負担します。 ただし、保護者にとって大きな負担とならないよう、世帯所得に応じた月額負担上限額が決められています。
・生活保護受給世帯、住民税非課税世帯: 0円
・住民税課税世帯(世帯年収 約890万円未満): 4,600円
・上記以外(世帯年収 約890万円以上): 37,200円
また、年少児から年長児は無償化の対象になっており、利用者負担はありません。2歳児までの子どもも、無償となる自治体もあるため、お住まいの自治体の窓口に直接問い合わせることをおすすめします。
有効期間と更新手続き
受給者証には有効期間があり、原則として1年間です。有効期限が切れる数ヶ月前になると、自治体から更新手続きの案内が届きます。引き続き療育の利用を希望する場合は、再度申請(利用計画案の見直しなど)が必要です。これは、子どもの成長に合わせて、支援内容が今も適切か(モニタリング)を確認するためでもあります。
引っ越した場合はどうなるか
受給者証は、発行した市区町村でのみ有効です。 もし他の市区町村へ引っ越した場合は、引っ越し先の自治体で新たに申請手続きを行う必要があります。
受給者証はすぐに発行されるか
いいえ、残念ながら申請してすぐに発行されるものではありません。 前述の通り、相談、利用計画案の作成、申請、審査、交付というステップを踏むため、相談から交付までに1ヶ月から2ヶ月程度かかるのが一般的です。 療育を始めたいと思ったら、早めに相談を始めることをおすすめします。
受給者証を持つデメリットは?
保護者の方の中には、受給者証を持つことで、将来の進学や就職に不利になるのではないかと心配される方もいます。 しかし、受給者証の利用履歴が戸籍や住民票などに記載されることは一切ありません。また、保育園や学校に受給者証の情報を開示する義務もありません(支援を連携する上では情報共有が推奨されますが、強制ではありません)。受給者証は、あくまで福祉サービスを利用するためだけのものです。子どもが必要な支援を受ける権利を行使することのデメリットは、制度上ありません。
療育に必要な受給者証の申請方法についてのまとめ
受給者証(障害児通所受給者証)とは、療育サービスを利用するための利用許可証であり、療育手帳とは異なるものです。 療育手帳を持っていなくても、医師や専門家が療育が必要と判断すれば申請できます。
この制度のおかげで、無償または1割負担という少ない自己負担で、療育を受けることができます。
手続きには時間がかかるため、子どもの発達が気になったら、まずはひとりで抱え込まず、お住まいの自治体の窓口や、ステラ幼児教室のような専門機関に相談することから始めてみてください。
ステラ幼児教室では随時見学受付中
名古屋市、大阪市に展開している児童発達支援事業所、ステラ幼児教室では随時見学を行っています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。
お気軽にご相談ください。














