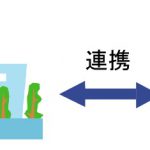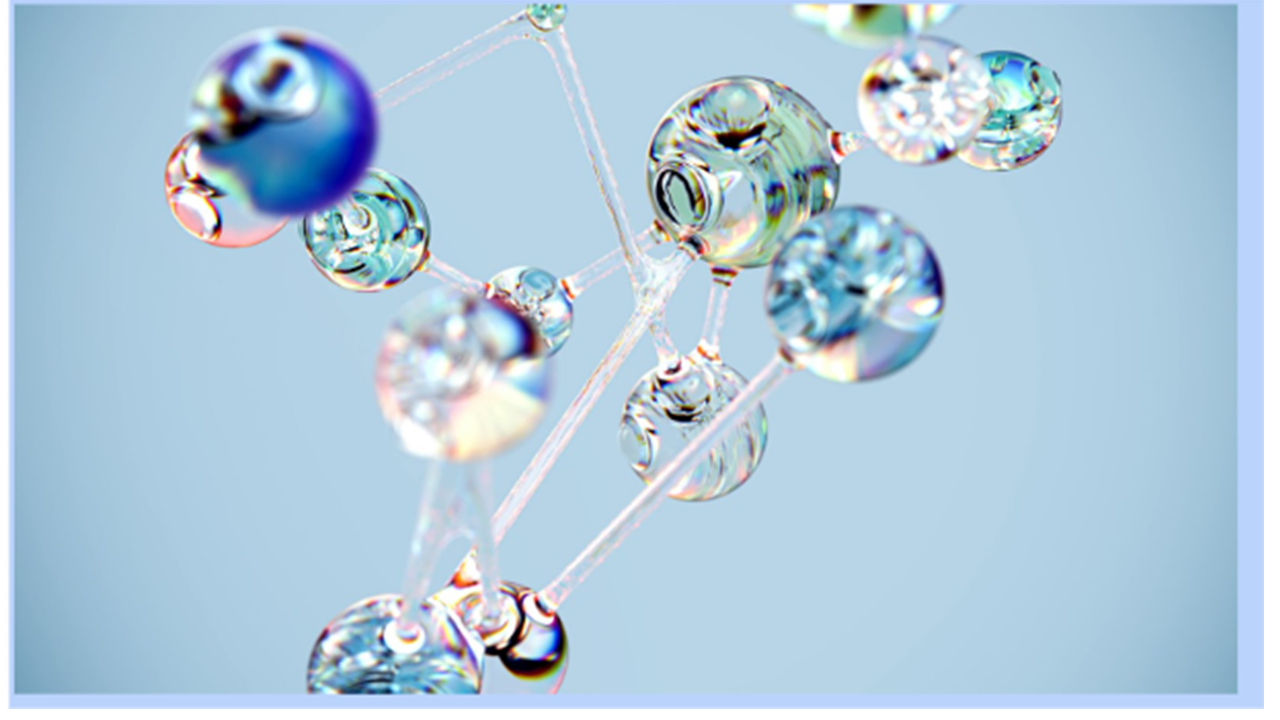
発達障害は、子どもが生まれつき持つ特性のひとつとされていますが、その原因にはさまざまな要素が関連しています。特に「遺伝との関係性」については、現在までに多くの研究が進められており、家族内での発症リスクや遺伝子の影響が指摘されています。
しかし、発達障害は単純な遺伝だけで決まるものではなく、環境要因とも複雑に絡み合っていることが分かっています。
そこで本記事では、発達障害と遺伝の関係性や原因、親からの遺伝、そして発達障害の子どもの支援についてもわかりやすく解説していきます。
発達障害と遺伝の関係性
「発達障害はどの程度、遺伝と関わっているのか?」という疑問は多くの保護者が持つところです。家族に同じ傾向があると「必ず遺伝するのでは」と心配になることもあるでしょう。
実際には、発達障害は遺伝的な要因と環境的な要因が重なって表れると考えられています。つまり「遺伝=発症」ではなく、「発症しやすい体質」として受け継がれることがあるということです。
ここでは、発達障害と遺伝がどのように関わっているのか、基本的な考え方を解説していきます。
発達障害の定義と種類
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
主には、自閉スペクトラム症障害(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)の3つに分類されます。
ASD
ASDは、対人関係やコミュニケーションに困難を伴う特性があり、特定の興味や行動へのこだわりが見られます。
ADHD
ADHDは、不注意や衝動性、多動性を特徴とし、集中力が続かないことや衝動的な行動を取ることが多いです。
LD
LDは、知的発達に遅れはないものの、特定の学習分野(読み書きや計算)に困難を抱える障害です。
これらは、それぞれ特性が異なりますが、併存する場合もあります。発達障害の特性を理解し、それぞれが持つ能力を発揮できる環境を整えてあげることが大切です。
参考元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000633453.pdf
遺伝的要因には関連性がある
発達障害の原因には、遺伝的要因が深く関わっていると考えられています。
研究によると、自閉スペクトラム症障害(ASD)の子どもがいる家庭では、兄弟姉妹にASDが見られる確率が3〜10%高くなると報告されています。また、注意欠如・多動症(ADHD)についても、親がADHDの場合、子どもに受け継がれる可能性が高いことが示されています。
これらの発達障害は、単一の遺伝子によるものではなく、複数の遺伝的要因が組み合わさって発現すると考えられています。しかし、遺伝がすべてではなく、環境要因とも密接に関連しており、遺伝と環境の両方を考慮した支援が必要です。
参考元:MSDマニュアル
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home
環境要因が総合的に作用する
発達障害は、遺伝的要因だけでなく、環境要因も関係していると考えられています。
たとえば、妊娠中の母体の健康状態や栄養状態、出生時の低体重や早産、周産期の合併症などが、発達障害のリスクを高める可能性があると報告されています。また、環境要因として幼少期のストレスや生活環境も影響する場合があります。
ただし、ワクチン接種や特定の養育方法が発達障害の原因になるという科学的な根拠はなく、この誤解は避ける必要があります。発達障害の要因は多様であり、原因を特定することよりも、本人の特性を理解し、適切な支援を行うことが何より大切です。
参考元:一般社団法人 日本小児神経学会
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ojjscn/47/3/47_215/_article/-char/ja/
発達障害が遺伝する原因

「なぜ発達障害は遺伝すると言われるのか?」と考える方も多いかもしれません。発達障害は一つの遺伝子が原因となる病気とは異なり、複数の遺伝子や脳の発達の仕組みが複雑に関わっているとされています。
また、妊娠・出産時の要因や育つ環境との相互作用によって、特性の表れ方は人によって大きく異なります。
本項では、発達障害が遺伝すると言われる背景や原因について、医学的にわかっていることをもとに解説していきます。
一卵性双生児
一卵性双生児の研究は、発達障害の遺伝的要因を理解する上で重要な役割を果たしています。
一卵性双生児は同じ遺伝情報を共有していますが、環境要因の違いにより、発達障害の症状や程度が異なる場合があるからです。このことから、遺伝と環境の両方が発達障害の発症に関与していることが示唆されています。
遺伝的な多様性
発達障害の発症には、遺伝的な多様性が影響を与えると考えられています。
特定の遺伝子変異やその組み合わせが、発達障害のリスクを高める可能性があるからです。しかし、これらの遺伝的要因は複雑であり、単一の遺伝子だけでなく、複数の遺伝子やその相互作用が関与しているとされています。
参考元:理化学研究所脳神経科学研究センター
https://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2018.900462/data/index.html
コピー数の変異
コピー数変異(CNV)は、特定の遺伝子や染色体領域の重複や欠失を指し、発達障害との関連が報告されています。
これらの変異は、遺伝子の機能や発現に影響を与え、神経発達に影響を及ぼす可能性があります。CNVの検出は、発達障害の診断や理解を深めるための重要な手段です。
参考元:神戸大学大学院医学研究科
https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2021_07_06_01/
発達障害の親からの遺伝について
「親が発達障害なら子どもも同じようになるのか?」という不安を抱く方は少なくありません。実際、家族や兄弟姉妹の中に発達障害がある場合、子どもに同じ特性が見られる可能性が高いことは知られています。
しかし、これは「必ず遺伝する」という意味ではなく、「似た特性が表れやすい傾向がある」ということです。親から受け継いだ特性が、子どもにとっては「強み」として働くことも多くあります。
そこで本項では、親から子どもへの遺伝についての考え方を具体的に解説していきます。
親や兄弟姉妹に発達障害がある場合
発達障害は「遺伝の影響を受けやすい」と言われています。実際、家族や兄弟姉妹の中に発達障害のある方がいると、同じ特性を持つ可能性が高まることが研究からわかっています。ただし、それは必ず「同じ診断名がつく」という意味ではなく、「似た特性や傾向を持ちやすい」ということです。
たとえば、親が注意力の持続に苦手さを持っている場合、子どもも集中に課題が見られることがあります。逆に、親や兄弟に発達障害があっても、全く特性が現れないケースも多くあります。大切なのは、家族歴を知ることによって「より早く気づき、適切にサポートできる」点です。
遺伝と「発症する・しない」の違い
「遺伝する」と聞くと、必ず発達障害になるのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。しかし実際には「遺伝=発症」ではありません。発達障害は、遺伝的な要因に加えて、脳の発達過程や環境要因が重なることで現れると考えられています。
つまり、親から受け継いだ遺伝子があっても「特性が強く表れる子」もいれば「ほとんど表れない子」もいるのです。これは身長や体質が遺伝と生活習慣の影響で変わるのと似ています。したがって、遺伝要素があっても「必ず発症するわけではない」と理解することが安心につながります。
遺伝的傾向と個性の重なりとは
発達障害の特性は「遺伝的傾向」と「その子の個性」が重なり合って現れます。たとえば、親から「言葉に強い興味を持つ傾向」を受け継いだ場合、それが学びの得意さとして表れることもあれば、逆に「細部へのこだわりが強い」といった困りごとにつながることもあります。
大切なのは、遺伝を「不安の原因」として捉えるのではなく「子どもの特性を理解するヒント」として見ることです。遺伝子は子どもの可能性を決めるものではなく、育つ環境や関わり方によって伸ばせる力がたくさんあります。保護者が子どもの強みに気づき、安心できる環境を整えることが支援の第一歩です。
発達障害の子どもの支援方法

「遺伝かもしれない」と思うと、保護者の方は将来を心配しやすくなるでしょう。しかし、大事なのは「原因を探すこと」ではなく、「どう支援していくか」です。
発達障害の特性は、適切な環境やサポートがあれば困りごとを軽減し、強みを活かすことができます。学校での支援、ご家庭での工夫、専門機関のサポートなど、取り入れられる方法はさまざまです。
そこで本項では、子どもの特性を理解し、日常生活や学習を支えるための支援方法を紹介していきます。
①子どもの特性を理解する
一人ひとりの特性や気質を理解し、それぞれに合った支援をすることが大切です。たとえば、視覚的な情報が優位な子どもには、絵や図を用いて説明するなど、個々の特性に合わせた対応が求められます。
②予防的な対応を心がける
特に怒られることが多い子どもに対しては、問題が起きてから対処するのではなく、子どもの様子をよく観察し、失敗経験を少なくすることが重要です。これにより、自己肯定感の低下による問題行動などの二次障害を防ぐことができます。
③専門家や支援機関を頼る
医療機関や教育機関、福祉サービスなどの専門家と協力し、適切な支援を受けることも重要です。ペアレントトレーニング※などのプログラムに参加することで、効果的な育児方法やストレス管理の技術を学ぶことができます。
※発達障害を持つ子どもの行動を理解し、適切に対応するための保護者向けの学習プログラム
④子どもが安心できる環境づくり
子どもの特性に応じて、生活環境を整えてあげることも必要です。たとえば、視覚刺激が入りやすい子どもには、部屋の中で見えるものを減らす、変化が苦手な子どもにはパターンを決めるなど、環境を工夫するとよいでしょう。
⑤保護者自身のケアや情報収集
保護者が自身の心身の健康を保ち、情報交換をすることも大切です。信頼性の高い情報源から最新の支援方法や制度を学ぶことで、不安の軽減になり、子どもへの支援にも役立ちます。
これらのポイントを踏まえ、子どもの特性に合わせた支援を行うことで、子どもの成長と発達をサポートすることができるでしょう。
まとめ:発達障害は、遺伝的要因と環境との相互作用で決まる
発達障害は、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などに分類され、いずれも脳の発達に関わる特性として現れます。
その原因には、複数の遺伝子の影響が深く関与していることがわかっていますが、「遺伝=必ず発症」ではありません。たとえば、親や兄弟に発達障害があっても同じ診断がつくとは限らず、逆に特性が全く見られない場合もあります。妊娠・出産時の要因や成長過程の環境も組み合わさって、特性の表れ方は人によって異なります。
つまり、遺伝的要因は「傾向を受け継ぐ」ものであり、それがどのように個性と重なって現れるかは環境との相互作用によって決まるのです。大切なのは原因探しではなく、子どもの特性を理解し、適切な支援や環境調整を行うことです。
専門機関の協力やご家庭での工夫、保護者自身のケアも含めて整えていくことで、子どもの強みを伸ばし、安心できる成長を支えることができます。
参考元
厚生労働省
MSDマニュアル
一般社団法人 日本小児神経学会
理化学研究所脳神経科学研究センター
神戸大学大学院医学研究科