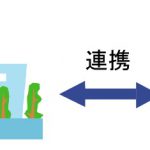自閉症がある子のこだわりに悩むママ必見!ご家庭でできる小学生の娘さんについて「他の子とどこか違う気がする」「何となく育てにくい」と感じることはありませんか。そうした違和感の背景には、発達障害の特性が隠れている可能性があります。特に女子の発達障害は男子に比べて発見が難しいとされ、支援につながるまで時間がかかるケースが少なくありません。
この記事では、発達障害とは何かを簡単におさらいするとともに、小学生に見られる一般的な特徴、女子特有のサイン、診断にいたらない「グレーゾーン」のチェックポイントを取り上げます。そのうえで、口に物を入れる、盗み癖、母子分離不安、癇癪などの問題行動への具体的な対応方法を詳しく解説します。また、専門機関への相談のタイミングや利用できる支援制度、家庭でできる工夫についても整理します。
発達障害の小学生に見られる主な特徴とは?
文部科学省の調査(令和4年)によると、普通学級に在籍する児童生徒の約6.5%に発達障害の可能性があるとされており、決して特別なことではありません。
小学生でとくに目立つのは、学習面での困難です。授業に集中できない、読み書きや計算に時間がかかるといったことがよく見られます。また社会面では、友達との関係づくりが苦手で、集団のルールを理解するのに苦労したり、相手の気持ちを読み取れなかったりすることがあります。さらに日常生活では、忘れ物が多い、時間の管理が苦手、感情のコントロールがうまくできないなど、さまざまな特徴が見られます。
発達障害の種類と基本的な特徴
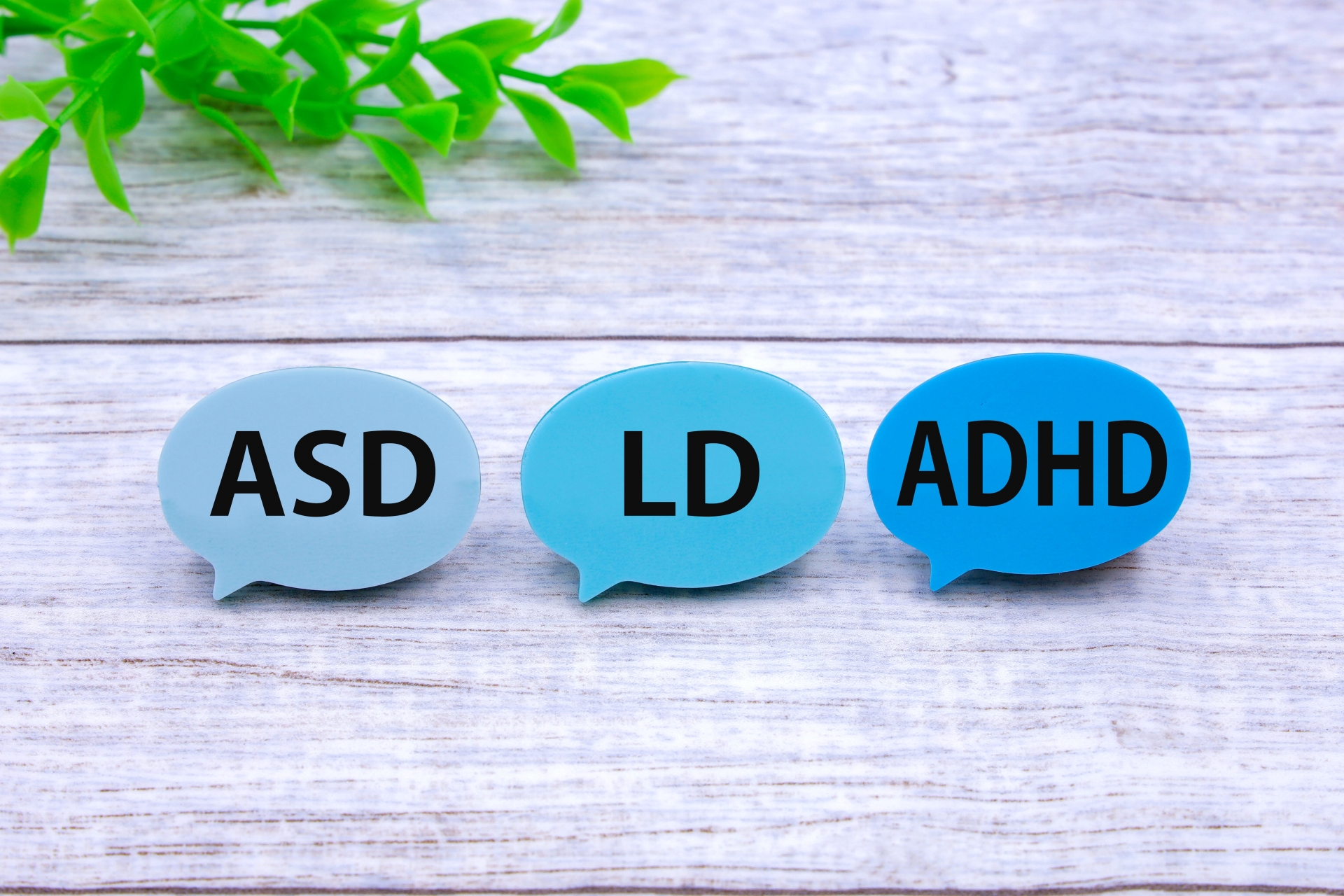
発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
大きく分けると、注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)の三つがあります。これらは単独で存在する場合もありますし、複数の特性が同時に見られる場合もあります。
注意欠如多動性障害(ADHD)の特徴
ADHDは、不注意、多動性、衝動性を主な特徴とする発達障害です。不注意の側面では、課題に集中できない、細かいミスが多い、話を聞いていないように見えるといった傾向があります。多動性としては、じっと座っていられず体を動かす、授業中に席を立つなどの行動が目立ち、落ち着きがないと見られがちです。衝動性の面では、質問が終わる前に答える、順番を待てない、相手の話をさえぎるといった行動が見られ、感情や行動のコントロールに難しさを抱えます。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴
ASDは、社会的コミュニケーションの困難と、行動や興味の強いこだわりを特徴とします。他者とのやり取りが一方的になりやすく、視線や表情、身振りといった非言語的なサインを理解することが難しい場合があります。その結果、年齢に応じた人間関係を築きにくいことが多いです。また、ルーティンを崩されることに強い不安を覚えたり、特定の物やテーマに過度に集中したりする傾向もあります。感覚刺激への過敏さや鈍感さも特徴で、音や光を苦痛に感じる一方、痛みに気づきにくい場合もあります。
学習障害(LD)の特徴
学習障害(LD)は、知的発達に遅れがないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」といった特定の学習能力に著しい困難を抱える状態です。以下の3つに大きく分けられます。
- 読みの困難(ディスレクシア)
文字を正確に読んだり、内容を理解したりすることが苦手です。読むスピードが極端に遅いこともあります。 - 書きの困難(ディスグラフィア)
文字を正確に書くことが困難で、文字のバランスが崩れたり、漢字を覚えるのに苦労したりします。 - 算数の困難(ディスカルキュリア)
数の概念を理解するのが難しく、簡単な計算でも時間がかかったり、文章問題が解けなかったりします。
小学生女子に現れやすい発達障害の特徴

女子の発達障害は男子に比べて発見されにくいといわれています。「女の子らしい」とされる行動の中に特性が紛れ込み、見過ごされる傾向にあるからです。例えば、特定の物事への強いこだわりが「丁寧な性格」ととらえられたり、人間関係で困難を抱えても「人見知り」と解釈されたりします。さらに、学業成績が良好な場合は困難が見えにくく、支援が遅れることがあります。
女子特有の症状の現れ方
女子に特徴的なのは「カモフラージュ(擬態)」です。周囲に合わせるために無理をして特性を隠すことが多く、一見問題がないように見えても、内面では強いストレスや孤独感を抱えている場合があります。そのため、思春期に入って人間関係が複雑になると、抑うつや不安といった二次的な問題が表面化することもあります。
男子との違いと見落とされやすいポイント
男子は外向的な行動に特性が現れやすく、落ち着きのなさや衝動的な行動から支援に繋がることが多いですが、女子は内向的で自分を責めやすい傾向が強く、困難を外に表現することが苦手です。そのため「おとなしい」「内気な子」と評価され、問題としてとらえられにくいことが多いのです。
発達障害のグレーゾーン?チェックしたいポイントはここ!
発達障害と診断されるほどではないものの、日常生活で困難が続いている状態を「グレーゾーン」と呼びます。
学習面では、宿題に時間がかかりすぎる、忘れ物が多い、授業中にぼんやりしている、文字を読むときに行を飛ばす、計算間違いに気がつかないなどが見られます。
対人関係では、友達との約束を守れない、相手の気持ちを理解できない、冗談が通じない、集団遊びが苦手、一人でいることを好むなどが挙げられます。
日常生活でのチェックポイント
日常生活の中で発達障害を疑うポイントとしては、朝の支度に時間がかかる、片付けができない、予定変更に強いストレスを示す、感覚刺激に過敏である、感情の起伏が激しいなどがあります。
こうしたサインが積み重なる場合は、専門機関への相談を検討するのもひとつの方法です。
チェックシートを活用しよう
「うちの子、発達障害かも?」と感じたら、発達障害の啓蒙活動を行う協会が監修した診断テスト(ADHD・自閉症)を試してみるのも一案です。ただし、あくまでもセルフチェックですので、おかしいなと思ったら医療機関を受診しましょう。
参照:ADHD・自閉症診断テスト|子ども発達障害チェックリスト【協会監修】
小学生の発達障害に伴う問題行動の特徴と対応策

発達障害のある小学生には、特性に関連した様々な行動が見られることがあります。これらは「問題行動」ではなく、その子なりの表現や対処方法として理解することが重要です。
今回は「口に物を入れる」「盗み癖」「母子分離不安」「癇癪」の4つに焦点を当て、それぞれについて簡単に解説します。
口に物を入れる行動への対処法
口に物を入れる行動は、感覚刺激を求める自己刺激行動のひとつです。不安やストレスを和らげるために行われることもあれば、集中力を高めるための無意識の手段であることもあります。
頭ごなしに叱るのではなく、安全に感覚を満たせる代替手段を与えることが大切です。シリコン製のグッズを噛ませたり、ストローやガムを活用したりすると良いでしょう。行動が始まる前兆(そわそわし始めるなど)を見つけ、先回りして代替行動を提案することで、未然に防ぐことができます。
盗み癖が見られる場合の適切な対応
盗み癖は、欲しい気持ちを我慢できない衝動性や、他人の物と自分の物の区別(所有)の概念の理解不足から起こることがあります。また、「盗むことはいけないことである」という認識が未発達である場合や、寂しさや不安から注目を集めたい気持ちが背景にある場合もあります。
冷静に事実を確認したうえで、所有の概念を丁寧に教え、「欲しいときは貸してと言う」といった適切な行動を具体的に指導することが重要です。
母子分離不安への理解と対処
母親と離れることを極端に嫌がり、登校を渋ったり泣き続けたりするのが母子分離不安の特徴です。不安が強いと、腹痛や頭痛といった身体症状が出ることもあります。
対処法としては、「必ず迎えに行く」と事前に予告して見通しを持たせることが有効です。短時間から練習を始めて徐々に時間を延ばしていく段階的な方法も役立ちます。
学校生活が原因で不安が強まっている場合は、担任の先生と密に連携し、学校での様子を共有することも大切です。決して無理強いせず、ゆっくりと不安を乗り越えていく手助けをしてあげましょう。
癇癪への適切な対応方法
癇癪は、発達障害の問題行動の中でも最も対処が難しいもののひとつです。ここでは癇癪が起こる原因と、起こった場合の対応手順、癇癪を起こさないための日常的な工夫について掘り下げて解説します。
癇癪が起こる原因を理解する
癇癪は、いわば「困っている」という心の叫びです。子どもが何らかの不快感や困難をうまく伝えられない時に起こります。主な原因としては、感覚過敏による不快感、予期せぬ出来事への混乱、そして疲労やストレスの蓄積が挙げられます。また、強いこだわりや衝動性の高さが、思い通りにいかないイライラや欲求不満に繋がり、癇癪を引き起こすことがあります。
癇癪が起こったときの対処法
癇癪が起きた際は、まずお子さんと周囲の安全を最優先に確保し、危険な物を取り除きましょう。次に、大声で叱らず、冷静かつ穏やかな声で話しかけ、物理的な制止は最小限にとどめます。
癇癪の原因を理解しようと、「辛かったね」「困ったね」といった共感の言葉で子どもの気持ちを受け止め、落ち着くまで見守りましょう。感情が落ち着いた後で、何が辛かったのかを一緒に振り返り、より良い対処法を考えることで、次の癇癪を予防する学習の機会になります。
癇癪を減らすための日常的な工夫
癇癪を減らすのに最も効果的なのは、癇癪が起きにくい環境を整えることです。
規則正しい生活リズムを確立し、十分な睡眠と栄養を確保することで、心身の安定を促します。また、予定の変更は事前に伝え、見通しを持たせてあげることで、不安を減らすことができます。
感覚過敏に配慮した静かな空間を用意したり、ルーティンを明確にすることも有効です。さらに、感情を言葉で表現する方法や困ったときの対処法を教え、成功体験を十分に褒めて自信をつけさせましょう。これらの工夫が、お子さんの心を安定させ、癇癪を減らすことに繋がります。
発達障害専門機関への相談と支援制度について

「もしかして発達障害かも?」と感じた場合、発達障害専門機関への相談が有効です。ここでは、相談すべきタイミングと利用できる支援制度とサービスについて簡単に解説します。
相談すべきタイミング
学習面や人間関係、日常生活などで困りごとが続き、お子さんや家族が強いストレスを感じているなら、その時が専門機関への相談を検討すべきタイミングです。
具体的なサインとしては、学習面では、授業に極端についていけない、宿題に毎回長時間かかる、特定の教科に著しい困難があるなど、人間関係では、友達とのトラブルが頻発する、集団行動が苦手などがあります。こういった状況が数か月以上続いたら、相談を考えてみましょう。
利用できる支援制度とサービス
発達障害のお子さんが利用できる支援制度やサービスは多岐にわたります。まず、気になることがあれば発達障害情報・支援センターや地域の発達支援センター、保健センターなどの公的な相談窓口に相談しましょう。
診断後は、学校での特別支援教育(通級指導教室や特別支援学級)や、放課後を過ごすための放課後等デイサービス、親御さん向けのペアレントトレーニングなどの福祉サービスが利用できます。さらに、特別児童扶養手当や自立支援医療といった経済的支援も用意されています。
厚生労働省と文部科学省が協力して運営する「発達障害ナビポータル」では、こうした支援制度について全国の情報が提供されています。ぜひ活用してみてください。
発達障害を疑う小学生に対し家庭でできる支援のポイント
家庭は子どもにとって最も安心できる場所です。子どもの特性を理解し、得意なことと苦手なことを把握することが出発点となります。いつ、どこで、何を、どのように行うかをわかりやすく示す「構造化」を取り入れると、子どもが安心して行動できるでしょう。スケジュール表やチェックリストなどの視覚的な支援も効果的です。
また、具体的で短い指示を心がけ、一度に複数のことを求めないことが大切です。小さな目標を立てて達成できたら具体的に褒め、成功体験を積み重ねることで自信を育てます。家庭内の工夫に加えて、学校や専門機関と情報を共有し、一貫性のある支援を行うことも欠かせません。保護者自身も無理をせず、必要に応じて周囲のサポートを得ながら長期的に取り組んでいくことが大切です。
発達障害がある小学生女子の特徴についてのまとめ

発達障害のある小学生女子は、男子とは異なる特徴を示すことが多く、そのために発見や支援が遅れがちです。しかし、特性を正しく理解するとともに、適切な理解と支援を行えば、その子らしい成長を遂げることができるはずです。
何より大切なのは、お子さんが自分らしく成長できる環境を整えることです。完璧を求めず、一歩ずつ、お子さんのペースに合わせて歩んでいきましょう。困った時はひとりで抱え込まず、専門機関や同じ経験を持つ保護者の方々と連携することも大切です。気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。