合理的配慮の提供が民間企業や事業者にも義務化されていることをご存じでしょうか。
この改正は、「障害者差別解消法」によるものです。
これまで学校や行政機関では努力義務とされていた合理的配慮が、今後は企業や民間施設でも「必ず行わなければならない」ことになりました。
教育現場、企業、福祉関係者、そして保護者にとっても、避けて通れない重要なテーマです。
この記事では、合理的配慮とは何か、その定義や目的、いつから義務化されたのかを解説。障害者差別解消法の概要と、学校での取り組み事例についてわかりやすくお伝えします。
合理的配慮とは?その定義と目的

まず、合理的配慮とは何か、その定義と目的から解説していきます。
定義
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の人と同じように社会生活を送れるように、社会の側が環境や対応を調整することをいいます。
障害者差別解消法では、次のように定義されています。
障害のある者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去のために必要かつ合理的な配慮を行うこと。
つまり、「合理的配慮」とは次のような考え方です。
- 障害のある人が「こうしてほしい」と伝えたときに、
- 相手側(行政・学校・企業など)が、
- 無理のない範囲で、環境を整えることが求められる。
目的
合理的配慮の目的は、「障害を理由に不利益を受けない社会」をつくることです。
障害がある本人の「努力」ではなく、社会の仕組みを変えることに重点が置かれています。
この考え方は、2014年に日本が批准した「障害者権利条約(国連)」に基づいており、世界的にも共通の方向性です。
障害者差別解消法の概要

「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」の概要を見ていきます。
法律の目的
「障害者差別解消法」は、2013年に制定され、2016年に施行された法律です。
その法律の目的は次の3つに集約されます。
- 障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止すること
- 障害のある人への合理的配慮を推進すること
- すべての人が共に生きる社会(共生社会)を実現すること
この法律によって、学校や行政機関、企業など、あらゆる組織が障害者への差別防止と配慮を行う責任を負っています。
合理的配慮はいつから義務化された?

合理的配慮はいつから義務からされたのでしょうか。冒頭でも少し触れたように、行政や学校で義務化された時期と、民間企業や事業者にも義務化された時期が違います。
行政や学校では2016年から義務化
まず、国や地方公共団体、学校などの公的機関では、2016年(平成28年)4月の法律施行時点から合理的配慮の提供が義務化されています。
教育現場では、文部科学省の通知に基づき、次のような観点から合理的配慮が実施されてきました。
- 発達障害や知的障害のある子どもに対する個別支援計画の作成
- 教材や指導方法の工夫
- 試験時の特別措置(別室受験、時間延長など)
民間企業や事業者は2024年4月から義務化
一方、民間事業者については、当初は「努力義務」にとどまっていました。
しかし、2021年の法改正を経て、2024年(令和6年)4月1日から、民間企業にも義務化されました。
つまり今では、以下のすべてが合理的配慮を「提供しなければならない」立場になっています。
- 学校(公立・私立問わず)
- 行政機関
- 一般企業
学校における合理的配慮の実例

学校現場では、合理的配慮は「特別な支援」ではなく、「誰もが学べる環境づくり」の一環として位置づけられています。
具体的な配慮の例
困りごとについて、どのような具体的な合理的配慮がなされているか、例を紹介します。
具体的な合理的配慮の例
| 困りごと | 合理的配慮の例 |
|---|---|
| 聴覚障害がある | 教師が口の動きを見せて話す、板書を活用する、音声文字変換アプリを使う |
| 視覚障害がある | 点字教材、拡大文字プリント、音声教材の使用 |
| 発達障害がある | 見通しのあるスケジュール提示、指示を短く具体的に伝える、支援員の配置 |
| 知的障害がある | ゆっくりしたペースの説明、繰り返し学習、成功体験を重視する指導 |
| 身体障害がある | バリアフリー化、机や椅子の調整、移動経路の確保 |
これらはすべて、子どもの「できない」を「できる」に変えるための社会的な工夫です。
過重な負担との関係
合理的配慮は義務化されましたが、すべての要望を無条件に受け入れるわけではありません。
法律上、「過重な負担」にあたる場合は、必ずしも対応を求められません。
過重な負担の判断基準
- 費用や人員など、実現に必要なコストが非常に大きい
- 組織の規模や性質から見て、対応が現実的でない
- 他の利用者や業務全体に重大な支障を及ぼす
ただし、「できない」と即答するのではなく、代替案を検討する努力が求められます。
たとえば「エレベーターがない建物」であれば、「1階で手続きを行う」などの代替対応が合理的配慮にあたります。
合理的配慮を拒否した場合の罰則は?
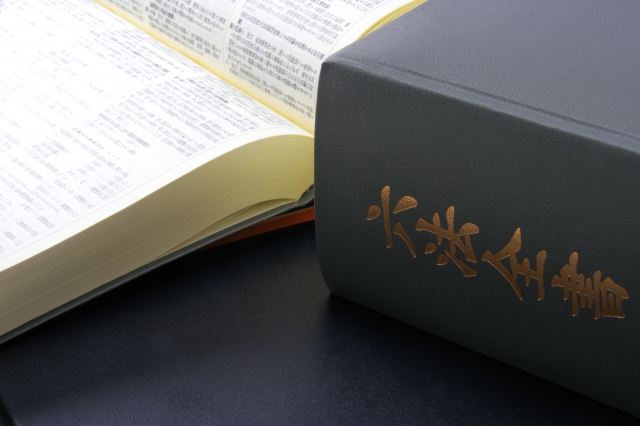
合理的配慮を拒否した場合の罰則について詳しく見ていきましょう。
罰則は原則として無し
障害者差別解消法では、合理的配慮を行わなかった場合の直接的な罰則はありません。
ただし、「罰則がない=何をしてもよい」という意味ではありません。
合理的配慮を怠り、障害を理由とした差別的な取扱いを行った場合には、
- 行政からの指導・勧告・公表
- 行政処分や訴訟(民事責任)
- 企業や学校の社会的信用の低下
などの形で大きな影響を受ける可能性があります。
行政対応の流れ
- 障害当事者などから相談・苦情が入る
- 行政機関が調査・指導
- 是正勧告や改善要請
- 応じない場合、行政機関が企業名などを公表
このように、直接的な刑事罰はなくても、社会的制裁が非常に重いのが現実です。
学校や企業が求められる今後の取り組み

合理的配慮の義務化により、教育・労働・医療・福祉の各現場で、具体的な行動が求められています。
学校の場合
- 児童・生徒の発達特性や障害の有無にかかわらず、個別の支援を検討する
- 保護者や支援員と連携して、子どもの困りごとを共有する
- 教員が発達障害や知的障害についての理解を深める研修を受ける
学校現場での合理的配慮は、単なる法令遵守ではなく、インクルーシブ教育(共に学ぶ教育)の実現に直結します。
企業の場合
- 採用面接や職場配置で、障害のある人に必要な配慮を行う
- 作業環境や勤務時間を柔軟に調整する
- 障害理解に関する社内研修を実施する
これらの取り組みは、障害者雇用促進法とも連動しており、多様性を尊重する企業文化の形成につながります。
合理的配慮を進めるための心構え

合理的配慮は、特別な支援ではなく、誰もが社会に参加できるための基本的な考え方です。
大切なのは対話
合理的配慮は、「相手の立場に立って考えること」から始まります。
障害のある人やその家族と丁寧に対話し、「どんなことに困っているか」「どうすれば一緒にやっていけるか」を共に考える姿勢が求められます。
一律ではなく個別対応
同じ障害名でも、必要な配慮は一人ひとり違います。
マニュアル的な対応ではなく、その人にとっての最適解を探す柔軟性が必要です。
合理的配慮に関するまとめ
最後に、「合理的配慮」についてまとめておきましょう。
合理的配慮とは、障害のある人が社会に参加するために、環境を整えることです。
いつから義務化されたかについては、行政・学校は2016年から義務化され、民間企業は2024年4月から義務化されました。
罰則はあるかについては、直接的な刑罰はないですが、行政勧告や公表、社会的信用の失墜などのリスクがあります。
合理的配慮の学校での実例は、教材・指導・環境面での調整が中心です。
今後の課題は、一人ひとりの特性に応じた柔軟な支援体制の整備です。
合理的配慮の本質は、「特別扱い」ではなく「公平なスタートラインをつくること」です。
障害のある人も、ない人も、同じ社会の一員として生きやすい環境を整えることが、これからの教育・企業・行政に共通する使命といえるでしょう。
ステラ個別支援塾では、発達障害の子ども専門の個別指導塾です。
子ども一人ひとりの特性に合わせた授業で、子どもの成長をサポートします。
お気軽にご相談ください。
ステラ個別支援塾では無料体験実施中
発達障害専門のステラ個別支援塾では、随時無料体験を実施しています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業で、学習をサポートします。
お気軽にご相談ください。














