いじめが原因で不登校になる子どもたちのサインには年齢によって特徴があります。
本記事では、小学生と中学生それぞれに現れる不登校のサインTOP10を比較し、親が早期に気づくためのポイントと適切な対応策を解説します。
子どもの変化を見逃さないために知っておきたい情報をまとめました。
いじめと不登校の関連性に関する最新データ

文部科学省の調査によると、不登校児の一定数がいじめを経験しており、特に小中学生での影響が顕著です。不登校児を増やさないためにも、いじめの早期発見と適切な対応が必要不可欠です。
不登校といじめの最新統計データ
文部科学省の2023年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、不登校児童生徒数は約34万6千人に達し、前年度比15.9%増加しています。
不登校の児童生徒のうち、26.2%がいじめ被害を訴えていることもわかっています。また、SNSを介したいじめの報告は5年前と比較して2倍に増加しており、デジタル環境でのいじめ対策の重要性が浮き彫りになっています。
年齢別不登校の傾向と特徴
1. 小学生の不登校原因ランキング
| 順位 | 原因 | 割合 |
| 1位 | 学校生活に対してやる気がでない | 22.4% |
| 2位 | 不安・抑うつ | 15.8% |
| 3位 | 生活リズムの不調 | 13.7% |
| 4位 | 親子の関わり方に関すること | 9.7% |
| 5位 | 学業の不振や頻繁な宿題の未提出 | 8.3% |
| 6位 | いじめを除く友人関係をめぐる問題 | 7.2% |
| 7位 | 家庭生活の変化 | 5.2% |
| 8位 | 障害(疑いを含む)に起因すること | 4.7% |
| 9位 | 個別の配慮について | 4.0% |
| 10位 | 転編入学・進学時の不適応 | 2.6% |
無気力や不安が圧倒的に多いことがわかります。また「なぜ無気力になるのか?」「何に不安を感じるのか?」は、児童自身がわかっていないことが多いです。
2. 中学生の不登校原因ランキング
| 順位 | 原因 | 割合 |
| 1位 | 学校生活に対してやる気がでない | 21.9% |
| 2位 | 不安・抑うつ | 16.7% |
| 3位 | 生活リズムの不調 | 13.9% |
| 4位 | 学業の不振や頻繁な宿題の未提出 | 10.6% |
| 5位 | いじめを除く友人関係をめぐる問題 | 9.3% |
| 6位 | 親子の関わり方に関すること | 6.5% |
| 7位 | 転編入学・進学時の不適応 | 4.5% |
| 8位 | 障害(疑いを含む)に起因すること | 3.8% |
| 9位 | 個別の配慮について | 3.8% |
| 10位 | 家庭生活の変化 | 3.7% |
中学生も小学生と同様に無気力や不安がきっかけで不登校になるケースが多いことがわかります。友人関係をめぐる悩みや学業に関する悩みが引き金になるケースは、小学生と比較して多くなっています。
小学生に見られるいじめが原因の不登校サインTOP10
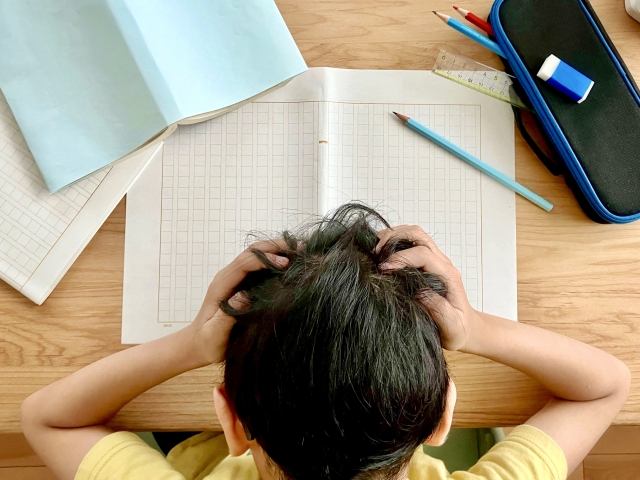
朝の体調不良(頭痛・腹痛・吐き気)
いじめを受けている小学生によく見られる体の反応です。
学校への恐怖や不安が自律神経に影響して、頭痛や腹痛などの本当の体調不良を引き起こします。この症状は月曜日や休み明けに強くなり、週末には良くなるのが特徴です。
子どもは「学校に行きたくない」と言わず、代わりに体調不良を訴えて学校を避けることがあります。このような体調不良が続く場合は注意が必要です。
持ち物の紛失や破損が増える
いじめっ子は、被害にあっている子の持ち物を隠したり壊したりすることがよくあります。
特に大事なものや新しい物が壊される場合や、特定の教科の道具だけが何度もなくなる場合は要注意です。子どもは恥ずかしさや怖さから「自分がうっかりした」と言い訳することが多いです。
学校の話題を避けるようになる
学校の話をしたがらなくなります。
「今日学校どうだった?」と聞いても、話を避けたり別の話題に変えたりします。前は学校の楽しい出来事をよく話していたのに、急に「別に」「普通」などの短い答えで会話を終わらせようとするなら、注意が必要です。
これはいじめのつらい経験から目をそらす自己防衛なので、学校の話を続けて避けるようなら、友達関係に問題がある可能性が高いです。
友達の名前を口にしなくなる
特定の友達の名前を話さなくなります。
前は友達のことをよく話していたのに、急に特定の友達やグループの話をしなくなったら注意しましょう。
子どもが親の質問をはぐらかしたり、友達の話題で表情が暗くなるのも、いじめのサインかもしれません。
急に成績が下がる
学校で集中できなくなるため、成績が突然下がることがあります。
いじめのストレスで不安や恐怖を感じ、授業に集中できず、勉強する気持ちも失います。
親は成績が急に下がったとき、単に「勉強していない」と決めつけず、いじめの可能性を考えて子どもの様子をよく見てあげましょう。
夜泣きや悪夢が増える
昼間の怖い体験やストレスが原因で夜寝られなくなるケースがあります。
急に夜泣きをしたり、「学校に行きたくない」と寝言を言ったり、悪夢を見ることが多くなります。
寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目覚めたりするのは、不安や心の傷のサインです。
帰宅後の様子が暗くなる
家に帰ると表情や態度が暗くなることがあります。
学校では感情を我慢していても、安心できる家では緊張がほぐれて、抑えていた感情が出てきます。
無言で部屋に閉じこもったり、とても疲れた様子を見せたり、家族と話したがらなくなったり、怒りやすくなったり、ちょっとしたことで泣いたりすることもあります。
些細なことで過剰に反応する
小さなことに強く反応することがあります。
小さな音や動きにびっくりしたり、誰かに話しかけられると警戒したりするのは、心の傷のサインかもしれません。
家族から軽く注意されただけでも、ひどく落ち込んだり反発したりするのは、学校でたまった気持ちが出てきているのです。
こうした感情の乱れが続くときは、学校での友達関係に問題があるかもしれないので、やさしく子どもの話を聞いてあげましょう。
体育や行事を嫌がるようになる
体育や学校行事を突然嫌がるようになることがあります。
なぜかというと体育の着替え時間や行事の自由時間は先生の目が届きにくく、いじめが起きやすいからです。
運動会や遠足では、グループ分けや自由時間にいじめられるのが怖いため、こうした行事に「お腹が痛い」などと言って参加したがらない場合、わがままではなく、いじめから身を守ろうとしている可能性があります。
SNSの使用を急に避けるようになる
ネット上でいじめられているか、学校でのいじめがSNSで広まることを怖がっている場合、SNSを突然使わなくなることがあります。
前は楽しんでいたアプリを消したり、通知を見なかったり、SNSの話題が出ると表情が暗くなったりするのがその兆候と言えます。
グループチャットから抜けたり、アカウントを非公開にしたりするのも、身を守ろうとしているサインかもしれません。
ネット上のいじめは昼も夜も続く可能性があり、普通のいじめよりも子どもに大きな影響を与えることがあります。
中学生に見られるいじめが原因の不登校サインTOP10

友人関係の急な変化(グループからの孤立)
中学生の友達関係では、いじめが始まると急に仲間から離されることがあります。
それまでの友達が距離を置き始め、一人だけ別の席に座らされたり、グループLINEから外されたりします。
「あの子と仲良くすると自分もいじめられる」という恐れや、周りに合わせる「空気を読む」心理からそのような行動を起こします。
子どもの話から友達の名前が消えたり、「一人でも平気」と言い訳するようになったら注意してください。
SNSの使用パターンの変化(頻度の増減、チェックの執着)
いじめを受けている中学生のSNSの使い方には特徴があります。
スマホの使用が急に増える場合、いじめの証拠を集めたり、自分についての噂を確認したりするために、頻繁にスマホをチェックします。
逆にSNSの使用が急に減る場合は、ネット上のいじめから逃げようとしている可能性があります。
また、特定のSNSを突然使わなくなる、アカウントを消す、匿名アカウントを作るといった行動も特徴的な使い方です。
SNSを見た後に表情が暗くなったり、スマホを親に見せたがらない場合も注意が必要です。
成績の急激な低下
心的負担が原因で、急に成績が下がることがあります。
ストレスや不安で集中できなくなり、授業中も周りの目が気になったり、休み時間のことが心配で勉強に集中できません。
とりわけ得意だった科目の成績低下や、グループ活動が多い授業での成績悪化が目立つ場合、クラスメイトと一緒に活動する場でいじめられているのが原因かもしれません。
宿題を出さなくなったり、テスト前に体調を崩したりするのもよくある兆候です。
成績が低下した場合でもただ叱るのではなく、いじめがあるかもしれないと考え、子どもが安心して話せる雰囲気を作ることが大切です。
持ち物の破損や紛失が増える
物をよく壊したり無くしたりするのもいじめの兆候の一つです。
ノートに落書きされたり、体操着や制服が汚されたり、文房具がなくなったり、ひどい場合は、スマホなどの高価な物が「なくなる」こともあります。
子どもは恥ずかしさや怖さから「自分で失くした」とウソをつくことがよくありますが、このような時は「どうして壊れたの?」と責めず、「何かあったら話してね」と優しく声をかけましょう。
容姿や身だしなみへの過度な気遣いや無頓着
見た目に対する態度が大きく変わることがあります。
見た目についていじめられると、その部分を極端に隠したり、逆に過剰に気にしたりします。
例えば、髪型や服装にこだわって長時間準備したり、特定の服だけを着たり、体型を隠すために変な服装をしたりしますが、これは「いじめられないように自分を守る」行動です。
反対に今まで身だしなみに気を使っていた生徒が急に無関心になる場合、自信を失って諦めたり、目立たないようにしたりする表れです。
特に女子中学生が化粧や髪型への態度を急に変えたら、いじめで自己イメージが傷ついているかもしれません。
感情の起伏の激しさ(イライラや無気力の交互)
怒りっぽくなったり、何も感じないような状態になったりを繰り返し、感情の波が激しくなります。
ストレスで小さなことにも過剰に反応し、家族に突然怒ったり、ちょっとしたことで泣いたりします。また、好きだったことにも興味がなくなり、やる気がなくなることもあります。
これはいじめのストレスから自分を守ろうとする反応で、思春期の体の変化も関係しています。
親は「単なる反抗期だ」と考えず、いつもと違う感情の変化が見られたら、いじめがあるかもしれないと考えて様子を見てください。
こうした状態が長く続くと、うつ病などの心の病気につながる可能性があるため、早めの対応が大切です。
保健室や遅刻の頻度が増加
保健室によく行ったり、学校に遅れて来たりすることがありますが、怠けているのではなく、いじめから身を守るための行動かもしれません。
朝のホームルームや休み時間など、いじめが起きやすい場面を避けようとしている可能性が高いです。
「頭が痛い」「お腹が痛い」と言って保健室に行くのは、心のストレスが起因となっていることもあります。
こうした行動が目立っていても「なぜ遅刻するの」と叱るのではなく、「学校で何か困っていることはない?」と優しく聞いて、安心して話せる環境を作ることが大切です。
学校行事や部活動への参加を避ける
前は楽しんでいた学校行事や部活動を急に避け始めます。
体育祭、文化祭、修学旅行などでは先生の目が行き届かず、いじめっ子と長く一緒にいなければならないため、「具合が悪い」「予定がある」などと言って参加しません。
部活動では、着替える場所やグラウンドなど大人が見ていない場所でいじめが起きやすく、特に団体スポーツでは仲間はずれにされたり、わざとぶつかられたりします。
親は「最近部活を休みがち」「行事に参加したがらない」という変化に気づいたら、いじめがあるかもしれないと考え、子どもの気持ちを尊重しながら、本当の理由をやさしく聞いてみることが大切です。
食欲不振や睡眠障害
ストレスから、好きだった食べ物に興味がなくなったり、極端に食べなくなったり、反対に食べ過ぎたりします。
睡眠では寝付きが悪くなる、夜中に目が覚める、悪夢を見る、いつも疲れているといった問題が出ます。
親は子どもの食事の変化や朝起きられない様子に気づいたら、単なる成長期だと決めつけず、いじめの可能性も考えて子どもをよく見守りましょう。
引きこもり傾向や家族とのコミュニケーション減少
家で過ごす時間が増え、家族との会話が減ります。
放課後すぐに自分の部屋に閉じこもり家族との食事や外出を避けますが、これは学校でのつらい経験から自分を守るための行動で、安全な自分の部屋で心を落ち着かせようとしています。
また、親に心配をかけたくないという気持ちから、「大丈夫」「何でもない」と表面的な返事をして本当の気持ちを話さなくなります。
親はいじめによる行動の可能性も踏まえ、無理に話を聞き出そうとせずに安心できる家庭環境を作ることが大切です。
不登校を防ぐために 親がいじめを察知したときの対処法

小学生への適切な声かけと対応
小学生は中学生と違って、自分の気持ちを上手に表現したり、整理したりする力が未成熟です。自分の思いを言葉にするのも難しいことがあります。
以下のような傾向を踏まえ、対処していきましょう。
親に頼る傾向が強い
小学生は問題があると大人の助けを求めることが多いので、親が受け入れる姿勢を見せることで子どもに安心感を与えられます。
周りの評価で自分の価値を決めがち
いじめられると「自分が悪いから」と思いやすく、親から「あなたは悪くないよ」とはっきり伝える必要があります。
自分で解決策を考えるのが難しい
いくつかの選択肢を示しながらも、最後は子ども自身に決めさせることで「自分でできた」という自信につながります。
子どもを安心させる言葉かけをする
・「いつでもあなたの味方だよ」と無条件に支えることを伝える
・「あなたは悪くないよ」と自信を持たせる言葉をかける
もしもいじめを訴えてきた場合
・担任の先生と早めに個別で話し合いの場を設ける
・学校のカウンセラーなど専門家に相談することも検討する
・必要なら学校を休ませて、心の健康を第一に考える
上記の対応をすみやかに行い、子どもの心理的なケアを優先的に行いましょう。
「学校に行くかどうかはあなた自身で決めていいよ」と子ども自身の判断を尊重する、クラス替えや転校など、いくつかの選択肢を一緒に考えるなど、子どもの気持ちを尊重する選択肢を示すことも大切です。
親が子どもの話を否定せず受け入れる姿勢を示した場合、いじめ解決率が約40%向上したという結果が出ています。
小学生は特に親の反応に敏感なため、感情的にならず冷静に対応することが重要です。
中学生特有の心理に配慮した接し方
思春期の中学生は自分の考えを確立する途中で、大人が口を出すことに敏感です。
この時期の子どもは、親から独立したいという気持ちと、頼りたいという気持ちの両方を持っています。
いじめられている場合は特に、「自分で問題を解決したい」と「誰かに助けてほしい」という相反する気持ちで悩みます。
むやみに親が介入すると、子どもの自信を傷つけ、より心を閉ざす原因になります。次のような接し方が効果的です。
距離感を尊重する
・無理に話を聞き出そうとせず、「話したいときはいつでも聞くよ」と伝える
・子どもの部屋という個人的な空間を尊重し、強引に引き出さない
間接的な会話方法を活用する
・SNSやメッセージなど、直接話すより楽な方法を提案する
・共通の趣味や活動を通じて自然に話せる機会を作る
自分で決める権利を大切にする
・「どうしたい?」と選択肢を与え、自分で決めることを尊重する
・親の考えを押し付けず、子どもの意見を最大限尊重する
SNSやオンラインでのいじめにも注意する
・直接話せないときは、スマホやパソコンの使い方に変化がないか気にかける
・オンラインでの友達関係を過度に心配せず、見守る姿勢を持つ
安心できる居場所を作る
いじめを把握したりその兆候を感じたら、問題を直接解決するよりもまずは子どもが安心できる家を作りましょう。
子どもを批判せず、そのままの姿を受け入れることが大切です。
また、フリースクールなど学校以外の選択肢も一緒に考えてみましょう。同じ悩みを持つ友達と出会える場所があれば、心的ストレスを抱えたまま毎日を過ごすよりも健康的です。
いじめが原因による不登校のサインについてのまとめ

ここまで小学生と中学生におけるいじめに起因する不登校のサインについて見てきました。
いじめは子どもが学校に行きたがらない大きな理由のひとつで、早く気づいて対応することが大切です。
子どもの行動や言葉遣いが急に変わる、学校へ行く前と帰ってきた後の様子が異なる、体調不良を訴えるなど、いじめを受けている兆候はさまざまです。
子どもの様子をよく観察して、毎日安心して過ごせる環境を作って行きましょう。












