成長段階にある小学生の子供は、何らかのタイミングで発達障害が出ることもあります。
発達障害は脳機能の発達に関係する障害であり、身体や学習、言語、行動などに偏りが出ます。
日常生活においても支障が出やすいため、早期発見によって改善策を見つけることが可能です。
しかし、小学生の子供を持つ方のなかには「どのように発達検査を受ければいいのかわからない」という悩みもあるでしょう。
当記事では、小学生の発達検査が相談できる機関や具体的な検査内容についてわかりやすく解説します。
発達検査の詳細を理解できるので、ぜひ参考にご覧ください。
小学生の発達検査について

発達検査とは、子供の発達状況を客観的に測定し、発達の遅れや特性(得意・苦手)を調べる測定です。
行動観察や言葉のやり取りなどを通して、運動や認知、言語、社会性などさまざまな領域の発達度合いを評価していきます。
発達検査にはいくつかの種類があり、子供の状況や年齢に合わせて検査方法を決定します。
検査結果から子供の発達の状況を理解できるため、対処方法を知りたいときに最適です。
注意点として、発達検査は発達障害の診断を下すための検査ではありません。
発達障害の診断には、発達検査以外にも、生育歴の聴取や医師による総合的な臨床診断の結果などから総合的に判断されます。
発達検査は、あくまで子供の発達に関する遅れや特性を調べる方法であると理解しておきましょう。
発達検査をおこなう目的
発達検査をおこなう目的は、子供の発達状況や特性を理解することです。
子供の発達状況や特性はそれぞれ異なるため、どのような支援や療育が必要なのかを理解するためにも発達検査が重要となります。
発達検査から子供の特性を理解できれば、学び方や支援方法、環境などに配慮できます。
発達状況は両親の目だけで判断することは難しいので、専門家に検査してもらうことで明確化できます。
検査結果を学校に情報共有すれば、関わり方に配慮してもらうことも可能です。
発達障害を早期発見することで、子供に合わせた支援や療育ができるようになります。
発達検査と知能検査の違い
発達検査と類似する検査として、知能検査があります。
発達検査と知能検査の主な違いは、調査領域や検査する年齢、検査結果の利用目的などです。
発達検査は運動や認知、言語、社会性など幅広い領域を検査するのに対し、知能検査はIQ(知能指数)や認知能力を評価します。
次に発達検査は乳幼児から大人まで幅広い年齢が対象ですが、知能検査は学齢期の子供が対象です。
最後に発達検査の結果は支援計画や療育に使われますが、知能検査は学習能力や特性を計測するために活用されます。
このように発達検査と知能検査には違いがあるため、何を調査するのかによって選択すべき調査方法が異なると理解しておきましょう。
小学生の発達検査の種類

小学生の発達検査にはさまざまな種類があり、それぞれ対象年齢や検査結果の表現方法が異なります。
事前に専門家から受けるべき発達検査を相談しておくことで、求める検査結果を理解できます。
基本的な発達検査の種類は、以下の4つです。
- WISC検査
- 新版K式発達検査
- 日本版デンバー式スクリーニング検査
- 乳幼児精神発達診断法(津守・稲毛式)
それぞれの詳細や特徴について説明するので、ぜひチェックしてください。
WISC検査
WISC検査は、5歳から16歳11ヶ月までの児童を対象とした知能検査です。
子供の知的能力を全体的に評価し、言語理解力、視空間能力、流動性推理力、ワーキングメモリ(短期記憶)、処理速度の5つの認知領域の特性を把握します。
子供の得意なことや苦手なことを明確化にし、発達の特性や困りごとの原因を解決するための支援・学習環境を考えるための情報を得ることが目的です。
検査結果はあくまでも現在の子供の姿を反映するものなので、発達障害かどうかわかるわけではありません。
子供の全体的な知的能力を理解するために、WISC検査がおこなわれます。
新版K式発達検査
新版K式発達検査は、0歳から成人までを対象とし、子供の姿勢・運動、認知・適応、言語・社会の3領域の能力を日常的なおもちゃや課題を用いて評価する心理検査です。
検査結果から発達年齢や発達指数(DQ)を算出し、子供の発達の全体像や各領域のばらつきを把握していきます。
検査方法には積み木など、普段の生活で使われるおもちゃや道具を用いて行われます。
新版K式発達検査は、子供の知的発達の問題を早期に発見することを目的とした検査です。
2012年にNPO法人アスペ・エルデの会がおこなった調査によると、乳幼児を対象とした検診をおこなう保健センターでは新版K式発達検査の利用が多いという結果が出ています。
参考ページ:厚生労働省 平成 24 年度障害者総合福祉推進事業 報告書 発達障害児者のアセスメントツールの効果的使用とその研修について
日本版デンバー式スクリーニング検査
日本版デンバー式スクリーニング検査は、アメリカのデンバー式発達スクリーニング検査(DDST)を日本の乳幼児向けに改訂・標準化した検査です。
デンバー式発達スクリーニング検査とは、生後16日から6歳までの乳幼児を対象に発達の遅れや偏りを早期発見し、必要な支援につなげることを目的とした検査です。
社会性、微細運動・適応、言語、粗大運動の4つの領域で評価し、同年齢の子供の90%ができる発達課題の目安を「90%発達月」として示します。
そして子供のできる・できないを客観的に評価し、発達段階を判定します。
検査方法は、保護者への問診を参考に子どもを観察しながら、日常で使う道具などを用いて評価する流れです。
乳幼児精神発達診断法(津守・稲毛式)
乳幼児精神発達診断法(津守・稲毛式)は、養育者が子供についての質問に答えて発達状況を調べる発達検査です。
子供の発達過程を運動、探索、社会、生活習慣、言語の5つの領域で診断します。
対象年齢は0~7歳ですが「1~12ヶ月」、「1~3歳」、「3~7歳」と子供の年齢によって質問項目が異なります。
質問項目は「できる」、「できたりできなかったりする、もしくはやったことがない」、「できない」の3つで評価する流れです。
5領域ごとに発達年齢が算出され、検査結果から検査項目と月年齢を軸にした発達プロフィールが作成されます。
発達プロフィールによって、それぞれの領域の点数をグラフ化して発達状態をチェックできます。
小学生の発達検査ができる機関

これから小学生の発達検査をしたいと考えている方のなかには「どこで受けられるのかわからない」という悩みもあるでしょう。
小学生の発達検査ができる機関として、以下のような3点が挙げられます。
- 医療機関
- 民間機関
- 公的機関
それでは詳しく解説します。
医療機関
医療機関では、小児科や児童精神科、発達外来などを取り扱う総合病院・専門クリニックで発達検査を受けられます。
医師から診断してもらうことができ、必要に応じて治療や医療的なサポートを受けることが可能です。
医療保険が適用される場合、費用をおさえられます。
ただし、多くの医療機関は予約が取りづらいため、数ヶ月ほど待ちになることも少なくはありません。
医療機関で子供の発達検査をおこなう場合、かかりつけの医者に相談して紹介状を書いてもらうようにしましょう。
民間機関
民間機関では、民間の発達支援センターや療育施設などで発達検査を受けられることがあります。
医療機関や公的機関よりも予約が取りやすいため、短期間のうちに子供の発達検査ができます。
また、子供の状況に合わせて、個別対応してもらうことができる点も特徴です。
ただし、医者が在籍していない民間機関では、医療的診断をおこなうことはできません。
さらに、費用も高額になりやすいので、予算が限られているのあれば別の機関をおすすめします。
機関によって予約状況や医者の有無は異なるため、気になるときは直接問い合わせするようにしましょう。
公的機関
公的機関では、児童相談所や発達障害支援センター、市区町村の福祉センターなどで発達検査を受けられることがあります。
費用が無料または低額なケースが多いため、予算が限られている方でも利用しやすいです。
ただし、該当機関に医師が在籍していなければ、医療的な診断をおこなうことはできません。
また、検査結果のフィードバックが簡易的なことが多いので、医療機関のように本格的な内容を受け取ることは難しです。
公的機関を利用するのであれば、住所近くの自治体の窓口で相談するようにしましょう。
小学生の発達検査の具体的な内容
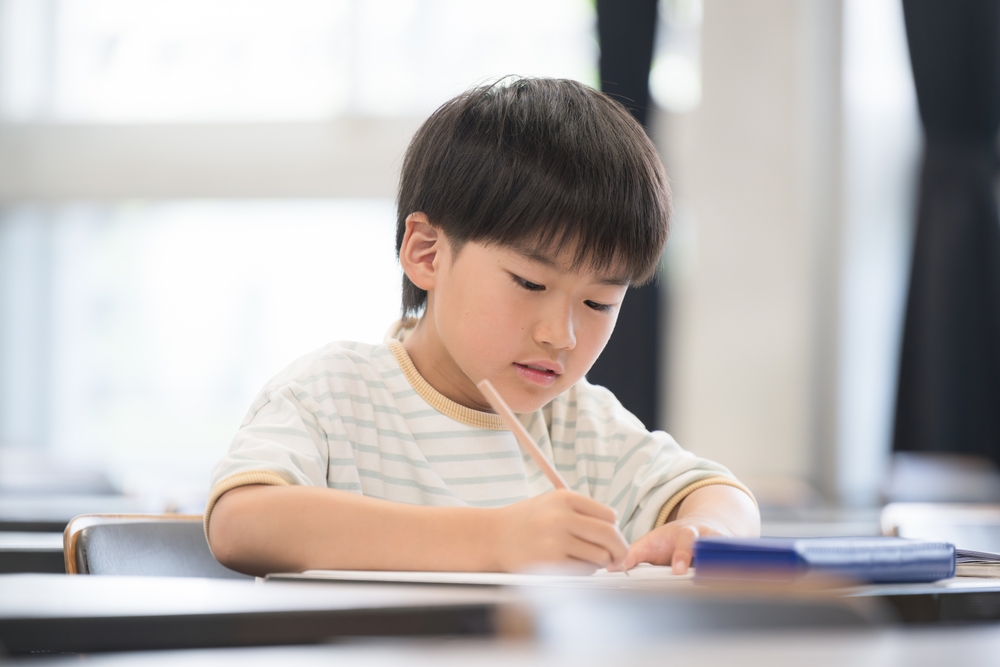
発達検査は、実施する施設や検査の種類のよって内容が異なります。
一般的な発達検査の内容は、以下の通りです。
- 認知・知能
- 言語
- 姿勢・運動
- 社会性
それでは詳しく説明します。
認知・知能
小学生の発達検査では、考える力や理解する力を確認します。
パズルや絵を使って形や数をどのように認識しているかを見たり、記憶力や集中力を試す課題をおこないます。
これにより学習に必要な基礎的な思考の土台や、問題解決の工夫の仕方を知ることができます。
【発達検査の内容】
- 絵や図形を使ってパズルを完成させる
- 似ているものを探す
- 短いお話を聞いて覚えているかを答えてもらう
- 数の問題を解いてもらう
言語
言語に関する発達検査では、言葉を理解し伝える力を確認します。
聞いた内容を理解して答える力、質問に自分の言葉で答える力などを調べます。
また、語彙の豊かさや会話の流れのつかみ方なども見られ、日常生活や学習でのコミュニケーションのしやすさを把握できます。
【発達検査の内容】
- 言葉を聞き取って意味を理解できるか調べる
- 絵を見て説明できるか調べる
- 質問に自分の言葉で答えられるか調べる
姿勢・運動
姿勢や運動の発達検査では、体の動かし方やバランス感覚を確認します。
机に座るときの姿勢を保てるか、手先を使った細かい動作ができるか、大きく体を動かして運動できるかを調べます。
これにより学習活動や生活動作をスムーズに行うための力を知ることができます。
【発達検査の内容】
- 机に向かって姿勢を保てるか調べる
- 鉛筆やはさみを正しく使えるか調べる
- ジャンプやバランスを取れるか調べる
社会性
社会性の発達検査では、友達や周囲との関わり方を見ます。
あいさつや会話の受け答え、集団でのふるまいなどを通して、人とどのようにやりとりするかを確認します。
協調性や思いやり、場の雰囲気を読む力なども把握でき、学校生活の適応に役立てられます。
【発達検査の内容】
- あいさつや会話の受け答えができるか調べる
- 協力して取り組めるか調べる
小学生の発達検査の費用

小学生の発達検査を受ける場合、利用する機関によって費用は大きく異なります。
一般的な発達検査の費用相場は、1.5万円〜4万円程度です。
各機関の相場については、下記項目を参考にしてください。
- 医療機関:5,000円〜2万円(保険適用の場合)
- 民間機関:3万円〜4万円程度
- 公的機関:無料〜1万円程度
健康保険が適用されるかどうかは、事前にチェックしておくようにしましょう。
小学生の発達検査を活用する方法

小学生の発達検査を活用するには、以下のような方法があります。
- 専門家に相談する
- 定期的に状況を検査する
- 発達支援を活用する
- 子供が得意とすることを把握する
それでは詳しく説明します。
専門家に相談する
発達検査の内容をもとに、専門家に相談することで具体的な支援方針を立てられるようになります。
検査から子供の強みや特性を把握できるため、専門家に的確な情報共有が可能です。
どのように対処すればいいのかアドバイスを受けることもできるので、発達検査の内容を専門家に伝えるようにしましょう。
定期的に状況を検査する
子供の状況は日々変化するため、定期的に状況を検査することが大切です。
発達検査を定期的におこなうことで、支援方針の見直しができます。
そのため子供の成長具合に合わせて、定期的に発達検査から状況を検査するようにしましょう。
発達支援を活用する
子供の発達検査の内容をもとに、発達支援を活用するようにしましょう。
学校や療育施設・医師などに検査結果を共有すれば、環境の応じた支援計画を立てられます。
家庭内の支援方法をについてもアドバイスを受けられるため、発達支援をうまく活用するようにしましょう。
【まとめ】気になることがあったら発達検査を受けて支援対策を立てましょう
今回は、小学生の発達検査が相談できる機関や具体的な検査内容についてわかりやすく解説しました。
発達障害はいつ露見するかわからないので、少しでも違和感があるなら発達検査をおすすめします。
発達検査によって発達の遅れや特性(得意・苦手)を調べられるため、具体的な支援対策を立てられるようになります。
ぜひ当記事で紹介した機関を参考にしながら、子供の発達検査をおこなって早期発見へとつなげましょう。














