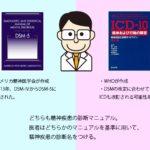「家では普通に話せるのに、学校では一言も話さない」「知らない人の前で話せなくなってしまう」—そんな子どもの様子に心当たりはありませんか?
このような状況が長期間続く場合、それは場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)と呼ばれる状態かもしれません。単なる「人見知り」や「恥ずかしがり」ではなく、本人の中で強い緊張や不安が生じて声を出せなくなっている状態です。
この記事では、場面緘黙症とは何か?その原因や種類、子どもと大人の場面緘黙症の違いを解説。発達障害との関係と支援の方法についても、わかりやすくお伝えします。
場面緘黙症とは?

場面緘黙症(Selective Mutism)は、特定の場所や人の前でだけ話せなくなる不安症の一種です。家では家族と普通に会話ができるのに、学校や職場など「特定の場面」では話せなくなるという特徴があります。
これは本人の意志で「話さない」と決めているのではなく、話したくても話せないという心の状態です。多くの場合、声を出そうとすると強い緊張や恐怖が生じ、喉が詰まったようになってしまいます。
精神障害の診断基準による定義
米国精神医学会(APA) が定めた「精神障害の診断と統計の手引き (DSM)の2013年改訂版 (DSM-5) の診断基準によれば、場面緘黙症は「社会的状況において一貫して話すことができない不安障害」とされています。
以下の条件を満たすと、「場面緘黙症」と診断されます。
- 家庭では話すが、学校や社会的場面では話せない。
- この状態が少なくとも1か月以上続いている。
- 言語能力や理解力に問題はない。
- 不安や恐怖が主な原因であり、他の障害では説明できない。
子どもに場面緘黙症が多く見られる理由
場面緘黙症は、主に幼児期から小学生の間に発症することが多いです。
初めて保育園や学校などの社会的な環境に出たとき、緊張や不安を強く感じることがきっかけになることがあります。
子どもに見られる特徴
場面緘黙症の子どもによく見られる特徴には次のようなものがあります。
- 家ではおしゃべりだが、学校では完全に無言。
- 先生に呼ばれても声が出ず、首を縦に振るだけ。
- 友達に話しかけられても表情が固まり、身動きが取れなくなる。
- 筆談やジェスチャーならできることもある。
多くの子どもは「話したいのに話せない」ことに苦しんでおり、本人もその状況を理解しています。そのため、無理に「話しなさい」「なんで喋らないの?」と言うと、プレッシャーでさらに悪化することもあります。
場面緘黙症の原因とは?

場面緘黙症の原因は一つではなく、心理的要因・性格傾向・環境要因・発達的要因などが複雑に関係しています。以下にその原因をわかりやすく整理します。
不安や恐怖による心理的要因
場面緘黙症の多くは、社会不安障害(社交不安症)と深く関連しています。
人から見られる・評価される場面で強い緊張を感じるタイプの子どもは、声を出すこと自体が「怖い」と感じてしまうのです。
たとえば、次のような不安が頭の中に広がり、話せなくなってしまいます。
- 「声を出したら笑われるかも」
- 「間違ったらどうしよう」
- 「注目されるのが怖い」
性格的な特徴
場面緘黙症の子どもは、一般的に「内向的」「慎重」「感受性が強い」「完璧主義」といった傾向があります。こうした性格は悪いことではありませんが、環境の変化やストレスに過敏に反応してしまうことがあります。
家庭や環境の影響
親が過度に心配性だったり、厳しい環境だったりすると、子どもが「失敗できない」と感じて緊張しやすくなることがあります。
また、転校や引っ越しなどの環境変化も発症のきっかけになることがあります。
発達障害との関連
場面緘黙症は、発達障害(特に自閉スペクトラム症:ASDや注意欠如多動症:ADHD)と併存するケースもあります。
自閉スペクトラム症の子どもは、コミュニケーションが苦手だったり、感覚過敏があったりするため、社会的な場面で強い不安を感じやすい傾向があります。
発達障害を併せ持つ場合、話さない理由は「不安」だけではなく、「状況の理解の難しさ」や「相手の感情が読み取りにくい」といった要素も関係してきます。
場面緘黙症の種類
場面緘黙症にもいくつかの種類があります。症状の現れ方や強度によって、支援の方法も異なりますので、主な種類を紹介します。
完全緘黙タイプ
学校や公共の場など、特定の環境では一言も話せないタイプです。
声を出すどころか、表情が硬くなり、体も動かなくなることがあります。
限定緘黙タイプ
一部の人や場面では話せるが、それ以外では話せないタイプ。
たとえば「先生とは話せるが友達とは話せない」「1対1なら話せるが集団では話せない」といったケースがあります。
非言語的コミュニケーション型
声は出せないものの、ジェスチャーや筆談、LINEなどの文字コミュニケーションなら可能なタイプ。
この場合、本人は「自分なりの伝え方」を見つけていることが多いです。
成人型
子どものころに発症し、大人になっても症状が残るタイプです。
社会生活に支障が出やすく、職場や恋愛、電話対応などで困難を感じることがあります。
大人の場面緘黙症とは?

場面緘黙症は子どもだけの問題ではありません。成長とともに改善する人もいますが、大人になっても話せない状況が続く人も少なくありません。
大人の場面緘黙症の特徴
大人の場面緘黙症には、次のような特徴があります。
- 会議や初対面の場で声が出ない
- 電話や店員との会話に強い緊張を感じる
- 「話さなきゃ」と思うほど体が固まる
- 職場では無口でも、家では普通に話せる
このような場合、「社会不安障害」や「場面緘黙症の残存型」として理解されます。
大人になると、周囲が「恥ずかしがり屋」「コミュニケーションが苦手」と誤解することが多く、本人が支援を受けにくい状況になってしまっていることがあります。
大人への支援
大人の場面緘黙症の支援方法には、次のようなものが有効です。
- 無理に発言を促さない
- メールやチャットなど、別の表現手段を尊重する
- 安心できる人間関係を少しずつ広げる
- 専門家によるカウンセリングや認知行動療法を活用する
場面緘黙症の支援や対処法

場面緘黙症は「治す」よりも、「少しずつ話せる場面を増やしていく」アプローチが大切です。
以下に効果的な支援法を紹介します。
安心できる環境をつくる
まずは「話さなくても大丈夫」という安全な環境づくりが第一歩です。
無理に話させようとせず、「うなずき」「指差し」「筆談」など、話す以外の方法でもOKと伝えましょう。
小さな成功体験を積む
「先生と挨拶できた」「友達に手を振れた」など、どんなに小さなことでも褒めることが大切です。成功体験を重ねることで、少しずつ「話しても大丈夫」という安心感が育ちます。
段階的なステップ
いきなり人前で話すのではなく、
「家で練習 → 録音して聞く → 録音を先生に聞かせる → 小声で話す → 普通の声で話す」
といった段階的なステップを踏むことで、徐々に慣れていくことができます。
専門家の支援を受ける
心理士や発達支援センター、児童精神科などで相談するのもおすすめです。
必要に応じて、認知行動療法(CBT)や遊戯療法などを通じて、不安の軽減を目指します。
子どもの場面緘黙症で悩んだときは、地域の保健センター、発達支援センター、学校のスクールカウンセラーなど相談できる機関があります。
ステラ幼児教室・個別支援塾では、一人ひとりの特性に合わせた個別指導で、子どもの成長をサポートします。
お気軽にご相談ください。
発達障害が併存するときの支援ポイント

発達障害(特にASD)を併せ持つ場合、コミュニケーションそのものへの理解支援が重要になります。
たとえば、次のようなポイントに留意して支援していきます。
- 構造化された環境(スケジュールで見通しを持たせる、落ち着ける場所を作るなど)
- 視覚支援(カードや絵で状況を理解しやすくする、困ったときにヘルプカードを出すなど)
- 感覚過敏への配慮(人混みや騒音を避ける、イヤマフを使用するなど)
発達障害の特性を理解しながら支援することで、本人が「安心して声を出せる環境」を整えることができます。
場面緘黙症のまとめ
場面緘黙症は、決して「甘え」や「怠け」ではありません。本人は「話したいのに話せない」苦しさを抱えています。
重要なのは、焦らず、理解し、見守ることです。少しずつ安心できる環境と信頼関係を築いていくことで、子どもも大人も「話す力」を取り戻していけます。
周囲が「どうして話さないの?」ではなく「どうしたら安心して話せるかな?」という視点に立つことが、回復への第一歩なのです。
子どもの発達障害や場面緘黙症で悩んだときは、ステラ幼児教室・個別支援塾にご相談ください。
ステラ幼児教室・個別支援塾では、一人ひとりの特性に合わせた個別指導で、子どもの成長をサポートします。
ステラ幼児教室・個別支援塾は生徒募集中
ステラ幼児教室・個別支援では随時生徒を募集しています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。
お気軽にご相談ください。