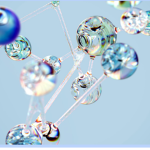「ADHDの診断を受けたけれど、障害者手帳の対象になる?」「手帳を取得するとどんな支援が受けられるの?」と悩む方は少なくありません。
特に、就労や日常生活に困りごとを抱えている方にとって、障害者手帳の取得が自分や家族にとってどんな意味を持つのかを知ることは大切なことです。
そこで本記事では、ADHDと障害者手帳との関係性や、もらえる場合・もらえない場合の具体例、受けられる支援内容についてわかりやすく解説します。
ADHDと障害者手帳の関係とは?
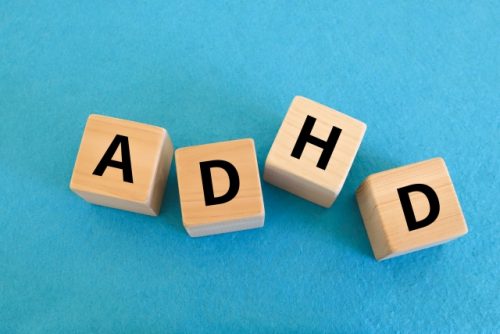
「ADHDは障害者手帳の対象になるの?」ということは、多くの当事者や保護者が気になる疑問だと思います。
ADHDは発達障害のひとつであり、生活への影響の度合いによっては、手帳の対象とされることがあります。
ただし、全員が取得できるわけではないため、制度の仕組みや基準を正しく理解しておくことが重要です。
そこで本項では、ADHDがどのような条件で手帳の対象となるのか、その背景や関連する制度について解説します。
ADHDは障害者手帳の対象になるの?
ADHD(注意欠如・多動症)は、症状の程度によっては障害者手帳の対象となります。
特に日常生活や社会生活に支障が出ている場合、「精神障害者保健福祉手帳」の対象になることが多いです。
子どもの場合や知的障害を伴う場合は「療育手帳」が交付されることもあります。
ただし、ADHDの診断があっても、すべての人が手帳を取得できるわけではなく、本人やご家族の困りごとや生活への影響度が大きな判断材料になります。
申請を希望する場合は、まずは主治医や自治体の相談窓口で丁寧に状況を説明することが第一歩です。
障害者手帳の種類(精神・療育・身体)とADHDの位置づけ
まず障害者手帳には、以下の3種類があります。
身体障害者手帳:視覚・聴覚・肢体などの身体的な障害が対象
療育手帳:知的障害が対象(自治体によって名称が異なる場合も)
精神障害者保健福祉手帳:統合失調症、うつ病、ADHDなど精神障害が対象
ADHDは、知的障害がなければ「精神障害者保健福祉手帳」の対象になることが多く、就学や就労、生活上の支援が必要と認められた場合に申請されます。
手帳の等級(1〜3級)は、日常生活への支障の程度によって判断されます。
診断名だけで判断されるものではなく、「どれくらい困りごとがあるかがポイント」になります。
精神障害者保健福祉手帳で支援を受けられることが多い理由
ADHDの方が障害者手帳を取得する際に、もっとも利用されるのが「精神障害者保健福祉手帳」です。
これは、ADHDが精神疾患としての診断分類に含まれているためであり、日常生活や社会生活に支障がある場合、3級から1級までの等級が認定されることがあります。
この手帳を持つことで、以下のような支援が受けられます。
●医療費の助成(自治体により異なる)
●就労支援や障害者雇用枠での応募
●公共料金の割引や税制優遇
●福祉サービスや支援機関との連携がスムーズになる
障害者手帳は、生活のしづらさに直面している方にとって、大きなサポートとなる可能性があります。ただし、手帳の取得は本人の自由であり、必要性を感じたときに選択するものであるというのも大切な視点です。
ADHDで障害者手帳がもらえるケースとは?

「具体的にどんな状態だと手帳がもらえるのか知りたい」そう疑問がでてくるはずです。
障害者手帳の取得は、支援につながる一歩でもありますが、対象となるかどうかは個々の状況により異なります。
ここでは、ADHDで障害者手帳を取得できる主なケースや診断書に記載されるポイント、等級の判断基準などについて解説していきます。
もらえる可能性があるADHDの具体例
ADHDと診断されても、障害者手帳がもらえるかは「日常生活や社会生活にどれくらい支障があるか」が重要な判断基準です。
たとえば…
●学校や職場で集中できず忘れ物・ミスが頻発
●感情が安定せず家庭内でのトラブルが多い
●自立した生活が難しく援助が欠かせない
こうした状態が「長期的に続いている」ことが条件のひとつで、初診から6ヶ月以上経過している必要もあります。
ADHDでも「困りごとが生活に強く出ている」場合、申請できる可能性があるため、まずは主治医や自治体に相談して判断を仰ぐのが安心です。
診断書に記載されるポイント
精神障害者保健福祉手帳の申請には、指定医による診断書が必須です。
この診断書には以下の内容が求められます。
●日常生活や社会生活への具体的な困りごと
●診断名(ADHD)と症状が長期にわたって継続していること
●初診日や治療経過の記録
●生活にどの程度支障があるかの具体的な記述
簡潔な内容よりも「困っている状況」が読み手に伝わることが重要です。
また、診断書は申請から3か月以内のもの※が必要なため、申請タイミングなどの調整も大切です。
※自治体によって異なる
障害者手帳の等級の目安(1級~3級)とその判断基準
精神障害者保健福祉手帳には1級〜3級の等級(1級が最も重い)があり、ADHDの特性による支障の程度に応じて判定されます。
1級:日常生活を営むのが困難で、常時援助を必要とする状態
2級:日常生活に著しい制限があり、支援が必要な状態
3級:日常生活または社会生活に制限があり、支援があると望ましい状態
ADHDの影響が「支援なしでは不安定である」「制限がある」と判断される場合に等級が与えられます。
申請から交付までの流れと必要書類
ADHDで手帳取得を検討される方のために、申請の流れと必要書類を整理します。
申請の一般的な流れ
医師の診断書や意見書を取得します。
↓
必要書類を準備します。
↓
市区町村の窓口で申請手続きを行います。
↓
審査を経て、手帳が交付されます。
必要な書類
●医師の診断書や意見書
●申請書
●写真(規定サイズ)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●印鑑(必要な場合)
なお、役所の対応によって提供形式や申請方法・審査所要期間は異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
障害者手帳がもらえないケースや注意点とは?
「診断があっても手帳がもらえないことってあるの?」という不安を抱える方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、症状が軽度と判断されたり、必要な書類が不十分であったりといった理由で、交付に至らないケースもあります。
また、制度の誤解や申請時の落とし穴により、申請自体が進まない場合もあるでしょう。
そこで本項では、手帳がもらえない代表的なケースや、知っておきたい注意点、「グレーゾーン」と言われたときの選択肢についても説明していきます。
ADHDの診断があっても「障害者手帳対象外」とされる例
ADHDと診断されていても、精神障害者保健福祉手帳が取得できないケースもあります。主な理由は以下の通りです。
・確定診断が出ていない(グレーゾーン)
医師による診断を受けていない、あるいは診断基準を満たさない状態では、手帳の交付対象にはなりません。
・初診から6ヶ月経過していない
障害が「長期にわたる」状態であることが求められており、初診日から6ヶ月以上が経過していない場合は申請できません。
こうした場合は、落ち着いて診断や生活の変化について主治医と相談を続けるのが安心です。
誤解されがちな申請の落とし穴
障害者手帳の申請時、以下のような誤解や落とし穴に陥りがちです。
・診断名があれば必ず取れると思っていた
実際には、生活上の「困難さ」が重視され、診断名だけでは不十分なケースもあります。
・初診からすぐに申請できると思っていた
前述の通り、初診から6ヶ月が経過していないと申請できません。
・グレーゾーンでも手帳がもらえると思っていた
“傾向があるだけ”の場合は診断要件を満たさず、申請対象にはなりません。
これらは申請前にしっかり確認することが重要です。
「グレーゾーン」と判断されたときの選択肢
「ADHDのグレーゾーン」と診断された場合でも、支援がまったく得られないわけではありません。
・他の障害(例:適応障害やうつ病)の診断がつくと対象に
ADHDの特性の結果として二次的な精神障害が診断されれば、手帳取得の可能性が出てくる場合があります。
・障害者手帳がなくても利用できる支援サービス
児童発達支援、自立訓練(生活訓練)、就労支援など、手帳なしで使える制度も多く、困りごとを補える場所があります。
・セカンドオピニオンの活用
診断に納得できない場合は、別の医師や医療機関に相談することもおすすめです。
手帳が取得できなくても、困りごとに合った支援を受ける選択肢は多くあります。
障害者手帳を取得するメリットと活用例
ADHDなどの診断を受けた際、障害者手帳を取得することで日常生活の中でさまざまな支援が受けられるようになります。たとえば、以下のようなメリットがあります。
●医療費の助成(通院・入院費の軽減など)
●就労支援の利用(ハローワークでの職業相談、就労移行支援など)
●税制優遇・公共料金の割引(住民税やNHK受信料の減免など)
●障害者雇用枠での働き方の選択肢(配慮ある職場での就労)
また、手帳を所持していると、相談支援事業所など福祉サービスへのアクセスがしやすくなるのも大きな利点です。ただし、手帳の提示は義務ではなく、必要な場面のみで構いません。
制度の詳細や利用できるサービスは、お住まいの自治体によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
障害者手帳の取得を検討する際の相談先・サポート機関
ADHDの診断を受け、「障害者手帳を取得すべきか迷っている」というときは、一人で悩まず専門の相談機関を活用することが大切です。
以下のような場所で、申請の可否や手続き方法、生活支援についてのアドバイスを受けることができます。
市区町村の福祉窓口(障害福祉課など)
手帳の申請手続きや支援制度の利用について、最初に相談する窓口です。
精神科や発達障害を専門とする医療機関
診断書の発行や、手帳取得の適否についての医学的判断を受けられます。
地域の相談支援事業所・発達障害者支援センター
具体的な支援についての情報提供や、サービスの計画作成をしてもらえます。
申請を急ぐ前に、こうした機関でじっくり話を聞いてもらうことで、自分にとって本当に必要な支援を見つける一歩になります。
まとめ:ADHDは、症状や生活への影響の度合いによって、精神障害者手帳の対象になることがある
ADHDの診断を受けた方やその保護者の中には、「障害者手帳がもらえるのか」「取得するメリットはあるのか」と悩む方も多いでしょう。ADHDは、症状の程度や生活への影響によっては「精神障害者保健福祉手帳」の対象となることがあります。
ただし、診断名だけで取得できるわけではなく、日常生活や社会生活にどの程度支障があるかが大きな判断基準です。実際には、診断書の記載内容や初診からの経過期間、生活上の困りごとなどが審査のポイントとなります。
一方で、症状が軽度な場合や診断が曖昧な「グレーゾーン」では交付されないこともあります。障害者手帳を取得することで、医療費助成や就労支援、税制優遇などの公的支援を受けることができますが、必ずしも全員が取得すべきというものではありません。
取得を検討する際には、医療機関や福祉窓口、支援センターなど専門機関への相談が重要です。
参考元
各 支援機関 等