「うちの子どもはどうしてじっとしていられないんだろう?」「注意してもすぐ忘れてしまうのは性格なの…?」そんな日々の疑問や不安を抱えていませんか?
ADHD(注意欠如・多動症)は、子どもの落ち着きのなさや注意力のばらつきなどの特徴が見られる発達特性のひとつです。ですが、その行動を見てすぐに「発達障害かも」と決めつけるのは難しく、多くの保護者が「様子を見ていいのか、相談すべきか」と迷いを抱えます。
そこで本記事では、ADHDの基礎知識をはじめ、ご家庭で気づきやすい15のチェック項目、チェック後の対応の考え方までご紹介していきます。
子どものADHDとは?まず知っておきたい基礎知識
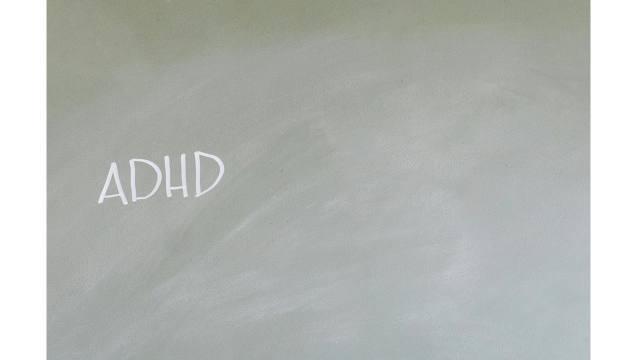
「ADHDって聞いたことはあるけど、具体的にはどんなこと?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
子どもが落ち着かない、話を聞いていないように見える…そんな様子が続くと、性格や育て方のせいだと感じてしまうこともあるでしょう。しかし、ADHDは生まれつきの脳の特性によって注意力や衝動のコントロールが難しくなる発達障害の一種です。
まずここでは、ADHDの基本的なことを正しく理解できるように、特性やどんな子どもに多く見られるか?などについて解説していきます。
ADHDとはどんな特性?
※ADHDとは、注意欠如や多動症などとも呼ばれ、年齢や発達段階に不釣り合いな「注意力の欠如」「多動性」「衝動性」を主な特徴とする発達障害の一種です。
たとえば「注意がそれやすい」「じっとしていられない」「思ったことをすぐに行動に移してしまう」などの傾向が見られる状態です。大きく分けて以下の3つのタイプがあります。
●不注意が目立つタイプ
●多動性・衝動性が目立つタイプ
●両方の特徴が混ざった混合タイプ
これらの行動は「しつけの問題」と誤解されることもありますが、脳の機能的な違いによる特性です。まずは「わざとやっているのではない」という視点を持つことが、子どもへの理解の第一歩になります。
ADHDはどんな子どもに多く見られるの?
ADHDは、おおよそ学童期の子どもの3〜7%に見られるとされており、男女比では3.5%ほど男児に多い傾向があります。※以下のような行動が日常的に見られる場合、ADHDの可能性があると言われています。
●授業中に立って歩いてしまう
●友だちの話に割り込んでしまう
●宿題や忘れ物が多い
●注意されても同じミスを繰り返す
ただし、これらはどの子どもにも一時的に見られることもあります。継続的に困りごとが続くか、日常生活に影響があるかがひとつの目安です。
※参考元:NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease07.html
ADHDが発達の個人差との見分けが難しい理由
子どもの発達には大きな個人差があり、「落ち着きがない」「話を聞かない」といった行動も、年齢的な成長過程でよくある姿です。そのため、「単なる性格なのか」「ADHDの特性なのか」の見極めは非常に難しいものです。
特に、未就学児や低学年では、自己コントロールの力がまだ発達していないため、一時的に多動的な行動が目立つこともあります。ご家庭や園・学校など複数の場面で行動の偏りが見られる場合や、本人が困っている様子が続いているときには、早めに相談窓口や小児科で話を聞いてもらうのも安心です。
ADHDかも?ご家庭で気づくためのチェックリスト15項目
「病院に行くほどではないかもしれないけど気になる…」そんなとき、ご家庭でも意識して確認できるチェックリストは、子どもの行動を見つめ直す良い手がかりになります。
ADHDは、目に見えにくい脳の特性のため、周囲の理解や支援がないと「だらしない」「わがまま」と誤解されてしまうこともあるため、気づきやサポートが必要です。
ご家庭での小さな気づきを大切にするために、ここでは保護者の方が日常の中で確認しやすい15のチェックポイントを項目ごとに簡単にご紹介していきます。
落ち着きがなく、じっとしていられない
歩き回ったり、貧乏ゆすりのように体を動かしてしまい、椅子に長く座っていることが苦手です。興味のあることには集中できる一方で、長時間静かにするのは難しい傾向があります。
順番を待つのが苦手で割り込みが多い
行列や会話の順番を待てず、先に行動してしまうなど、衝動的な行動が見られます。「早くやりたい」という気持ちが強く、どうしても我慢が続かない傾向があります。
忘れ物や失くし物がとても多い
鍵や学用品、宿題などを頻繁に失くしたり、忘れたりすることが長期間続く場合、それは注意が散漫になっているサインかもしれません。単なるうっかりミスとは異なり、特性に基づく傾向です。
話しかけても聞いていないように見える
呼びかけに対して反応が鈍かったり、理解していないように見えることも頻繁にあります。「聞いてる?」と何度か声をかけたくなることも多いでしょう。
気が散りやすく、すぐに注意がそれる
テレビの音や周りの音など、外部刺激に自分の注意がふらふらと移ってしまい、集中が続かない様子が見られるときも、ADHDの可能性としてのひとつの特徴になります。
指示を聞いても最後までやりとげられない
「やる」と言ったものの、途中で違うことを始めてしまい取り組み切れない、という場面がよくある場合は、注意がそらされやすい特性が現れていることがあります。
話を最後まで聞かずに遮ることが多い
話の途中で「それそれ!」と話に割り込んでしまうことが頻繁にあるなら、聞くより話したくなる衝動性が関係しているかもしれません。
おしゃべりが止まらず、よく話しすぎる
つい多く話してしまい、その場の空気やタイミングに関係なく会話を続けてしまう傾向があります。本人は気づかず、周囲が困惑することもあるかもしれません。
感情の切り替えが苦手で癇癪を起こしやすい
ちょっとのことで泣きわめく、切り替えが難しくすぐ癇癪になるなど、感情を抑えることが難しい場面が多い傾向にあります。
ケアレスミスやうっかりミスが頻繁に起きる
簡単な計算ミスや見落とし、同じミスの繰り返しが頻繁に続く場合、それはできないのではなく、意識しても“見逃してしまう”という特性が背景にあることもあります。
急な行動や思いつきの行動が多い
考える前に行動してしまいがちで、衝動的に飛び出したり、新しいことにすぐ手を出したりする様子は、ADHDの衝動性の特徴のひとつです。
\
友だちとよくトラブルになってしまう
順番を守れなかったり、会話に割り込んでしまったりすることが、友だちとの関係に影響している場面もあります。本人も戸惑っていることが多いです。
時間や約束を守るのが苦手
「あと5分で行こうね」と約束してもなかなか守れないことが続くなど、時間の感覚がうまく持てず、予定がずれやすい傾向があります。
刺激に対する感覚が過敏
音や光、触感に敏感で、たとえば洋服のタグが気になって落ち着かなかったり、大きな音に強く反応することがあります。
「できる時」と「できない時」の差が激しい
同じことでも、できる日もあれば急にできなくなる日もあり、そのムラがADHDの“波”を反映している場合があります。変動が激しいことも特性のひとつです。
ADHDのチェックが多く当てはまったら?どう対応すればいい?
「いくつも当てはまっているけど、すぐに病院に行くべき?」と不安になる方もいるかもしれません。ですが、まず大切なのは「慌てずに、相談できる場所を知ること」です。
子どもの発達には個人差があり、特性と個性の境目はとてもわかりづらいものです。
そこで本項では、診断を急ぐのではなく“相談から始める”という視点で、相談先の選び方や、ADHDと向き合う際の心構えについて解説していきます。
すぐ診断というよりもまずは相談
チェック項目に多く当てはまると「診断しなきゃ…」と焦ることもありますが、まずは“相談”から始めるのがおすすめです。
各地域の発達支援センターや保健師・市区町村の相談窓口では、気になる行動について専門家と気軽に話すことができます。診断はそれから、という選択も十分有効です。相談は「誰かと話すことで気持ちが軽くなる」素晴らしい一歩になります。正しい情報や支援につながるだけでなく、家庭での対応も前向きに進みやすくなります。
相談先の種類と選び方
相談窓口にはさまざまな選択肢があります。それぞれ特徴を理解したうえで、自分や子どもに合った場所を選びましょう。
市区町村の相談窓口
子育て支援課や障害福祉課などで、子どもの発達についての相談や情報提供を受けられます。
児童相談所
子育てや子どもの発達について専門的な相談を受けられ、必要に応じて発達検査などが受けられます。
発達支援の事業所
児童発達支援、放課後等デイサービスがあり、子どもに合わせた療育プログラムを受けられます。
[参考]療育(発達支援)とは?意味や内容、受けられる施設をわかりやすく説明
小児科・発達外来(病院)
診断や医療的な検査、投薬などが必要な場合に相談するとよいでしょう。
発達障害者支援センター
発達障害についての相談や情報提供などが受けられます。
まずは地域の相談窓口に連絡し、「次のステップ」でどこに繋がれば安心かを一緒に考えてもらいましょう。
子どものADHDと向き合う時のヒント
ADHDの特性をもつお子さんとの日々は、安全や成長の安心のために、いくつかのヒントが役立ちます。
・視覚による伝え方を意識する
言葉だけよりも、絵カードやタイマー、スケジュール表など“目で見て確認できる”工夫が効果的。
・小さな成功体験を大切にする
「できたね」と素直に褒めてあげることで自己肯定感が育ちます。
・環境調整を試す
気が散る要因を少なくしたり、静かなスペースで宿題をするなど、環境を整えてあげましょう。
・合っているやり方を一緒に探す
学習スタイルや遊び方など得意な方法を共有して、本人が自信を持てる支援を探すことも大切です。
子どもの小さな変化を認めて、一緒に前へ進む関わりが“育ちの支え”になります。
まとめ:ADHDかも?気になるときはまず相談を。
ADHDは「注意の持続が難しい」「落ち着きがない」「衝動的に行動してしまう」といった特性をもつ発達障害のひとつで、子どもにしばしば見られます。
ただし、このような行動は成長過程でも見られることがあるため、特性か個性かの見分けがつきにくいのが現状です。
そこで、ご家庭の気づきになりやすいように特性のチェックリストを理解することで、困りごとの傾向を把握する手がかりになります。チェックに当てはまる項目が多くても、すぐに診断を急ぐのではなく、まずは地域の発達支援窓口や医療機関などで相談することが大切です。
また、ADHDのある子どもと接する際には、視覚的に伝える・環境を整える・成功体験を増やすなど、特性に合った関わり方が効果的です。
大人が子どもの特性を理解し、無理なく対応していくことが、子ども自身の安心や自信につながります。
参考元
NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease07.html
各 支援機関 等















