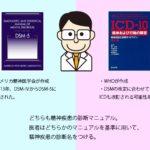ADHDとASDの違いとは

落ち着きがなく、いつも動き回っているのはADHDだからだろうか」 「こだわりが強く、友達とうまく遊べないのはASDかもしれない」
子育てをする中で、わが子の成長や行動に違和感を覚えたとき、インターネットや育児書で調べて「ADHD(注意欠如多動症)」や「ASD(自閉スペクトラム症)」という言葉に行き着く保護者の方は少なくありません。
これらはどちらも生まれつきの脳の特性による発達障害の一種です。 一見すると、集団行動ができない、癇癪を起こしやすいなどの、似たような困りごととして現れることがあります。そのため、専門家でも短時間の観察だけでは見分けがつきにくいことさえあり、混同しやすいのが実情です。
しかし、その行動を引き起こしている背景や、本人の感じ方には明確な違いがあります。この違いを理解することは、その子に合った適切なサポートをするための第一歩となります。
この記事では、ADHDとASDそれぞれの基本的な特徴と、両者の決定的な違いについて詳しく解説します。また、両方の特性をあわせ持つ併発(混合型)の可能性や、診断を受けるまでの流れ、近年注目されている大人のケースについても触れていきます。
不注意や多動性が目立つADHDの特徴

ADHDは、日本語で注意欠如多動症と呼ばれます。 脳の前頭葉と呼ばれる部分の働きに関連があると考えられており、自分をコントロールする力(実行機能)がうまく働かないために、年齢に見合わない不注意、多動性、衝動性といった特性が現れます。
不注意の特徴とは
集中力が続かず、気が散りやすい特性です。好きなことには過集中する一方で、興味のない課題には取り組むのが極端に難しいという側面もあります。
・忘れ物や失くし物が非常に多い
傘や水筒を頻繁になくす、宿題を持ったのに提出し忘れる。
・話を聞いていないように見える
話しかけられても上の空で、返事をしても内容を覚えていない。
・気が散りやすい
宿題の途中で目に入った漫画を読み始めてしまい、元の作業に戻れない。
・整理整頓が苦手
机の中や部屋がいつもぐちゃぐちゃで、必要なものがすぐに見つからない。
・順序立てて行動できない
着替えて、歯を磨いてから、カバンを持つといった一連の動作をスムーズに行えず、途中で別のことを始めてしまう。
多動性や衝動性の特徴とは
じっとしていることが苦手で、身体が勝手に動いてしまうような感覚や、考えずに行動してしまう特性です。
・じっとしていられない
授業中に離席する、椅子に座っていても常に身体を揺らしたり貧乏ゆすりをしたりする。
・おしゃべりが止まらない
相手の状況に関係なく、思いついたことを一方的に話し続けてしまう。
・順番が待てない
ゲームや遊具の順番待ちができず、列に割り込んでトラブルになる。
・衝動的な行動
質問が終わる前に食い気味に答えてしまう、道路に急に飛び出してしまう。
・感情のコントロールが苦手
カッとなるとすぐに手が出たり、大声を出したりしてしまう。
対人関係やこだわりが強いASDの特徴
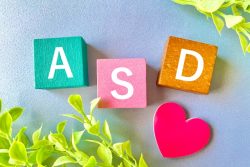
ASDは、日本語で自閉スペクトラム症と呼ばれます。以前は自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害などと別々に呼ばれていたものが、連続したひとつのスペクトラムとして統合された診断名です。対人関係・社会性の困難と興味・行動の強いこだわり(想像力の偏り)の2つが主な特性です。
対人関係やコミュニケーションの特徴
人との関わり方において、独特の難しさを抱える特性です。相手の気持ちを推測するという、多くの人が無意識に行っていることが苦手なため、集団の中で孤立しやすい傾向があります。
・視線が合いにくい
話している相手と目を合わせようとしない、表情が乏しく何を考えているか分かりにくい。
・場の空気が読めない
暗黙の了解が分からず、その場にそぐわない発言をしてしまう。
・一方的なコミュニケーション
相手が興味を持っていないのに、自分の好きな話を延々と話し続ける。
・言葉を文字通りに受け取る
ちょっと待ってての「ちょっと」が具体的に何分か分からないと不安になる、冗談や皮肉が通じず真に受けて傷ついてしまう。
・ごっこ遊びが苦手
見立てをする想像力が独特なため、ほかの子と一緒におままごとや戦いごっこをするのが難しい。
こだわりの強さや感覚の偏り
特定の物事に対して、強いこだわりや感覚の過敏さ(または鈍麻さ)が見られます。これはいつもと同じであることで安心感を得たいという心理の裏返しでもあります。
・ルーティンへのこだわり
登校ルート、手順、物の配置などがいつもと同じでないとパニックになる。
・限定的な興味
電車の時刻表、特定のマーク、数字の羅列など、非常に狭い範囲に深く没頭し、驚異的な記憶力を発揮することがある。
・感覚過敏
運動会のピストル音や特定の機械音をひどく嫌がる(聴覚過敏)、服のタグがチクチクして着られない(触覚過敏)、偏食が極端に激しい(味覚・嗅覚過敏)。
・感覚鈍麻
暑さ寒さを感じにくく体温調節が苦手、怪我をしても痛がらないことがある。
特徴別に見たADHDとASDの違い

ADHDとASDは、どちらも集団行動が苦手、落ち着きがないといった姿を見せることがあります。しかし、なぜその行動をとるのかという理由には大きな違いがあります。
興味を持つ対象の違い
・ADHD(次々と移り変わる)
好奇心旺盛で、新しい刺激にすぐに反応します。興味の対象が次々と移り変わり、ひとつの遊びが長続きしません。熱しやすく冷めやすいのが特徴です。
・ASD(深く狭く)
一度興味を持った特定の物事に対して、何年にもわたって深くのめり込みます。新しいことよりも、慣れ親しんだ反復行動を好みます。
対人関係の違い
・ADHD(関わりたいがうまくいかない)
人への関心は強く、友達と仲良くしたいと思っています。しかし、衝動的に余計なひと言を言ったり、遊びのルールを待てずに割り込んだりしてしまうため、結果としてトラブルになりやすいです。悪気がないため、なぜ怒られたのか分からないこともあります。
・ASD(関心そのものが薄いか独特)
他者への関心そのものが薄く、一人遊びを好む場合があります。または、関わりたい気持ちはあっても、アプローチが一方的で独特なため(相手の都合を考えずに話しかけ続けるなど)、コミュニケーションが成立しにくい傾向があります。
ルールの捉え方で違う点
・ADHD(分かっているけど守れない)
頭ではルールを理解しています。してはいけないと分かっているのですが、衝動性を抑えられずについ身体が動いてしまいます。やってしまった後で「またやってしまった」と自己嫌悪に陥ることも多いです。
・ASD(融通が利かないほど守る)
ルールやマニュアルを絶対的なものとして厳格に守ろうとします。そのため、状況に応じた特例や、「適当にやっておいて」といった曖昧な指示に対応できず、混乱してしまいます。他人がルールを破ることに対しても厳しく注意してしまい、トラブルになることもあります。
併発もあるADHDとASDの混合型

ADHDとASDは、実はどちらか一方だけとは限りません。両方の特性をあわせ持つ、併発(混合型)のケースも非常に多く見られます。 以前の医学的な診断基準では、ASDと診断された場合はADHDの診断はつかないというルールがありましたが、現在の最新基準(DSM-5)では、両方の特性がみられる場合は併発として診断できるようになりました。
混合型とはどのような状態か
混合型の場合、ADHDの衝動性・不注意と、ASDのこだわり・社会性の困難が混ざり合って現れます。 例えば、「普段はこだわりの強さからじっと座っている(ASD)が、興味のあるものが目に入ると衝動的に飛び出してしまう(ADHD)」といった具合です。
併発すると特徴が分かりにくくなる理由
併発している場合、本人の中で相反する特性が衝突し、より強い生きづらさを感じていることがあります。 「ASDの特性(変化を嫌い、ルーティンを守りたい)」と「ADHDの特性(じっとしていられず、新しい刺激を求める)」が同時に存在するため、自分でもアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような苦しい状態になりがちです。
また、一方の特性がもう一方を隠してしまうこともあります。例えば、ADHDの多動性があっても、ASDの「真面目にルールを守らなければ」という強いこだわりによって、学校では必死に多動を抑え込んでいるケースなどです。この場合、学校では問題のない子と見られ、家庭で反動が出て激しく荒れることもあります。
特性に合わせた関わり方のヒント

ADHDとASDでは、行動の背景にある理由が違うため、効果的なサポート方法も異なります。それぞれの特性に合わせた関わり方のヒントを紹介します。
ADHDを持つ子どもへのサポート
ADHDの子どもは、情報が多すぎると混乱しやすく、刺激があるとそちらに気が逸れてしまいます。
・環境調整
勉強するときは机の上を何もない状態にする、おもちゃを目隠しカーテンで隠すなど、視覚的な刺激を減らします。
・短く具体的な指示
「部屋をキレイにして」ではなく、「本を棚に戻そう」とひとつずつ具体的に伝えます。
・できたことを認める
叱られる経験が多くなりがちなため、当たり前のことでも「座っていられたね」「最後まで聞けたね」とこまめに褒めて、自尊心を支えることが大切です。
ASDを持つ子どもへのサポート
ASDの子どもは、見通しが立たないことや曖昧な状況に強い不安を感じます。
・視覚的な支援
言葉だけで伝えるよりも、写真やイラストを使ったスケジュール表などを見せて、視覚的に次に何をするかを伝えます。
・事前の予告
予定変更がある場合は、できるだけ早く伝えて心の準備をさせます。
・クールダウンの場所
感覚過敏などでパニックになりそうなときに、ひとりで落ち着ける静かな場所(カームダウンスペース)を確保しておきます。
大人の発達障害と診断を受けるには

発達障害は、子どものころは特性が目立たず「少し変わった子」程度で見過ごされ、大人になってから社会生活での困難さに直面して初めて気づくケース(大人の発達障害)が増えています。
子どもの診断はどのように行われるか
子どもの場合、小児科、児童精神科、小児神経科などの専門医療機関で診断を受けます。 血液検査や画像検査で分かるものではないため、医師による保護者からの詳細な聞き取り(問診)、本人の行動観察、心理検査(WISC-IVなど)の結果などを総合的に判断して診断されます。 診断基準(DSM-5)には、「症状が12歳以前から存在していたこと」といった項目もあり、幼少期の様子が重要な判断材料になります。
診断がつかないグレーゾーンの場合
検査の結果、確定診断の基準には満たないものの、発達障害の傾向がみられる状態をグレーゾーンと呼ぶことがあります。 グレーゾーンの子どもは、診断名がつかないために公的な支援につながりにくい一方で、日常生活では確かな生きづらさを抱えています。診断の有無にかかわらず、その子の困り感に寄り添い、特性に合わせた療育的サポートを行うことが非常に重要です。
大人のADHDやASDの特徴と困りごと
大人の場合、仕事や家庭生活で具体的な支障が出ることがきっかけになります。
・大人のADHD
仕事のケアレスミスが多い、約束の時間に遅れる、タスク管理ができず締め切りを守れない、片付けられず部屋がゴミ屋敷化する など。
・大人のASD
職場の暗黙のルールが分からない、雑談が苦手で孤立する、臨機応変な電話対応などが極端に苦手、パートナーとの情緒的な交流が難しい など。
こうした困難が続くと、自己否定感からうつ病や適応障害、不安障害などの二次障害を発症してしまうリスクが高まります。
診断は専門の医療機関へ相談を
自分は(うちの子は)発達障害かもしれないと悩んだときは、自己判断せずに専門家へ相談することが大切です。 大人は精神科や心療内科、子どもは小児科や児童精神科が窓口になります。また、診断がつかないグレーゾーンの場合でも、特性に合わせた環境調整やサポートを受けることで、生活のしやすさは大きく変わります。
ADHDとASDについてのまとめ
ADHD(注意欠如多動症)は不注意・多動性・衝動性による行動制御の難しさ、ASD(自閉スペクトラム症)は対人関係の困難・こだわりによる社会性の独特さが主な特徴です。
一見似たような行動でも、その背景にある原因は異なります。また、両方の特性をあわせ持つ併発(混合型)のケースも多く、その場合はより複雑な困難さを抱えている可能性があります。
大切なのは、診断名をつけることそのものではなく、その子の得意なことと苦手なことを正しく理解し、個性に合った適切なサポートを行うことです。子どもの発達で気になることがあれば、ひとりで悩まず早めに専門機関へ相談しましょう。
ステラ幼児教室・個別支援塾では、ADHD、ASDの子どもに関する相談にも対応しています。
お気軽にご相談ください。
ステラ幼児教室・個別支援塾は生徒募集中
ステラ幼児教室・個別支援では随時生徒を募集しています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。
お気軽にご相談ください。