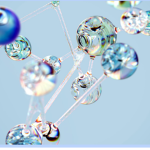どうして夜になっても寝てくれないの?」「昼寝を全くしなくて、こちらがくたくた…」
2歳頃の子どもの睡眠について、悩みを抱えている保護者の方は少なくありません。
なかなか寝ない姿に、ついイライラしてしまったり、「もしかして発達障害では…?」と不安になることもあるかもしれません。
そこで本記事では、2歳児の睡眠に見られる特徴やよくある行動、発達障害との関係性について解説するとともに、睡眠リズムの整え方や正しい生活習慣を取り戻すためのポイントもご紹介します。
2歳で寝ないのはよくあること?睡眠の特徴

「同じ年頃の子どもはもっと寝ているのに、うちの子どもはなぜ…?」と感じたことはありませんか?
2歳児は個人差が大きく、睡眠のリズムが整いきらない時期でもあります。
昼寝をしなかったり、夜なかなか寝付けなかったりといった行動は、発達の一環として“よくあること”の範囲内であることも少なくありません。
そこで本項では、2歳児の平均的な睡眠時間や生活リズム、よくあるお悩みとその原因について解説します。
2歳児の平均的な睡眠時間と生活リズム
2歳児の理想的な睡眠時間は、夜間の睡眠+昼寝を合わせて11〜14時間が目安とされています。
厚生労働省なども1〜2歳の平均睡眠時間をこの範囲と推奨しています。
日本では夜の就寝が遅れがちで、夜9時以降に寝る子どもが多いですが、それでも朝7時ごろに起きるご家庭が多く、睡眠時間が不足しやすい傾向にあります。
2歳までに睡眠リズムがある程度定まることが重要なので、日々のリズムづくりはこの時期に意識して整えていきたいところです。
参考元:厚生労働省「こどもの睡眠」
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-02-007
昼寝をしない・夜なかなか寝ないなどよくある悩み
「昼寝をしない」「夜が遅くなって寝つきにくい」と2歳前後で悩む保護者は多く、厚生労働省調査でも11.5%の2歳児が昼寝をしないと報告されています。
午後の遊びに夢中になってしまい、あえて昼寝を拒むこともよくあります 。
また、夜の環境(スマホや照明など)や日中の活動量が足りずに寝つきが悪くなるケースもあります。
こうした悩みは決して珍しくありませんので、ご家庭のリズムを少しずつ調整していくことが大切です。
参考元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/73-22-01.pdf
発達段階にともなう一時的な睡眠トラブルの可能性
2歳は「イヤイヤ期」の真っただなかで、自我と自立心が強くなっている時期で、これがストレスとなり、夜の寝つきが悪くなることもあります。
また、2歳までに睡眠リズムがつくられるため、この時期に夜型化が定着するとその後もリズムが崩れやすくなると指摘されています。
成長の一環としての変化なので、無理に正常化しようとせず、生活リズムや環境を整えて安心して眠れる状況を作ることが大事です。
寝付きが悪い・昼寝をしないなど寝れない原因とは
2歳頃の子どもが「なかなか寝ない」「昼寝をしない」といった睡眠の悩みには、いくつかの背景や原因が考えられます。
すぐに改善できるものばかりではありませんが、まずはどのような要因があるのかを知っておくことが大切です。
●脳の発達による興奮(日中の刺激が多く、頭がさえて寝つきにくくなることがあります)
●昼寝の時間帯や長さが不適切(遅い時間の昼寝や長すぎる昼寝が夜の眠りに影響します)
●生活リズムの乱れ(就寝・起床・食事などの時間が日によってバラバラだと体内時計が整いません)
●眠る環境に刺激が多い(部屋が明るい、音がうるさい、テレビやスマホの光などが影響することがあります)
子どもの状態や環境を少しずつ見直しながら、眠りやすい習慣を整えていくことが大切です。無理のない範囲でできることから始めてみましょう。
寝ない=発達障害?気をつけたいサインとは
寝つきの悪さや、夜中に何度も目覚める様子を見て、「これは大丈夫だろうか」と心配になることがあるかもしれません。
発達障害がある子どもの中には、睡眠に関する困りごとを抱えるケースも報告されています。ただし、「寝ない=発達障害」とは言い切れません。大切なのは、睡眠だけに注目するのではなく、日中の行動や発達の様子を合わせて見ていくことです。
ここでは、子どもの睡眠において注意して見ておきたいポイントや相談の目安についてご紹介します。
発達障害のある子どもに見られやすい睡眠
発達障害のある子どもは、睡眠障害を併発することが多いと報告されています。
たとえば、自閉症スペクトラム障害(ASD)では64〜93%もの子どもに何らかの睡眠問題(入眠困難・途中覚醒・早朝覚醒など)が見られます。
ADHDの場合も、脳の興奮状態が続くことで寝つきが悪くなり、結果的に日中の眠気や集中力の低下につながることがあります。感覚過敏などの特性から光・音・布団の感触が苦手で、寝室環境そのものがハードルになることもあるでしょう。こうした特徴から、発達障害のある子どもは「寝ない=ただのわがまま」と片づけないで、専門的な支援が有効なケースも少なくありません。
参考元:国立精神・神経医療研究センター
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2013/133081/201317044A_upload/201317044A0010.pdf?utm_source=chatgpt.com
睡眠だけでなく日中の行動や発達の様子も観察
子どもが寝ないときは、夜だけでなく昼間の様子にも目を向けることが大切です。
たとえば、日中に過度に興奮しやすい、集中が続かない、感情の切り替えが苦手などの行動特性が見られる場合、発達特性の可能性があります。
また、睡眠不足があると情緒不安定になったり、癇癪が増えたりすることもあります。
こうした複合的なサインを総合的にみながら、発達外来や小児科、保健センターなどに相談することで、必要な支援を受けやすくなります。
気になる場合は専門機関に相談をしましょう
まだ2歳と幼いうちは一時的な睡眠トラブルであることも多いですが、「寝ない=発達障害」と考えるのは早計です。
しかし、次のような場合には早めの相談が望ましいです。
●夜に3日以上続けて寝付きが悪い・頻回に起きる
●日中に普通より極端な眠気や落ち着きのなさがある
●成長の遅れや言葉・対人面の日中行動に気になる点がある
まずは、小児科やかかりつけ医、自治体の発達支援窓口へ相談してみてください。必要に応じて睡眠専門クリニックや療育機関に紹介されることもあります。専門家の視点を借りて、子どもと保護者の双方が安心できる生活リズム整備の第一歩を踏み出しましょう。
保護者の心が限界になる前に…生活改善のヒント
毎晩の寝かしつけや昼寝の悩みによって、保護者自身の睡眠や気力が削られてしまうこともあると思います。
子どものために頑張っているつもりが、気がつくと自分の心が限界に近づいている…。そんな声も少なくありません。
ここでは、ご家庭でできる生活改善の工夫や、子どもの眠りを促す環境づくり、保護者自身の休息時間を確保するためのポイントをお伝えします。
睡眠リズムを整えるためのポイント
毎日の生活リズムは、子どもだけでなく保護者の心身にも影響します。
朝起きる時間と夜寝る時間をある程度一定にすることで、自然な眠気が訪れやすくなります。
朝はカーテンを開けて光を浴びる、夜は少しずつ照明を落とすなど、リズムを意識した環境づくりもおすすめです。無理のない範囲で、毎日の過ごし方を見直すだけでも、子どもの睡眠や保護者の心のゆとりにつながっていきます。
入眠儀式やをルーティンをつくる
寝る前の“いつもの流れ”があると、心が落ち着きやすくなります。
たとえば「お風呂に入って、絵本を読んで、おやすみなさい」というシンプルな順番を毎日繰り返すことで、入眠スイッチが入りやすくなることがあります。
親子で心地よく続けられるルーティンを見つけていくことが大切です。
特別なことをしなくても、同じことを同じ順序で行うだけでも十分な効果が期待できます。
光や音、刺激を減らすための環境づくり
眠る前の過ごし方や環境(光や音など)が、寝つきの良し悪しに影響することもあります。
夜は部屋の照明をやさしい色に切り替えたり、テレビやスマートフォンの画面を見る時間を短くしたりするだけでも、眠りにつきやすくなることがあります。
寝具の感触や部屋の音・気温なども、眠るための快適さに影響することがあるので、一度見直してみるのもよいかもしれません。
保護者が休める時間を確保するのも大切
子どもの睡眠の悩みは、保護者の休息時間を削ってしまいがちです。
しかし、親が元気でいることは、ご家庭全体の安定にもつながります。
「5分だけでも横になる」「子どもが遊んでいる間にお茶を飲む」など、小さな“休み”を意識的にとることで気持ちが軽くなることもあります。
周囲の人や支援制度に頼ることも、子育てを続けるうえでとても大切なことなのです。

まとめ:生活リズムの見直しや刺激を減らす環境づくりを それでも難しい時は専門機関に相談も検討
2歳の子どもがなかなか寝ない、昼寝をしないといった悩みは、多くのご家庭で見られる身近な困りごとです。
2歳前後は睡眠リズムが整いきらず、自我の芽生えや活動量の増加によって、寝つきにくくなることもあります。
特に夜の就寝時間が遅れがちになり、日中の行動にも影響を与えることがあります。
一方で、こうした睡眠の悩みが発達障害に関連している可能性もゼロではありません。
自閉スペクトラム症(ASD)やADHDでは、睡眠障害をともなうケースが多く報告されています。
ただし、「寝ない=発達障害」と決めつけるのではなく、日中の行動や発達の様子を総合的に見て判断することや専門的な判断が必要です。
また、保護者自身の心身の健康も見逃せません。
生活リズムの見直しや入眠儀式、刺激を減らす環境づくり、そして親が休める時間を意識して確保することが、子どもの安定した眠りにもつながります。
睡眠の悩みは決して珍しいことではないため、一人で抱え込まずに必要に応じて専門機関に相談することも大切です。
参考元
厚生労働省
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-02-007
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/73-22-01.pdf
国立精神・神経医療研究センター
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2013/133081/201317044A_upload/201317044A0010.pdf?utm_source=chatgpt.com